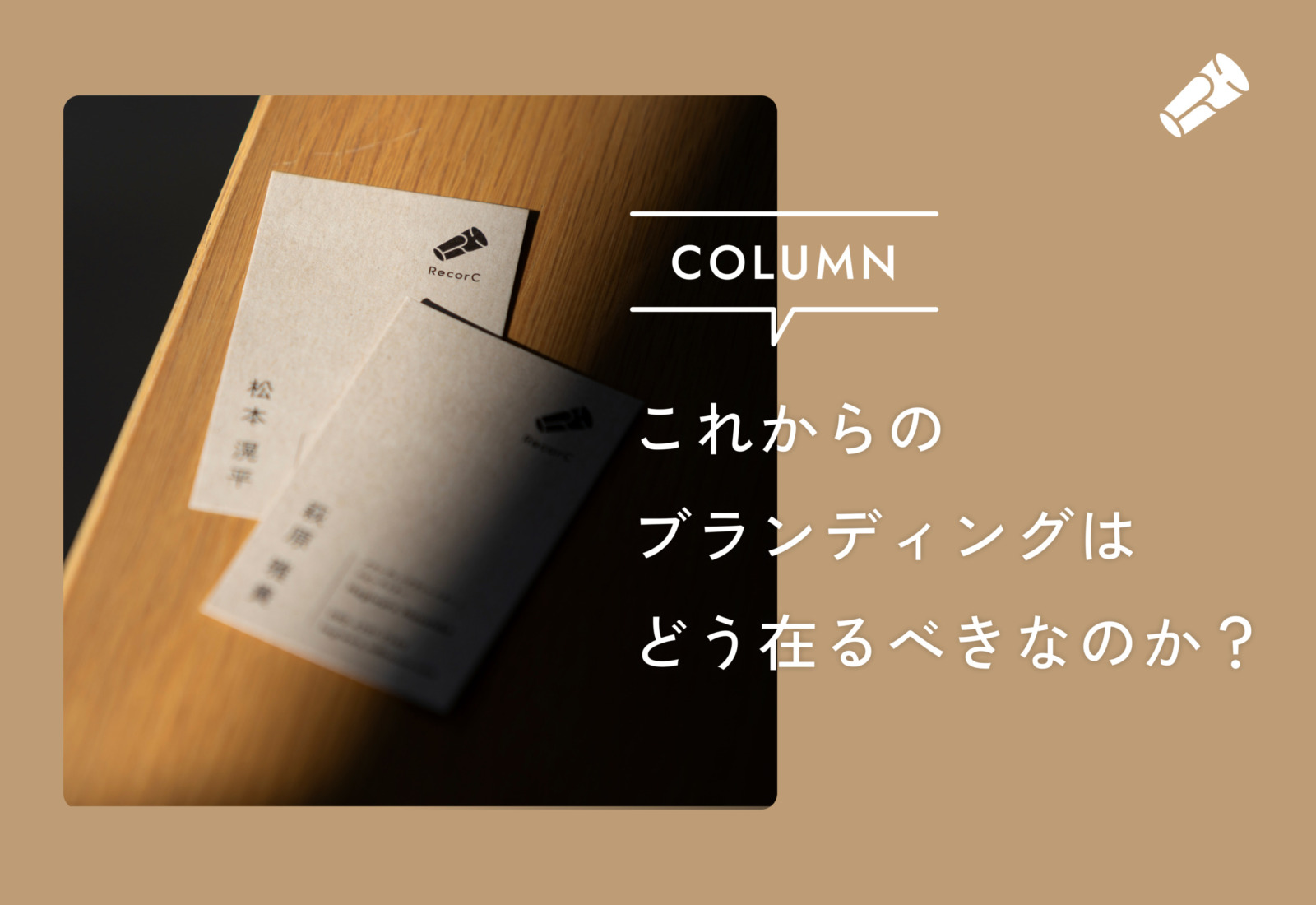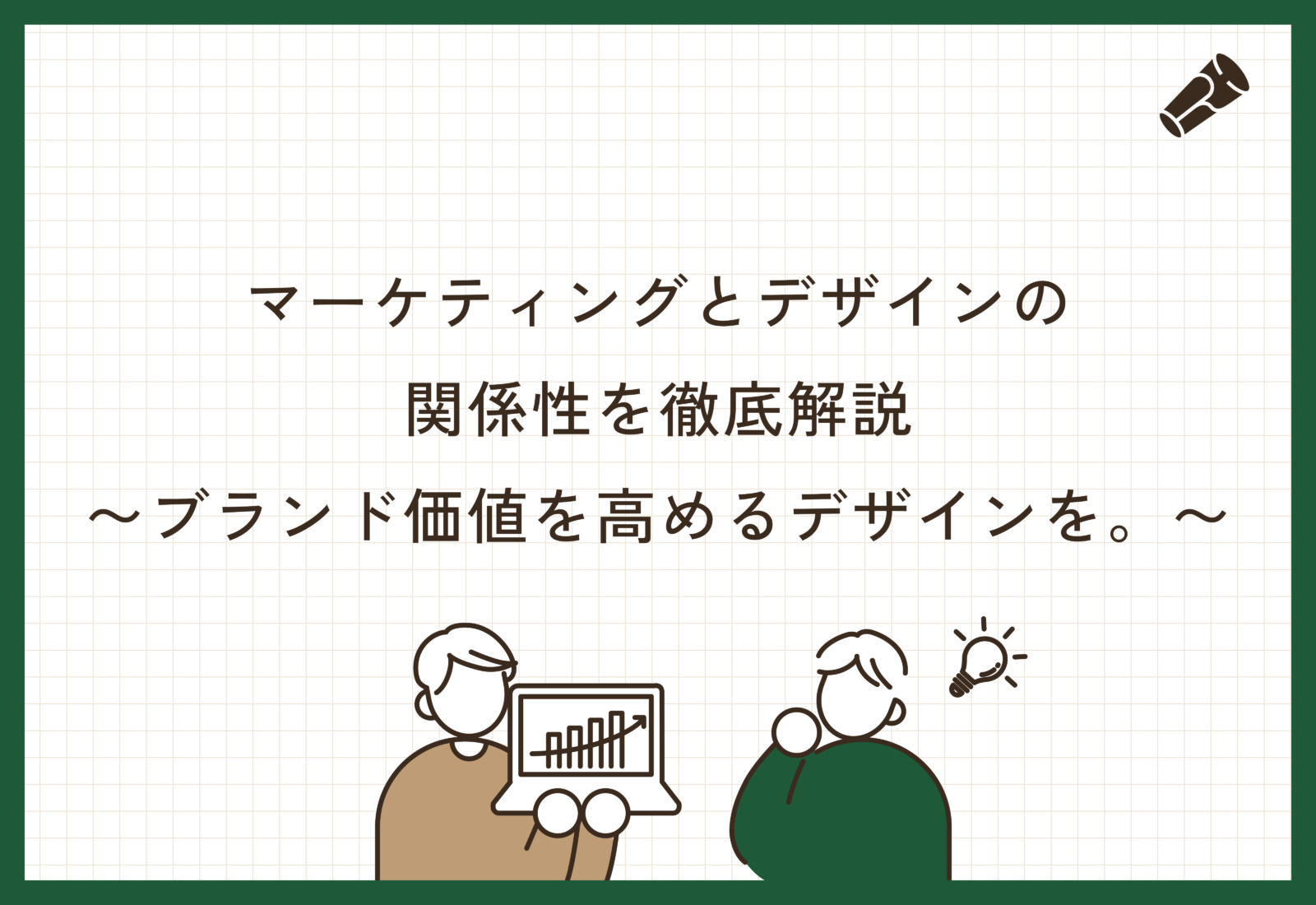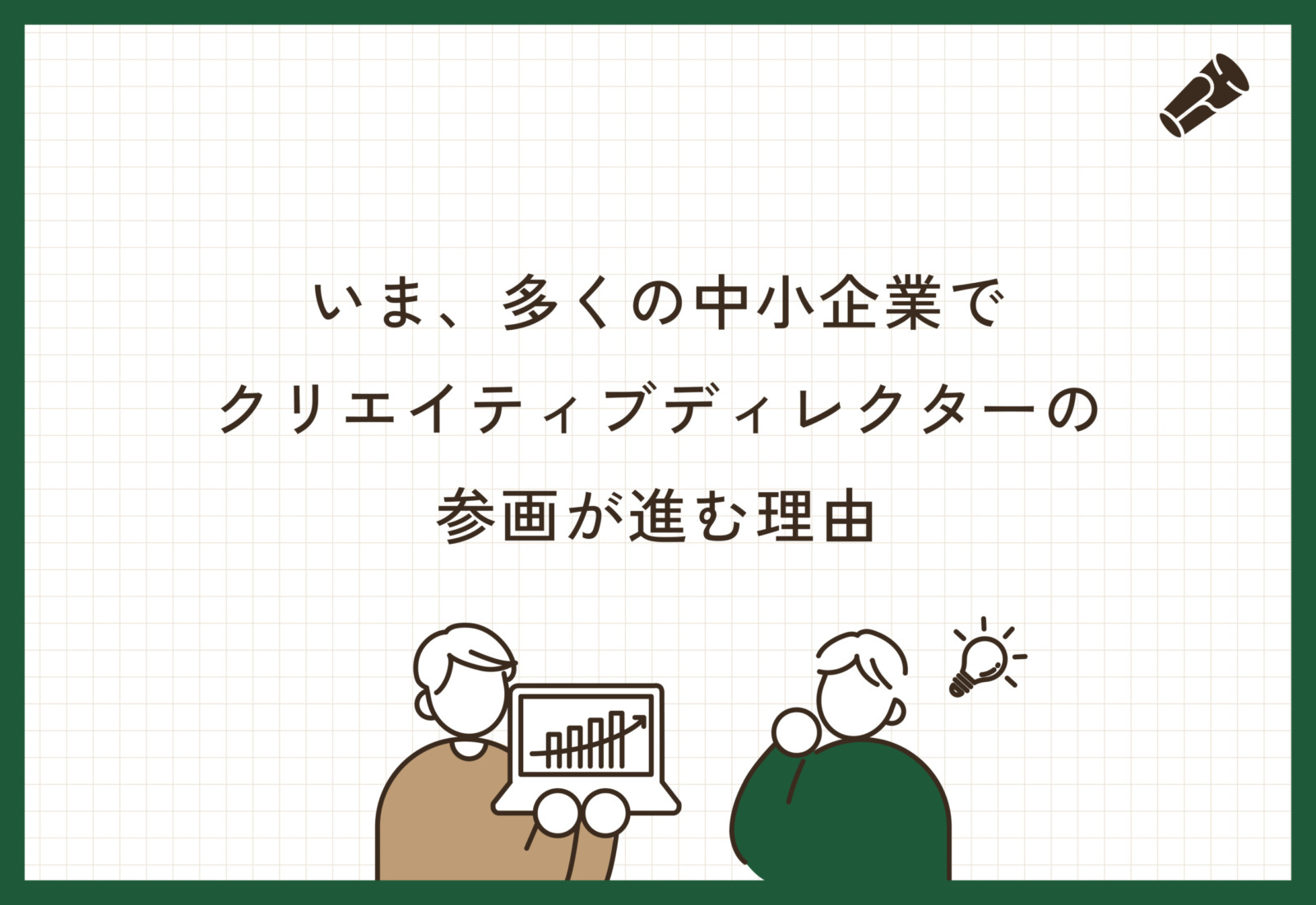Index
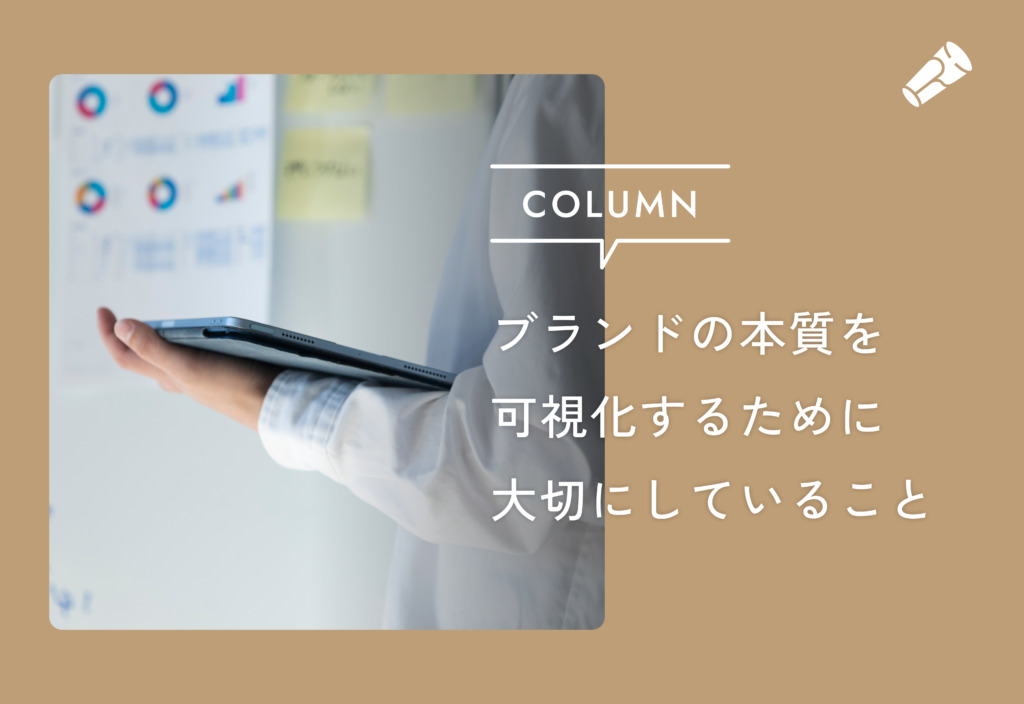
近年、競争が激化している市場や世の中の価値観の変化に伴い、企業やサービス、商品は、独自性や価値を見出し、唯一無二の存在として選ばれ続けるために、ブランディングに沿った経営が求められています。
また、ブランディング戦略に基づいたクリエイティブ制作ができるクリエイターの存在もますます重要になっています。
そのため今回の記事では、ブランディングの考え方を取り入れることで、デザインがどのように課題解決に役立つのかを、ブランディングの要素をデザインに組み込むステップを紹介しながら説明します。
クリエイティブ制作において、ブランディングの思考を取り入れることの重要性
ブランディングを進める過程で、社会や顧客との関係性から企業やサービス、商品の強みや弱みを分析し、独自性を見つけ出します。
それと同時に、現状の課題についても明らかにします。
リコルクでは、“デザイン”を課題解決の道筋を設計すること”と定義しています。
そのため、ブランディングの考え方を制作に取り入れることで、お客様の課題をより深く理解することができ、成果につながるアウトプットになると考えています。
また、ブランドの本質をターゲットに対して視覚的に伝えるデザインを“ブランドデザイン”と呼び、社会との関係性から浮かび上がるブランドの独自性や在り方・在りたい姿を可視化することができます。
これはブランドのポジショニング戦略を推し進める上でも重要な役割を担っており、ブランドの居場所や輝く場所をデザインの力で後押しします。
実際に、デザインにブランディングの要素を落とし込む際のステップ
実際に、デザインにブランディングの要素を落とし込む際のステップ、以下の3つのステップがあります。
(1)思考の軸をつくる
(2)型に落とし込む
(3)形に現して可視化する
まず、“(1)思考の軸をつくる”では、お客様の顧客の視点に立ち、ブランドが存在する社会的意義・強み・特徴・顧客のニーズなどそれぞれの本質をしっかり捉えて、編集していきます。
“(2)型に落とし込む”では、ブランディングは一貫性が求められるため、ブランドの方針やルールに則ってクリエイティブをつくることで、消費者に一貫したイメージを浸透させます。
(1)と(2)をアウトプットで表現するのが、“(3)形に現して可視化する”です。
思考の軸をつくるためには“編集力”が必要だ
私は、ブランドデザインには“編集力”が必要不可欠だと考えています。
特にブランディングは単なるものづくりではなく、ものづくりも含めた「ものがたりづくり」。
ものがたりを作るためには編集力が必要であり、クリエイターはその視点をクリエイティブに活かしていくことが求められています。
編集を行う際のポイントは3つあります。
- 顧客のニーズが生まれた背景や文脈、ブランドの歴史を知ること
- 要素を分解し価値を具体的に捉えること
- 接続ポイントを見つけ掛け合わせること
顧客のニーズが生まれた背景や文脈、ブランドの歴史を知ること
「ブランドが生まれた背景」や、身近なところでいくと「なぜこの担当者さんはこの言葉を使っているんだろう?」といった、目に見えないもの(裏側)への理解が重要です。
こうした背景、文脈は、徹底して「過去」に焦点を当てると見えてきます。
過去は教えを乞うためにあるので、そこを基点に、現在、未来へと視点を移しながら、以下を整理していきます。
- ブランドが一貫して大切にしてきた価値観は何なのか?
- その価値観を貫いた先にはどんな未来があるのか?
- その未来に近づくためには、現在はどんな課題を解決しなければならないのか?
まだまだ明確にしたい情報はありますが、このようなブランドの本質に迫るポイントを一つひとつ整理しながら具体化していきます。
このプロセスがなければ、まずブランドを本当の意味で理解することができず、何をどう編集したら良いかも見えてきません。
要素を分解し、価値を具体的に捉える
これは、ブランドの強みや独自性、顧客ニーズなど、まだ抽象的で曖昧になっていることを“複数の要素”に分けてより具体的にするということです。
例えば、とあるカフェの強みが「新鮮なコーヒーを飲める体験価値の高さ」である場合、これにおいても「新鮮なコーヒー」という要素を分けて整理する必要があります。
「焙煎したてだから?店舗に保管している期間が短いから?」
「実際に焙煎してからどれくれいで提供してもらえるのか?」
「焙煎したてだと何がどう違うの?」
など
新鮮なコーヒーが何を指しているかで強みが変わってくるため、ざっくりとした強みや抽象的な言葉をより具体的にし、ブランドの強みを明確にしていきます。
接続ポイントを見つけ、掛け合わせる
どんなに相反することでも、接点や繋がるポイントは必ずあります。
なので、ここまでに明確にしてきたブランドの価値観や強み、顧客のニーズ、そしてそのニーズが生まれる背景などの要素がどこで繋がるのかを見極め、一つの言葉に凝縮します。
接点が見つからない要素に関しては、思い切って切り捨てます。(選択と集中)
そこから、誰が聞いてもパッとイメージできる言葉になるまで、何度でも言葉を磨き、そのブランドならでは”の独自価値をわかりやすくしていきます。
むしろ、一見接続できなさそうな要素を接続できた時の方が、面白いものが出来上がることもあります。
このように、”思考の軸をつくる編集”というのは、ブランドをあらゆる角度から捉え直し、それぞれのポイントを組み合わせて「誰に何を伝えるか」を明らかにすること。
つまりコンセプトメイクそのものです。
デザインする際、持つべきではない視点や思考
これも3つあります。
まず1つ目は、“視点が外側に向かず、相手への関心が無い”こと。
自分以外の何かに関心がないと、理解不足につながり、誰のためのデザインなのかが曖昧になってしまうと思います。
2つ目は、“好みで片づけてしまう”こと。
デザインの判断で迷った時に「この点は好みですね」で終わるのではなく、最後まで理由を持つことが重要です。
サービスを受け取る顧客はサービスを好みで選んでいるかもしれないけれど、作り手は好みではなくコンセプトに基づいた論理で選ぶべきで、最後の最後で直感や感性を頼りにするべきだと思います。
クリエイティブジャンプも思考や論理、知識を積み重ねていかなければいつになっても起こりません。
3つ目は、“0→1ではない”こと。
ものづくりは、何かと何かを組み合わせて別の価値をつくること。
つまりゼロから何かをつくることなんてほぼありません。
料理をつくるようなイメージで、素材の良さ見極めた上で、複数の素材をどう組み合わせれば新しいものをつくるか。
私たちの仕事もそこを問われています。
だから、0→1で何かを生み出そうという視点が強ければ強いほど何も出てこない。
・・・
1〜3全てに共通する持つべきでない考え方は、「モノづくりという行為は自分の承認欲求を満たすためではない」ということ。
常に冷静に、このような思考に陥ってないかチェックすることが大事です。
目にみえるものにコストを割くとブランドは弱くなる
ブランディングの考え方を制作に取り入れることは、「想像と編集」の繰り返しです。
実際に手を動かして何かを描く時間よりも、リサーチや思考プロセスにかかる時間の方が圧倒的に長いことがほとんどです。
ここから分かるのは、ブランドの本質を伝えるには、単に制作物に対してコストをかけるのではなく、想像力や編集力、アイディアなどの目に見えないところにコストをかけるべきだということです。
そのため、「単に綺麗な見た目がほしい」「なんとなくあったほうが良いと思ったから」という理由でデザインを依頼するのは非常にもったいないです。
また、「話しやすいから」「頼みやすいから」という理由で依頼するクリエイターを選ぶのも、結果的に無駄になってしまうことが多いです。
私自身もこの点を非常に重視しているため、誰かにデザインを依頼する際は、制作物(ポートフォリオ)から得られる「気づき」や、「対話の質」を確認した上でデザイナーに発注しています。
最後に簡単にまとめると、この記事を書こうと思った最大の理由は、目に見えない資源に対してお金を払う重要性を伝えたかったからです。
現代は知識社会です。モノや情報が溢れる時代では、「つくる」こと自体の価値は下がっています。
だからこそ、知識や知恵に投資し、本物を生み出すことが求められているのだと感じています。