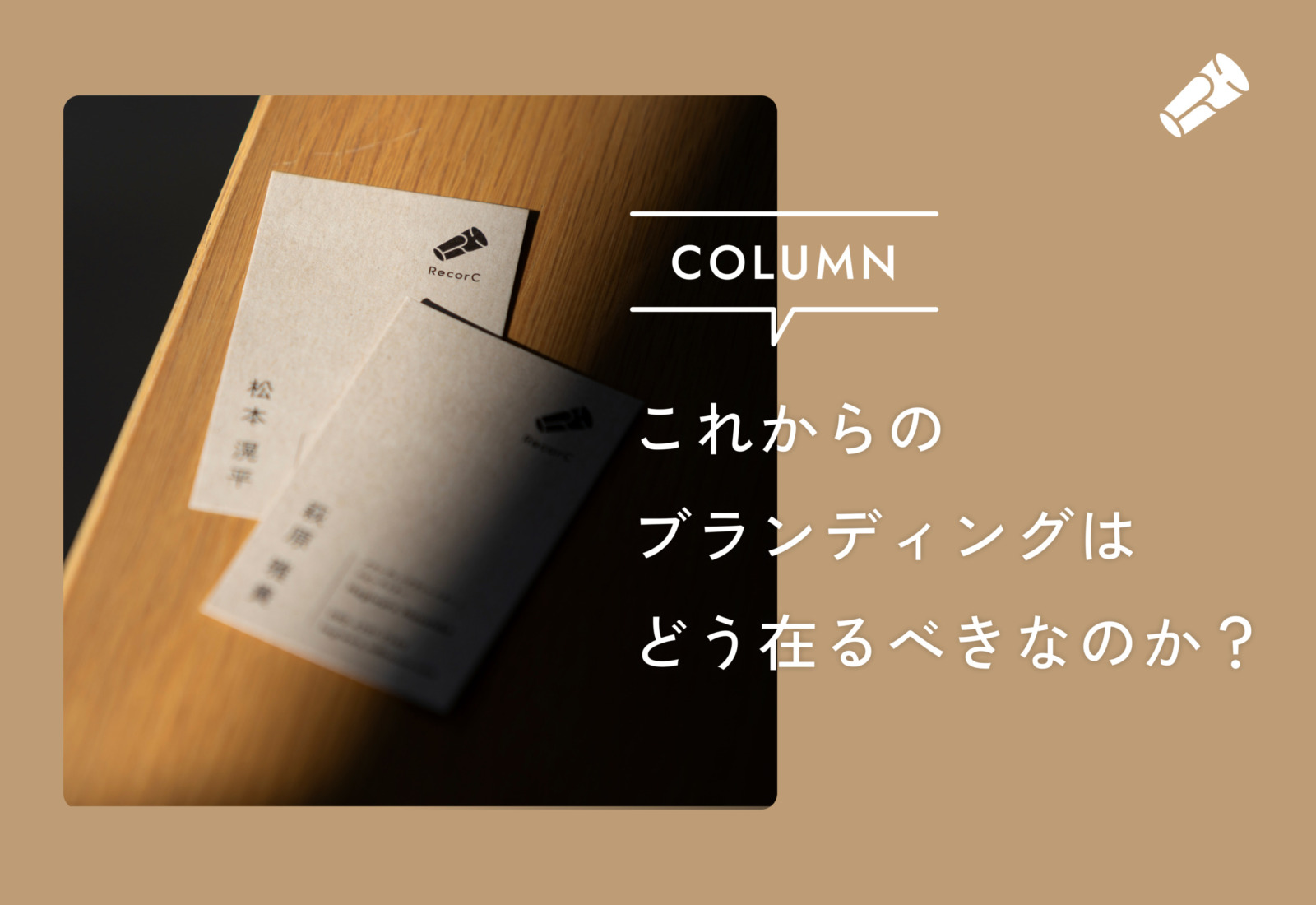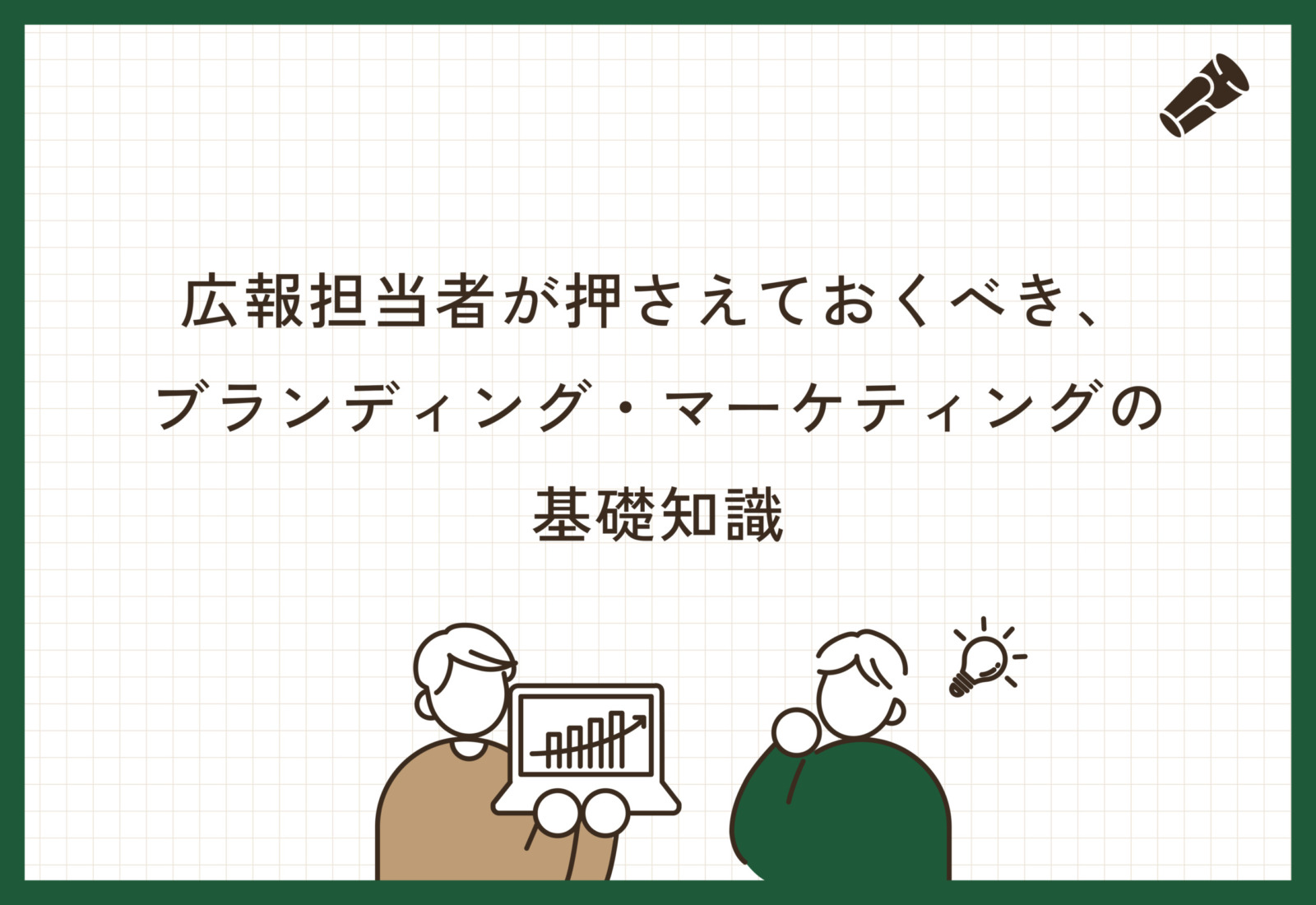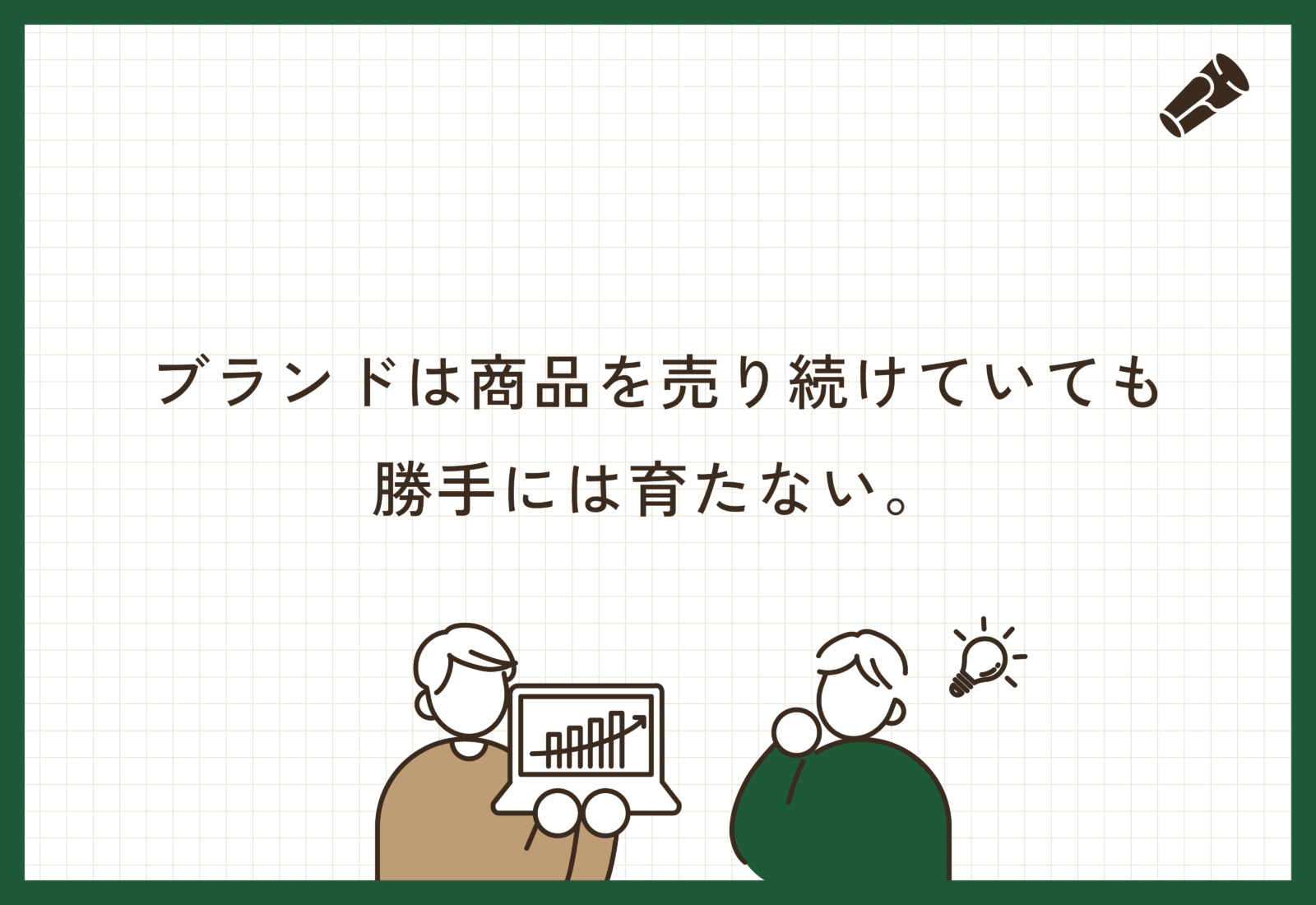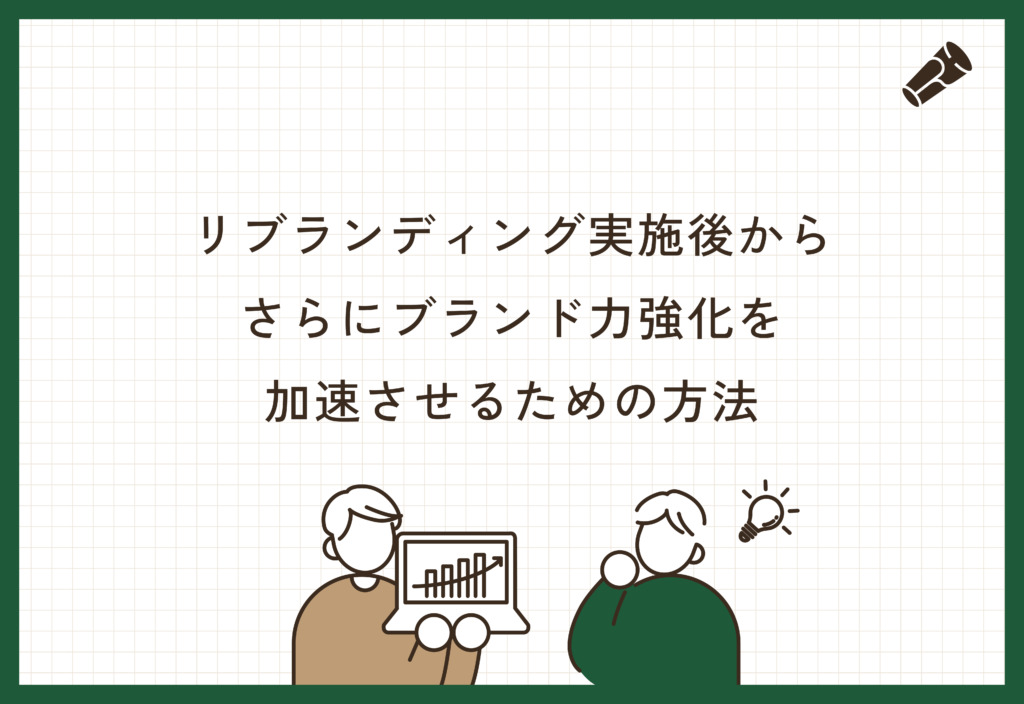
リブランディングプロジェクトが販促物への落とし込みまでで終わってしまうケースは少なくありません。
MVV(ミッション/ビジョン/バリュー)、ブランドコンセプト、ロゴ、ホームページ、パンフレット。
これらを一つひとつ見つめ直し、一新することはできたが、その後、特にそれらしきアクションを起こせていないという声は意外と多くの方から聞く話です。
原因をお聞きしてみると、
「リブランディング実施後から急に忙しくなり、時間を割けなくなってしまった」
「少し落ち着いてからもう一度取り組もうと思っていたが、そのまま何もせずにいた」
「諸々刷新した後、どう次のアクションを設計すればよいかわからなかった」
「そもそもリブランディングはコンセプトや販促物の刷新まで(以下開発フェーズと表記します)だと思っていた」
など、さまざまです。
そして、こうしたお話とセットでよく聞くのが、「伸び悩み」です。
もちろんリブランディングはメリットばかりではなく、デメリットも多く存在します。
伸び悩むという現象は、そうしたデメリットが引き起こされたことによる結果であり、リブランディング以降もアクションを継続しなければ、そのデメリットが引き起こされる確率は高くなります。
反対にリブランディング直後から、開発フェーズで定めた戦略に沿ってコツコツと取り組みを継続しているクライアントさんは、当時では想像すらできなかったほどの成果をあげています。
伸び悩むブランドと成果を上げ続けるブランド。この二つの違いを一言で言うならば、「プロジェクト化の有無」です。成果を上げ続けているブランドは、リブランディング以降もプロジェクト単位で日々の取り組みを管理しています。
なんだそんなことか、と思われた方もいるかもしれませんが、案外日々の活動を一つのプロジェクトの推進として捉えているメンバーは多くありません。
「ホームページの改修の流れの中で情報発信の必要性を知ったから、なんとなく書き続けている。」
「SNSを始めようという話になったので、とりあえず日々の活動を更新し続けている。」
「これまでの流れに沿って同じような広告を流している」
「毎月恒例だからとりあえずイベントを企画している」
そういった例は少なくありません。
やっぱり、せっかくリブランディングを実施したならば、そのメリットを大いに感じていただきたい。
なのでここからは、リブランディング実施後の「成果を上げるプロジェクト化」について書いていきたいと思います。
目的の再解釈
まずはブランディングを推し進めていくメンバーで、目的の再解釈を行います。
例えば、
「そもそもなぜリブランディングプロジェクトが始まったのか?」
「中長期的にどこを目指しているのか? どんな状態を作りたいのか?」
など、改めて議論し、共通認識を持つ必要があります。継続的なコンテンツ制作や発信、クリエイティブも、必ず何らかの目的から逆算して作られます。
なので、そもそも目的が明確に言語化されていなかったり、認識がバラバラな状態であれば、間違いなく良い取り組みにはなりません。ちなみにあえて「再解釈」と表現したのは、手段が目的化されてしまうことを防ぐためです。
たとえば、とある住宅会社(以下、A社)で「価格競争に巻き込まれないブランドを目指そう」という目的があったとします。
そのために差別化を図るための情報発信を行うことになった際、差別化が目的化してしまうことで、
ユニークではあるものの、実際には売上に直結しない情報発信が多くなってしまうことがあります。
顧客に価値として理解してもらうために、住宅性能や構造、デザインの独自性を伝えていく必要があったが、いつの間にかとにかく映える写真をSNSにアップすることに躍起になってしまったり。
または、施工中の真摯に取り組む姿を写真に収め、自社のスタンスに関してわかりやすく伝えるための情報が、全く顧客に理解されない超専門的な技術の話に偏ってしまったり。
そうした事例は少なくありません。
なので、プロジェクトの立ち上げ時には必ず「何のための取り組みか?」を改めて再解釈する機会を作ってください。ここがうまくできていないと、今後投資するコストが全て無駄になる可能性が高くなるので、最も気をつけていただきたいポイントでもあります。
問題、阻害要因の抽出
次に、先ほどの目的を実現するための問題と阻害要因の抽出を行います。
今回はリブランディング実施後における話なので、「ホームページや販促物が古臭い」「ブランドコンセプトが曖昧でスタッフすらチームメンバーすら腹落ちできていない」という問題は、一旦対策済みであると仮定して話を進めます。
問題に関しては、目的と現在の差分をもとに抽出するイメージで、ここでは思いつく限り書き出すことが大事です。
先ほどのA社を例に挙げると、以下のようなイメージです。
- 自社の強みや特徴(機能的な便益と独自性)を体感してもらえる場所がない。
- 営業担当者によって、強みや特徴(機能的な便益と独自性)の認識がバラバラ。
- 顧客との接触回数が少ない。
- プランニングが顧客に刺さっていない。
などです。(あくまでも例です)
こうした問題点を洗い出せたら、そこから「なぜ?」を最低でも2〜3回繰り返して、今度は阻害要因を抽出します。
ここでも例を挙げると、以下のようなイメージです。
Q. なぜ、顧客との接触回数が少ないの?
A. あまり積極的に情報発信を行なってこなかったから。他社に比べてイベントの開催などしてこなかったから。
Q. あまり積極的に情報発信を行なってこなかったの? 他社に比べてイベント開催などしてこなかったの?
A. 何度か試みたけど、あまり申し込みがなかったから。
Q. なぜあまり申し込みがなかったの?
A. 情報が届いていなかったから。魅力的な場であることを伝えられていなかったから。
例え話なので、深掘りはここまでにして、ちょっと強引に阻害要因を言語化すると、「そもそもイベント自体の体験設計が甘いと接触頻度を高めることはできない」ということになります。
課題の設定
問題点や阻害要因が明確になったところで、今度は課題を言語化します。
空想の世界ですが、これまでの話の流れを踏まえて、課題を「お金を取れるくらい価値のある新しいライフスタイルを提案するイベントをつくる。」とします。
もしこの課題を突破することができたら、先ほど別の問題点にも挙げた「自社の強みや特徴(機能的な便益と独自性)を体感してもらえる場所がない。」も同時に解決できそうですね。
ただこれだけだと実際に何をしたら良いのか曖昧なので、細かくタスク化する必要があります。例えば以下のようなイメージです。
- 予算確保
- 住宅会社のイベントに関する不満・不安・不便を整理する
- イベントに関するニーズや顧客が知りたいであろう情報を特定する
- 他社でどのようなことをやっているのか調査する
- 自社のリソースを考慮した上で実施可能な企画案を挙げてみる
- イベントコンセプトを言語化する
- 企画書を作成する
- リサーチを行った上で発信媒体を決定する
- 販促物を作成する
- 経費をまとめる
- など…
もっと細かく設定しても良いかもしれません。とにかくここでは、「誰が」「いつまでに」「どれくらいのコストをかけて」「何をやるのか」を明確にする必要があります。そうすることでプロジェクトが円滑に進むようになります。
先ほど、例としてさらっと「お金を取れるくらい価値のある新しいライフスタイルを提案するイベントをつくる。」をコア課題として設定しましたが、実はここの特定、言語化はめちゃくちゃ重要です。
これによって後々必要になるコンセプトやクリエイティブ、体験デザイン、もちろん細かなタスクなども全てが変わってきます。
コアな課題を特定し、言語化し、共有すること。ここがブランド価値を引き上げ、業績を改善していく上での大きな鍵となります。実際、私は普段ブランディングディレクターとして活動していますが、業務の大半はこのコアな課題の特定に時間やコストを割いています。
ちなみに、良い課題設定の特徴は、その根本的な一つの大きな課題を解決することで、その周辺にある小さな課題も同時に解決されるような課題です。
プロジェクトリーダーを決める
プロジェクトリーダーの人選は、プロジェクトの行末を大きく左右します。しかし、よくやってしまいがちなのが、その人選をやる気や頼みやすい人になんとなくお願いしてしまうことです。
やる気があること自体はとてもありがたいことなのですが、そうした人選をしてしまうとプロジェクトが失敗に終わるケースが多いです。なぜなら、プロジェクトは試行錯誤の繰り返しで、基本的に失敗の連続だからです(もちろん、失敗することが当然になってはいけません)。
やる気の種類にもよりますが、うまくいかずにいる時こそ、やる気はあてになりません。
一つの選定基準として参考にしていただきたいのが、以下です。
- 問題が発生した際に、根本的な課題の特定ができる人
- チームメンバーのニーズ(モチベーションの源泉や今の状況)を把握している人
- 暗黙知を形式知にできる人(言語化能力に優れた人)
また、プロジェクトリーダーに「具体的にどこまで任せるか」も慎重に決める必要があります。リーダーが権限や裁量を持たず、意思決定ができない状況では、プロジェクトは容易に停滞してしまいます。名ばかりのリーダーにしてしまうと、本人も混乱し、意思決定のたびに多くの確認が必要となり、次第に伝書鳩のような役割に陥ってしまうことも少なくありません。
予算設定や最低限確認してほしいことなどを細かく伝達しておくと、この問題は解消されるはずです。
目標は細かく設定する
施策が有効だったのか否かを判別するためにも、目標設定は重要です。また、チームを強くしていくためには、初めの段階で特に成功体験を積み重ねていく必要があります。なので、目標はできるだけ細かく設定する必要があります。
先ほどの「お金を取れるくらいのイベントをつくる」を例にした場合、「イベント来場者20名が目標!」と掲げるだけでは足りません。
20名の方に来ていただくために、ホームページへのアクセス数やエンゲージメント率、SNSからの遷移数など、大きな目標から逆算した小さな目標を設定しておくことが大切です。(KGIとKPIの考え方)
ちなみに、目標は状況を見て絶えず変えていく必要があります。ずっと固定であることは結構稀なので、常に現状を分析し、今の目標が本当に最適なのかを疑うことも重要です。
ルールの設定
人は自由すぎると、かえって動きが鈍くなることがあります。
かなり極端な例えですが、誰かに手紙を書こうと思った時に、真っ白な紙を用意すると一瞬どこから書き始めようか迷うと思います。
ここに罫線・ラインがあれば、自然と紙の先頭に手が動き、スムーズに書き始めることができます。つまり、一定のルールを設定することで、一つひとつの判断が容易になり、運用のハードルが下がり、一貫性も保つことができます。
ちなみに、ルール化の一つの例として、クリエイティブガイドラインを作成しておくことをお勧めします。クリエイティブガイドラインには、最低でも以下の項目に対して自社ブランド独自のルールを設定しておいてください。
▼主に構築フェーズで明確にした内容を基に作成する
- ブランド戦略に関する情報
→ インサイト、ターゲット、ポジショニング、ブランドアイデンティティ、ブランドパーソナリティなど
- ロゴを使用するにあたってのルール
→ デザインのコンセプト、プライマリーロゴ、セカンダリーロゴ、アイソレーション、使用禁止例など
- カラーに関するルール
→ プライマリーカラー、セカンダリーカラー、アクセントカラー、カラーの使用例など
- タイポグラフィーに関するルール
→ 和文英文それぞれの魅せる書体、読ませる書体、WEBフォントなど
- 写真の使用ルール
→ 被写体やテイスト等のNG例、推奨例、ブランドによってLightroomプリセットを用意しているところもある
- テキスト/文章作成時のルール
→ 1人称、2人称、口調、使用可能な記号等
上記で設定したルールの範囲内で自由に思考し行動できる状況を作ることが大切です。ちなみに、クリエイティブガイドラインは一度作って終わりではありません。
これに関しても、運用していく中で気づいたことや課題となったことがあれば、絶えず修正・ブラッシュアップが必要になります。
クリエイティブガイドラインの他にも、判断基準(行動指針)を明文化したり、コンテンツガイドラインも作成しておくと、よりリブランディング後の運用がスムーズになります(※一貫性も増します)。
最後に
継続的にブランドを育てていくためには、日々本質的な課題を突破するために、適切な判断を下すことが求められます。
モノや情報が溢れ、単に見た目として綺麗なビジュアルも飽和状態にある現代において、今日書かせていただいたような「プロジェクト化」や「運用力」がブランドの成否を大きく左右します。
以前、私がリブランディングおよびブランディングのインハウス化支援をさせていただいたクライアントさんは、オンラインショップからの売上を年々伸ばしています。(毎年80%増)
これまでのブランドイメージも一定引き継ぎつつ、今後のビジョンも反映し、より洗練されたビジュアルになることによって売上が増えることはもちろんあります。
ただし、多くのブランドが一過性で終わらせてしまう傾向があるため、ぜひ長く売れ続ける仕組みを「戦略に基づいた”プロジェクト化”」で構築していただきたいと思います。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級