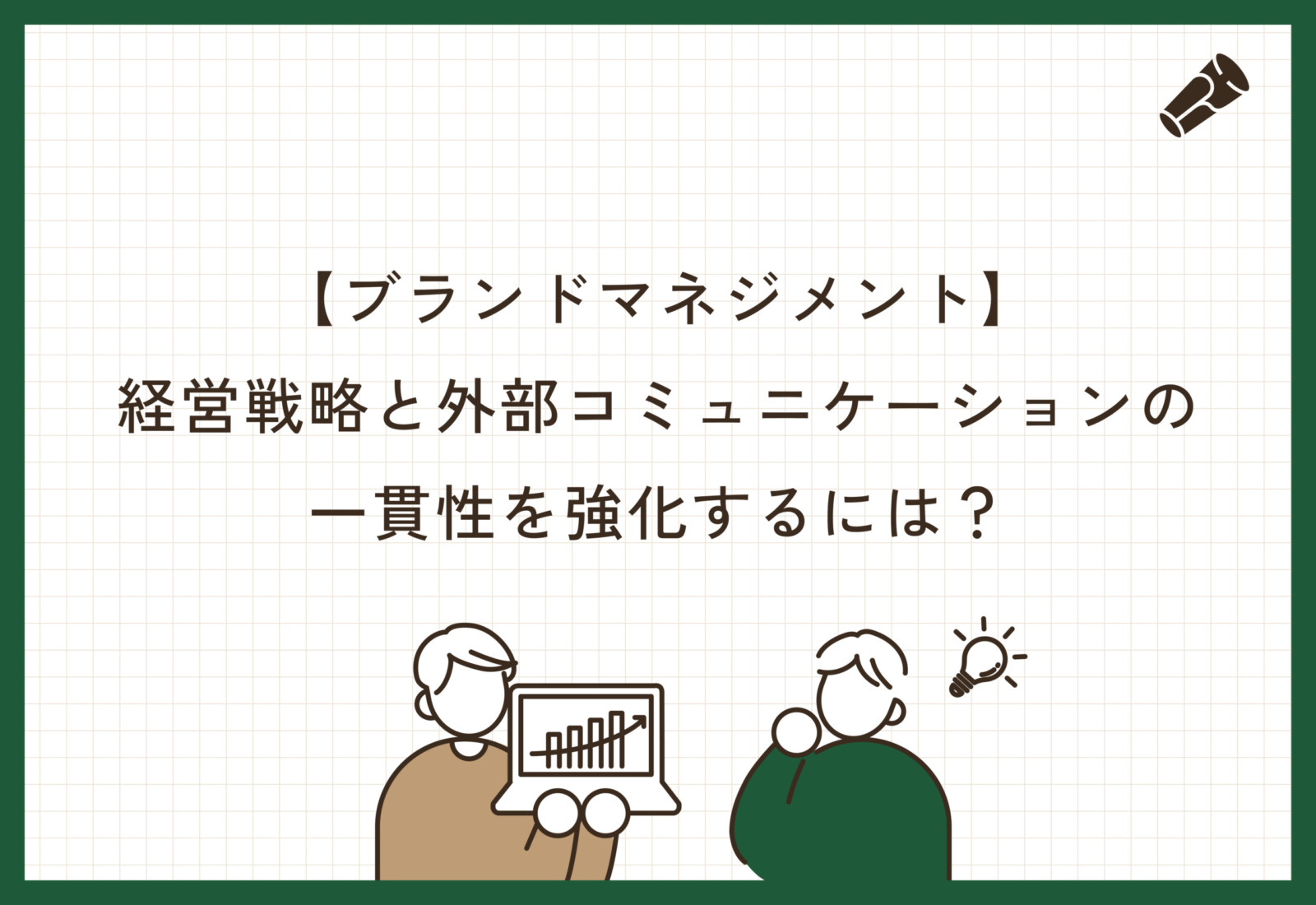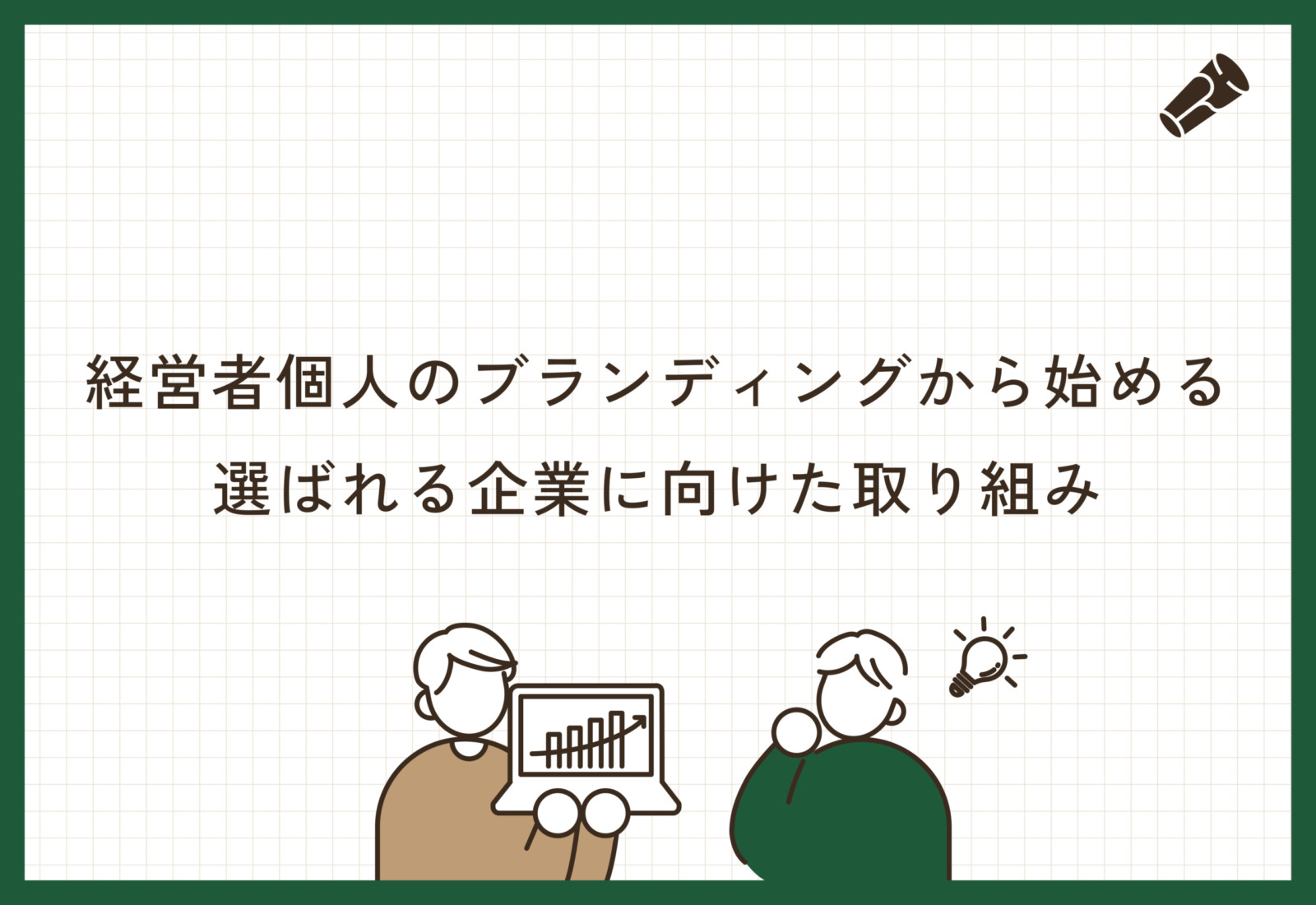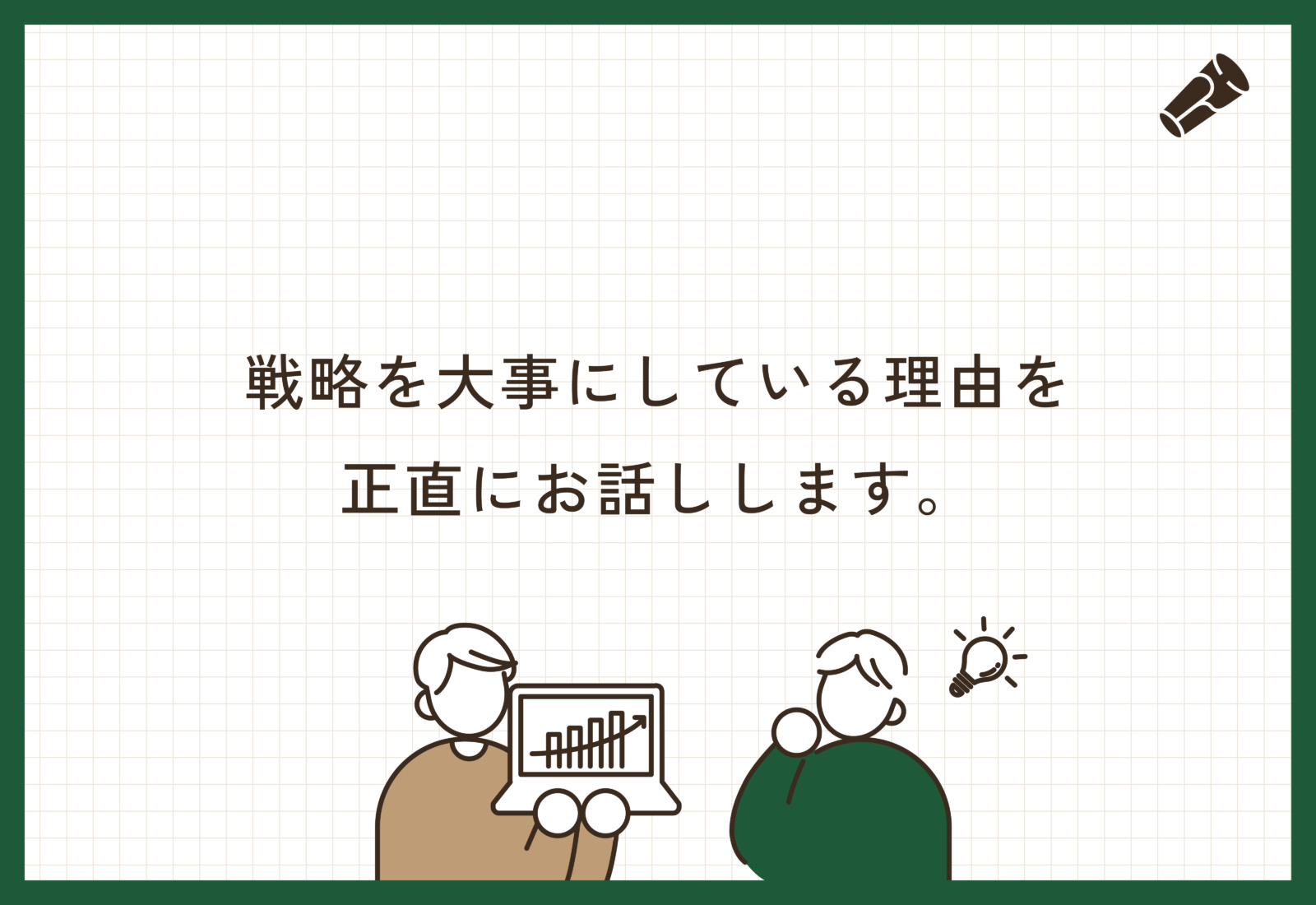Index
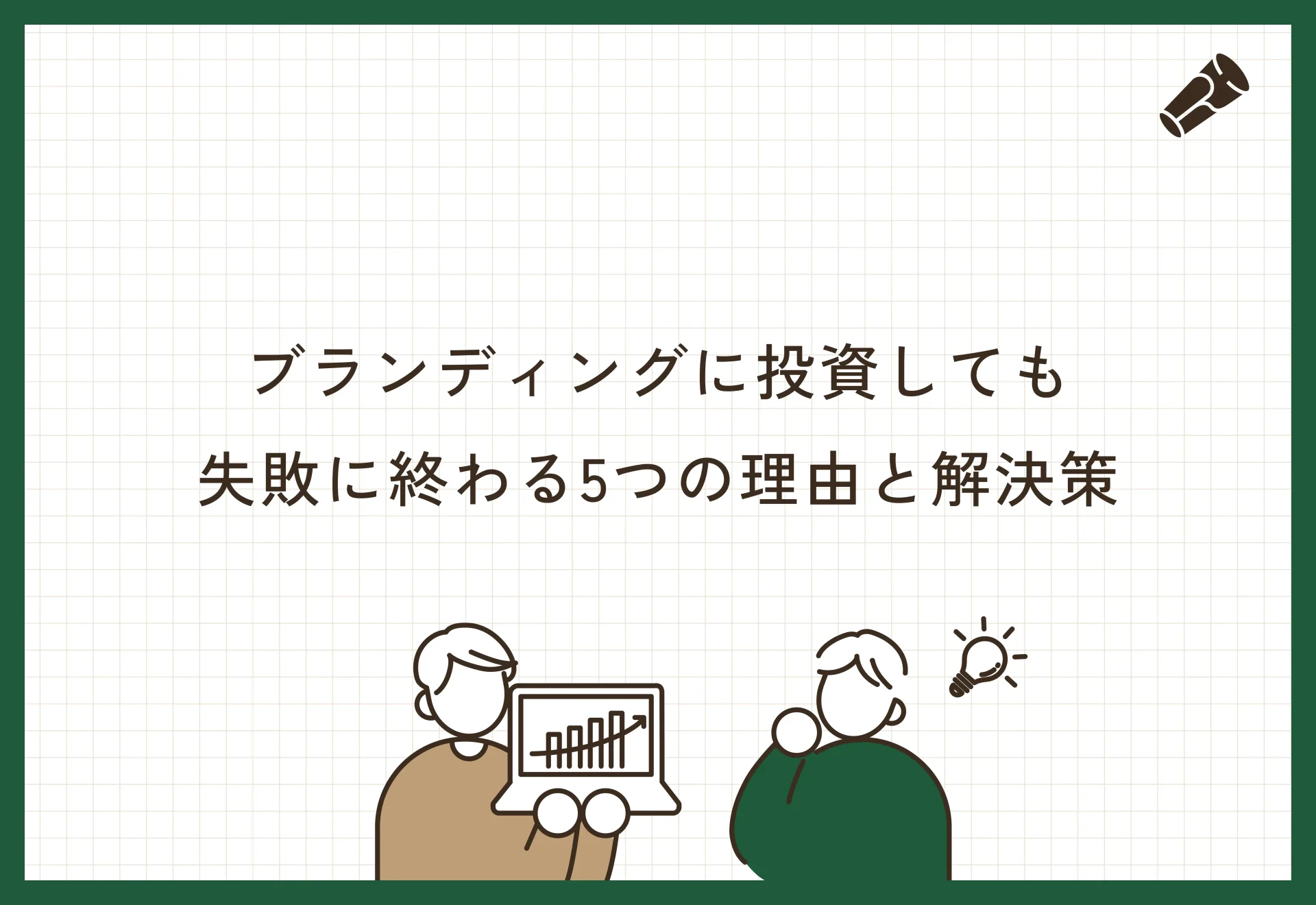
「以前企業としてブランディングに取り組んでみたが、なんだか意味を感じなかった。」
新規でお問い合わせいただいた経営者の方から、こういったご相談をいただくことがあります。実のところ、私自身もブランディングを本気で学び始める前は、同じような感覚を持っていました。
「ブランディングって、名ばかりじゃない?」
この疑問の背景には、いくつかの要因が考えられます。実際にブランディングに力を入れてみたものの、思うような成果を感じられなかった企業には、共通した落とし穴が存在します。
今回は、これまでの経験の中で特に多く見られた5つの失敗要因について解説します。
これは、すでにブランド開発を終え、運用フェーズに入っている方にとっても重要なポイントです。
01 スタイル重視の嘘つきブランディング
ブランディングには、経営課題を解決する力があります。
しかし、ブランディング”だけ”取り組んでも課題解決には至りません。
例えば、「問い合わせ数を増やしたい」という目的でブランディングに取り組んだ場合、それだけで即座に成果が出るわけではありません。
もちろん、長期的に見ればブランドの確立が問い合わせ数の増加につながることもあります。
しかし、マーケティング施策や広告戦略と組み合わせてこそ、本来の力を発揮するものです。
それに、「とにかくおしゃれなデザインにしよう」「競合と差別化するために奇抜なビジュアルを作ろう」と、見た目ばかりにこだわる企業も少なくありません。
これがスタイル重視の誤ったブランディングの典型的なパターンなのですが、ブランディングに対して上記のような解釈をしていると、むしろ事業の成長が停滞する可能性すらあります。
ブランディングとは、「企業や商品の愛される理由を基点に、一貫したイメージをステークホルダーと共有し、共感や応援を生むための戦略や活動。」です。
そのためには、目的をしっかり明確にし、ビジュアルだけでなく、ビジョンや戦略、商品サービス、展開している場所、価格、PR、セールス、採用人事など…企業活動を構成するすべての要素と一貫したアプローチを取ることが欠かせません。
「ブランディングをやっても意味がなかった」と後悔しないためには、まず「何のためにブランディングをするのか?」「今解決したい問題や課題は何なのか?」を明確にし、その目的に合った適切なアクションを選択することが重要です。
02 深掘り不足による理解不足と言語化不足
ブランドづくりは、徹底的な理解から始まります。
理解すべき対象は、自社ブランド、顧客、競合など多岐にわたります。自社ブランドの理解だけでも、以下のような要素をしっかり深掘りする「腹落ち」させる必要があります。
- 自社ブランドはどこへ向かっているのか
- 自社は何のために存在するのか
- どのような独自の強みを持っているのか(他社との違いは)
- どのポジションで最も力を発揮するのか
これらの問いに対する答えが曖昧なまま進めてしまうと、「結局、何が変わったのか分からない」「何のための取り組みなのかわからない」といった事態に陥りがちです。
よくある失敗のひとつが、ブランドミーティングが単なる発表会で終わってしまうケース。
限られた時間の中で意見交換が十分にできず、誰かが言ったことをそのまま採用するだけでは、議論が深まりません。時間的な制約や参加メンバーの多さ、ファシリテーションの質など、さまざまなことが原因でこのような事態を招いてしまいます。
ブランディングは、まず自分たちが「体現」できなければ成功はありません。
だからこそ、「なぜ自社はこの価値観を大切にしているのか?」「いつも顧客に自社の特徴として説明しているこの強みはどのようにして育まれてきたのか?」「なぜあえてこの弱みは強化しないのか?」などを徹底的に深掘りし、メンバー全員が納得できる言葉を見つけていくプロセスにこそ意味があるんです。
ここをおざなりにしてしまうと、ブランド構築の過程で違和感が生まれ、後になって「やっぱり違う」と方向転換することになりかねません。
これは企業内だけの話ではなく、制作や運用に関わる外部のクリエイターにも当てはまります。
だからこそ、ヒアリングやディスカッションの場を大切にし、徹底した理解を深めることが重要なのです。
03 変化や継続できる体制ができていない
新しい何かを生み出し、最大の成果を得るには、何かを手放す決断が不可欠です。
また、戦略においても、必要なのは「何を捨て、何を選ぶか」。
過去に画家のピカソは「すべての創造の第一歩は破壊である」という名言を残しています。
また、Appleの創業者スティーブ・ジョブズも「古いものを捨てなければ、新しいものを作ることはできない」と言っています。
つまりブランドを成長させるための、破壊と創造はセットなんです。
時には慣習を壊し、人材の入れ替えが必要になることもある。
現状維持は、緩やかな後退に過ぎないんです。
もちろんやみくもに壊せばいいわけではなく、残すべきものと手放すべきものを見極め、慎重に進めることが大切。
とはいえ、人は無意識のうちに現状維持を望むもの。
なのでここをどう乗り越えるかが、ブランディング成功のカギになります。
社内が一番の抵抗勢力になることも少なくありません。
社長が変革の必要性やブランディング、マーケティングを理解し、プロジェクトを推し進めようとしても、社内の反発でプロジェクトが頓挫するケースを何度も見てきました。
本当にもったいない。 だからこそリコルクは、経営者の方と二人三脚でブランディングやマーケティングを推進することを大切にしています。
この前提を踏まえたとき、一番避けるべきなのは、水面下で進めること。 関係者の理解を得ないまま動けば、変化への抵抗は強まり、せっかくの取り組みが無駄になりかねません。
プロジェクトの初期段階から背景を共有し、納得感を持ってもらうこと。 そうした取り組みを事前に行なっていれば、最終的にはトップダウンで進めるのも十分アリだと思います。
04 手段ファーストの戦略運用
「とりあえずSNSを始めよう」「広告を打てば認知が広がる」「YouTubeをやれば売れる」──。
こういった手段先行のブランディングが、結果として事業の成長を阻害してしまうケースは本当に多いです。
流行っているから、競合がやっているから、手軽に始められるから。理由はいろいろあると思いますが、大切なのは「それが本当に自社にとって必要か?」を見極めること。
例えば、SNS運用がブランディングにおいて有効な手段であることは間違いありません。しかし、ターゲット層の多くがオフラインで情報収集をしている場合、そこにリソースを集中させるのは正解でしょうか?
また、「知り合いのデザイナーにロゴを作ってもらった」「とりあえずHPをリニューアルした」といったアプローチも、手段が目的化してしまった典型例です。
自社のブランドに合った制作者を見極めずに、見た目を整えたところで、ブランドの魅力は正しく伝わらないんです。
実際に、リコルクではこうした失敗事例を次に活かすために、あえて自社で特定のクリエイターを抱えず、マーケティングやブランディングに精通したディレクターのみで構成しています。
そうすることで、各課題に対して手段を固定化することなく、最適なメンバーを選定し、本当に必要な手を打つことができています。
05 多数決による意思決定
「できるだけ衝突は避けたい」「せっかくだから意思決定に参加してもらいたい」──。
こうした思いから、ブランドに関わる重要な意思決定を多数決で決めてしまうケースは少なくありません。
しかし、多数決は、結果として「無難な選択」に落ち着くことが多く、ブランドの個性を損なう原因になります。
もちろん、誰もが意見を言いやすい雰囲気は大切。
そして意見に耳を傾けて咀嚼にすることも大切。
でも、それは「全員の意見を均等に採用すること」とは違います。
たとえば、自社サービスのコンセプトを理解している人と、単なる好みで意見を述べる人がいた場合、その意見の重みは同じでしょうか?
「なんとなく違和感がある」「こうしたほうが良さそう」──。多数決では、こうした曖昧な意見が積み重なり、最終的にブランドの軸がぶれてしまうリスクがあります。
意思決定において大切なのは、「誰が決めるべきか」を明確にすることだと思っています。
ブランドの核となる部分は、顧客視点を持ち、本質を理解している人がリードしなければならない。
これはアンケートをとること自体が悪いと言いたいわけではないんです。
たとえ、賛成派が反対派よりも多かったとしても、Aを選択すべきなのにBを推す人が多かったとしても、最終的にはコンセプトを起点としたトップダウンが必要になる時もあるんです。
なので多数決の結果をそのまま意思決定に反映させることは極力避けていただきたいなと思います。
ブランディングはゴールが見えないからやらない?
「以前、会社としてブランディングに本腰を入れてみたけれど、正直、意味があったのかわからない。」
そんな相談を受けるたびに、悔しさを感じます。
ブランディングの本質は、企業の独自性を明確にし、それをマーケティング、デザイン、人事、セールスといったあらゆる企業活動と結びつけることにあります。
ただロゴを変えただけ、スローガンを掲げただけでは、本当の力は発揮されません。
「意味がなかった」と感じるのは、ブランディングに対する捉え方やプロセスのどこかに問題があった証拠。
成功に絶対の法則はないですが、失敗には共通点があります。
だからこそ、過去の失敗事例を知ることが、成功の確率を高めることにつながります。今回ご紹介した5つの要因を振り返りながら、自社のブランディング戦略を見直すきっかけにしていただければと思います。
そして、最後に。
「ブランディングはゴールが見えないからやらない」という声をよく耳にします。それはおそらく、効果検証がしにくいと感じているからでしょう。
でも、それ自体がよくある誤解のひとつ。
課題が明確になれば、注視すべき指標は必ず見えてきます。
・・・
兎にも角にも「ブランド化」には継続が欠かせません。
とはいえ、「ブランド化に向けた運用は何をすれば良いの?」というご質問もよくいただきます。
この点については、以前の記事でも触れています。ぜひご一読ください。
リブランディング実施後から、さらにブランド力強化を加速させるための方法
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級