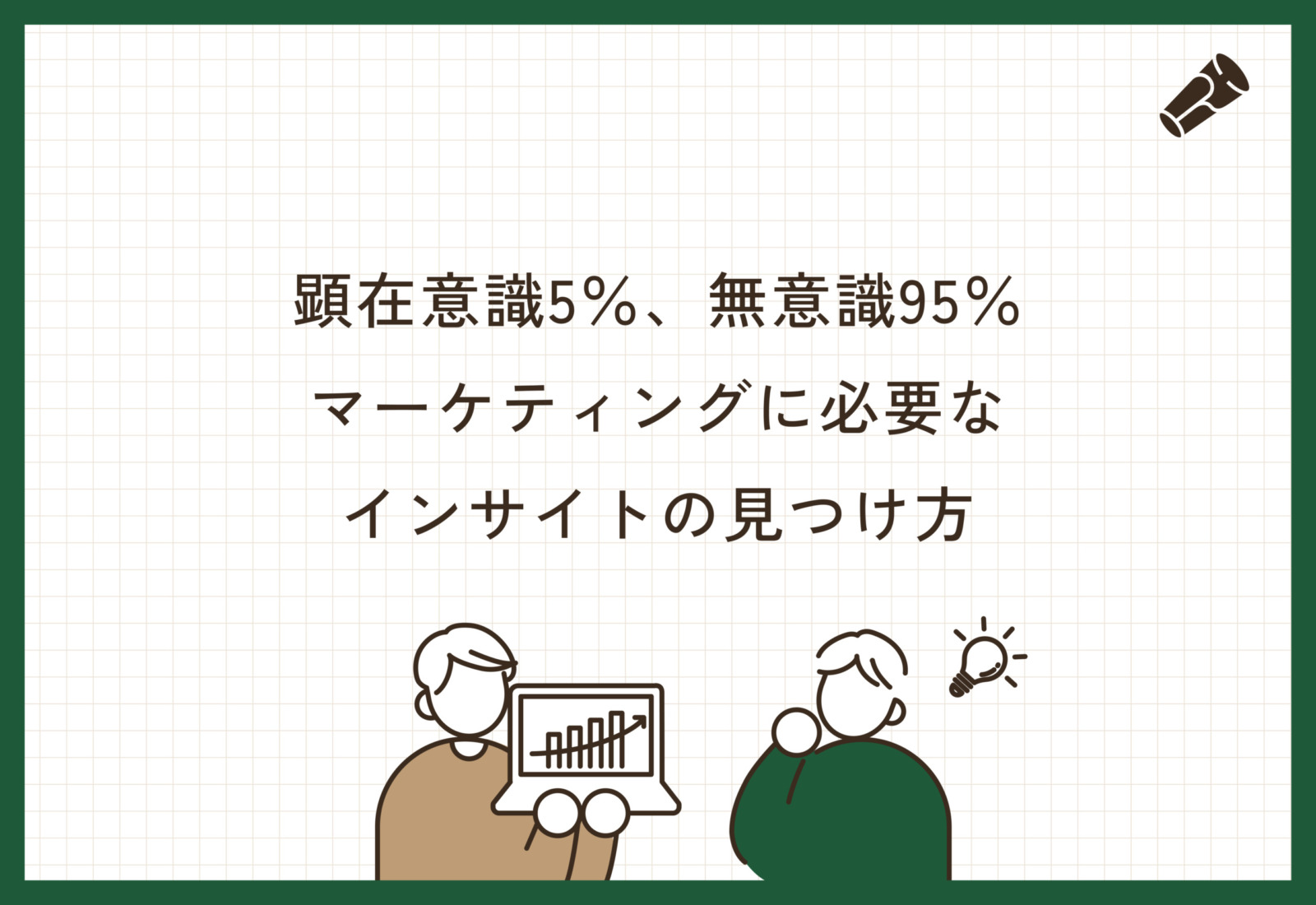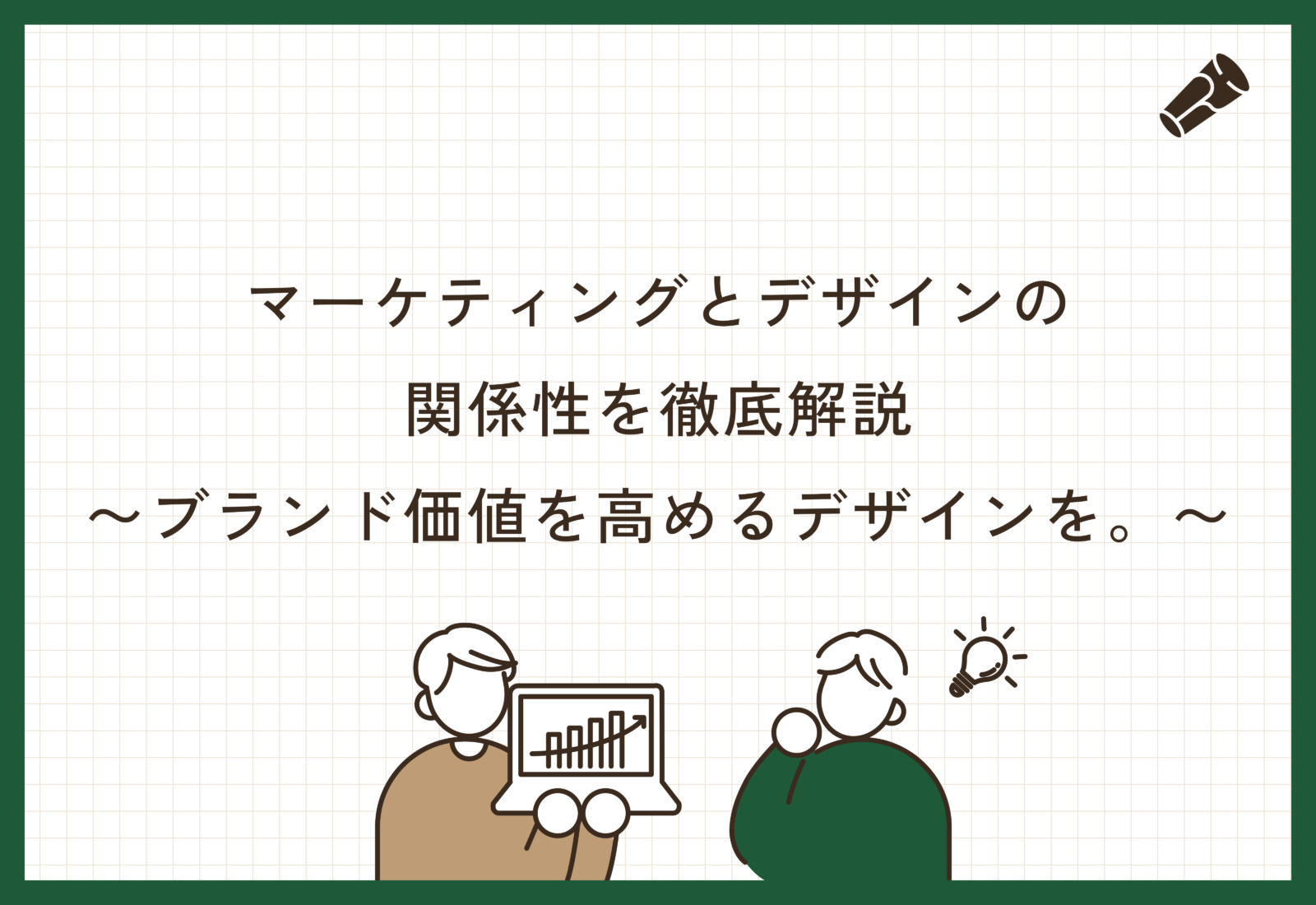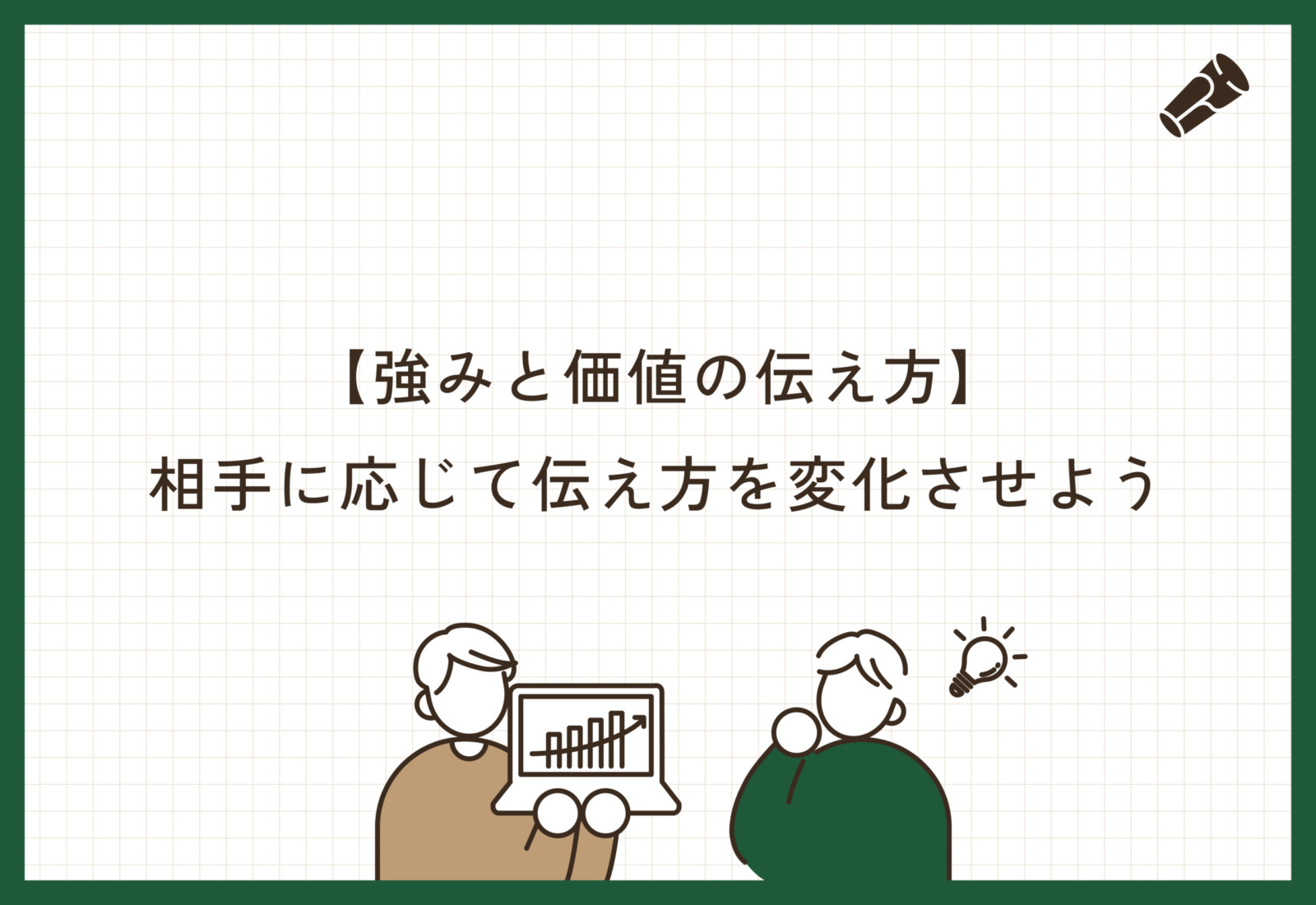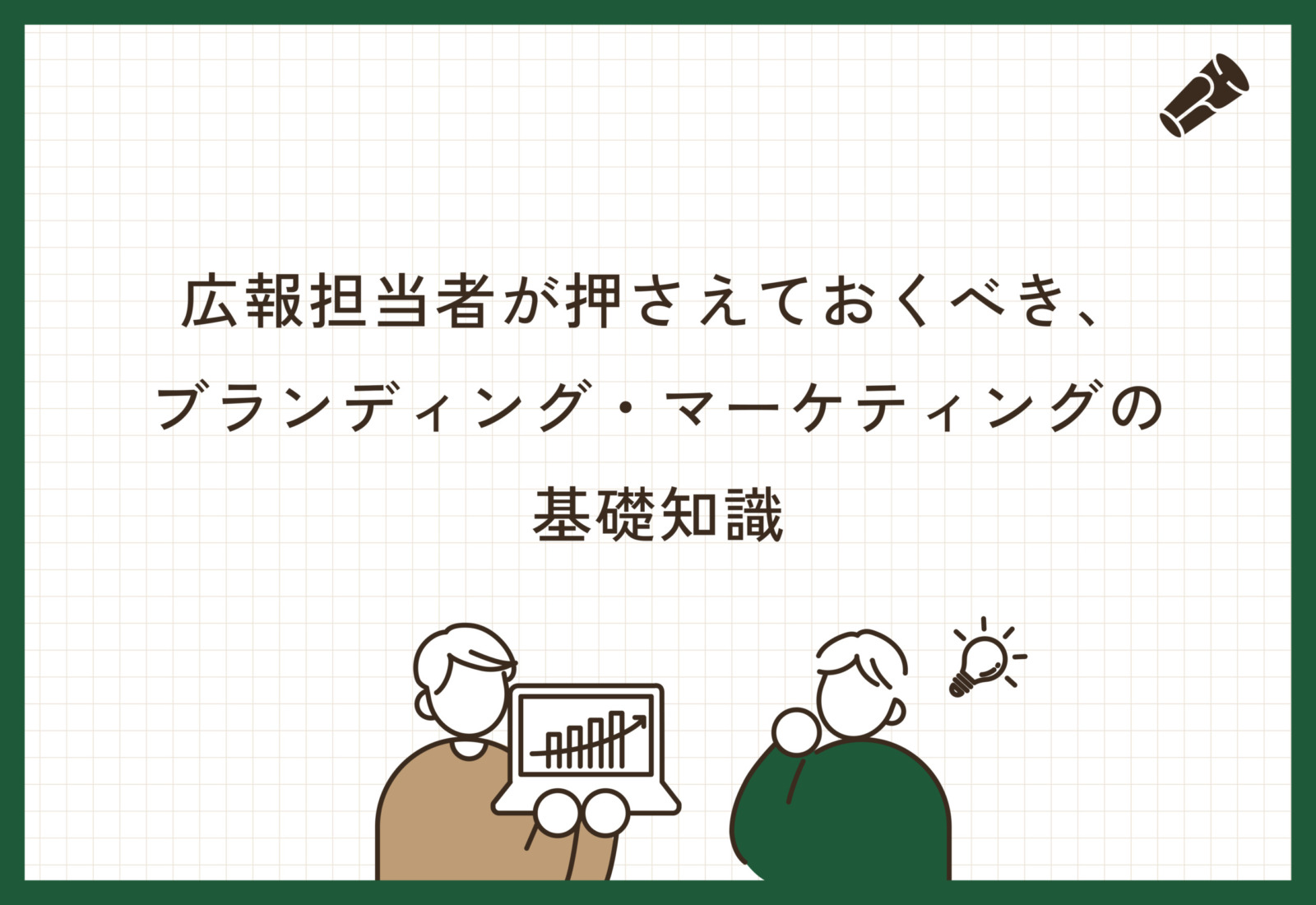Index
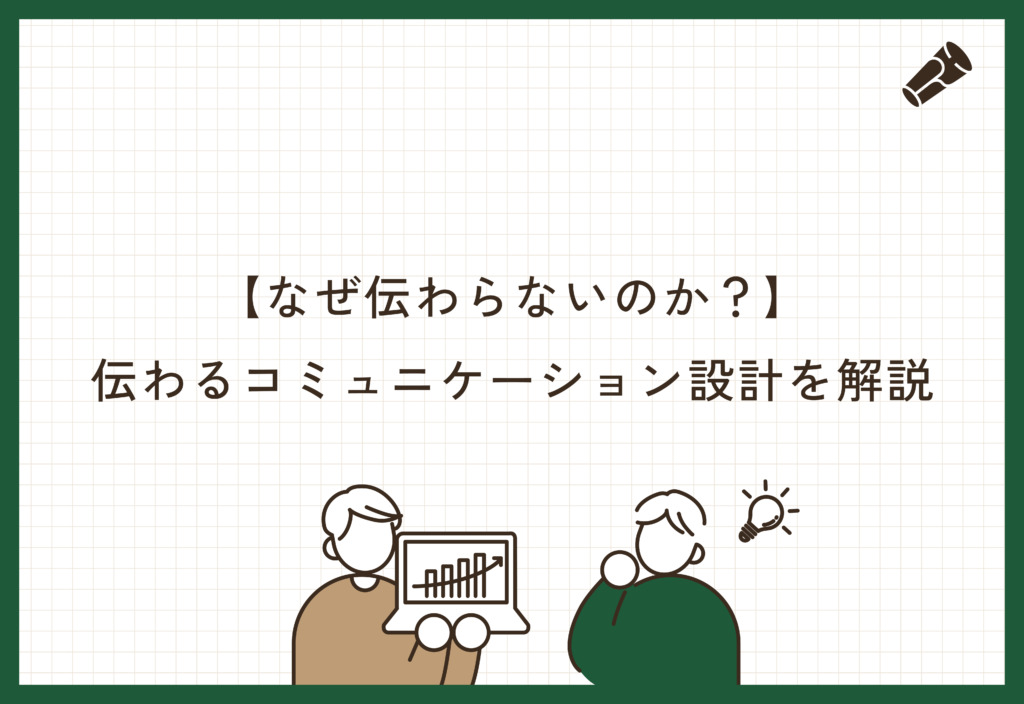
伝えたいことがうまく伝わらないのは、多くの場合、「文章力がない」「話すのが下手」といった理由が原因だと思われがちです。
確かに、それらの能力不足が伝わらなさにつながるケースも多々あります。
しかし、それ以上に重大で、多くのシーンで見られる本当の原因は、前段の設計にあります。つまり、実際に文章を書く前や話す前の段階に、大きな問題が潜んでいるんです。
私はかれこれ何年もコミュニケーションデザインに関わる仕事をしてきました。
コピーライティングをすることもあれば、広告やメディアで記事の企画を立てたり、コンセプトメイクも数えきれないほど行ってきました。
この仕事に「完璧」というものはないので、まだまだ思考も技術も知識も高めていかなければなりません。しかし、少なくともコミュニケーションによってクライアントからフィーをいただいているのは事実です。
そこで、今回の記事では、普段私がコミュニケーションを設計する上で気をつけているポイントをお伝えしたいと思います。
まずは基本に立ち返る
コミュニケーションは基本的に、以下の順序で組み立てます。
- WHO(誰に)
- WHAT(何を)
- HOW(どのように)
これはよく知られているフレームワークです。
この3つが明確に定義されていないコミュニケーションは、何をやっても伝わりません。もしこのフレームワークを知らなかった方がいれば、覚えておいて損はないと思います。
これ以降の話も、基本的にこのフレームに沿った(これらの項目を深掘りするような)内容になりますので、「誰のどんなニーズを満たすために、何を主なメッセージにして、どう伝えるのか」という設計の流れを常に頭の中に置いたまま、読み進めていただければと思います。
不満・不安・不便、ニーズを特定する
伝えたいことを伝えるためには、まず相手が「何を求めているのか?」を正確に捉えることが必要です。
情報発信の際、多くの人が「自分が伝えたいこと」ばかりにフォーカスしがちですが、受け手にとって価値がなければ、そもそも耳を傾けてもらえません。
特に、不満・不安・不便といったネガティブな感情は、人の行動を促す大きな要因となります。
例えば、
- 「毎朝の支度が面倒だ」と感じている人には、時短テクニックの情報が有益。
- 「新しいスキルを身につけたいが、何から始めればいいかわからない」という不安を持つ人には、具体的なステップを示したコンテンツが刺さる。
このようなイメージで、受け手の悩みを明確にし、それを解決する情報を提供することで、初めて伝えたいことが届くようになります。
何かを手に入れたい、役に立つ情報を収集したいというニーズは、基本的に何かしらの「不」があってこそ発生します。なのでまずは、ユーザーはどんな「不満不安不便」を感じているのかを洗い出してみることをお勧めしたいです。
話の結論を短くまとめておく
「結局、何が言いたいのか?」と思われた時点で、そこで試合終了です。
現代は情報があふれ、長々とした説明は敬遠されがちです。本当に伝えたいことは、一言でまとめておくに越したことはありません。事前に結論をシンプルに整理しておけば、それがタイトルになったり、最後の締めとしてインパクトを強めたりできます。
また、伝え手自身の思考も明確になり、コンテンツ全体に一貫性が生まれます。反対に、結論が曖昧なままでは、話が抽象的になり、遠回りなコミュニケーションになりがちです。
「結論を短く。本質を一言で。」それは、発信の軸をつくるということ。
この意識を持つだけで、「伝わる力」はさらに高まります。
全ての技術はあくまでも手段の一つでしかない
伝える手段は、言葉、デザイン、写真、動画…さまざまですが、それらはあくまで「手段」に過ぎません。つい目的を見失い、得意な伝達手段を選択してしまいますが、それは結果的に得意を不得意にさせてしまっています。
大切なのは、手段に振り回されず、目的を見失わないこと。
「このメッセージを伝えるのに、本当に言葉が必要なのか?」「写真は効果的か?」「デザインを加えることで、より伝わりやすくなるのか?」そんな問いを、一度立ち止まって考えてみてほしいです。
言葉よりも数字のほうが説得力を持つこともあれば、むしろ写真がメッセージの邪魔をすることもある。意外にも、伝え方をシンプルに削ぎ落としたほうが、より伝わる場面は多いんです。
手段はあくまでニュートラルに。
何を伝えるべきかを見極め、最適な形にすること。それが、本当に届くコミュニケーションにつながります。
誰が言っているのか?に目をむける
「何を伝えるために、誰が伝えるのが最も適しているのか?」を設計することです。
私は普段とあるブランドのメディアを運用していますが、企画段階で毎度必ずこの点を入念に設計しています。
もちろん、実際に文章に起こすときは「書くことが上手い人」が記事を書くわけではが、「実際にその発言をしている人」はまた別で設計しています。
大事なのは説得力。
情報のオーセンティシティ(信頼性)が高いほど、受け手は安心して耳を傾けるようになります。伝え手の立場やブランド力を活かすことも、伝達の重要なポイントです。
何事も腹八分目
「伝え切ること」にこだわりすぎると、かえって相手の理解を妨げることがあります。完璧さを追求しすぎるあまり、情報量が増えて受け手が飽きてしまうリスクが高くなります。
過剰な情報提供は、相手の集中力を失わせるだけでなく、要点がぼやけてしまうことにもつながりかねません。
一方で、あえて「もう少し知りたいと思わせるくらいの余白」を残すことで、受け手が興味を持ち、さらに深掘りしたくなる心理を引き出すことができます。
余白を意図的に作ることで、次のアクション—例えば、追加の情報を求める、質問を投げかける、次のステップへ進む—を促すことができます。
まずは伝えたいことを思う存分書き出してみてください。その後に必ず、話の結論に沿って腹八分目まで断捨離してください。
完璧な伝達を目指すのではなく、受け手にとっての「バランス」がとにかく大事です。
状況やシーンを想像し的確なタイミングと媒体で
情報を発信するときは、「相手がどんな状況で、どんな気持ちでその情報を受け取るのか?」を意識することが大切です。
たとえば、忙しいビジネスパーソンがスマホでサクッと情報をチェックする場面では、要点を簡潔にまとめ、リアルタイムで届く媒体を活用すると効果的。
移動中でも読みやすいように、短くインパクトのある表現を。
逆に、じっくり学びたい人には、ブログ記事やYouTube動画のように深く掘り下げられるコンテンツが向いています。
特に、朝や寝る前など、落ち着いて情報を吸収できる時間帯に読まれることを想定すると、より伝わりやすくなります。
相手の状況をイメージし、最適な伝え方を選ぶこと。それが、情報をしっかり届けるためのカギになります。
最も伝わる伝達手段とは?
言葉や映像、デザインなど、情報を伝える手段はさまざまですが、最も強力なのは「行動で示すこと」です。
誰の言葉だったかは忘れてしまいましたが、「自分が感銘を受けた素晴らしい何かを、第三者に最も魅力的に伝える方法は、それによって自分自身の行動が変わった姿を見せることだ」という言葉を読んだことがあります。
つまり、「言葉」と「行動」が一致していることこそ、最も説得力を持つのです。
そう考えると、私たちがやるべきことは二つ。
一つは、「一貫性のある行動を起こすこと」。もう一つは、日常の何気ない活動を振り返り、その価値を再解釈し、可視化することです。
多くの人は、日々の業務や小さな出来事にあまり価値を感じないかもしれません。
しかし、もし普段発信しているメッセージと行動が一致しているなら、その行動を意識的に可視化することで、着実に伝えたいことが伝わりやすくなります。
「行動を可視化する癖」はつけておいて損はないと思います。
最後に
誰かに何かを伝えるためには、ただ綺麗な言葉やデザインを並べるだけでは不十分です。
聞き手の心理状態、聞く準備ができているか、誰の言葉なら信頼できるのか──これらをしっかり設計した上で、適切な伝達手段を選ぶことが重要です。
もちろん、受け手がもともと興味を持っている前提で伝えられるケースもあります。しかし、多くの場合は、潜在的なターゲットに振り向いてもらう必要があるため、そのための「伝わる設計」が求められます。
今日の記事が、より効果的なコミュニケーションを考えるヒントになれば幸いです。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級