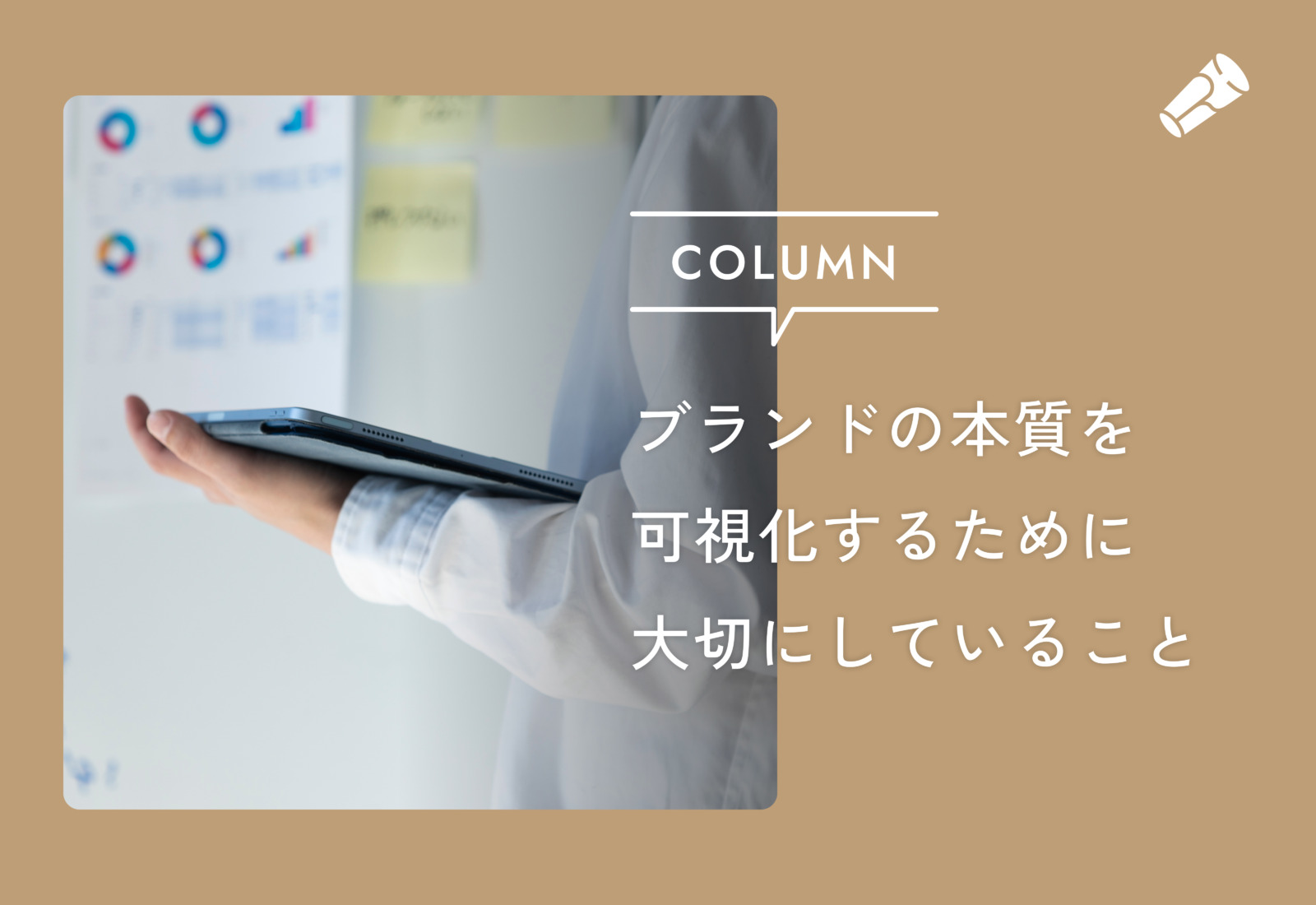Index
この記事では、特にお役立ち情報をお伝えするわけではなく、弊社のコンセプトに込めた思いや背景を率直にお話しします。最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
ブランディングやマーケティングに対して誤解をしていた時の話
「ブランディングなんて見せかけだ」「マーケティングは、ただ露出を増やし、言葉巧みに人を操って買わせる手法にすぎない」
かつての私は、そう考えていました。
実際、ブランディングやマーケティングは定義が曖昧な部分があり、本質を理解するまでに時間がかかるものです。
それに、私自身も以前、コンサルティングという形でブランディングやマーケティングの支援を受けたことがありますが、正直「今、自分たちは何に取り組んでいるのか」がよくわかりませんでした。
だからこそ、そう思っていたのかもしれません。
とはいえ、当時の私は、自社は何者なのか?という点や、自社の商品やサービスの独自性や特徴を、うまく顧客に伝えられていたとは言えませんでした。
セールスや接客をする際に抱いていた拭いきれない違和感
新規のお問い合わせに対する初回の打ち合わせや、既存顧客との商談の場で、とりあえず特徴を3つほど挙げてみる。
けれども、そのたびに「これは本当に特徴と言えるのか? 他社でも普通に実現しているし……」「確かに機能面では違いがあるけれど、それは顧客にとって本当に意味があるのか?」と、疑問やモヤモヤを抱えながら提案をしていました。
さらに、既存の商品やサービスに機能が追加されることで、結果的に値上げする流れにも違和感がありました。
なぜなら、顧客の立場になって考えたとき、「いやいや、その機能、特に必要ないんだけど」と本音では思っていたからです。
違和感はまだありました。
自社の独自性を、現場の人たちが自信を持って顧客に伝えられていないのに、広告やプロモーションにコストをかけることに何の意味があるのか?
それでは、穴の空いたバケツに水を注ぐようなものではないか。
そんなふうに感じていました。
なぜ、こんなにも弱みを強化することばかりが重視されるのだろうか?
集客面だけでなく、組織の在り方についても疑問を持っていました。
「なぜ、こんなにも弱みを強化することばかりが重視されるのだろう?」と、何度も考えたことがあります。
誰にでも弱みはあります。
それと同じように、誰もが強みも持っているはずです。
なのに、「あなたは、ここがあの人より弱いから、今後はそこを伸ばして、もっと幅広く業務をこなせるようにしよう」と何度も言われてきました。
もし、それが強みとの相乗効果を生むための弱点強化なら納得できたはずです。
しかし、当時の言われ方は「とにかく何でもこなせる人材になれ」と言わんばかりのものでした。
確かに、「何でもできるほうが、自分にとってプラスになるのかもしれない」と思い、幅広く学んでいましたが、どこか腑に落ちない感覚がありました。
なぜなら、当時、自分が伸ばそうとしていたのは「すでに誰かが圧倒的に強みを持っている分野」だったからです。
それなら、その人との連携を強化したほうが良いのではないか? そんなことを考えていました。
もちろん、幅広い知識を持つからこそ、自分とは異なる強みを持つ人をより理解できるようになり、相手からの意見も尊重できるようになります。
ただ、すべての業務をたった一人が担うことには、どうしても大きな意味を見出せませんでした。
こうした疑問や違和感を拭うために、膨大な書籍を読み、何度も仮説を立ててあらゆることにトライしていきました。
そして最終的に「これが最も重要な概念だ」と辿り着いたのが、かつては疑いの目を向けていた、ブランディングやマーケティング戦略でした。
先ほど挙げた違和感や疑問をすべて払拭するには、ブランディングやマーケティングの本質をさらに深く追求しなければならない。そう気付いたことが、このキャリアを歩み始めたきっかけです。
すべて強みの上に築いていく
「現代経営学の父」とも称されるピーター・ドラッカーは著書『経営者の条件』の中で以下のように述べています。
「Build on your strength(強みの上に築け)」
「人は強みによって雇われる。弱みによってではない。」
また別の書籍では以下のようにも述べています。
ピーター・ドラッカーの著書 『ドラッカー名著集 組織の論理』より再び引用します。
「組織とは、強みを成果に結びつけつつ、弱みを中和し無害化するための道具である。」
私はこの言葉と出会ったとき、それまで感じていた違和感が一気に解消されるような感覚になりました。振り返ってみると、物事がうまく進まない原因の多くは、強みを無視していたことにあったように思います。
- 強みを無視してあれもこれもやろうとするから、いつしか独自性が見えづらくなる
- 強みを明確に整理できていない状態で、プロモーションを優先するから、期待値がブレ、新規顧客がリピーターにならない。
- 自社の強みと顧客ニーズの接点が不明確だからこそ、オーバースペックな商品サービスが生まれて売れなくなる。
- 人の弱みばかりを指摘するリーダーやマネージャーがいるから、チームのメンバーも強みを活かそうとしない。
ブランディングやマーケティングという戦略、考え方はこうした状況をすべて解決する力があります。
なぜなら、ブランディングやマーケティングは、先ほど書いたドラッカーの考え方に基づいているからです。
掛け算を生み出す会社 〜”肩組んで”の意味〜
話がガラッと変わりますが、弊社のコンセプトには、「肩組んで」という言葉が含まれています。
これまで私は、店舗マネジメントや新規事業の立ち上げなど、さまざまな役割を経験してきました。
その中で、どのタイミングだったかは忘れてしまいましたが、「理想的なチームとは何だろう?」「面白いアイデアが次々と生まれ、すぐに実行に移せるチームはどうやって作るのだろう?」と考える時期がありました。
そんなとき、ふとこれまで関わってきたチームを振り返り、「あのチームは無敵だったな」「あのチームにいた時は本当に楽しかった」と感じたチームがあったか?と自分に問いかけてみたところ、いくつかすぐに思い浮かびました。
当時、それらのチームの特徴を整理したメモがあるので、そのまま記載します。
- それぞれが「自分にできること」を精一杯こなし、苦手なことは思い切って任せている
- できるはずのこと、得意なことに対して怠慢が見られたときは、スタッフ同士でしっかり指摘し合える
- 相手へのリスペクトが大前提としてある
- 遠慮をしない
- 仲間の得意領域についても理解しようと努める
- すべてをやり切ったあと、みんなで思いっきり飲みに行く(おまけ)
そして、そんなチームに所属していたときは、「自分とは真逆の特技・特性を持った人と働いているときが、いちばん楽しい!」と心から感じていました。
よく「楽しいと思える仕事をしよう」という言葉を耳にしますが、そこには前提があると考えています。
楽しい仕事とは、成果を出せる仕事であること。
成果を出せるからこそ、仕事は楽しくなる。もし「楽しい」が先に来てしまうと、それはいずれ「やりたくない仕事」に変わってしまうのではないでしょうか。
これまでの経験上、自分とは真逆の特技・特性・独自性を持つ人と働いているときこそ、最も成果を出せていました。
そして、仕事が楽しくなっていました。
もちろん、自分と似た特技を持つ人と仕事をするのは気楽です。意見も合いやすく、コミュニケーションのストレスも少ない。
ただ、そういう環境では、案外何も生まれなかったりします。
一時期、大きな成果を出せているわけでもないのに、なぜか忙しさだけが増していた頃がありました。そのとき私は「自分がもう一人いたら…」と考えていました。
でも、今振り返ると、それは誤った発想だったように思います。
「自分がもう一人いたら…」と考えているからこそ、何も生み出せずに忙しくなっていた。
なので、「肩組んで」という言葉には、単に仲良くしようという意味ではなく、互いの強みやクリエイティビティを掛け合わせ、その相乗効果で想像以上の成果を追求していこうという思いを込めています。
つまり、リコルクは、クライアントやパートナー会社の方との「掛け算を生み出す会社」です。
事業やモノづくりに情熱をそそぐ経営者の方と。
ここでリコルクのブランドコンセプトを紹介させてください。
モノづくりに情熱をそそぐ人と
肩組んで、越えていく。
独自の強みや価値を最大限に活かし、それを別の何かと掛け合わせて生まれる相乗効果は、ブランドの成長や社会全体の発展に欠かせないと考えています。そのため差別化を目的とせず、情熱の奥にひそむ独自性を起点に物事を推し進めます。
複雑で気が遠くなる課題も、絶えず問われる変化も、それぞれの固有の価値を活かし、掛け合わせることで乗り越え、新たな価値と繋がりを築く伴走を行っていきます。
このコンセプトの意味は、これまで散々書いてきたので何となく意図が伝わっていると嬉しいです。
他社や他者との「違い」を受け入れ、自社や自分の「弱みや強み」も受け入れた先に、本当に面白いものがあり、人が惹きつけられるブランドが築かれていくと考えています。
一人でやる方が効率的で早いかもしれないし、現状を維持する方が安心です。ただ、私たち自身も、そのいずれの道も取らないことに決めました。
クライアントと共に素敵な商品サービスを届けつつ、この事業を本気で成長させていきたいからこそ、共同代表という体制をとりつつ、自社のブランド開発プロジェクトにも多く方にご協力いただきました。
そして、私たちがブランディングやマーケティング、コミュニケーションデザインを生業にし、経営者さんに伴走しているのは、
- 独自性や強みといった魅力を、丁寧に掘り起こし、伝えること。
- ブランド本来の価値を、多角的な視点から捉え直すこと。
- デジタルを駆使しながらその価値を届け、指名買いを増やすこと。
これらに対して、別の視点を取り入れたい方や、苦手意識があったりリソースが不足している方には、その部分をお任せいただき、一緒にブランドを強化していきたいと考えています。
その結果、商品やサービスが多くの人々に届き、喜んでいただけることができたら、最高じゃないですか。
内製化を進めるべきか、外部との連帯を強化すべきか
でもそうすなると「戦略クリエイティブ、広告、PR活動等の内製化を進めない方が良いのか?」という疑問が湧いてくると思います。
あくまでも私個人の考えですが、もし今は別の業務をしているものの、上記の分野に強い興味・関心があり、「今後は専属でその分野を担っていきたい」という人材が社内にいる場合、内製化を進めることに意味があると思っています。
現時点ではまだブランディングやマーケティング、PR活動などを本格的に任せることができないかもしれませんが、そんな方は今後企業にとって非常に重要なキーパーソンになるはずです。
なので未来への投資として育成し、少しずつ内製化を進めていくべきだと考えます。
実際に弊社にもそういった経緯で内製化支援のご相談をいただくケースはよくあります。
一方で、もしそのような人材がまだ見つかっていない場合は、無理に内製化を進めても、結局は思ったような結果には繋がりません。
それどころか、遠回りをしてしまうだけなんです。
やっぱり、「強みの上に築く」ことが大事ですし、それが一番トラブルが少なく、生産性の高いチームへと繋がると思います。
最後に
有形無形関わらず、事業に情熱をそそぐ経営者の方、未来を見据えクリエイティブな一歩を踏み出す全ての人と、肩を組みながら、あらゆる課題を突破していけたら嬉しいです。
そのために私たちは、それぞれの独自性や強みを活かし、相乗効果を生む伴走を行っていきます。
▼弊社のビジョンやミッションに関する情報は以下で紹介しています。ご興味がありましたら併せてお読みいただけると嬉しいです。
RecorCの経営理念
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級