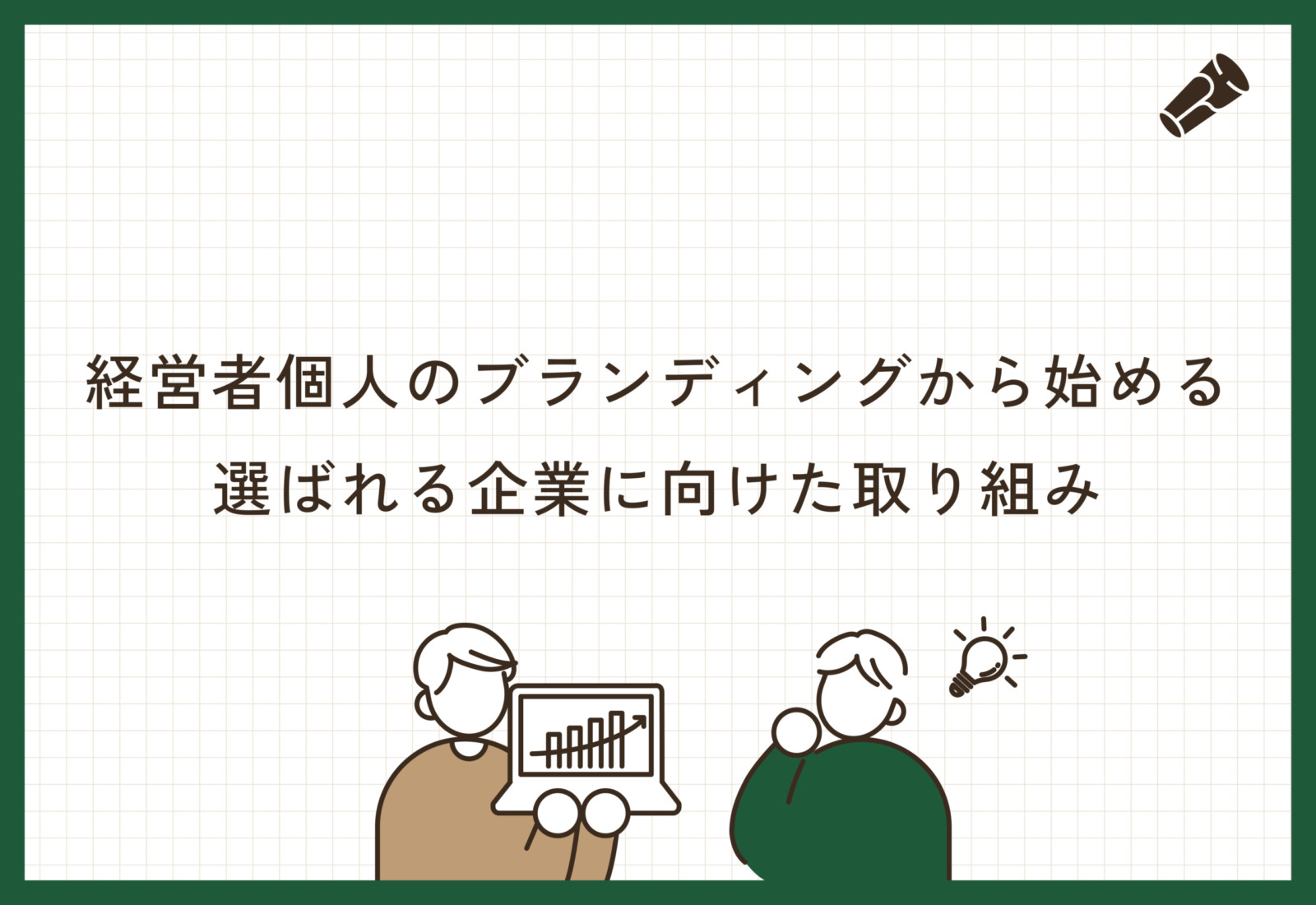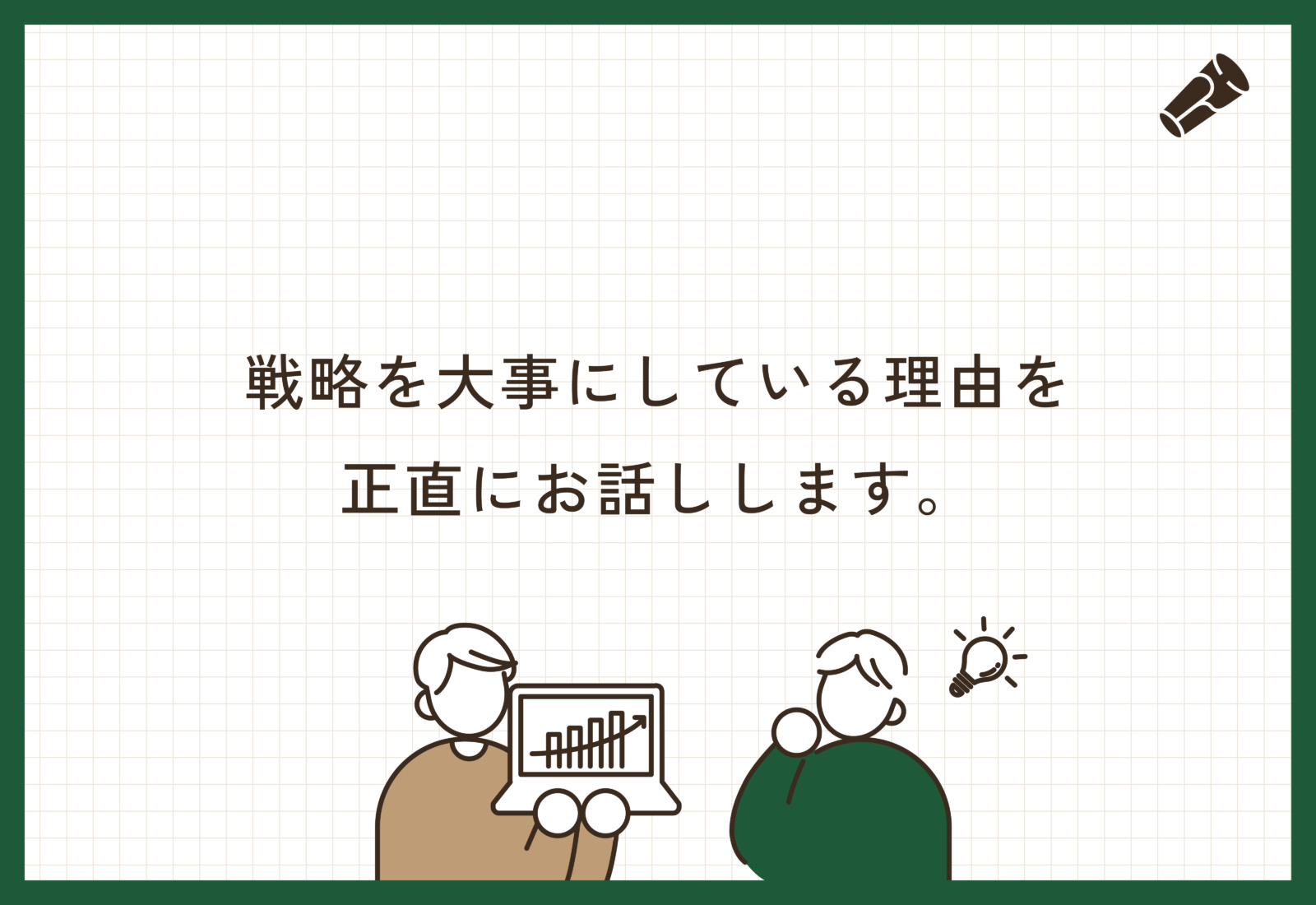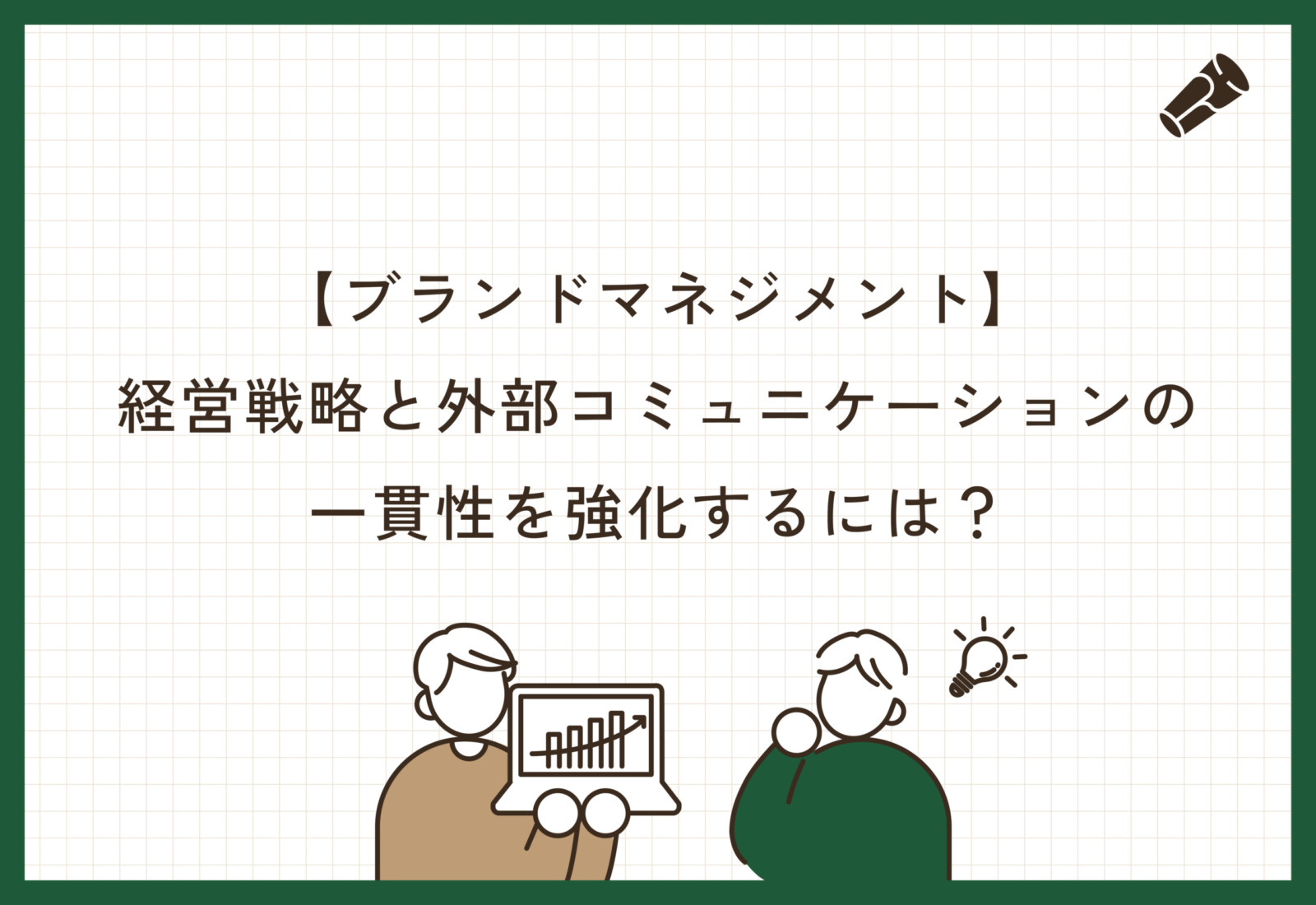Index
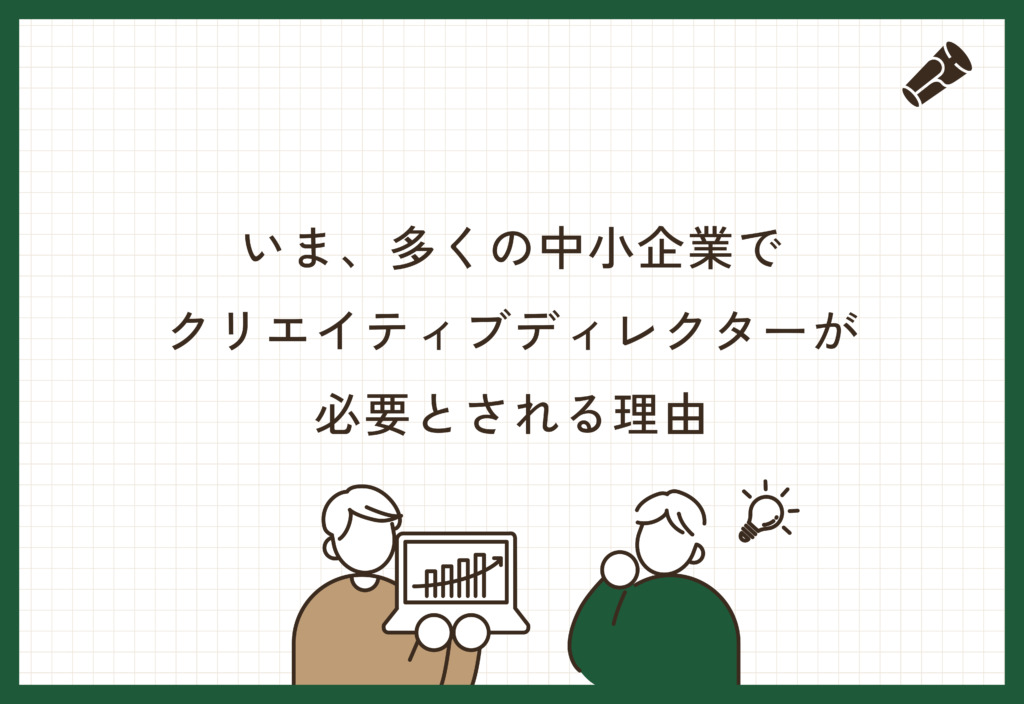
クリエイティブディレクター(略して、CD)を名乗る人々は、普段どんな業務をこなし、どんな価値を提供してくれるのだろう?
現在、私は「ブランディングディレクター」または「クリエイティブディレクター」という肩書で日々活動し、中小企業の経営者の方々とお仕事をしています。
そのため、日常業務の大半が「クリエイティブディレクション」です。
そこでこの記事では、普段私自身が担っている役割や仕事内容を紐解きながら、クリエイティブディレクションという技術について解説していきたいと思います。
各章ごとにクリエイティブディレクションに関する様々な定義が出てきますが、多少表現が違えど本質的には言っていることは同じです。
ですので、あらゆる角度から捉えていただけると嬉しいです。
「クリエイティブディレクター」や「クリエイティブディレクション」という言葉自体は聞いたことがあるけれど、実際に何をする仕事なのか、どんな役割を担っているのか、まだ少しふわっとしている。という方は、ぜひ最後まで本記事をご覧ください。
クリエイティブディレクションとは?
まずはAIに聞いてみました。
クリエイティブディレクション(Creative Direction)とは、ブランドやプロジェクトのビジュアル、コンセプト、アートワーク、メッセージ性を統括し、全体的なクリエイティブな方向性を決定する役割を指します。この役割には、デザイン、広告、映像、ウェブ、製品開発など、さまざまなメディアや表現方法におけるクリエイティブな指針を示し、プロジェクトが一貫性を持ちながら完成するよう導くことが含まれます。
とのこと。
これを読むだけで何となく何のための仕事なのかが見えてきます。
ただ、これだけで終わらせてしまっては面白くないので、もう少し深掘りしていきたいと思います。
ブランディングプロジェクトでは実際に何をしているのか。
これは実際に普段私がやっていることでもありますが、大きく分けると以下の内容です。
- 各プロジェクトにおけるゴール設定
- 各プロジェクトにおけるルールづくり
- 阻害要因の抽出・根本的な課題の特定
- ブランド戦略・コンセプト設計
- プロジェクトメンバーへのイメージ共有
- キャンペーンやコンテンツ制作の企画・アイデア開発
- クリエイターマネジメント
- 制作物の精度向上、クオリティ管理
- 次プロジェクトの立ち上げ
かなりざっくりとしていますが、上記6つが主な仕事です。
責任の範囲や領域がかなり幅広い仕事です。
クリエイティブディレクションを活かす場所は広告分野に留まらず、商品・サービス開発や店舗開発、さらには組織開発(インナーブランディング)の現場など、さまざまな場所に顔を出す存在です。

クリエイティブディレクターとデザイナーの違いを深掘り
実際にブランディングの現場でクリエイティブディレクションという技術がどんな意味を持つのかについて。
結論からお伝えすると、「これまでうまく伝えきれなかった価値、潜在的になっていた価値が、コストを最小限に抑えながらも伝わるようになる」。
これに尽きます。
少し話が逸れますが、単に制作物が欲しいからという理由でデザイナーに直接制作物の作成を依頼するケースが見られます。
しかし、多くの場合、このようなケースで想像以上の成果が得られることは、ほとんどありません。
なぜなら、デザイナーは依頼の目的やブランドの伝えたいことに合わせて制作するプロだからです。
どういうことかというと、デザイナーは、「なぜその制作物が必要なのか?」「その制作物は誰に向けて、何を伝えたいのか?」といった前提部分を設計するプロではないんです。
稀に、この点も相談に乗ってくださるデザイナーがいらっしゃいますが、ごくわずかです。
ただ、そのような方でもデザイナーとしての仕事をしながら、クリエイティブディレクションも掛け持ちしているはずなので、おそらく大半の時間は制作よりもディレクションに費やしているはずです。
つまり、クリエイティブディレクションという技術、スキル、職業は、「ブランド戦略やマーケティング戦略に沿って、“伝わる”をつくるための全体設計と制作物のクオリティ管理」を担っているということです。
これは、「ブランド」という捉えどころのない存在を、どのように輪郭を描き、ターゲットの記憶に残すかというブランドマーケティングのミッションにとって、これは欠かせない領域です。
クリエイティブディレクションが機能しないとどうなるのか
では、ブランディングプロジェクトにおいて、クリエイティブディレクションが機能しないとどうなるのでしょうか?
先ほど、クリエイティブディレクションがなければ「想像以上の成果が得られることは多くない」とお伝えしましたが、もう少し掘り下げてみたいと思います。
あらゆる制作物やブランディング・マーケティング施策に多くのコストをかけたにもかかわらず、イマイチ成果が得られない主な理由は、以下のいずれかに起因しています。
- 誰のどんなニーズに対するアプローチなのかが曖昧
- 結局何を伝えたいのかが曖昧
- 狙っている場所が小さすぎる(狭すぎる)
- 情報発信する場所やタイミングが適していない。
- コピーとデザインに一貫性がない
- 情報過多。
- 事実に基づいたコミュニケーションになっていない。
- 受け手の感情の流れに沿った話の流れを組めていない。
- 意外性、新規性、信頼性(説得力)、独自性が欠けている。
- 受け手にメリットやベネフィットを提示できていない。
など…
そして上記のような伝わらない要因は、以下のような根本的な原因も潜んでいます。
- 目的が不明確。
- 施策や制作物のゴールイメージが湧かない。
- 自社の強みや可能性に気づけていない。(腹落ちしていない)
- チームメンバーのそれぞれが好みで意見を出し合っている。
- 客観的(顧客視点で)に制作物や施策をチューニングできていない。
- 「もっとこうして欲しい」を依頼主がうまく言語化できない。
- 「こういう意図がある」をデザイナーがうまく言語化できない。
- 落とし所や第3案を見つける人が不在。
- チーム内に個々の強みを引き出し、掛け合わせるコミュニケーションが存在しない。
- クリエイティブやコンテンツにまつわるルールがない。
など…
心当たりがある方もいらっしゃると思います。
こうした要因によって、コストや戦略を無駄にしてしまうケースは本当に多くの場面で見受けられます。
ただ、このようなことが起こってしまった場合、主にクリエイティブディレクションを担う人がそのプロジェクトに不在だと、誰も責任を追うことができません。
▼「クリエイティブやコンテンツにまつわるルールがない。」という方に向けてクリエイティブガイドラインの役割や作り方を記事にしてありますので、よければご覧ください。
クリエイティブガイドラインをつくる目的とは?作り方と策定内容についても解説

それでもなぜクリエイティブディレクションにコストをかけないのか
これまでご一緒してきたクライアントに対し、なぜプロジェクトにクリエイティブディレクションを導入してこなかったのか、アンケートを取ったことがあります。
その理由のベスト3が以下です。
- クリエイティブディレクションという存在自体をあまり詳しく知らなかった
- 初期コストを抑えたかった
- 身近にいる頼みやすいクリエイターに依頼していた
1つ目はおいといて、2つ目と3つ目に関しては本当に勿体ない話です。
その理由は、そもそもの目的を見失ってしまっているからです。
本来、「つくる」という行為は、伝えたいことがあってこそ生まれるもの。
つまり、伝えるべきことを伝えて”成果を得ることが目的”のはずです。
それにもかかわらず、初期コストを抑えることや、手間を省くために頼みやすい人に仕事を依頼することが目的になってしまうと、「つくる意味がない」のと同じです。
「もっと早くここに気付けていたら…」とおっしゃる方も少なくないほど勿体ないことなので、今後もしそういった場面に直面した際は、ぜひこの話を思い出していただけたら嬉しいです。
千利休の事例から学ぶ、”伝える”の本質
千利休が提唱した「侘び寂び」は、当時主流だった豪華な茶の湯に対して、「質素で無駄を省いた美を追求する」新たな価値観を生み出しました。
この価値観は、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを重視し、日常生活の美的感覚に大きな変化をもたらしました。
利休は、「不完全で美しいもの」や「使い込まれた茶碗、自然に変化する風景」に美を見出し、これを茶の湯に表現しました。
この質素さが新しい美の基準を作り出したのです。
また、利休は茶室の設計にもこだわり、ここでも無駄を排除しつつ、あえて茶室の入口を低くし、客が頭を下げて入る動作を強いられるように設計しました。
これにより、非日常的な空間が作り上げられたのです。つまり、「侘び寂び」という考え方のもと、茶を存分に楽しむための最適な空間が演出されたわけです。
利休が行っていたことをまとめると、
- 自身の物の見方や視点を変え、価値を再定義した。
- 常識を疑い、新しい価値や意味を体験やビジュアルに落とし込んだ。
- 人の感情の流れを想像し、あらゆる接触ポイントから新しい価値を上手に伝達した。
これらは現代のクリエイティブディレクションにも通じています。
そしてこれは、大きなコストをかけて実現した話ではありません。
たった一つの考え方、捉え方、企画アイデアのもと、あらゆる要素を見つめ直し、”引き算を徹底的に行い、”多くの人に価値を伝えた事例です。
この点こそ、中小企業にクリエイティブディレクションが必要な理由だと考えています。
中小企業にこそ必要な考え方、技術である
ここまでの話で、クリエイティブディレクションの重要性をご理解いただけたかと思います。
これまでの話を踏まえ、クリエイティブディレクションの役割を一言でまとめるならば、「新たな価値を伝えるための指針や着眼点を明確にし、無駄を省きながらも、細部までブランドを宿す役割」を担っています。
言い換えると、「ブランドのビジョンやブランディング・マーケティング戦略の本質を見抜き、言語化し、その方向性を示しながらビジュアルや施策に落とし込むためのディレクション」です。
以前、戦略に関する記事を書いた際に、その中で「大企業に比べてリソースに限りがある中小企業こそ、戦略の重要性が高い」と書きました。
▼以前書いた、「戦略そのもの」について解説した記事です。
https://recorc.com/media/strategy-importance/
現代は情報があふれ、回りくどい表現や嘘っぽい表現、そして丸く収まった情報や表現が敬遠されがちです。
つまり、莫大なコストをかけて大量に情報を流すか。
それとも、独自性のある研ぎ澄まされた情報でないと伝わらない(情報が届かない)のです。
だからこそ、私たちのような中小企業は、大企業以上に、戦略や独自性基点で”伝わる”を設計・企画をする必要があります。
こうした背景により、年々中小企業の中でもクリエイティブディレクションの重要性が高まり、その需要は膨れ上がっています。
まとめ
繰り返しになりますが、クリエイティブディレクションとは、単なるデザインの管理や指示を超え、ブランドやマーケティング戦略の本質を捉え、それを一貫したビジュアルや施策に落とし込むための技術です。
そして、この技術を活かすためには、「徹底的に社会・顧客・ブランドを理解すること」は欠かせません。
この記事では、さまざまな角度からクリエイティブディレクションを定義し、その業務内容についてご紹介してきましたが、その根本にあるのは「聴くこと、想像すること」です。
本記事を通じて、クリエイティブディレクションの価値や重要性を少しでも理解していただけたなら幸いです。
※ちなみに、私のX(旧Twitter)アカウントでは、クリエイティブ、ブランディング現場での気づきを日々言語化しています。興味がある方はぜひご覧ください。
https://x.com/hagimaru31
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級