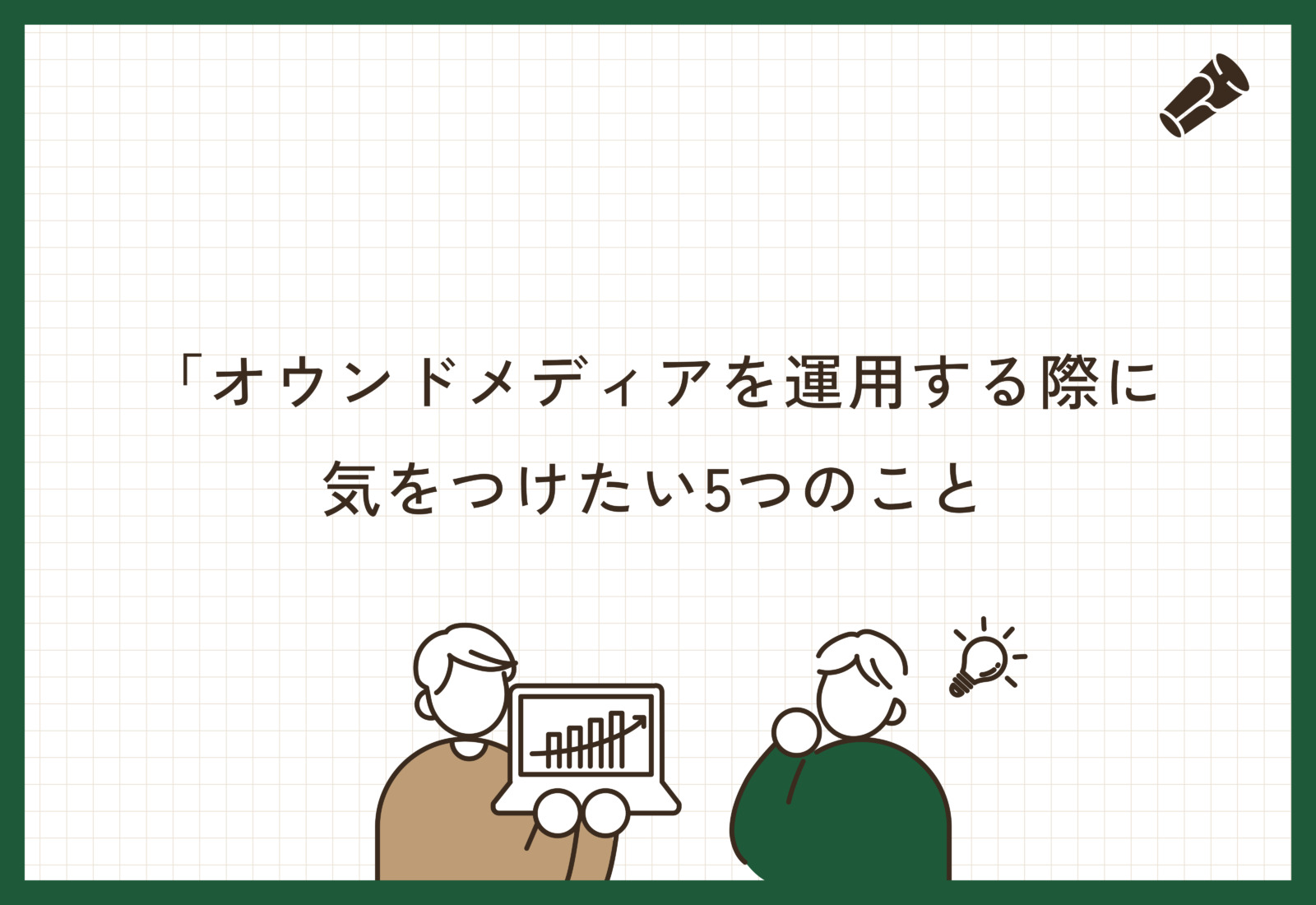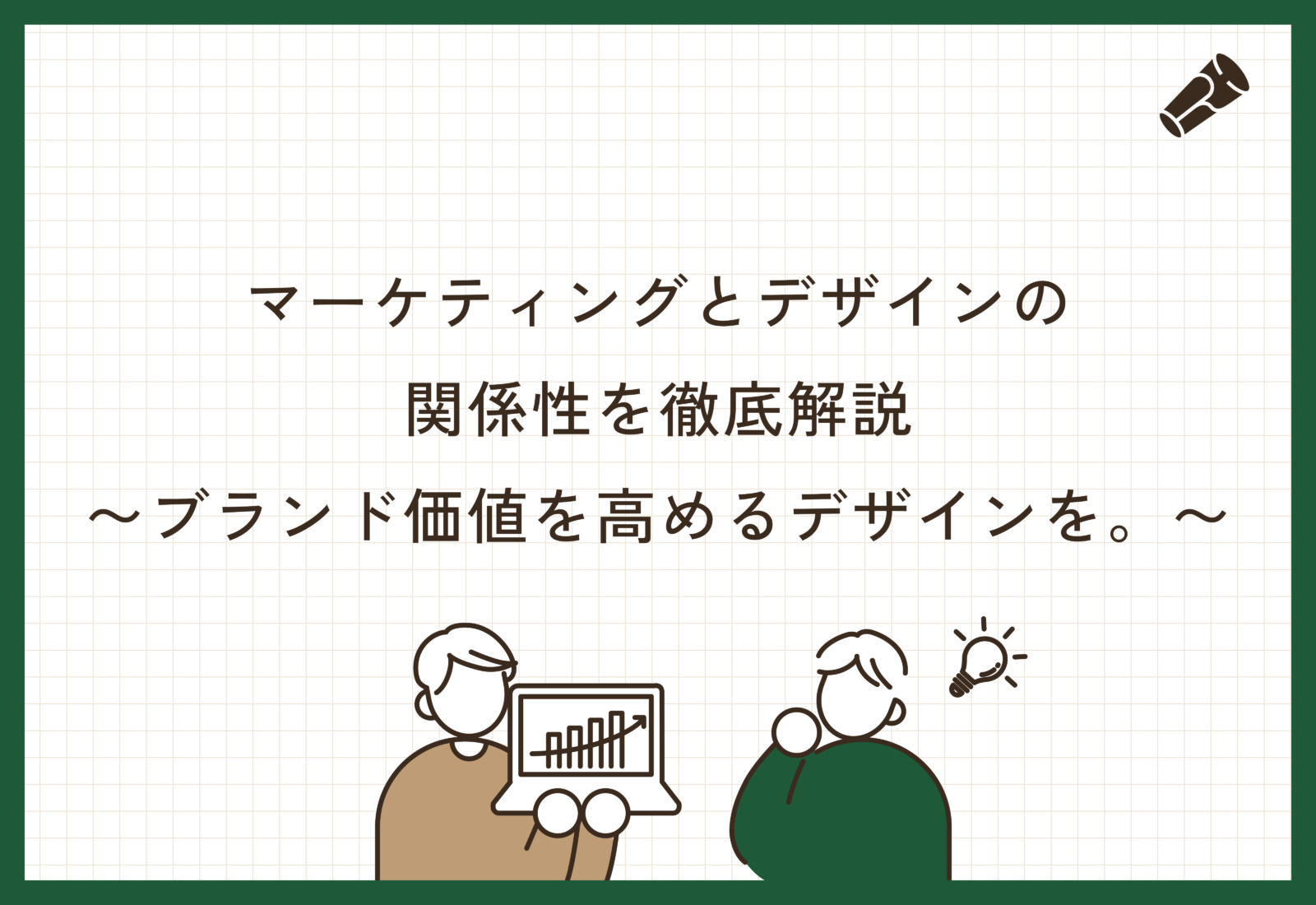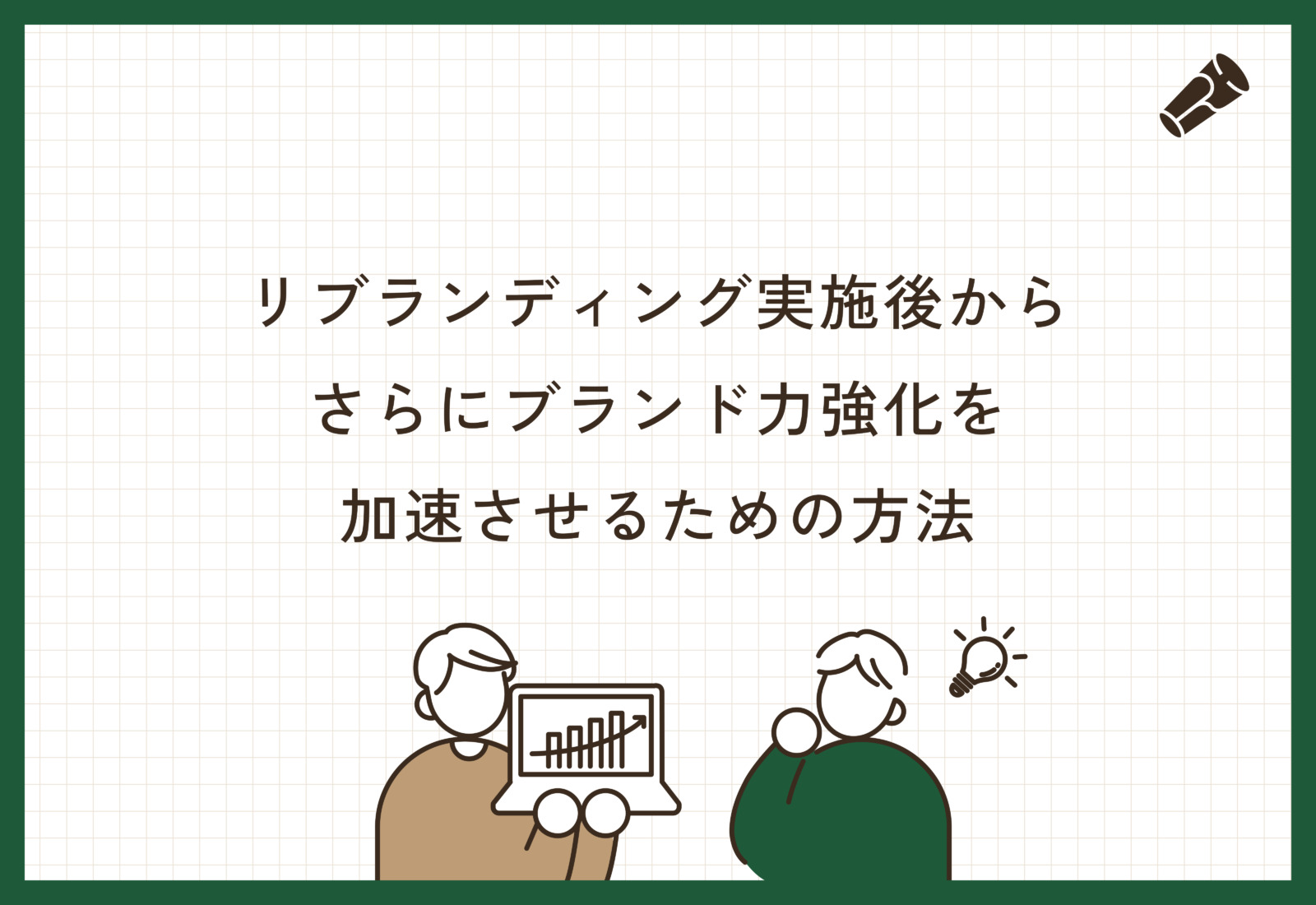Index
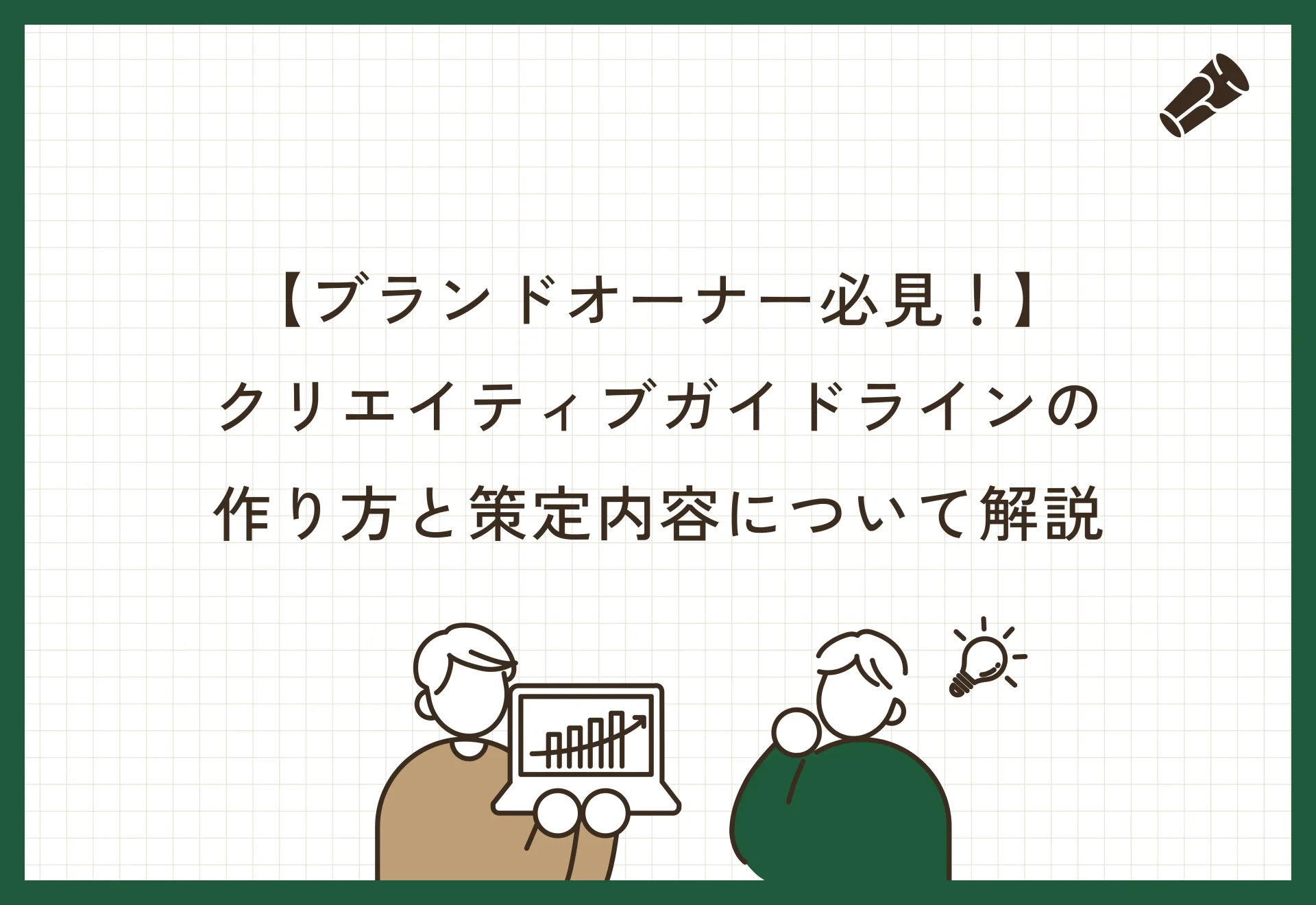
「作ってる販促物が、自社らしくない気がする」
「フォントやカラーの選定が感覚頼り」
「独自性があるはずなのに見た目では伝わってこない」
「出来上がったデザインがいまひとつ印象に残らない」
そんなモヤモヤを抱えているなら、まず取り組んでいただきたいのが“クリエイティブガイドライン”の整備です。
実は、「うちはブランディングに力を入れている」と公言する企業であっても、このガイドラインがきちんと整っていないケースは、驚くほど多い。
ですが、私たちの結論ははっきりしています。クリエイティブガイドラインは、必ず作るべき。
この記事では、その理由を具体的に紐解きながら、どんなステップでガイドラインを作っていくかについても詳しく解説していきます。
クリエイティブガイドラインの役割とは
ブランドを“伝える”ことは、思っている以上に繊細な作業です。
同じ言葉でも、見せ方ひとつで伝わり方は大きく変わります。
だからこそ、言葉・色も含めたブランドスタイル全体をどのように扱うかを、あらかじめ定義しておくことが大切です。
そこで必要なのが「クリエイティブガイドライン」。
これは単なるデザインマニュアルではなく、ブランドを正しく扱うための説明書のようなもの。
ブランドの世界観、トーン、使用する色やフォント、写真の質感までを明文化することで、誰が関わっても同じ方向に進める状態をつくります。
例えば、テレビやパソコンなどの精密機器には必ず取扱説明書がついています。
誤った操作をすれば壊れてしまうこともあるし、そもそも正しい使い方をしないと、その製品が持つ性能を十分に活かせません。
ブランドもそれと同じ。
表現に一貫性がなかったり、らしさのないアウトプットを繰り返せば、印象に残りにくくなるだけでなく、ブランドそのものの信頼性が揺らぎます。
どれだけ優れた商品やサービスがあっても、それを届ける「表現」にブレがあれば、受け取る側にとってはその価値が見えづらくなる。
だからこそ、ビジョンや戦略から、商品・サービスの価値、外部へのコミュニケーションまで、一貫性を保ちながら価値を届けていくために、クリエイティブガイドラインが不可欠です。

クリエイティブガイドラインを策定するメリットとは?
ここからから実際にクリエイティブガイドラインがどのように役立つのか、またはそのメリットについて書いていきます。
メリット1.企画立案から施策実行までのスピードが上がる
人は「何でも自由にしていい」と言われると、かえって動けなくなることがあります。
たとえば、真っ白な紙を前にしたとき、どこから書き始めようかと一瞬戸惑うことがある。
けれど、罫線が引かれていれば、自然と手が動き出す。
ガイドラインも同じで、一定のルールがあることで、判断の手間が省け、迷いが減る。
何をどう決めて、どう実行すればよいのかが明確になるから、企画立案の初速が早くなる。
実行段階でも、都度の確認やすり合わせの必要が減るので、チームの動きにも無駄がなくなります。
特に複数人で動くプロジェクトでは、このスピード感が成果に直結してきます。
メリット2.一貫性が向上しつつ、企画や制作物に遊びが生まれる
アイデアは、無限の自由の中ではなく、ある程度の制約やルールがある環境下でこそ生まれやすくなります。
もし制限がなければ、逆に「考えなくてもいいか」と思考が止まってしまうこともある。
クリエイティブガイドラインは、企画の“軸”を見失わないようにするガードレールのようなもの。
守るべきルールがあることで、関係者全員が同じ方向を向いたまま、そこに“遊び”を加えていくことができます。
統一感がありながらも、堅苦しさのない、発想豊かなアウトプットが可能になるのです。
結果的に、自由度と精度を両立した企画や表現が実現できます。
メリット3.印象がクリアになり、覚えてもらいやすくなる
「いいものをつくれば、勝手に伝わる」——そんな理想は残念ながら現実とは少し違います。
届けたい価値を正しく伝えるには、言葉選び、トーン、ビジュアルの方向性など、あらゆる接点に一貫性が必要です。
ガイドラインがあることで、社内の担当者や外部パートナーが同じ視点で判断・制作できるようになる。結果として、打ち手ごとの世界観やメッセージがずれにくくなり、ブランドとしての印象がクリアになります。
また、制作物の質が安定することで、ブランドへの信頼感も積み上がっていく。
ガイドラインは、単なるルールブックではなく、ブランディングを加速させるための、いわば共通言語です。
▼ちなみに、「ブランディング」については以下の記事で詳しく解説していますのでぜひ併せてご覧ください。
未来のブランディングはどう在るべきなのか?歴史を紐解きながら考察してみた

クリエイティブガイドラインの作り方と掲載内容
まず大前提として、クリエイティブガイドラインはブランドのビジョンや戦略がきちんと構築されていなければ、そもそも意味をなしません。
ブランドの核となるコンセプトが存在しなければ、何を基準にトーンやビジュアルを決めていくのか判断がつかず、表現の指針も定まりません。
ガイドラインは「コンセプト=戦略」を外部に向けて実行していくための“運用指針”です。だからこそ、「単なる見せ方のルールブック」ではなく、「戦略を実装・運用するためのツール」として捉えるべきです。
まだビジョンやコンセプトが曖昧な段階で作るのは、方向の定まっていない羅針盤を使うようなもの。まずはブランドの核を整えること。それがすべての出発点になります。
そのため、以降はもうすでにブランドビジョンやコンセプトが構築されている前提で話を進めていきます。
▼以下の記事にコンセプトについて詳しく解説していますのでぜひ併せてご覧ください。
ブランドコンセプトの価値とは?一貫性も、選ばれる理由も、すべてコンセプトから始まる。
誰とつくるか
クリエイティブガイドラインは、誰がつくるかによってその有効性が大きく変わります。
ブランドの本質を理解している人、つまり単に商品やサービスの概要を知っているだけではなく、そのブランドが何を目指し、どうありたいのかまで共有できている人と取り組むことが大切です。
また、それを視覚・言語化する力を持つアートディレクターの存在も欠かせません。
コンセプトを体現するトーンやビジュアルのニュアンスは、戦略とデザインの双方に通じた人でなければ落とし込みが難しい領域です。
ブランド理解と表現力、この二軸を併せ持ったチームでの制作が理想的です。
何を載せるか
ガイドラインの内容は、ブランドごとに“どこまで細かく記述するか”の判断が分かれます。
最初から隅々まで定めてしまうと、運用の自由度が損なわれることもありますし、逆に曖昧すぎると実行段階で判断に迷いが出るリスクもあります。
そのため、最初は“必要最低限+少しの余白”がバランスの良いスタート地点です。
使っていく中でルールが足りないと感じたら追加し、逆に不要と感じたら削る。
そんなふうに、アップデート可能な“進化するガイドライン”が理想です。
以下に、その中でも基本として掲載しておくべき項目を紹介していきます。
当ガイドラインの目的を言語化/整理する
まず記載しておきたいのは、「なぜこのガイドラインを作ったのか」という目的です。
ただの表現ルールではなく、“ブランドのらしさ”をどう守るか、どう伝えるかをチーム内外に共有するためのツールであることを明示する必要があります。
たとえば、「ブランドの世界観を統一し、どのチャネルでも一貫性ある印象を届けるため」や「クリエイティブの再現性を高め、内製・外注問わず運用の質を担保するため」といった目的を簡潔に記載すると、使う側の意識が変わります。
ブランド戦略やマーケティング戦略に関する情報を記載する
ブランドの方向性を共有するため、戦略面の情報も簡潔に記載しておきます。
ここでのポイントは「詳細すぎないが、背景がつかめる」くらいの粒度です。(戦略が詳細に書かれたブランドステートメントは別で制作する必要あり)
具体的には、ターゲットのインサイト(まだ言語化できていない顧客の欲望)、ブランドのポジショニングや価値提案(バリュープロポジション)、ブランドアイデンティティ、パーソナリティなど。
どんな人に、どんな価値を、どんな語り口で届けるのかを共通認識として置くことが目的です。
ロゴ使用に関するガイド
ロゴはブランドの顔。
だからこそ、その扱いには細やかなルールが必要です。
まずはロゴの”デザインコンセプト”とその意味を記載し、どんなときにどのロゴを使用するか、「プライマリーロゴ」と「セカンダリーロゴ」の使い分けも明示します。
また、アイソレーション(他要素との余白の取り方)や最小使用サイズ、背景との組み合わせ、使用禁止例などを掲載することで、ロゴの誤用やブランド毀損を未然に防ぐことができます。
運用のリアルに即したルール整備が重要です。
カラーに関するガイド
カラーは視覚的な印象を左右する重要な要素です。
プライマリーカラー(最も使用する基準色)、セカンダリーカラー(補助色)、アクセントカラーなどを明確に定め、使用例とともに提示します。
ブランドカラーは、見た目の印象だけでなく、感情的なトーンも左右します。
「信頼感」「遊び心」「品のよさ」など、ブランドの世界観に直結するため、カラーパレットの構成理由や背景も簡潔に記述しておくとより活用しやすくなります。
タイポグラフィーに関するガイド
書体の選定も、ブランドらしさに大きく関わる要素です。
和文・英文それぞれについて、「魅せる書体(タイトル用)」「読ませる書体(本文用)」を明確に定義します。
また、WEBで使用する場合は、フォントのライセンスや読み込み速度、デバイスごとの最適化も加味する必要があります。
ブランドの独自性を“文字でどう語るか”を考える作業として、細部まで意識を行き渡らせたいポイントです。
写真の使用に関するガイド
写真は、ブランドの空気感や価値観をダイレクトに伝える手段です。
使用する被写体や撮影スタイル、色味の傾向に関して、NG例・推奨例を提示することで、表現の統一感を図ります。
ブランドによっては、Lightroomなどでプリセットを用意し、トーンを整えるところもあります。
表現の自由を担保しつつ、世界観の“にじみ出し方”を制御する。
それがこのセクションの目的です。
テキスト/文章作成に関するガイド
最後に、文章に関するガイドです。
ここでは、1人称、2人称、口調、使用可能な記号など、「文体」や「語尾の揃え方」「使わない表現」などの細かいルールに加え、「どう思考し、どう表現するか」の指針を明示するのが理想です。
たとえば以下のようなイメージです。
■ 思考の指針
- 私たちは論理よりも共感を優先するのか?
- 数字よりも物語を大事にするのか?
- 解釈の余白を残すのか、それとも明快さを徹底するのか?
- 「反応を狙う」のか、「理解を育てる」のか?
■ 表現の指針
- 丁寧語か、くだけた口調か?
- 比喩を多用するか、事実ベースで伝えるか?
- “静けさ”を大事にするのか、“勢い”で魅せるのか?
- 文章は短く端的に? それとも情緒豊かに長く?
上記のトーンや方向性を踏まえながら、自由な発想でコンテンツを生み出せる“土壌”を整えるのが目的です。
そして何より重要なのは、ガイドラインは一度作ったら終わりではないということ。
運用しながら、チームの声を拾い、ブランドの変化とともに更新していく姿勢が求められます。
ブランドの“らしさ”を守るのは、結局は人の想像力
上記に記載した内容に沿ってクリエイティブガイドラインをつくることで、一定以上のそのブランドらしさを表現できると思います。
けれど、仕組みに頼りすぎるのも良くありません。
クリエイティブの“最終ジャッジ”を担うのは、あくまでも人であるべきだと、私たちは考えています。
なぜなら「ブランドは細部に宿る」から。
その言葉の意味は、“そのブランドによって誰かが喜ぶ姿を、どこまで細かく想像できるか”ということ。
ターゲットはどんなことに不満や不安を抱え、何に心が動くのか。
伝えたいことが、どんなふうに届いてほしいのか。
結局のところ、最後の一押しは仕組みではなく、人の想像力です。
だからこそ、ガイドラインで余計な迷いやズレを減らしつつ、企画のロジック構築や、感性を使った“詰め”にこそ、しっかり時間を使いたい。
ルールに縛られるためではなく、超えていくために。
クリエイティブガイドラインは、ブランドの独自性をより具体的にする土台となります。
まとめ
クリエイティブガイドラインは、見た目や表現を整えるためのマニュアルではありません。
ブランドが目指す世界観や価値観を、社内外に共有し、具体的な企画や表現に“落とし込んでいく”ための実践的なツールです。
「どう動くか」「どう表現するか」に対して、余白を残しつつも方向性を与える。
だからこそ、作って終わりではなく、運用しながらチューニングしていく姿勢が欠かせません。
ブランドが進化すれば、当然ガイドラインも更新されていくべきもの。
ガイドラインは“ブランドらしさ”を担保しながら、クリエイティブの可能性を広げる、いわば「羅針盤」のような存在です。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級