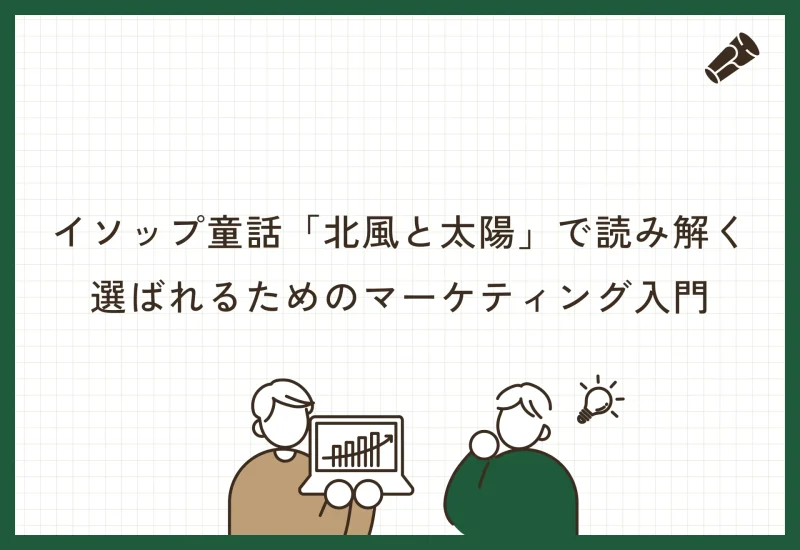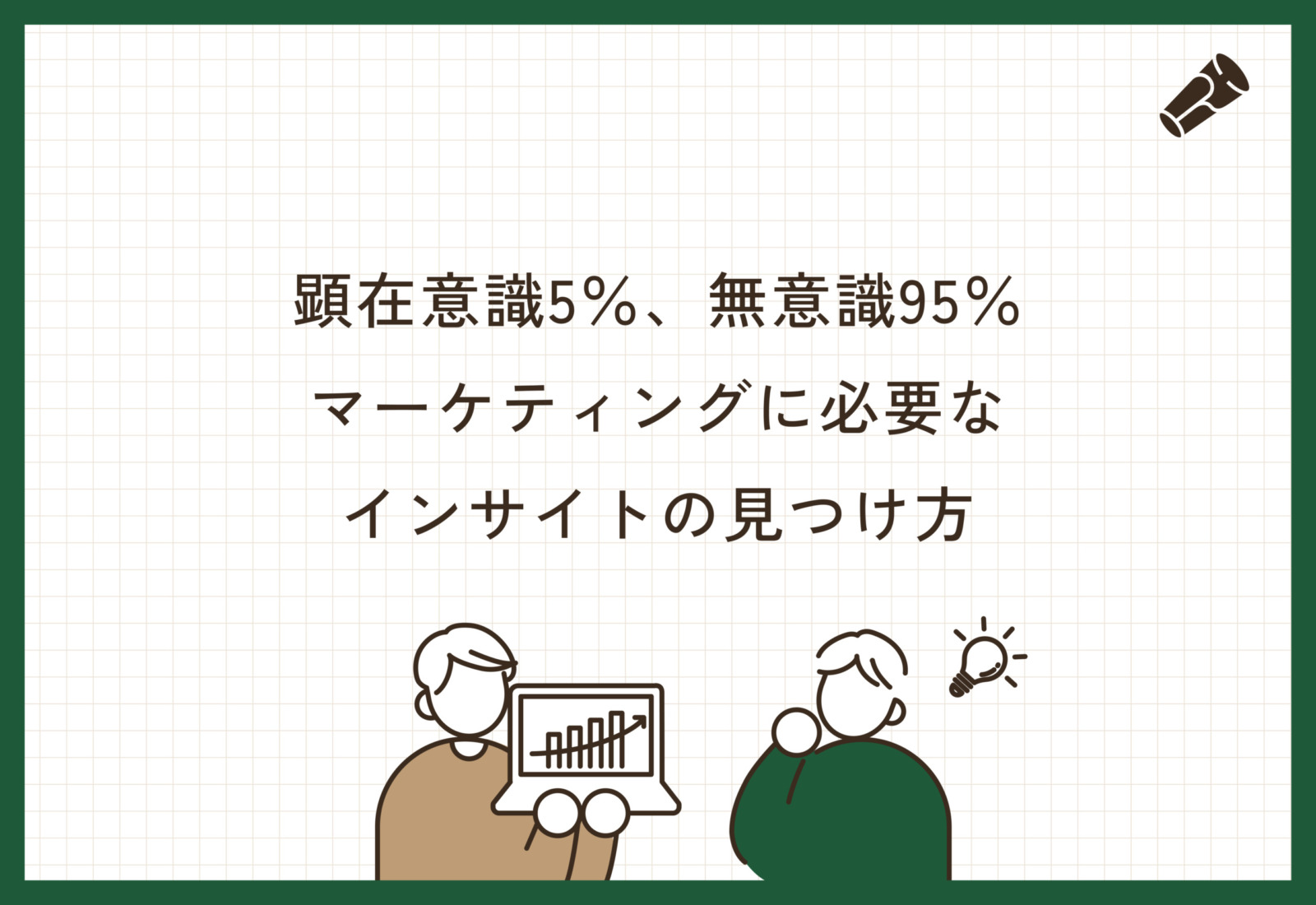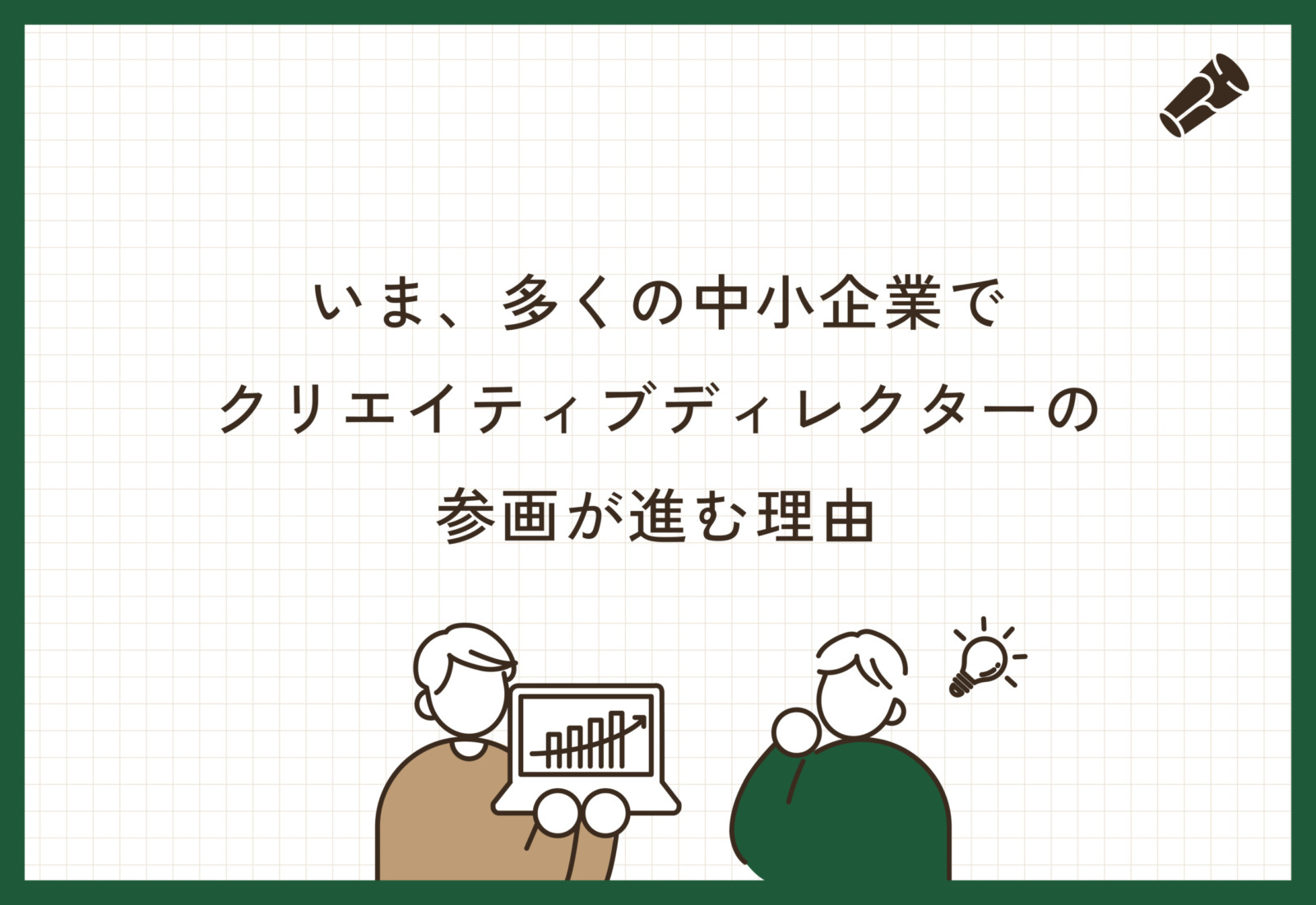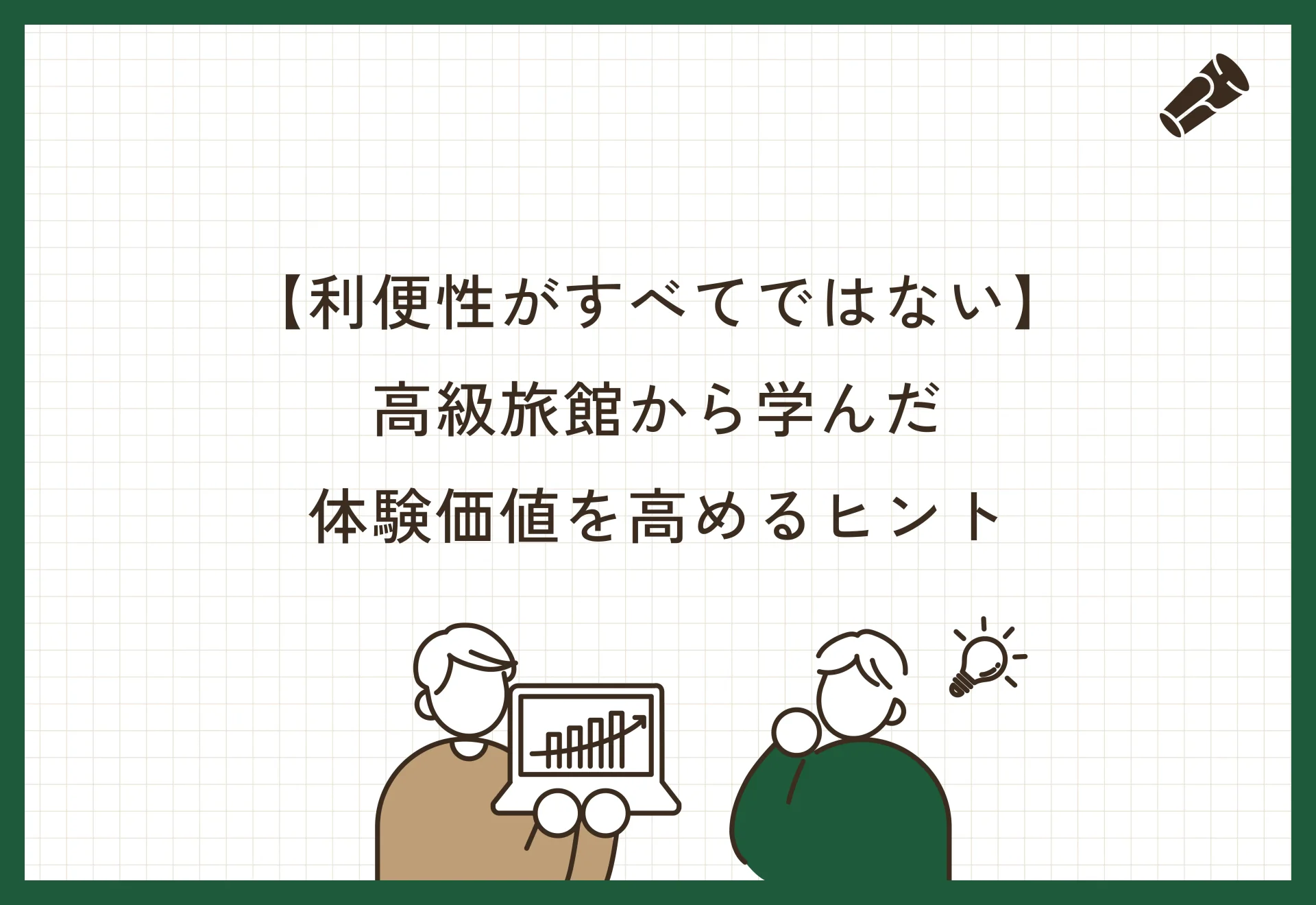
顧客からの要望に応え、あらゆるモノやサービスの利便性を高めることは、企業にとって常に大切なことです。
WEBサイト一つをとってもそう。
ユーザーがストレスを感じることなく、直感的に求める情報にたどり着けるように設計する。
その結果、ユーザーの離脱率は減り、回遊性が高まり、届けたい情報が効果的に伝わります。
今のビジネス環境で成長を続けるためには、あらゆる“不便”を取り除き、「〇〇しやすい」を徹底的に追求することが求められます。
とはいえ、「利便性を追求することだけが、本当に正しいのか?」と、最近ふと思うことが増えてきました。
そこで今回は、少し視点を変えて、「不便をデザインし、体験価値を高める」というテーマで書いてみようと思います。
利便性は大きな価値
今の時代、「便利であること」はビジネスにおける最低条件であり、同時に最大の競争軸でもあります。
スマホひとつで欲しいものが手に入り、数回のタップで料理が届く。
そんな利便性が“当たり前”になった現代では、人々の期待値そのものが大きく引き上げられています。
背景には、「時間が足りない」という感覚があると思います。
情報量は爆発的に増え、私たちは毎日、無数の選択と意思決定を迫られています。
SNS、広告、ニュース、メール……どれを受け取り、どこに時間を使うのか。
便利になっているはずなのに、なぜかいつも忙しい。
そんな矛盾すら感じるほどに、現代人の時間は細かく分断されています。
この事実は、私たち企業側の目線で見れば、ユーザーの“可処分時間”をどう確保するか、という問いでもあります。
睡眠や仕事などの不可避な時間を除いた、限られた「自由に使える時間」を、いかに「自分にとって価値ある体験」として届けられるか——。
だからこそ、「便利であること」はもはや“加点”ではなく“前提”になっています。
ちなみに、総務省が2022年8月に発表した「令和3年社会生活基本調査」*¹ によると、日本人の2021年の生活時間のうち、睡眠や食事などの一次活動、仕事や家事といった二次活動を差し引いた残りの時間は、1日あたり6時間16分とのこと。
¹出典:総務省「令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果 結果の要約」
平日に限定したらもっと少ないはずです。
見つけにくい、買いにくい、わかりにくい。そんなサービスは、それだけで候補から外れてしまう。
選ばれるための第一歩は、「ストレスなく届く」設計であることが欠かせません。
便利であること。それは企業がまずクリアすべき、基本のラインです。
不便であることはもう求められていないのか?
このように利便性を追求することは企業活動においてマストと言えますが、とはいえ、「不便であることが全てにおいて悪なのか?」と問われたらそれもまた違うなと思います。
たとえばキャンプやバーベキュー。
もう存在自体が不便の塊です。
外に出かける、火を起こす、食材を準備する、自分で肉や野菜を焼く、後片付けをする。
一見すれば「手間のかかる面倒な行為」ですが、そこにしかない楽しさや充実感があるからこそ、今も人気が続いています。
旅行に関してもそう。
わざわざ長い移動時間と、決して安くはない交通費をかけて行ったことのない町に行く。
訪れた町ではこれまで食べたことのないご当地グルメを食べたり、わざわざ交通のアクセスが悪い秘境に行って見たことのない景色を眺める。
考えてみれば不便でしかありません。
しかし、面白いなと思うのが、いま例としてあげたキャンプやバーベーキュー、旅行などは世の中が便利になればなるほど需要が増しているということ。
観光庁の調査によると、2024年の国内旅行消費額は前年比14.6%増の25兆1175億円(2019年比14.5%増)となり、過去最高値を記録したそうです。
キャンプに関しても、ブームは去ったと言われていますが、むしろそれは、新たにギアを買う人が減っただけであり、「アウトドアカルチャーとして定着した」と捉える方が適切です。
現代は便利さが追求される時代であり、それ自体が大きな価値である一方で、「不便さ」へのニーズも年々確実に高まっていえます。
何とも難しい時代ですね。
不便さが、圧倒的な満足感に変わった宿泊体験
話が変わりますが、先日、とある温泉旅館に泊まりました。
旅行には一切ケチらないと決めているので、今回はちょっと背伸びして、少し贅沢な部屋とコース料理を予約。
結果的に、大大大満足の旅となりました。
この満足感の裏側に何があるのだろうと考えると、ただ温泉や接客サービスが素晴らしかったから、というだけではない気がして——
帰ってきてからじっくり振り返ってみると、「ならではの不便」が、あの満足感を支えていたのだと気づきました。
その「不便さ」と、その時感じた「感情」を整理すると…
たとえば、夕食のコース。
- 全9品、一品ずつ運ばれてくるため不便。
→けれど、次は何が出てくるんだろうと、毎回ワクワクする。 - 提供の間隔がゆっくりめで不便。
→けれど、急がずに素材の味をじっくり味わおうとするし、会話も自然と深くなる。 - お造りはドライアイスでモクモク演出。だからすぐに食べられず不便。
→けれど、素材の鮮度が伝わるし、息子がその演出に大はしゃぎ。 - 料理ごとにいちいち紹介が入り不便。
→けれど、板前さんのこだわりや「一番おいしく食べるコツ」が分かって、より豊かに味わえる。
・・・
どれも、スピードや効率を求めるなら「面倒」と言えてしまうものばかり。
ビュッフェ形式という選択肢もありましたが、結果的にはコース料理を選んで本当によかったと感じています。満足感は想像以上でした。
もちろん、日常の中で意図しない不便さを感じさせてしまえば、それはストレスになります。
ただ、あえての「不便」があることで得られる充実感や没入感、深い満足感は確かにある。
不便さは、便利の対極にあるものではなく、目的に応じて選ばれる選択肢。
そう捉えると、「不便さ」も、これからの体験価値を支える一つの鍵になり得ます。
そんなことを、旅館の食事から教えられた気がします。
適切な“不便”の設計は、体験価値を底上げする
たとえ不便でも、その不便が「その場でしか得られない価値」があれば、人はそれを不満とは感じない。
なんでもかんでも「便利」であることが正義のように語られる今、逆説的に「不便だからこそ生まれる価値」にこそ目を向ける必要がある。
先ほどの旅館の話もそうですが、“その場でしか得られない感情”には、たいていちょっとした手間や余白がセットになっています。
繰り返しになりますが、もちろん、利便性が求められるシーンで突如として不便さを押し付けてしまえば、ただのストレスです。
ですが、「この時間に、ここに来ているからこそ感じたい何か」があるような文脈では、むしろその“不便”が体験価値を高めるためのスパイスになり得ます。
考えてみれば、フェラーリこそがその象徴です。
国産車と比べると明らかに不便な点も多い。
それでもなお、選ばれるのは、そうした不便さの中にこそフェラーリならではの魅力があり、「選ぶ理由」になっているからだと思います。
安さや利便性ではなく、体験価値で勝負するブランドや、感情に働きかけたいサービスにこそ、あえて不便さを設計してみる。
それが体験価値として受け取られるためには、当然、価格設定や伝え方のデザインも問われます。
「自分たちのサービスの中に、もし「不便」を取り込めるとしたら?」
「その不便を、価値として認識してもらうにはどんなストーリーを語ればいいのか?」
一度、問い直してみる価値は大いにあると思います。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級