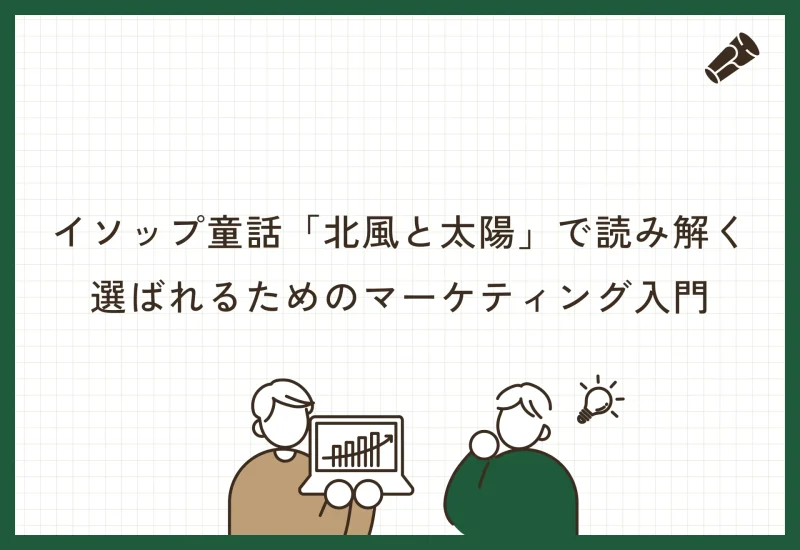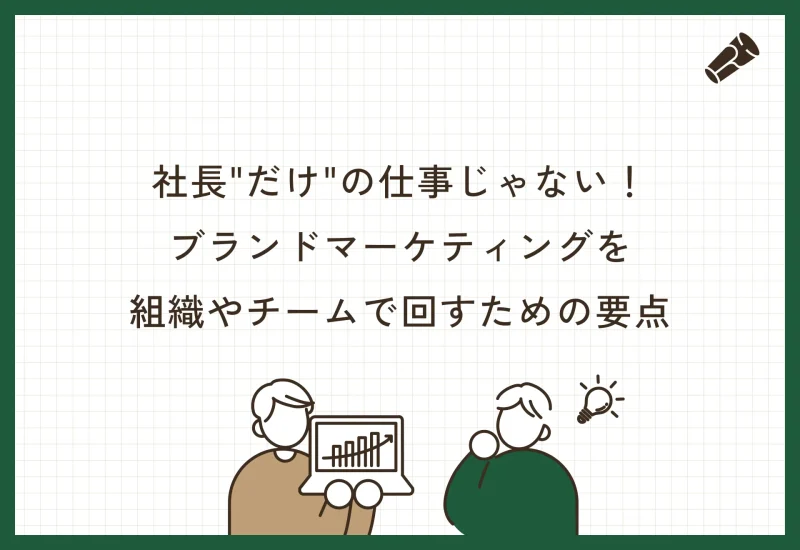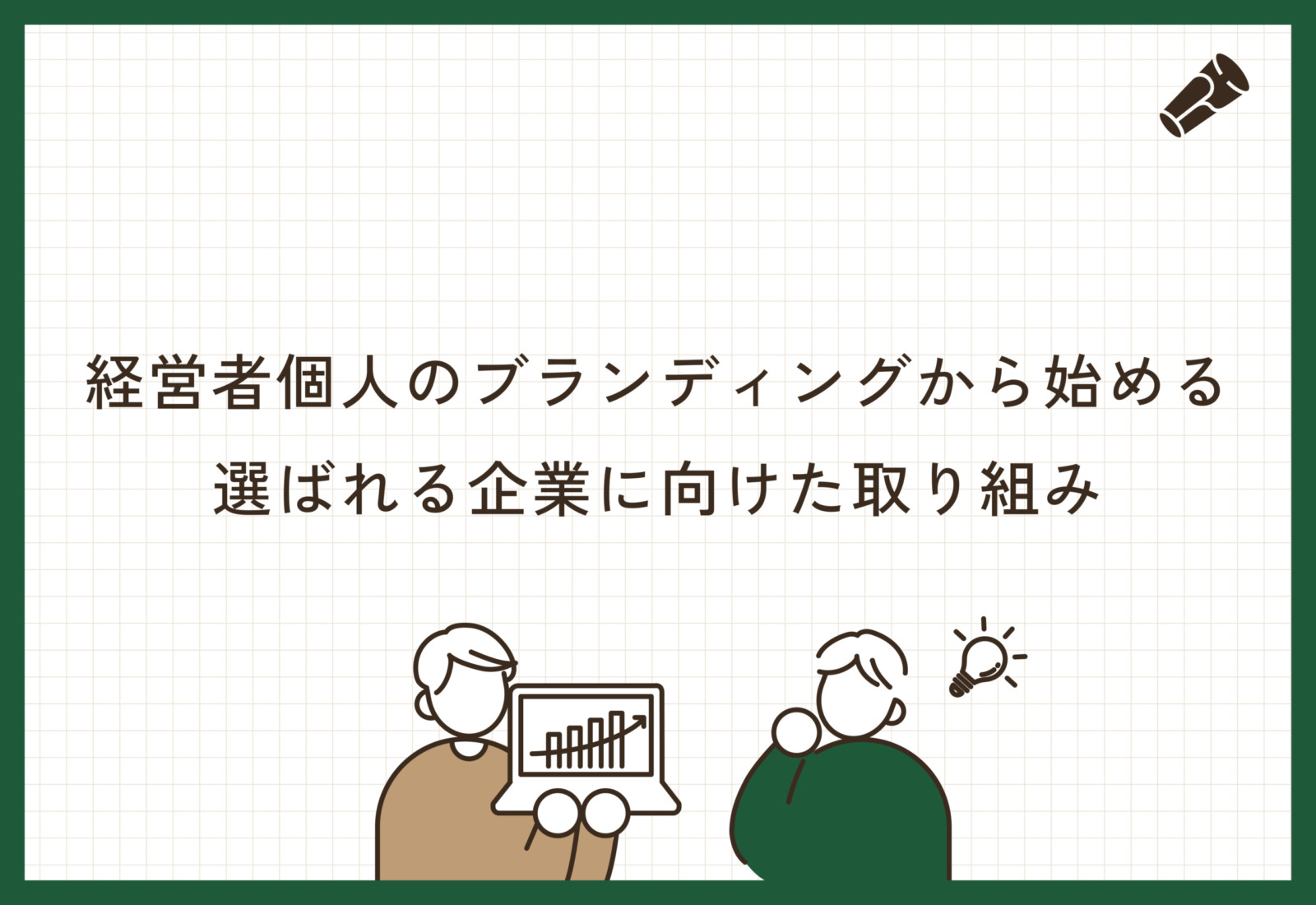Index
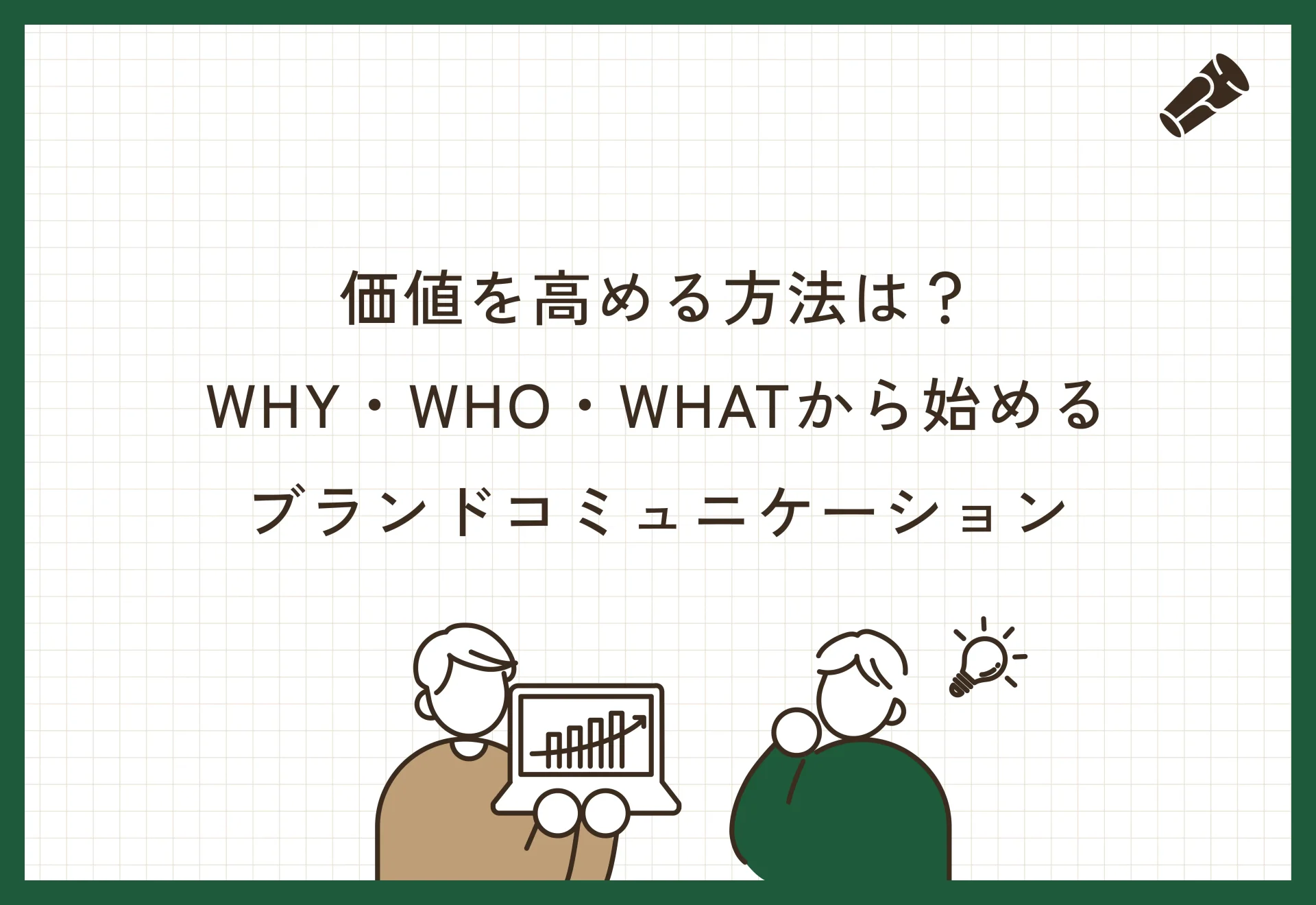
「価値を高めよう」
「価値ある商品をつくろう」
こうした言葉はあらゆるビジネス現場で飛び交っています。
しかし、その“価値”とはいったい何なのか、そしてそれを“高める”ために具体的に何をすればよいのか。
明快に答えられる人は意外に少ないのが現実です。
商品のスペックを磨けばいいのか、広告を打てばいいのか、SNSやブログを運営すれば良いのか、ストーリーを語ればいいのか。
考えられる選択肢はいくつもあると思います。
しかし、これらはすべて手段であり、解決の一部にすぎません。
この記事では、そもそも価値とは何か、そしてそれをどう高めていくのかという問いに、マーケティングやブランディングの構造的な視点から徹底的に答えていきます。
そもそも商品やサービスは価値伝達の”手段”である
まず前提の話からになりますが、ブランディングやマーケティング、さらにはあらゆるコミュニケーションにおいて非常に重要なフレームワーク「WHT→WHO→WHAT →HOW」について触れておきたいと思います。
- WHY(なぜ)
- WHO(誰に)
- WHAT(何を)
- HOW(どのように)
「何のためにこの事業を行い(WHY)、誰に(WHO)、どんな価値を(WHAT)、どう届けるのか(HOW)」。
これが明確に定義されていなければ、何をやっても価値が伝わりません。
しかしながら、価値をあげようと思った時、多くの方が真っ先に手をつけ始めるのは、「商品サービスの改善や開発」、「情報発信」です。
これは多くの企業が陥りがちな落とし穴。
もちろん、商品そのもののクオリティは重要です。
しかし、それだけで市場に評価されるかというと、話は別なんです!
なぜなら、商品やサービスの開発という行為そのものは、あくまで「価値どう届けるかという手段・道具(HOW)」であって、実は“価値そのもの”ではないからです。
「文脈」こそが価値を決める
差別化しにくいコモディティ市場において、HOW(商品、サービス、機能など)だけで戦っても、価格競争や過剰なスペック合戦に陥る可能性が高い。
大前提、顧客が商品にお金を払うとき、それは商品そのものに対してではなく、「その商品を通じて得られる体験」や「自分の価値観と合致する感情的満足」に対して払っています。
つまり、価値とはWHAT(=体験価値)であり、これを明確に定義しないかぎり、いくらHOWを磨いても“価値が高まる”ことにはなりません。
そして、このWHAT(体験価値)を成立させるためには、WHY(なぜそれをやるのか)、WHO(誰に向けて提供するのか)を明確に定義しなければなりません。
WHY・WHO・WHATが一貫していて(一本筋で通して)初めて、HOWに込めた意味が顧客に伝わる。
これが「文脈が価値を決める」という構造です。
逆に言えば、この文脈が不在のまま技術やアイディアで勝負しても、顧客には単なるスペックにしか映りません。
感情に届かない商品サービスやコミュニケーションでは、心が動かず、結果として“選ばれる理由”をつくることができないんです!
WHY・WHO・WHAT・HOWを深掘り
ここからは先ほど少し触れた「WHT→WHO→WHAT →HOW」をそれぞれ丁寧に紐解いていきます。
WHY(なぜやるのか)
売る側には「なぜ自分たちはこれを売るのか」という動機が必要です。
これは単なる企業理念ではなく、その事業や商品が“存在する意味”の定義です。(文脈の根っこ)
そして、現代の消費者はこのWHYに強く反応します。
「誰が、なぜこれを届けているのか?」という背景に共感できなければ、商品自体に興味を示さないことさえあります。
WHYが明確であることは、ブランドとしての芯の強さに直結します。
- なぜそれをやるのか。
- なぜそうあるべきなのか。
- この事業は社会の中でどんな意味を持つのか?
その答えの中にこそ、“選ばれる理由”の原石が眠っています。
だからこそ、「WHY」が言語化されていなければ、どれだけ想いがあっても、その魅力は届かないまま。選ばれる理由は、いつまで経っても伝わらないのです。
・・・
事例として私たちの事業(ブランドグロース事業)のWHYを取り上げたいと思います。
(もうある程度WHYについて理解が深められている方は読み飛ばしてください)
私たちリコルクにとってのWHY。
つまりなぜクライアント企業に本質的なブランディングやマーケティングを提供しているのかというと、「応援を集め、未来に向けた挑戦を支えていきたい」からです。
これは、漠然とした将来への不安から生まれたものです。
環境問題や人口減少、地域社会の希薄化など、目の前の子どもたちが大人になる頃には、今よりも多くの困難に直面するかもしれない。
そんな社会を変えるには、「挑戦し続けられる仕組み」が必要だと感じました。
しかし、どんなに優れた挑戦も、その価値が正しく伝わらなければ共感は生まれず、顧客や応援も集まりません。
資金が続かず、志が潰えてしまうケースも見てきました。
だからこそ、私たちが提供するのは、その場しのぎの部分最適や、ハリボテのような表面的な見せかけではありません。
事業のど真ん中にある本質的な価値を顧客の脳髄に叩き込み、市場で唯一無二の「ポジション」を確立するためのサポートです。
「何をしている会社なのか」
「どこに向かっているのか」
「ならではの魅力は何なのか?」
それらを丁寧に整理し、伝わる言葉と形にする。
結果として、応援されやすくなり、選ばれる状態が築かれ、未来に向けた事業活動や新しい挑戦が止まらずに進み続けられる。
そこに私たちの仕事の意味があります。
長くなりましたが、これが私たちにとってのWHYです。
この「なぜ」がなければ、誰に届けるのか(WHO)、何を届けるのか(WHAT)、どう届けるのか(HOW)にも意味が乗りません。
だからこそ、ここがすべての出発点になっています。
WHO(誰に届けるのか)
WHOは単に「どの属性の人か」というターゲティングではありません。
価値を届けたい相手の“未解決の欲求”や“内面的な渇望”を深く理解することが本質です。
相手がどんなライフステージにいて、どんな違和感や不安、夢や理想を抱えているのか。
その奥底にある“インサイト(まだ消費者自身も気づいていない欲望)”を見抜くことが、価値設計の起点になります。
たとえばハワイが世界中の観光客から支持されているのは、訪れる人々が無意識のうちに求めている「現実からの解放」「時間のゆるやかさ」「心身の再起動」といった欲求を、的確に汲み取っているからです。
つまりターゲットは“旅行好きな人”ではなく、“癒しや開放感、現実逃避を求める人”。
このようにWHOが高精度で定義されているからこそ、価値がブレず、深く届くんです。
「誰に届けるのか」を明確にすることは、「何を届けるか」の設計精度を高めるために欠かせません。
▼消費者インサイトについては、別の記事で詳しく紹介しています。興味のある方は、以下の記事もあわせて読んでみてください。
【顕在意識5%、無意識95%】マーケティングに必要なインサイトの見つけ方
WHAT(何を提供するのか)
WHATは、顧客にとっての「意味の定義」です。
商品やサービスがどのような感情を喚起し、どんな変化をもたらすのか。
それが言語化されたものこそが、価値の本体です。
人は感情の生き物です。
にもかかわらず、WHATを単なる“機能やスペックの説明”にしてしまうと、消費者にとって商品はただのモノになってしまいます。
ここでもハワイを例に出してみると、ハワイ旅行のWHATは「南国の海を見ること」ではありません。
そこにあるのは、「大切な人と過ごす非日常の時間」「日常を忘れ、自分を取り戻す体験」です。
この“変化の定義”こそが価値であり、人の心を動かす理由。
つまり、WHATとは、提供する体験価値の設計そのものであり、それがどれだけ顧客の文脈と接続しているかが成否を分けます。
WHATの強さは、WHOと向き合った深さに比例します。
そして、WHYに照らして初めて納得感のある価値として立ち上がります。
HOW(どう届けるか)
どれだけ本質的な価値を磨き込んでも、伝わらなければ意味がありません!
だからこそ、HOW(どう届けるかの設計)は、価値を成立させる最終工程であり、極めて重要な領域です。
しかし実際には、「HOW=制作物やSNS運用のこと」と誤解されている場面が多くあります。
たとえば、Webサイト、パンフレット、店舗空間、動画、広告出稿……。
確かにこれらはすべてHOWですが、それはあくまで手段にすぎません。
本来のHOWとは、もっと根本的な「価値の伝達設計」のことです。
届けたい相手が、どんな文脈で、どんな場面で、どうすればこちらの価値に共鳴してくれるか。
どんな言葉で語れば伝わるのか。“相手の頭の中から逆算していく”のが、HOW設計の本質です。
たとえば、**癒しという体験価値(=WHAT)**を届けたいなら、まずその価値が何によって構成されているのかを深掘りする必要があります。
またまたハワイを例に取れば、
- 美しいビーチ
- リゾートホテル
- アロハシャツ
- レイの演出
- 独特なダンス
- 地元の人たちのあたたかいホスピタリティ
これらはすべて、「癒し」というWHATを具体化するためのHOWです。
WHOやWHATと整合性の取れた、一本筋の通ったコミュニケーションと言えます。
つまり、HOWは、WHAT(=体験価値)をどう具体化し、体験として届けるかという戦略そのもの。
ちなみに「誰に届けたいか」によって、最適なHOWは変わります。
どんな媒体を使うのか、誰の言葉で語ってもらうのか。
WEB、SNS、空間、インフルエンサーや顧客自身の口コミなど、その選択肢は多岐にわたります。
けれど、その選択が的確になるのは、「届けるべき相手」や「届けたい価値」が明確だからこそ。
WHO(誰に)やWHAT(何を)が定まっていれば、HOW(手段)はブレず、結果としてブランドが“選ばれる理由”へとつながっていきます。
以下の記事では、強みや魅力の伝え方について解説しているので興味のある方は、あわせて読んでみてください。
強みの伝え方を解説!興味関心を惹くために、相手に応じて伝え方を変化させよう。
価値を高めたければ、WHY・WHOを突き詰め、強いWHATを!(まとめ)
繰り返しになりますが、WHATの定義があいまいなままでは、差別化もできず、顧客の記憶にも残りません。
WHATは単なる「商品説明」ではなく、「提供する価値」を言語化したもの。
そして、強いWHATとは、顧客の内面に響く明確なベネフィットを含んでいる必要があります。
WHATの精度を高めるには、「顧客の変化」を想像することが有効です。
- この商品を使った後、顧客の生活はどう変わるのか?
- どんな気持ちになるのか?
- どんな不安や不便が解消されるのか?
こうした変化にフォーカスして言語化することで、WHATは単なるモノの説明から、価値の定義へと進化します。
さらに、競合との差異を意識することも大切。
他社と似たようなベネフィットしか提示できない場合、顧客の頭には残りません。
ちなみに、対象ブランドにとってのWHY、WHO、WHATに沿った、そのブランド独自のコミュニケーション(HOW)のことを、私たちは「ブランドコミュニケーション」と呼んでいます。
ポイントは、目先で売ることだけを目的にせず、「選ばれ”続ける”こと」を目的としたコミュニケーションであるため、WHYも含まれているという点です。
リコルクはこのブランドコミュニケーションの設計を、一つの武器としています。
だからこそ、目先の施策にとどまらず、その前提となるWHY・WHO・WHATの明確化に力を注いでいます。
最後に
「価値を創造する」という言葉の本質は、「市場を創造すること」と限りなく近い意味を持ちます。
新たな価値を定義し、それに共感する人々を集めていく。
これはつまり、マーケットそのものを生み出す営みです。
さらに噛み砕くと、「消費者がまだ気づいていない潜在的な欲望にアプローチし、価値に気づかせ、顧客化・ファン化していくこと」こそが価値を創造するということです。
そのためには、届ける相手や価値を明確に定義し、文脈に沿って伝えることが欠かせません。
WHY、WHO、WHATを構造的に設計し、それに合ったHOWで表現する。これが戦略的なマーケティングの要です。
記事の中で例として出した、ハワイの事例が象徴的です。
あの場所は「癒し」「非日常」「家族との時間」といった価値を、長年にわたって意図的に設計し、観光客に浸透させてきました。
アロハシャツ、青い海、白い砂浜。
すべてが価値を構成するHOWであり、体験価値(WHAT)と文脈(WHY・WHO)に基づいた戦略的設計です。
一方で、日本では「つくれば売れる」という高度経済成長期の成功体験に引きずられ、“価値を伝える努力”が軽視されがちでした。
その結果として、価値の低迷と市場の停滞が起きた側面は否めません。
今後、中小企業が生き残っていくには、まさにこの「価値設計」の視点を持つことが鍵になります。
単にモノをつくるのではなく、意味をつくり、伝え、信じてもらう。
この積み重ねが、価値を高める方法であり、選ばれる会社への第一歩です。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級