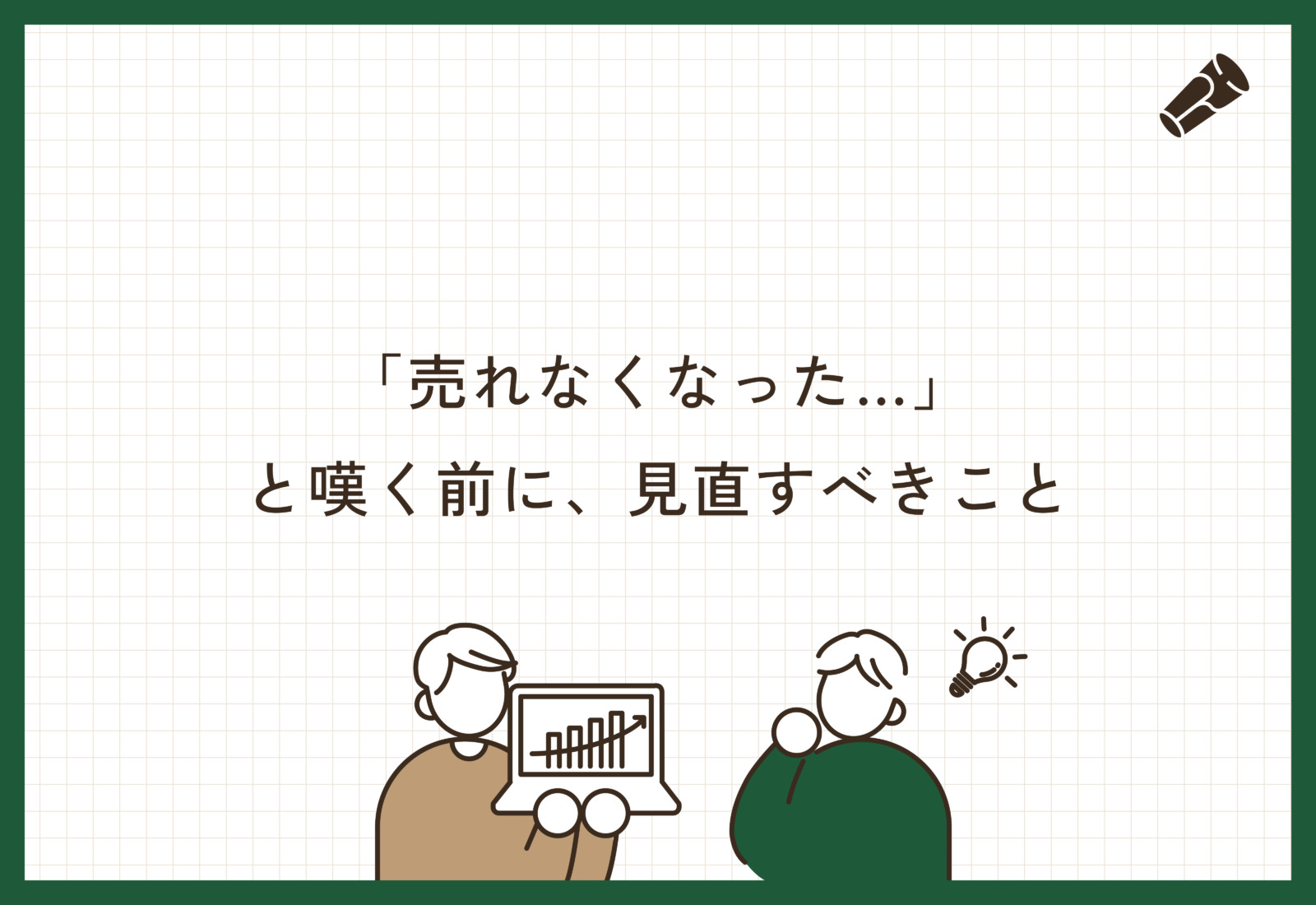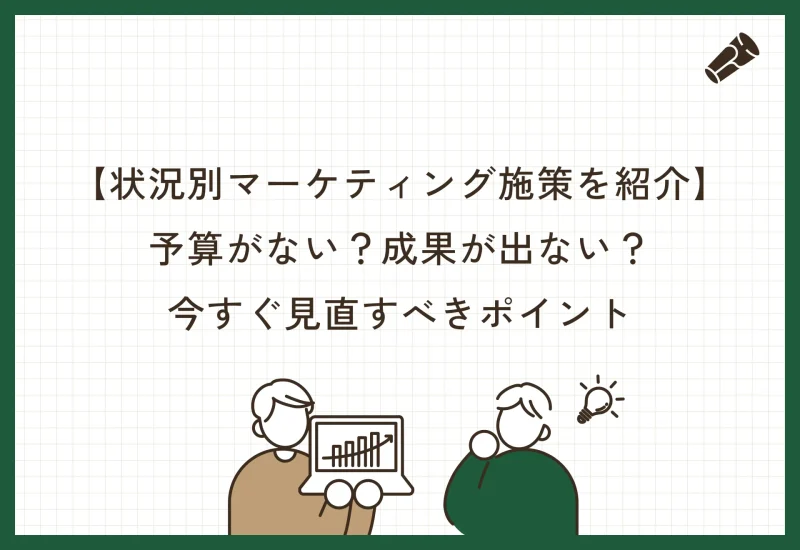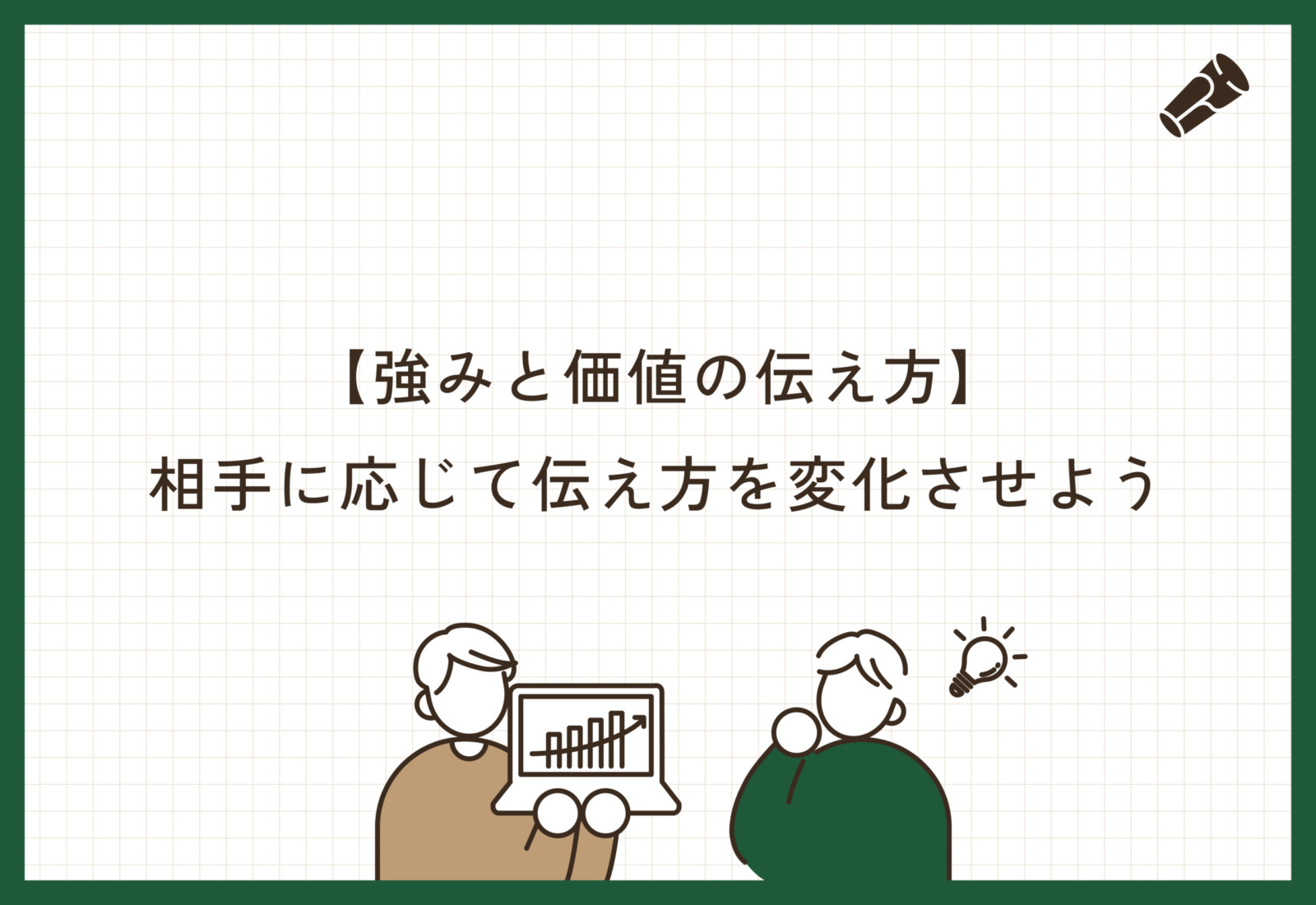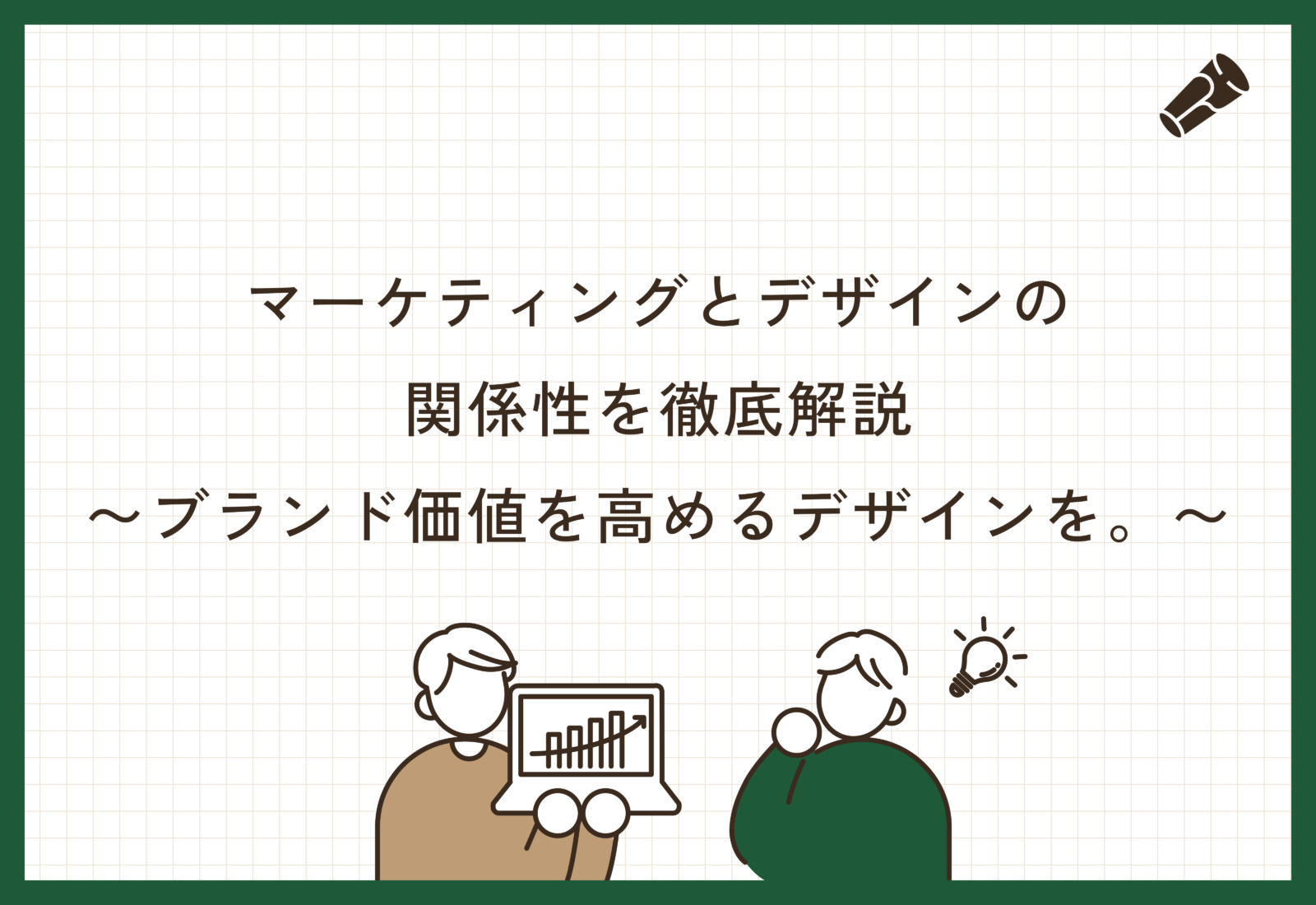Index
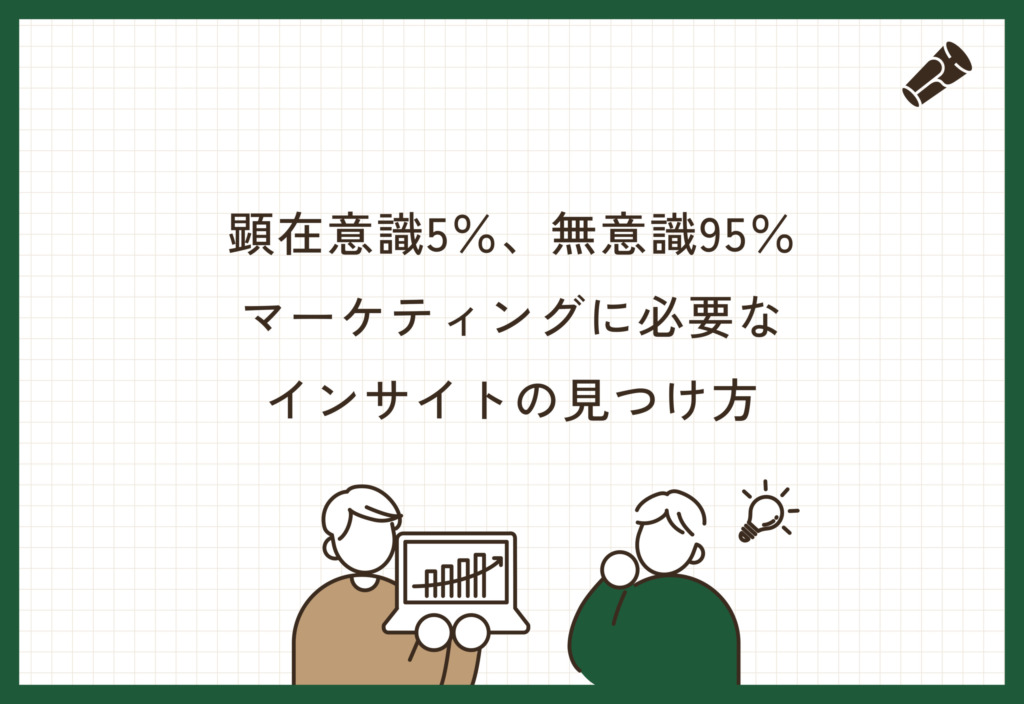
「人の顕在意識はたったの5%」と言われています。
このことを示す理論の一つに、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの研究があります。彼は著書『ファスト&スロー』(2011年)の中で、人間の思考プロセスを「システム1」と「システム2」に分類しました。
- システム1:直感的で無意識的な思考。瞬時の判断や感情的な反応を司る。
- システム2:論理的で意識的な思考。時間をかけて分析し、熟考するプロセス。
カーネマンの研究によると、私たちの意思決定の大半はシステム1(無意識)によって行われており、意識的に考えるシステム2の関与はごくわずかだとされています(Kahneman, 2011)。
つまり、人は自分で論理的に選んでいるつもりでも、その選択の多くは無意識の影響を強く受けているということ。
この事実から分かるのは、私たちがよく「〇〇がほしい」「〇〇部分が良かった」と口にする言葉は、たった5%の顕在意識のもとで言語化されているにすぎないということです。
これは、すべてのサービス提供者が常に念頭に置くべきことで、集客や採用を強化するうえで誰かの発言をそのまま鵜呑みにするのは非常に危険だと言えます。
消費者の意見を鵜呑みにして失敗したマクドナルドの事例
マーケティング界隈ではよく聞く事例なのですが、以前、マクドナルドは「サラダマック」という商品を開発し、販売しました。
しかし、結果は予想に反して大失敗に終わったそうです。
事前のアンケート調査では、「もっとヘルシーなものを食べたい」という声が多く寄せられ、低糖質やダイエット、栄養を意識する消費者のニーズが浮かび上がっていました。こうした声を受け、マクドナルドは健康志向のハンバーガーとして「サラダマック」を投入したのです。
ただ、実際に消費者がマクドナルドに求めていたのは、ヘルシーなメニューではなく、「ジャンキーなハンバーガーを食べて刺激を得たい」という欲求だったのです。
この事例は、「消費者の声をそのまま受け取るのではなく、もっと消費者の心の奥深くにある本当の欲求を見抜かなければならない」ということを教えてくれた事例です。
無自覚の欲望、インサイトとは?
マーケティング用語に「インサイト」という言葉があります。
インサイトとは何かを一言で表すなら、「その人自身もまだ気づいていない欲望」 のことです。
ここまでじっくり読んでくださった方なら、すでにお気づきかもしれませんが、顕在化されたニーズにそのまま応えれば、感謝自体はされるかもしれません。けれど、それが大きな喜びにつながることはほとんどありません。
つまり、「このブランドが好きだ!」と思ってもらうには、インサイトに目を向けなければいけないんです。
冒頭で 「人の顕在意識はたったの5%である」 と書きましたが、これは言い換えれば、「人は自分の本当の欲求をすべて理解しているわけではない」 ということ。むしろ、多くの欲望は心の奥深くに眠ったままで、言葉にすることすら難しいものなんです。
だからこそ、インサイトを突くことができれば大きな喜びに変わるんですね。
自身のインサイトに気づくの瞬間
では、そんな隠れた欲望、つまりインサイトは、どうすれば表に出てくるのでしょうか?
それは、ある商品やサービスを目の前にした瞬間、あるいは誰かに問いかけられたときにふと気づくことが多いんです。
たとえば、誰もが一度は経験したことがあると思いますが、ある商品を見た瞬間、「そうそう! これが欲しかったんだ!」と、心が躍るような感覚に襲われたことありませんか?(私はつい最近とあるカメラマンにとっていただいた写真を見たときにそんな感覚になりました)
その瞬間こそが、自身の奥底に眠っていたインサイトに気づいた瞬間です。
ちなみに、Appleの創業者スティーブ・ジョブズもかつて「人は、実際に目にするまで自分が何を求めているのか分からない。」と述べていたそうです。
これはまさにインサイトの本質を表しています。インサイトは、顕在化するまで本人すら気づかないもの。だからこそ、それを見つけ出し、言葉や形にすることが、マーケティングやブランディングにおいて超超超重要なのです。
インサイトの見つけ方
例えば、ノンアルコール市場について。
コロナ禍を機に需要がさらに伸びたと言われていますが、その背景には健康志向の高まりや若者のアルコール離れがあると言われています。
ただ、そもそもノンアルコールがこれだけ売れ続けているのは、「ほろ酔い気分よりも、飲んでる気分を味わいたい」「お酒は飲めないけれど、飲みの席は好きで、その場の雰囲気を崩したくない」といったインサイトにうまく答えているからだと思っています。
では、どうやってそのインサイトを見つけていくのか。
- 自分でも身を持ってそのシーンを体験する
- 他者を徹底的に観察する
- 仮説検証を繰り返す
これらを何度も繰り返していくしかないと考えています。
簡単に見つけられたら苦労はしません。
行動して、体感して、感想を書き残して、定量調査を入れて、仮説を立てて、ターゲットを観察して、ターゲットに憑依して、視点を増やして、テストして、また行動して…
といった具合なので、机にかじりついているだけでは到底見えてこないものです。
だから、現場に足を運ばず、理論だけを振りかざしている人の意見は無視してください。
定量的な調査は意味があるのか?
「定量的」とは、数値で示すことができるデータのことを指します。例えば、アンケート調査の結果やWebサイトのアクセス履歴などがこれに当たります。
一方で、「定性的」とは、数値では表現しにくい感情や心情などのデータを指します。定性データを収集する際には、1対1のインタビューや行動観察を通じて、複数のサンプルを集めることが重要です。
戦略を作る際や情報発信のヒントを得るために、顧客にアンケート調査を行うことはよくあります。ただ、先ほどのマクドナルドの事例からも分かる通り、そこで得た調査データを鵜呑みにしすぎるのはもちろん良いことではありません。
調査の目的や質問の仕方にもよりますが、定量的データは、全体的な傾向やパターンを把握する上では非常に有効で、あくまで仮説検証を行うための参考として捉えるべき。
ちなみに、グループインタビューも本音を見つけ出すのは困難だと思います。理由は、他の参加者がいることで、どうしても建前の発言が出てしまうからです。人は無意識のうちに、他者の反応を気にして本当の気持ちを言いづらくなることが多いです。特に、グループ内での調和を保とうとする傾向が強くなりがちなので、本当の意図や感情を引き出すには工夫が必要です。
もちろん、それらが無意味だと言いたいわけではありません。
繰り返しになりますが、重要なのは、現場に足を運んで自分で体感したり、行動観察やインタビューなどの定性的な調査と定量調査を上手に組み合わせて、PDCAを繰り返しながら進めることです。
良い企画が思い浮かばない最大の原因
インサイトが明確であれば、企画はスムーズに進みます。
よく「企画が思いつかない」「何を伝えればいいか分からない」といったご相談を受けますが、実はそれはインサイトがぼんやりしていて、ターゲット像がはっきりしていない証拠です。
長年一緒にいる親しい友人へのプレゼントなら、何を贈ろうかすぐに思い浮かびますよね。それと同じように、アイデアが浮かばないということは、ターゲットのことをまだ十分に理解できていないということです。
インサイトを見つける
↓
インサイトに基づいて、自社の強みを価値に昇華させる
↓
コンセプトに落とし込む
↓
コンセプトに沿って、必要な機能やデザインを設計し、商品・サービス開発を行う
↓
コミュニケーションをデザインする
(ビジュアルやコピーなど、どう伝えるかの設計)
インサイトをしっかり見つけられれば、その後の工程は驚くほどスムーズに進みます。
上記の流れは商品やサービス開発を例にしていますが、情報発信においても基本的に流れは同じです。
例えば、ブログ記事を作成する場合も、基本的にインサイトを見つけることがスタートです。読者がどんな情報を求めているのか、どんな問題に直面しているのかを理解したうえで、それに合った価値を提供する内容を考えます。
お客様が本当に求めている成果を追求したいからこそ
ちなみに、リコルクでは新規のお客様、既存のお客様を問わず、ご相談をいただいた際に入念にヒアリングをさせていただいています。それは、お客様が本当に悩んでいることや、実現したいことを正確に把握したいからです。(でないとお客様が本当に求めている成果を追求することができない)
実際にあった事例として、「集客を強化したい」というご相談をいただき、じっっくりヒアリングをしてみると、「実は集客自体は今の状態をキープしながら、適正に自社のサービスを評価してくれる顧客からの問い合わせをもっと増やし、単価を安定させたかった」という本当の依頼目的が明らかになりました。
その後のプロジェクトでは、単に客数を増やすための施策は取らず、じっくり自社サービスの独自性を掘り起こし、それを可視化する取り組みを行いました。
結果的に、単価が3倍に増え、さらに副次的に客数も増加するという成果が生まれたのです。
まとめ
人が発する言葉や行動の裏側に注目し、インサイトを発見することの重要性は、情報発信や商品開発の現場に限った話ではないと思っています。
人と人が向き合い、思いやりをもって対話を重ね、その中でインサイトに近しい欲望に気づき、それをそっと差し出す。
これは、身近な誰かとのコミュニケーションにおいても非常に重要なこと。そして、そのような行動を取っている人には、自然と人が集まってくるものだと思います。
よく会話の中で、自分が話すよりも質問を多く投げかける人を見かけます。こうした人は、相手に喜んでもらいたいという気持ちを持ち、誠実に向き合っていると感じます。
なので、日常的にインサイトを意識することは、決して無駄にはなりません。
私もこの考え方を今後も大切にしていきたいと思います。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級