Index
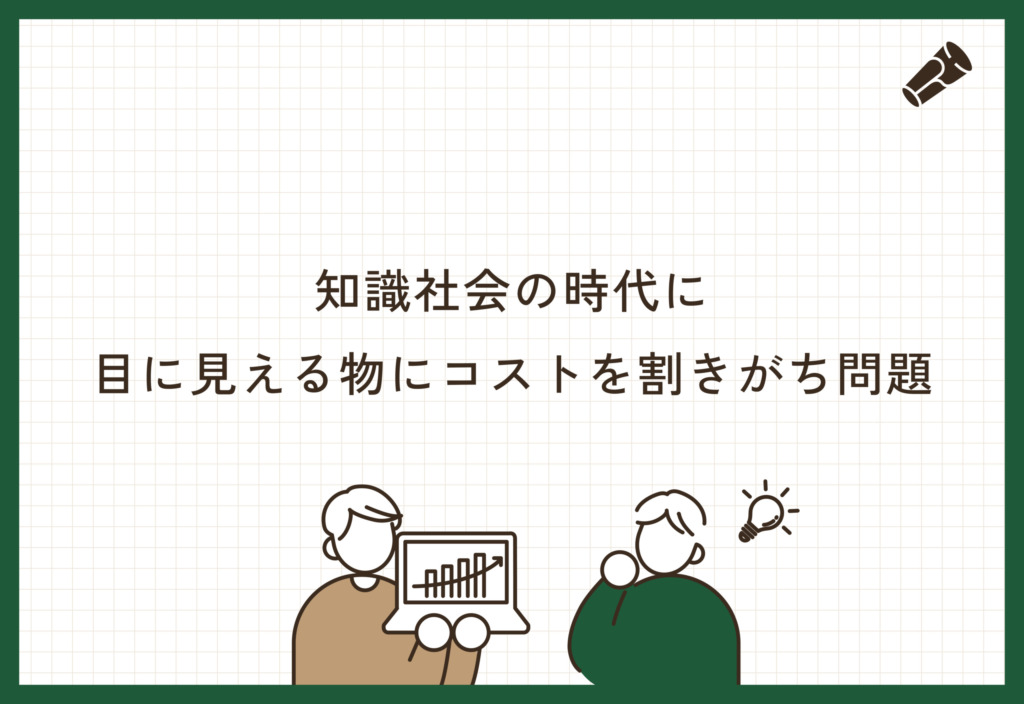
私たちの幼少期に頃に比べると現代はモノや情報が溢れかえっています。
総務省が発表したデータによると、「2002年のインターネット全体の情報量を10とした場合、2020年にはその6000倍にあたる6万」になっているそうです。
6000倍なんて言われても正直ピンときませんが、今と昔とで何が違うかと問われると、確かに情報へのアクセスのしやすさは段違いだなと肌で感じています。
それに加えて、欲しいものを手に入れることや、繋がりたい人と繋がることのハードルもかなり低くなっています。
Amazonで欲しい商品をポチれば外に出かけなくてもすぐに欲しいものが手に入る。 クラウドソーシングサービスを利用すればデザイナーやエンジニアとすぐにでも繋がることができます。
こうした利便性がどんどん高まっていくことで私たちの企業活動においてどんな変化があったか?
この問いが今回の記事のテーマです。
初めに結論からお伝えしておくと、知識社会になった今、「目に見えるモノに対する価値が下がってきている。だから目に見えるものばかりに投資していると、当然、企業やブランドの価値も下がっていくから、気をつけないと。」という話です。
これは自分たちへの戒めのつもりでもあります。
そもそも知識社会って何?
「知識社会」って言葉、最近よく耳にするようになりましたよね。 でも、具体的にどんな社会のこと?と聞かれると、ちょっと言葉に詰まってしまう人もいるかもしれません。
簡単に言うと、知識社会とは「知識そのものが価値を生み出す社会」のこと。 これまでのように、モノを作ったり、売ったりするだけでは、なかなか価値を生み出しにくくなってきているんです。
繰り返しになりますが、インターネットやスマートフォンの普及によって、私たちはいつでもどこでも、膨大な情報にアクセスできるようになりました。
その結果、誰もが簡単に情報を手に入れ、発信できるようになった。 つまり、知識を持っている人が、それを活用して新しい価値を生み出すことができるようになったんです。
例えば、YouTuber。 彼らは、自分の持っている知識やスキルを動画にして発信することで、多くの人を楽しませたり、役に立つ情報を提供したりしています。 その結果、広告収入や企業案件などで、大きな収入を得ている人もいますよね。
これも、知識社会ならではの現象と言えます。
目に見えるものばかりに投資するとどうなるのか?
知識社会において、目に見えるものばかりに投資していると、どうなってしまうのでしょうか?
先ほども書きましたが、企業やブランドの価値が下がってしまう可能性が高いです。
なぜなら、知識社会では、目に見えるモノよりも、目に見えない知識や情報、アイデアといったものの方が、価値を生み出しやすくなっているから。
顧客視点に立つとわかりやすいと思います。
例えば、あなたが新しい洗濯機を買うとします。 デザインやスペックも重要ですが、それ以上に、その洗濯機がどんな体験をもたらしてくれるのか、どんな課題を解決してくれるのか、といった「目に見えない価値」を重視するのではないでしょうか?
顧客は目に見えない価値を重視している時代なのに、企業側がそこ重視せず、目に見えるところばかりに投資をし続けていたら、競争優位性を保つことは難しいですよね。
だからこそ、知識社会においては、目に見えるモノだけでなく、目に見えない知識や情報、アイデアといったものにも、積極的に投資していく必要があるんです。
綺麗でおしゃれな見た目は、飽和状態
この話は私たちのような業界も例外ではありません。
AIの進化で、整ったデザインや読みやすい文章は、誰でも簡単に作れるようになりました。加えて、フリーランスのデザイナーやライターも増えたことで、「綺麗なホームページ」「綺麗なキャッチコピー」は世の中に溢れています。
私がよく発信しているのは、「綺麗でおしゃれな見た目は、すでに飽和している(=見た目のコモディティ化)」という話。ただ技術的に洗練されたものを作るだけでは、他社との差別化がどんどん難しくなっています。
それでもなお、「見た目」や「目に見える技術」”だけ”コストをかける企業は少なくありません。
誤解のないように伝えると、ビジュアルに投資すること自体を否定しているわけではありません。問題は、そうした「目に見えるところ”だけ”」にリソースを割いてしまうこと。
目に見えないものへの投資は、最終的に「見える化」されてこそ価値になる。だからこそ、重要なのはバランスです。
こうした事実を受けると私たちもうかうかしてられません。
私たちもより一層、目に見えないところにリソースを割いていかなければ、期待以上の成果を出すことが難しくなるので。
ブランディング・マーケティング業界も二極化が進んでいる
これまでの話ともつながりますが、ブランディング・マーケティング業界では、いま二極化が進んでいます。(おそらくこの業界に限らず、多くの分野で同じ現象が起きているはずです。)
その二極化とは、「単に制作物が欲しい・広告を回したい」というニーズと、「根本的な課題を解決したい」というニーズの分断。そして、それに応じて支援する会社も二極化しています。
- 要望通りに制作物をつくり、納品・運用する会社
- 前提を疑い、潜在的なニーズや価値を汲み取り、付加価値をつくる会社
発注する側の立場に立って考えても、どちらの会社を選ぶかは状況や課題によって変わります。ただ、「要望通りに作る・運用する会社」に対して、”大きな予算を割いて”ブランディングやマーケティングを依頼することはないと思います。
なぜなら、何度も書いてきたように、情報は溢れ、テクノロジーは進化し、「作るだけ・広告を回すだけ」の価値は低下し続けているから。
企業が投資すべきなのは、「成果物」ではなく「成果」。
こうした流れを踏まえると、今後 「前提を疑い、成果を出せる会社」 の希少性はさらに高まっていくはずです。
なぜなら、多くの人がこの事実を無視して「目に見えるもの」だけにリソースを割き続けるからです。
知識社会の時代に適した投資先は?
では、知識社会に適した投資先とは、具体的にどんなものなのでしょうか?
もちろん、企業の状況によって異なりますが、いくつかの重要な領域を挙げるとすれば——
- 人材育成 / 組織開発:従業員のスキルアップや能力開発に投資することで、企業全体の知識レベルを底上げし、持続的な成長を促す。
- テクノロジーの活用:テクノロジーを活用し、業務効率を上げながら、AIとの共存によって生産性をさらに高める。
- クリエイティビティ:人の創造性や独創性を育む環境を整え、組織としての創造力を強化する。
- 戦略設計とその運用:成果が出ない原因の多くは、戦略の段階で生じている。常に前提を疑い、確度と一貫性の強化を図る。
- 理念の具体化・可視化:企業の理念やスタンスを行動によって伝達し、ステークホルダーとの強い信頼関係を築くことで、事業の土台をより強固なものに。
- コミュニケーション:どんな時代になっても、対話と相互理解が企業の成長を支える。常に互いに気づきを与え合い、より良い形を模索し続ける。
これらの投資は、いずれも目に見えない価値を生み出すためのものです。
知識社会においては、こうした目に見えない価値に積極的に投資していくことが、企業やブランドの成長につながります。
知識労働者は、今後ますます引っ張りだこになる
先ほど、「“前提を疑い、成果を出せる会社”の希少性はますます高まっていく。」と書きましたが、もちろんこれは個人においても同じことが言えます。
知識社会の進展に伴い、知識労働者の価値はますます高まっていくことは間違いないです。
(知識労働者とは、知識や情報、アイデアなどを活用して、新しい価値を生み出す人のこと。)
経営学者であり、「マネジメントの父」とも称されるピーター・ドラッカーは、知識労働者の役割について多くの示唆を与えています。彼の著書『マネジメント』(1973年)から、次の言葉を引用します。
「知識労働者にとって最大の資産は自らの知識であり、それをいかに生産的に活用するかである。」
知識労働者は、知識社会において、企業やブランドの成長を牽引する重要な役割を担っています。
だからこそ、企業は、知識労働者との繋がりをより一層大切にすべきですし、知識労働者がやりがいを感じるような環境を整備することが、ますます重要になってくるはずです。
人それぞれのクリエイティビティが掛け合わさる文化を
クリエイティビティとは、新しいアイデアや発想を生み出す力。そして個人的には、それは人それぞれの「クセ」のようなものであり、情熱そのものだと思っています。
けれど、まだ多くの現場では、個々のクリエイティビティが十分に活かされていないように感じます。異なる知識や経験を持つ人々が交わり、刺激し合うことで、もっと大きな力が生まれるはずです。
そして、「目に見えない価値」とは、知識やアイデア、クリエイティビティだけではありません。
人とのつながり、信頼関係、共感性——そうしたものも含まれます。
知識社会において、これこそが競争力の核になります。
あらゆるモノや情報が溢れ、「目に見えるもの」が飽和している今、企業やブランドが持続的に成長していくためには、自由に意見を交わし、情報をシェアできるオープンな文化。
そして、新しい挑戦や失敗を受け入れられる「心理的安全性」のある環境をつくることも重要です。
最後に、感情に訴えかけ、心を動かすものの背後には、強い哲学があると感じています。
「本当に大切なものは、目には見えないんだよ。」
この言葉は、世界2億部以上の発行部数を誇る『星の王子さま』に登場する、あまりにも有名な一節。
情報とテクノロジーが加速する時代だからこそ、このメッセージを、私たちはもっと深く受け止める必要があるのかもしれません。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級





