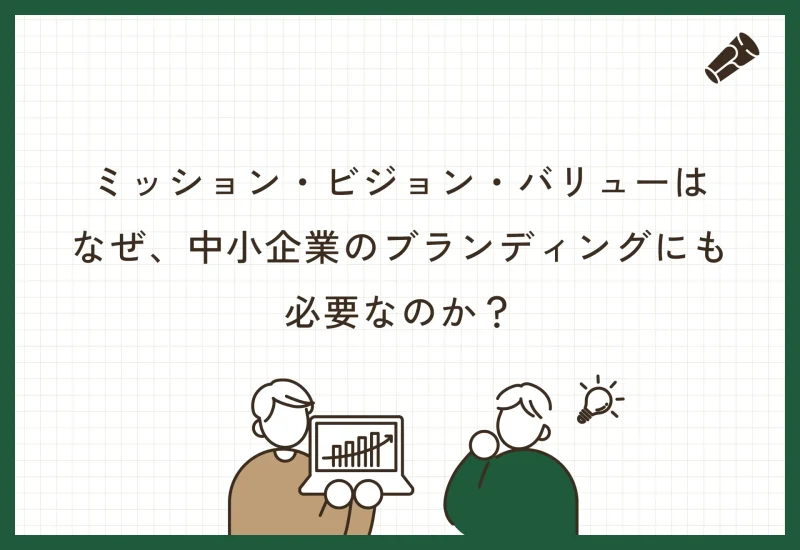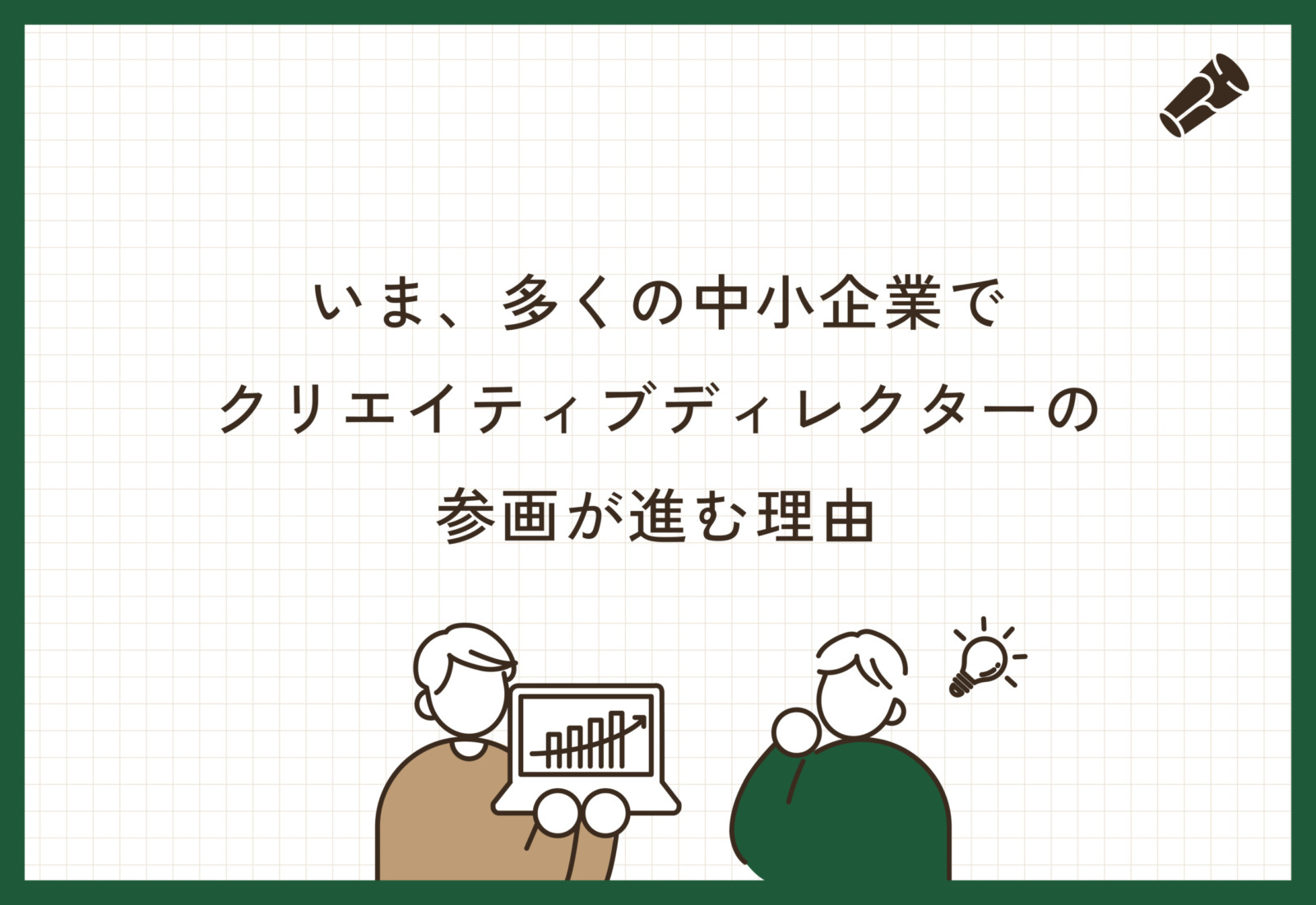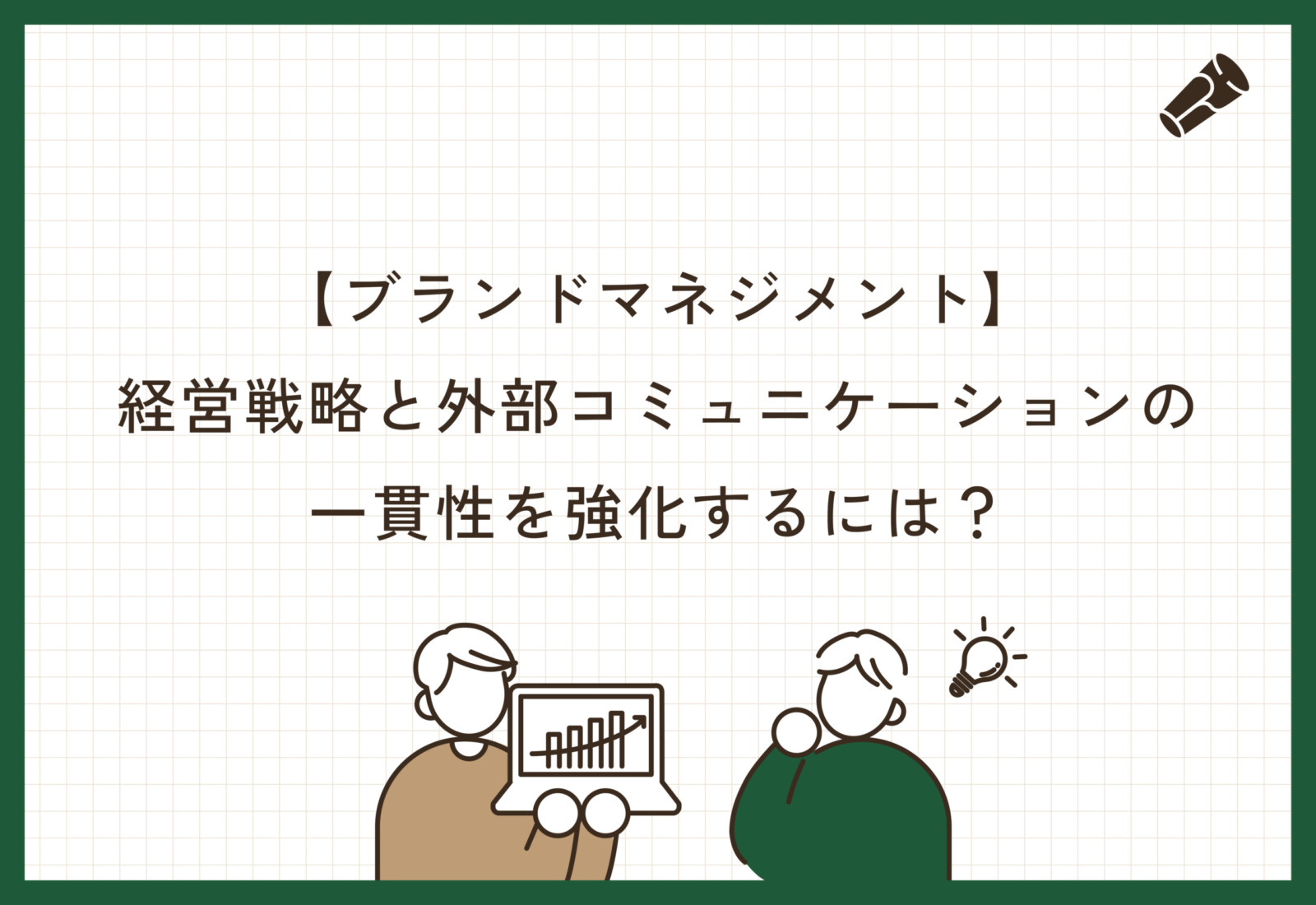Index
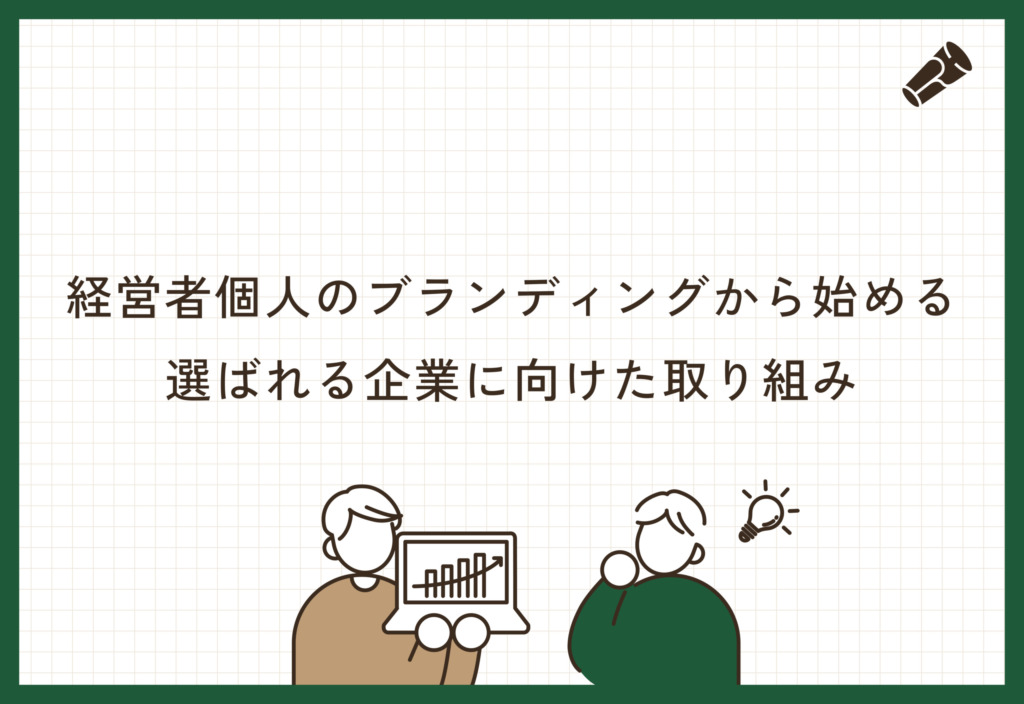
コーポレートブランディングに関するご相談を受け、いざプロジェクトを始める段階で、私が必ず行っていることがあります。それは、経営者の方へのインタビューです。
そのインタビューは、一対一で行うこともあれば、プロジェクトメンバーが同席する場合もあり、形式は企業ごとに異なります。しかし、個人的にはこのフェーズが非常に重要だと考えています。
なぜなら、企業というブランドは、必ず 創業者一人の価値観や考え方、ビジョンを”起点”に形作られているからです。
もう少し噛み砕くと、今こうして継続的に利益を生み出し、存続できているエッセンスは 「創業者の想い」 にあるということです。
もちろん、すべてがそれで成り立っているわけではありません。現場のスタッフさんの丁寧な対応や技術力があってこそ、日々の売上が成り立っていることは間違いない。
しかし、それでも企業がこうして活動を続けられているのは、たった一人の中にあった「こういう人を喜ばせたい」「こんなサプライズを届けたい」「こんな素敵なものを埋もれさせておくのはもったいない」 といった思想が原点になっているはずです。
だからこそ、企業価値を高めるためのコーポレートブランディングにおいては、まず企業のリーダーにお話を伺わなければ始められないのです。
ブランドは強みを土台に作られていく。
企業のブランドを築くうえで、経営者自身のブランディングが不可欠であるという視点は、意外と見落とされがちです。しかし、「現代経営学の父」とも称されるピーター・ドラッカーは著書『自己探究の時代』の中で以下のように述べています。
“一流の仕事をするには、まず自己の強みを知ること。そして、仕事の仕方を知り、学び方を知る。自己を知ることで得るべきところが分かり、なすべき貢献が明確になる。”
これはセルフマネジメント的にな話ですが、私個人の捉え方としては、「まず自分自身をブランディングできなければチームや組織もブランディングできない」といっているように思います。
「自分は何者で、何を使命に、どんな価値観に従って活動しているのか?」
「自分の強みは何で、どんな役割を担いながら顧客や社会に貢献していくべきなのか?」
そんな問いを突きつけられているような言葉です。
またドラッガーは以下のようにも述べています。「マネジメント-エッシャル版-基本と原則(ダイヤモンド社)」から引用
“人は弱い。悲しいほど弱い。(中略)しかし人は、これらのゆえに雇われるのではない。人が雇われるのは強みのゆえであり、能力のゆえである”
自分自身の強みを理解して活かせていなければ、他人の強みを理解して活かすことできない。この一文からわかるように自分や誰かの弱みばかりに目が向いてしまうと、企業は生産的にならず、弱くなっていく一方です。
経営者が一貫していなければ、何をやっても無意味
また、企業としての一貫性を強化する上でも、たとえば、アップルのスティーブ・ジョブズやテスラのイーロン・マスクのように、強い思想を持つ経営者の発言や行動が企業のビジョンと直結しており、その一貫性が信頼を生み出しています。
また、BtoB企業においても、経営者個人の考え方や人間性が、顧客やパートナー企業との関係性に影響を与えます。特に中小企業やスタートアップでは、経営者自身が「企業の顔」として見られることが多く、その発信力が企業のブランド価値に大きく寄与します。実際、経営者がSNSやブログを通じて自らの価値観や想いを発信し続けることで、共感を生み、ファンを増やしているケースは少なくありません。
さらに、採用面においても優秀な人材ほど「この会社で働きたいか」ではなく、「この経営者のもとで働きたいか」を重視する傾向があります。経営者が明確なビジョンを持ち、それを発信することで、価値観に共感する人材が集まり、企業文化の形成にもつながるのです。
つまり、企業のブランドを強化するには、まず経営者自身が「何者なのか」「何を大切にしているのか」を明確にし、それを一貫して発信することが欠かせません。経営者のブランディングは、企業の未来を左右する重要な要素です。
よくあるコーポレートブランディングの失敗原因
コーポレートブランディングを進める企業は増えていますが、そのすべてが成功するわけではありません。むしろ、途中で頓挫したり、期待した成果が得られなかったりするケースは多くのところで見られます。なぜブランディングがうまくいかないのか?そこには「共通する失敗パターン」があります。
それは大きくまとめると以下になります。
- ブランドを「見た目」だけで捉えてしまう
- 経営者の意思がブランドに反映されていない
- 「ターゲット=全員」と考えてしまう
- 短期的な成果を求めすぎる
一つずつ説明していきます。
ブランドを「見た目」だけで捉えてしまう
よくあるのが、ロゴやWebサイトのデザインを刷新すればブランディングが完了すると思い込んでしまうケース。確かに、デザインはブランドの印象を左右する重要な要素ですが、それだけでは企業価値は向上しません。というか、そんなに簡単だったら苦労しません。
ブランドとは 企業の理念やビジョンを軸に、一貫した体験を提供することで成り立つもの。外見だけを整えても、顧客との接点にるける体験価値や社内文化が変わらなければ、ブランドの本質は伝わらず、期待した効果は得られません。
経営者の意思がブランドに反映されていない
ブランディングをマーケティングチームや外部のパートナーに丸投げしてしまうのも、大きな落とし穴です。特に、経営戦略や企業として一貫して大切にしたいスタンスが全く共有されないままだと企業の本質とズレたメッセージが発信されてしまいます。
そのような状態で万が一、それで目にみえる成果が出たとしても、その成果が長期的に継続されている場面を私はみたことがありません。
つまりそれは偽ったブランディングだから。表面的には魅力的に見えても、時間が経つと「なんとなく違う」「うちはこんな会社じゃない」と社員や顧客が違和感を覚え、ブランドが機能しなくなるのです。
「ターゲット=全員」と考えてしまう
ブランドは、特定の顧客に深く刺さるものでなければなりません。
しかし、すべての人に好かれようとするとメッセージが曖昧になり、結果的に 誰の心にも響かないブランド になってしまいます。
特に日本企業では、「幅広いお客様に対応する」という発想が根強く、ターゲットを明確に絞り込むことをためらう傾向があります。
しかし、成功しているブランドは例外なく 「誰に届けるか」を明確にし、そのターゲットが強く共感するメッセージを打ち出している のです。
ある意味、「ターゲット以外の人からは無視されてもいい。なぜなら、その人たちに時間を割けば割くほど、本当に届けたい相手に集中できなくなるから」 というくらいの割り切りが、ブランドの独自性を際立たせ、その魅力がより一層伝わるようになります。
短期的な成果を求めすぎる
ブランディングは、時間軸を長めにとった上で行うべき投資です。
これを私なりに言い換えると、 長期的な視点で「売上の向上」ではなく、「利益の向上」に焦点を当てた投資 と言えます。
しかし、企業の中には「半年で効果を出したい」「すぐに売上につながらないなら意味がない」といった短期的な視点で判断し、途中でブランディングをやめてしまうことがあります。
ブランディングは、短期的な広告施策とは異なり、 顧客や市場との信頼関係を築いていくプロセス です。そのため、一貫した発信を続け、時間をかけて 「選ばれる理由」 を確立していくことが重要です。
—経営者のスタンスは企業文化の一部となる
なぜこの記事で失敗の原因を深掘りしたかというと、上記の「3つの失敗原因」を経営者(リーダー)自身が抑えられていないケースがよく見られるからです。
たとえば、「ターゲット=全員」という価値観は、企業としてだけでなく、 経営者自身が常日頃からその考え方に基づいて、あらゆる人に対して八方美人を演じている場合。スタッフも経営者の行動や態度に影響され、同じように対応するようになってしまうのです。
しかし、このような状態では、 ブランディングプロジェクトを立ち上げても、コストを無駄に使ってしまうだけ です。
そのため、企業ブランディングにおいても、経営者個人のパーソナルブランディングにおいても、上記の3つの失敗要因はしっかり抑えておくべきです。
実際に必ず深掘りしていること
前提として、これから記載する内容はあくまで基本的なものであり、これらの項目からさらに深掘りしていきます。また、これは単なる表面的なヒアリングではなく、企業の本質を浮き彫りにするために行うもの。そのため、ここで明らかになった内容をそのままコーポレートブランドのコンセプトとして掲げるかどうかは後々判断します。
この目的を見失わないよう、一つひとつ慎重に進めていきます。
以下、インタビュー時の5つのポイントです
①なぜこの事業を始めたのか?
②どんな価値観を大切にしているのか?
③なぜこれまで選ばれてきたのか?
④10年後、どうなっていたいか?
⑤スタッフにはどんな人生を歩んでほしいか
① なぜこの事業を始めたのか?
どんな企業にも、その事業を立ち上げた理由や背景があります。
「儲かりそうだから」「市場にチャンスがあったから」という理由で始めたとしても、さらに掘り下げると、「解決したい課題」や「世の中に提供したい価値」 が見えてくるはずです。
例えば、
- 幼少期や過去の経験から「こんなサービスがあれば助かった」と感じた
- 前職での課題意識から「業界の仕組みを変えたい」と思った
- お客様との出会いを通じて「もっと多くの人に届けたい」と決意した
この「なぜ?」を突き詰めることで、事業の原点となるストーリーが明確になり、ブランドの核を見つける第一歩となります。
② どんな価値観を大切にしているのか?
企業ごとに大切にしている価値観は異なります。
「誠実さ」「挑戦」「お客様との関係性」「持続可能性」など、経営者が何を軸に意思決定しているのかを明らかにすることで、ブランドの方向性が定まります。
ここで重要なのは、単なるスローガンではなく、実際の経営判断にどのように影響しているかを掘り下げること。
- なぜその価値観を大切にしているのか?
- その価値観を持つようになったきっかけは?
- 過去の意思決定の中で、その価値観が反映された具体例は?
この部分の深掘りは個人的にはかなり重要だと思っています。ここを入念に深掘りすることで、経営者の考えと企業のブランドが 一貫性を持って伝わるようになります。
③ なぜこれまで選ばれてきたのか?
ここでは、企業が なぜお客様や取引先に選ばれてきたのか を改めて整理します。この問いに対する答えは、企業の「本当の強み」を明確にする手がかりになります。(この段階ではあくまで手掛かりです)
たとえば、
- 価格ではなく「サービスの質」で選ばれているのか?
- 他社にはない「専門性や技術力」が評価されているのか?
- お客様との関係性の深さが、リピートにつながっているのか?
意外と、経営者自身がこの問いに即答できないケースもあります。ただ、クリエイティブやサービスに一貫性をもたらし、ブランド力や企業価値を高めていくには、まず経営者の方が、自社や自身の魅力をしっかり言語化できることが大切なんです。
だからこそ、私たちは現場の声や実際のお客様の声に耳を傾けつつも、経営者の方と二人三脚で自社や商品サービスの潜在的な価値を丁寧に掘り起こすことから始めています。
④ 10年後、どうなっていたいか?
ブランディングは短期的な施策ではなく、長期的な方向性を示すものです。そのため、経営者がどんな未来を描いているのかを具体的にお聞きします。
- 10年後、どんな社会を実現したいか?
- 会社はどんな存在になっていたいか?
- 今のまま進んだ場合、その未来は実現できるのか?
このビジョンが明確になることで、企業の成長に伴いブランドがブレることを防ぐことができます。また、問題や課題は未来の理想像がなければ特定することができません。たとえ未来の理想像が現状維持だったとしても、維持するための問題や課題もあるはずです。(現状維持志向には少し危険なニオイがしますが…)
ともあれ、最近では「ビジョナリーカンパニー」や「ビジョニング」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。ビジョニングとは、企業や個人が未来に向けて理想的な状態を描き、その実現に向けた方向性や戦略を明確にするプロセスのことです。周囲から共感を得て目標達成を実現するために、欠かせないものとなります。
しっかりと「今」と向き合うために、未来を想像することは大切なことです。この点は必ず深掘りしています。
⑤ スタッフにはどんな人生を歩んでほしいか?
企業のブランド価値は、社員の意識や働き方にも大きく影響を受けます。そこで、経営者がスタッフに対してどのような人生を歩んでほしいと考えているのかを深掘りします。
- どんな価値観やスキルを持った人材に成長してほしいか?
- 会社での経験が、スタッフの人生にどんな影響を与えることを望んでいるか?
- 仕事を通じて、社員にどんな達成感を味わってほしいか?
この問いへの答えが明確になると、企業文化がブランドの一部として機能するようになります。
ちなみに、私が担当しているクライアントの社長さんは、この問いを、知り合いの経営者からされたそうで即答できずに焦りを感じたとおっしゃっていました。
というのも、その社長さんが経営する会社は採用人数は多いものの、退職者もそれなりに多く、人事面でかなり苦労していたためです。
この問いは、意外にも人事面に大きな影響を与えるため、採用ブランディングの視点でも重要です。「この会社で働くことでどんな成長ができるのか?」が明確になることで、求職者に対して魅力的なメッセージを発信できるようになります。
経営者/社長個人のブランディングは企業活動のあらゆる場面で活きる
ここからは、具体的にどのような場面で経営者/社長個人のブランディングが活きるのかについてお話ししたいと思います。
ただ、その前に前提をお伝えしておきます。誤解してほしくないのは、創業者と企業の世界観が全て「イコールになる」わけではないということです。これは、ブランディングの失敗事例としてよく挙げられる点でもあります。
もし、創業者の個人的な世界観がそのまま企業の表現に落とし込まれてしまうと、関係性が近い人から心が離れていく可能性が高くなります。その理由は、「誰のためのブランドなのか」が曖昧になり、「判断基準が創業者に依存してしまう」からです。
身近な人が一度そのように認識してしまうと、企業のビジョンとスタッフのビジョンの接点も曖昧になり、その会社に居続ける理由が徐々に薄れてしまうんです。
創業者の想いが企業の存在意義に繋がり、創業者の一貫性が企業の一貫性に影響を与えるのは確かですが、企業と創業者はあくまでも別々のブランドであり、別人格です。
これを、子育てに例えると分かりやすいかもしれません。親と子供は似ている部分があっても、それぞれが異なる個性を持っています。
この前提を踏まえた上で、話を進めていきます。
前提のすり合わせが全ての採用現場でミスマッチを最小限に
人材採用において、「待遇や福利厚生」以上に重視されるのが 企業のビジョンや価値観 です。
求職者は「この会社に自分のキャリアを預ける価値があるか?」を考える際、単なる会社概要や制度だけでなく、経営者がどんな未来を描いているのか、どんな想いで事業をしているのか を重視するようになっています。
たとえば、採用サイトや説明会で経営者自身が
- なぜこの事業をしているのか?
- どんな人と一緒に働きたいのか?
- 会社での経験を通じて、社員にどんな成長をしてほしいのか?
を発信することで、企業の理念やカルチャーに共感する人材が集まり、ミスマッチの少ない採用が実現できます。実際に、経営者の発信に共感して応募する求職者は定着率も高くなる傾向があります。
営業の現場でスピーディーかつ理念に沿った対応が可能になる
BtoB、BtoCを問わず、ビジネスは最終的に「人と人の信頼関係」で成り立っています。
現代は、モノや情報が溢れている時代なので、「人検索の時代」とも言われています。そのため特に競争が激しい市場ではこの流れが急速に進んでいます。
「この企業と取引したい」「どうせ買うならあの人から買いたい」顧客からそう思ってもらうために、製品やサービスのスペックに加えて、「企業スタンスの可視化」や「サービス力」が肝になります。
こうした状況下において、経営者や企業の価値観が明確であれば、社員も自社の価値観を理解し、それに基づいた意思決定ができるようになります。この状態こそ、「ブランドが仕組み化された理想的な形」です。経営者が直接関与しなくても、社員一人ひとりが自律的に動ける組織へと成長していきます。
実際、インナー広報やインナーブランディングに力を入れ、社長が自身の考えや日常の気づきを発信することで、それが共感を生み、ビジネスのきっかけになるケースも多くあります。
ストーリーを活かした発信が可能になる
企業が発信するメッセージの中で、「経営者自身の言葉」は非常に強い影響力を持ちます。
同じ事業内容であっても、
- どんな想いで事業を始めたのか
- なぜその価値を提供し続けるのか
- 社会にどんな変化をもたらしたいのか
といったストーリーが加わることで、企業のブランドに共感を得てもらいやすくなります。
最近では、企業のPR活動において経営者が直接登壇したり、インタビュー記事やブランドムービーを通じてメッセージを伝える機会が増えています。これは、単なる広告やマーケティングメッセージよりも、「経営者自身の生の声」や「ストーリー性」が人々の心に響き、記憶にも残りやすいためです。
経営者のブランディングが強化されると、企業の広報戦略も一段と効果的になります。
戦略の方向性が明確になる
企業経営において、「戦略の軸がブレること」は最も避けるべきリスクの一つです。
特に、成長フェーズにある企業では新規事業の立ち上げや市場の変化への対応が求められますが、その際に経営者自身の価値観や判断基準が明確になっていないと、場当たり的な経営判断になりやすい という問題があります。
経営者のブランディングが確立されていると、事業の方向性を決める際にも、以下のような一貫性を持つことができます。
- どんな価値を提供し続けるべきか?
- どんな市場で勝負すべきか?
- どのようなパートナーと組むべきか?
たとえば、Appleのスティーブ・ジョブズは、「美しく、シンプルで、革新的なプロダクトを届ける」という信念を貫き続けました。その結果、Appleの全ての製品・サービスがその理念のもとに統一され、世界的なブランドへと成長しました。
経営者の価値観が定まっていないと、短期的な市場のトレンドに振り回され、一貫性のない事業展開 になってしまいます。しかし、ブランディングが確立されていれば、事業の成長とともに 企業のアイデンティティが揺らがないという強みを持つことができます。
顧客や求職者から選ばれ続けるために
最終的に、企業が持続的に成長するためには、 顧客や求職者から「この会社だから選びたい」と思われる存在であり続けること が不可欠です。
そのためには、企業のブランド力を高めることはもちろん、経営者自身の考えを明確にし、一貫したメッセージを持つことが大きな武器になります。
経営者のブランディングが確立されると、
- 顧客にとっては、「この企業なら信頼できる」と思える理由になる
- 求職者にとっては、「ここで働きたい」と感じる決め手になる
- 社員にとっては、「自分たちが目指すべき方向」が明確になる
といった 企業活動全体にポジティブな影響をもたらします。
また、「選ばれる企業」になるためには、
- 機能的な便益と独自性
- スタイルとしての付加価値
- スタンスへの共感
上記の3つが一つの軸に沿って設計し、購買につながるような特定のイメージとして伝えていかなければなりません。(この三つの要素に関しても非常に重要なポイントなので後日記事にしたいと思います)
その軸を明らかにするために、企業の表面的なブランディングだけでなく、その根幹にある 経営者自身の考えや価値観を明確に言語化し周囲に発信し続けることが何よりも大切です。
自社のブランドをより強く、より選ばれるものにするために、まずは 経営者自身のブランディングから取り組んでみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級