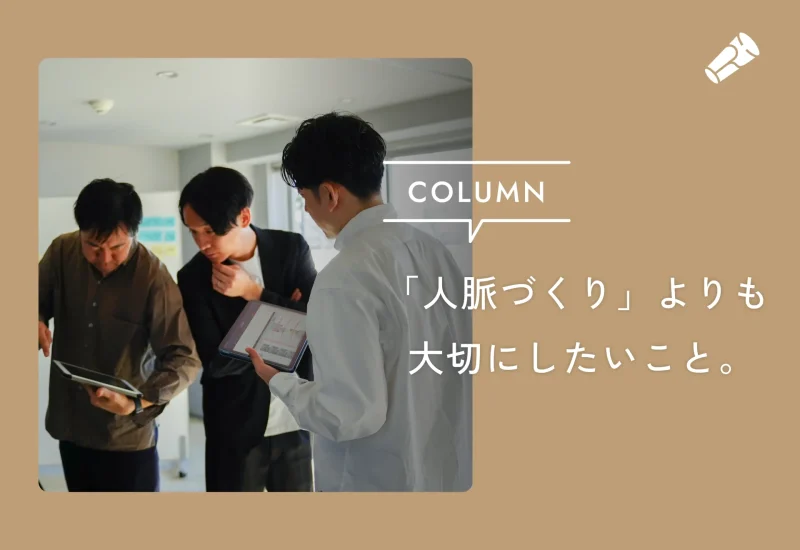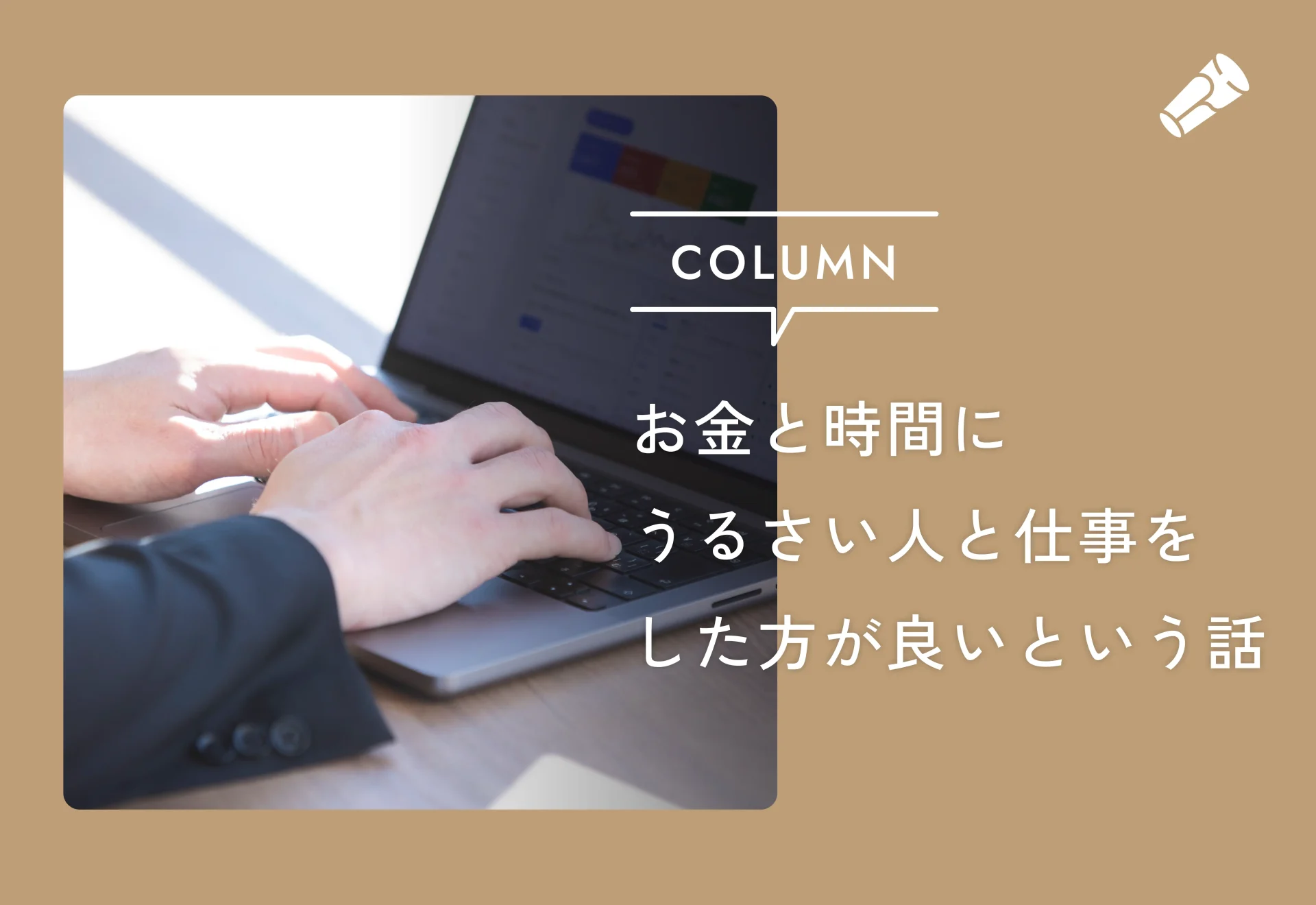
私の経験上、お金と時間にうるさい人いるプロジェクトは大抵、生産性が高いですし、成果も想像以上になります。
にもかかわらず、お金と時間の話から目を背けようとする方は少なくありません。
ただ、ここから目を背けてしまうといつまで経ってもブランドを成長させることはできませんし、大切な仲間を守ることもできません。
理想を現実にするためには、お金と時間も欠かせない資源なので当然と言えば当然なのですが、この事実は特に経営者以外の方にこそ意識していただきたい話です。
またどんな小さなプロジェクトであれ、お金と時間にうるさい人は必ず必要になってくるのでその理由についても書いていきたいと思います。
お金や時間と向き合うからこそ付加価値が生まれる
私自身、かつては「お金や時間の話は面倒くさい」と感じていた時期がありました。
細かく管理するのが苦手で、数字に縛られることでクリエイティブの自由度が下がるような気さえしていたからです。
でも、それは現実を見ていない甘えでした。
転機となったのは、20代後半で店舗運営や事業責任を任されたときです。
売上や利益、スタッフの稼働時間や諸経費など、すべてに目を配らなければ、事業が回らない現実に直面しました。
そこではじめて、「お金や時間と正面から向き合うことこそ、理想を実現するために欠かせないプロセスだ」と実感したのです。
・・・
たとえば、カフェで新メニューを開発するとします。
ただ「美味しいものをつくりたい」だけでは足りません。
原価はどれくらいか、仕込み時間は現場に無理を強いないか、価格設定は利益を確保できるか——
その一つひとつを現実と照らし合わせて考えなければ、どんなに魅力的な商品でも継続できません。
感覚だけで動くと、結果的に現場にしわ寄せがいきます。
スタッフの稼働が限界を超えれば、サービス品質は落ち、最終的にお客様に届けたい価値まで損なわれてしまう。
時間もお金も大量にかければ、ある程度良いものが出来上がるに決まってます。
けれども、多くの企業がリソースに制限があるからこそ、そして、先ほどあげたリスクを回避するためにも、お金や時間の視点で逆算する力や視点が必要なんです。
何かを諦めるためではなく、「どうすればこのアイデアを持続可能な形で実現できるか」を考える。
その起点にあるのが、数字と向き合う姿勢です。
人件費を軽視すると持続しなくなる
コスト管理の中でも、最も見落とされやすいのが「人件費」です。
目に見えないから、つい見過ごしてしまう。
けれど、この“見えにくさ”が、プロジェクトの持続性を根底から揺るがすことがあります。
たとえば、100万円の予算でイベントを開催するとします。
チラシ制作や会場費、飲食の手配など、外注費や実費はすぐに積算できますが、「誰がどれだけの時間を使って準備し、当日どう動くのか」という人的リソースにかかるコストは、把握されないまま進行するケースが少なくありません。
仮にその準備・運営に50万円分の人件費がかかっていたとしたら、実質的な総コストは150万円。
表面上は100万円に見えても、実際には大きな負荷がかかっているわけです。
ここで問題になるのは、表面上の数値に合わせて「来年もこの内容で、同じ金額でお願いします」と言われたとき。
現場は疲弊しますし、リピート実施を前提にした改善も生まれづらくなります。
そうなると、結果としてクオリティが下がり、参加者の満足度も低下。
続ける意義そのものが揺らぎます。
どこにどれだけの力が注がれているのかを、はじめから丁寧に可視化しておかないと、企画全体の設計がズレていきます。
持続性を担保するためにも、「人件費をどこまで織り込むか」を曖昧にしないこと。
これは、小さなプロジェクトでも、大規模な事業でも変わりません。
知識人材へのお金と時間を値切ったら終わり
今の時代は「知識社会」と言われます。
つまり、“知識そのものが価値を生む”時代に突入しているということ。
裏を返せば、ただモノをつくって出すだけでは、選ばれない。
だからこそ、これからの事業でますます重要になるのが、「知識人材とのつながり」です。
ここでいう知識人材とは——
私なりの定義ですが、特定分野に深い知見や経験をもち、それをクリエイティブに活かす力があり、人との信頼関係や共感性を生み出せる人たちのことを指します。
企業として、こうした人材を社内に抱えるのか、外部と協業するのかはケースバイケース。
ただ、どちらにしても一つだけ、大前提があります。
それは、「値切ったら、そこで終わり」ということ。
依頼する側は、まずその仕事にどれくらいの工数や準備が必要か、最低限でも想像する努力が必要です。
そして、「どのくらいの報酬であれば、相手の知見や発想力を最大限に引き出せるのか」まで含めて、誠実に考えるべきだと思います。
この前提を理解していない人がプロジェクトを仕切っている限り、本質的に良い成果が出ることはありません。
お金や時間と向き合うというのは、単にコストを切り詰めることではありません。
むしろ大事なのは、仲間やパートナーの力を最大限に引き出せるような“取引条件”や“関係性”をどう築くかということ。
たとえば、「他の人はもっと安くやってくれるから、あなたもこの金額でお願いできませんか?」と交渉した瞬間——その人が本来もっている価値や創造性は、もう引き出せなくなってしまいます。
知識やアイデアに対する敬意がなければ、競争優位につながるような発想力や提案力なんて、手に入りません。
ちなみに弊社では、外部パートナーと日常的に連携していますが、「値切る」という交渉は一切していません。
むしろ、きちんと対価を払った方が、結果としてずっと良いアウトプットにつながると、実感しています。
もちろん、こちらが適正な対価を支払っても、成果に納得できないこともゼロではありません。
でも、そのときは粛々と依頼先を見直すだけ。そこで騒いだり責めたりはしません。
それくらい、「知識に対価を払う」という前提を、おろそかにしないことが、これからの時代においては何よりも大切だと感じています。
お金や時間の管理者もまたクリエイティブ職
プロジェクトにおいて、お金や時間の管理を担うのは、主にプロジェクトマネージャー(PM)です。
ブランディングやWEB制作など、さまざまなプロジェクトに関わってきて感じるのは、PMの存在がいかに大きいかということ。
この役割がなければ、プロジェクトが予算内・スケジュール通りに完了することはまずありません。
そして、実は“クオリティ”にも大きな影響を与えています。
よく「クリエイティブディレクターがいればPMは不要では?」と思われがちですが、それは違います。
そもそも、両者の役割はまったく別。
PMがいない場合、ディレクターがスケジュール管理や契約調整まで兼任することになりますが、それでは本来注ぐべきリサーチや思考の時間が削られ、クリエイティブの質が落ちてしまうことにもつながります。
先日、建築会社でPM的な役割を担っている方とお話ししました。
「私は基本的に、お客様とする話は堅苦しいものばかりなんです。予算のこと、スケジュールのこと、契約周りのこと。でも、その調整役を担うことで、“言った・言わない”のトラブルを防げて、結果的にプロジェクトがうまくいく。私は目立たない立場だけど、この仕事がすごく好きなんです。」
そう語る姿に、何だか胸が熱くなりました。
もし、こういう人がプロジェクトを支えてくれていたら、クリエイターはもっと制作に集中できるし、クライアントも不安なく任せられる。
PMがいなければ、完成後の「やりきった」という気持ちよさも薄れるし、そもそも“付加価値”なんて生まれないのかもしれません。
そう考えると、予算やスケジュールという“数字の領域”に真摯に向き合いながら、プロジェクト全体の成果を設計するプロジェクトマネージャーもまた、立派なクリエイティブ職だと、私は思います。
だからこそ、「お金と時間にうるさい人と仕事した方が良い」これが私の結論です。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級