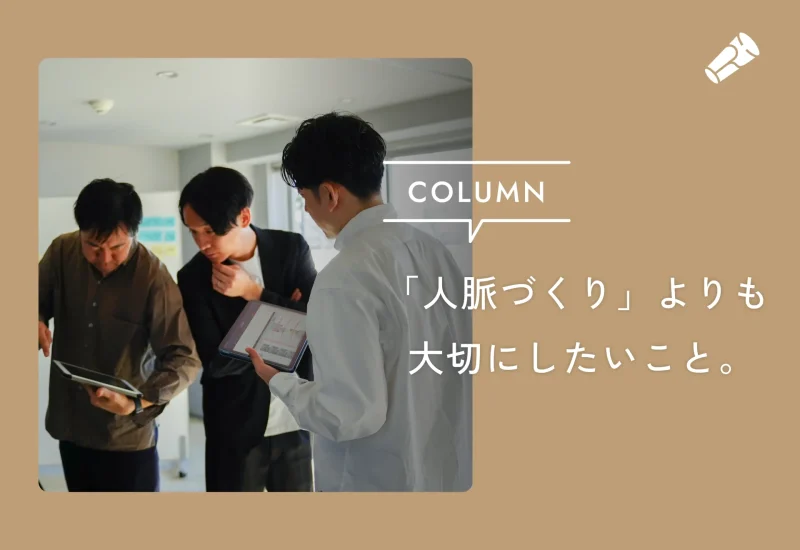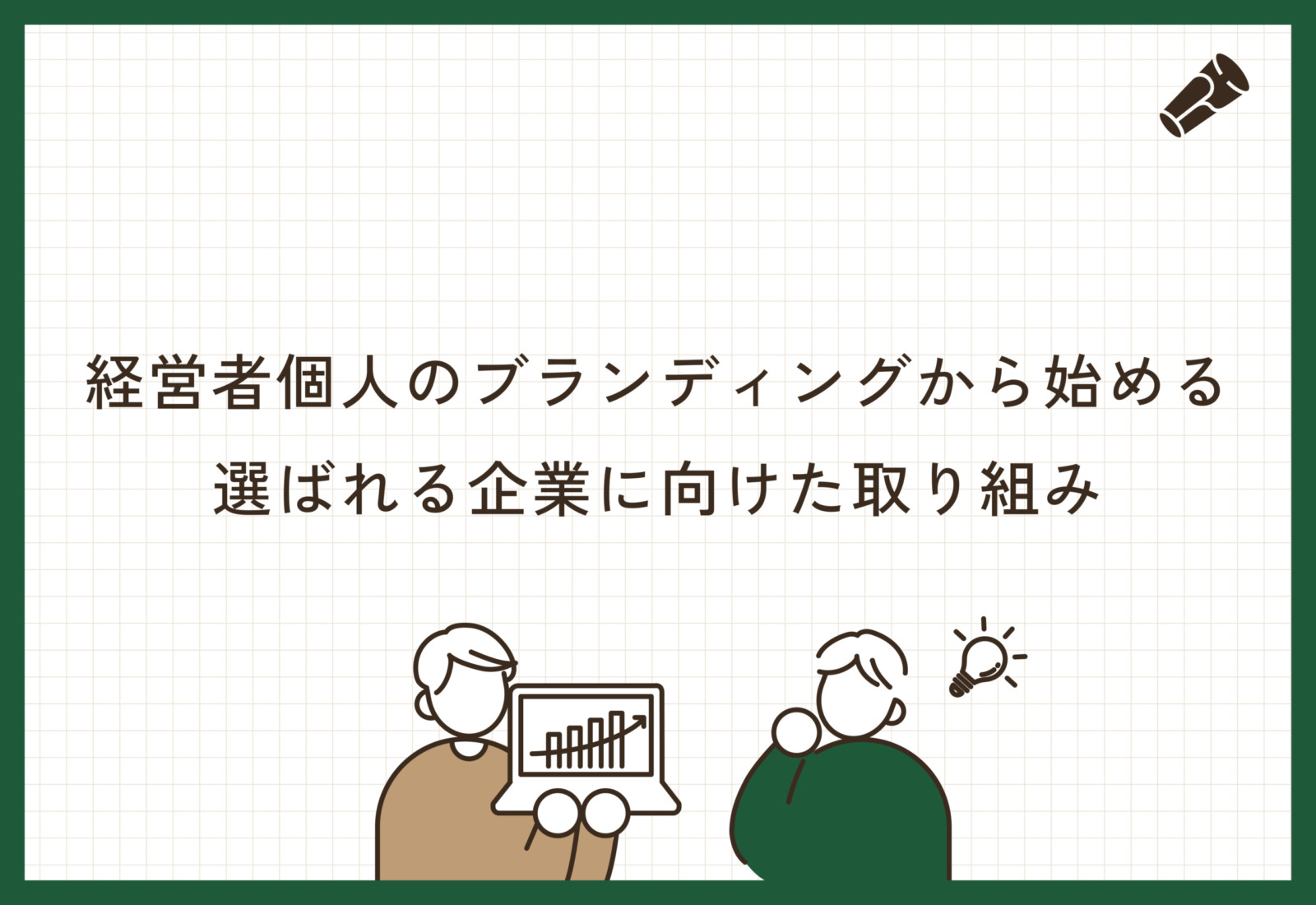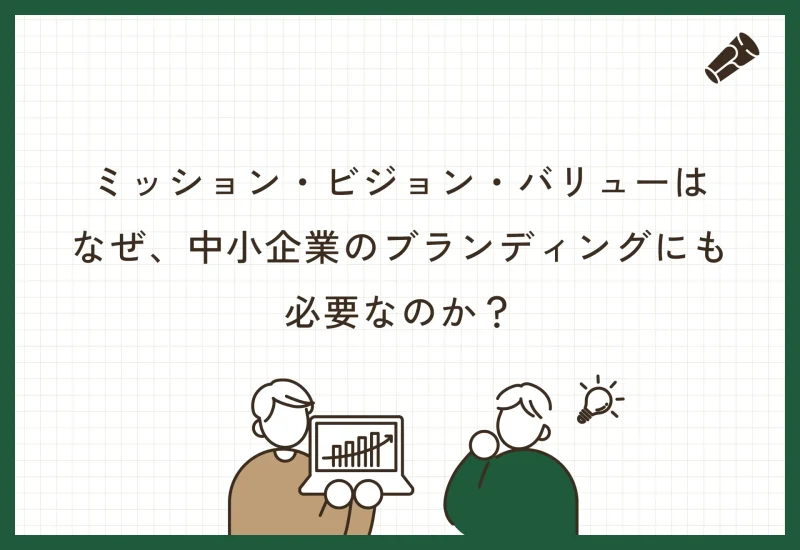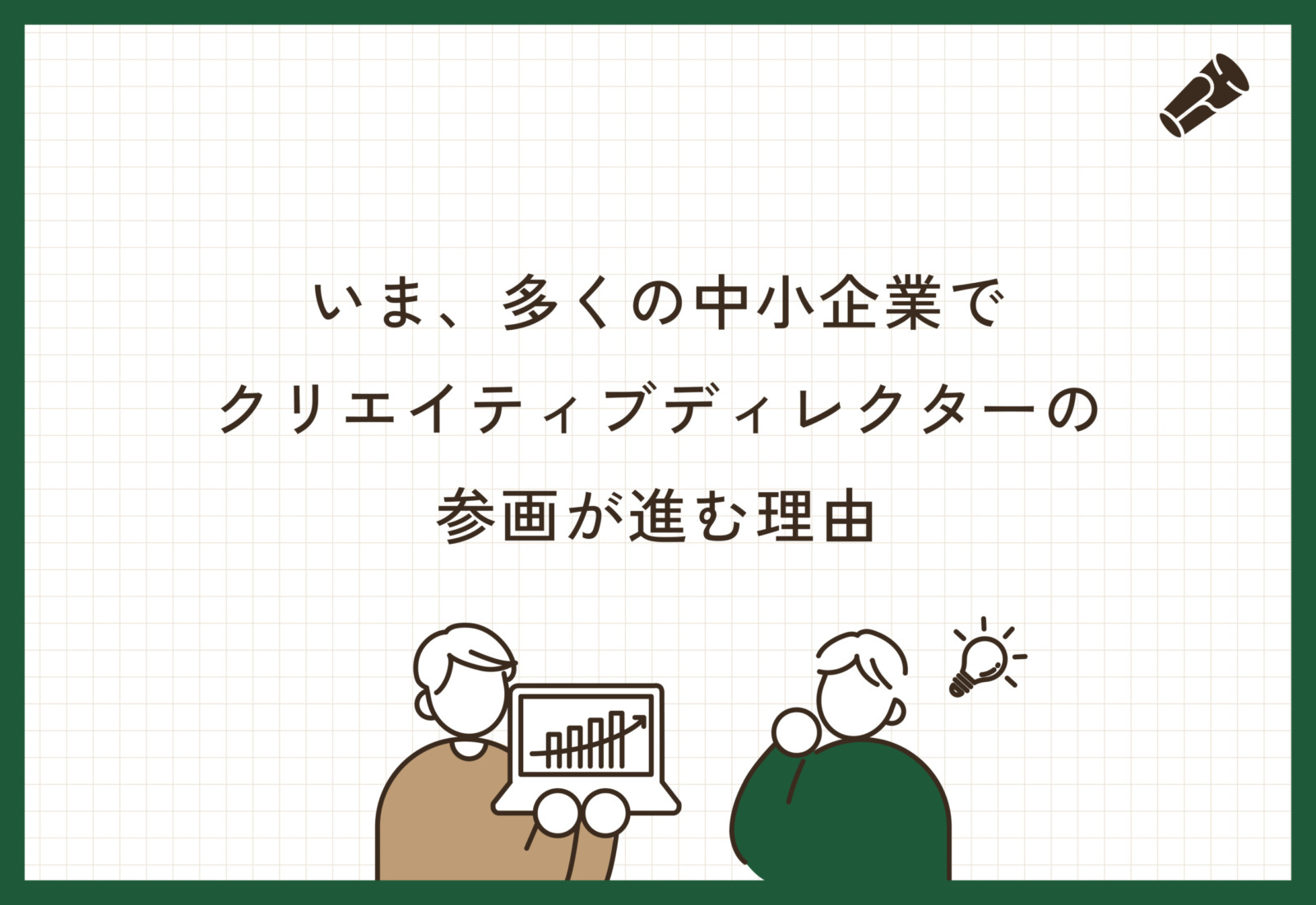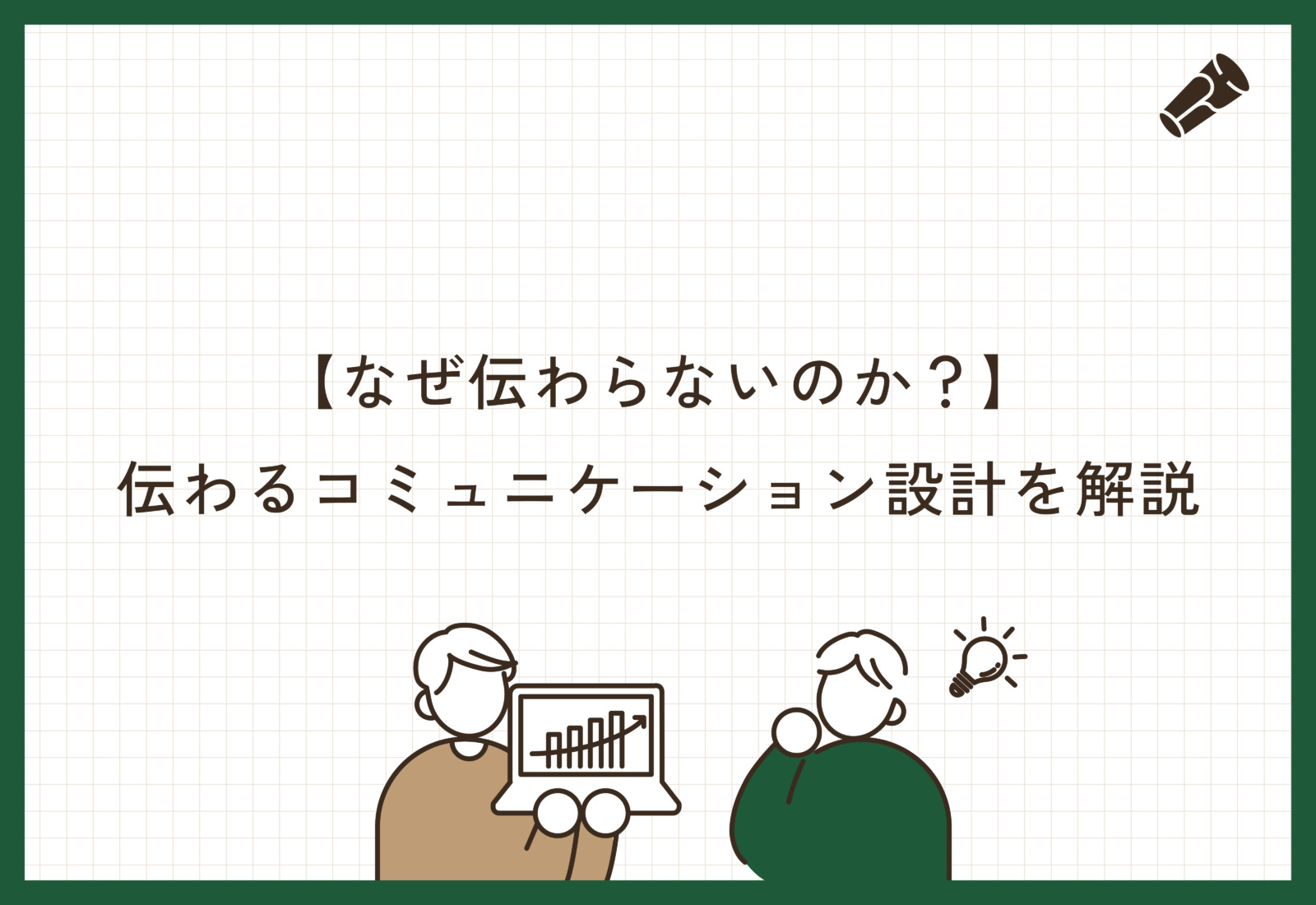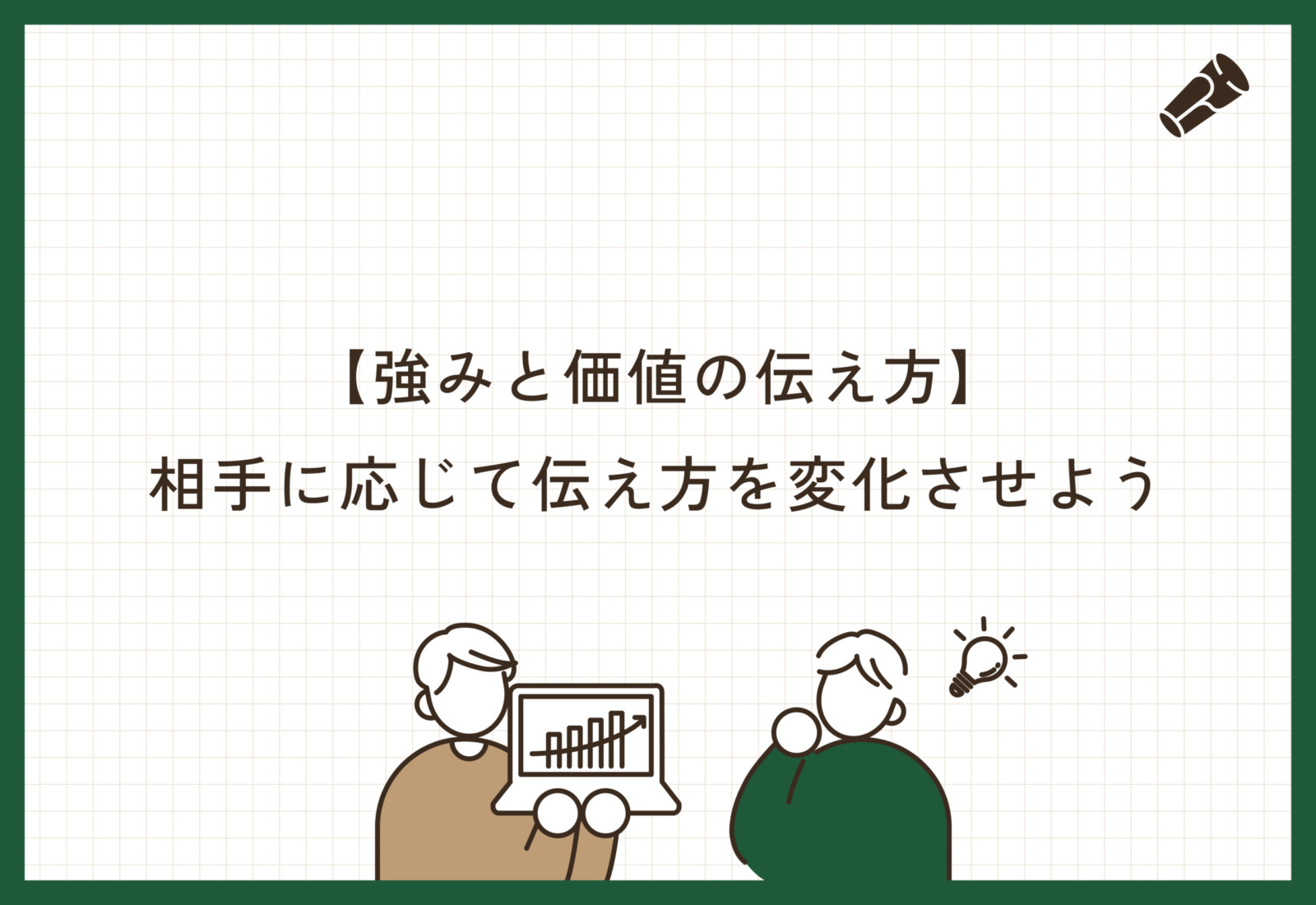「人の目を気にするな!自分は自分なんだから!」
SNSが流行し始めた頃からか、よくこのような意見を耳にするようになりました。
確かにごもっともで、周りの目を気にしすぎると、その人のポテンシャルを十分に発揮することができません。(企業活動においても同じことが言えると思います)
ただ、これって白か黒か(善か悪か)の話ではないんです。
「誰にどう思われたいか」を明確にしよう
私はブランディングを専門として活動をしています。
その中で、クライアントさんによくお伝えしているのが、「誰にどう思われたいかに答えられなければ、何者かにはなれない」ということです。
ブランディングとは、何者かになるための活動。
つまり、主語を強くする活動です。
言い方を変えるなら、「誰にどう思われたいかに答えられなければ、ブランディングはできない」ということになります。
この話をすると、よく「それって人の目を気にするってことですか?」と聞かれます。
もちろん、答えはYESです。
ブランディングは、人の目を意識しないと始まりません。
「人の目」と言うと少し抽象的かもしれませんが、つまりは「誰のどんなニーズを気にするか」ということ。
そして、「どう思われたいか」とは、「どんな存在として記憶されたいか」「どんな感情を残したいか」「どう記号化されたいか」と言い換えることもできます。
ここが定まっていなければ、ブランディングは「自己満足」や「内輪ノリ」で終わってしまいます。
ブランディングは、他者の視点で自分(や企業)をどう位置づけるかということ。
だからこそ、人の目——もっと言えば、人の欲求を気にせずに成り立つはずがないんです。
・・・
補足になりますが、「何者かになる」というのは、別に有名人になることを指しているわけではありません。
私自身も、有名になりたいとは思っていませんし、もし「何者かになる=有名になる」だったら、おそらくこの仕事はしていないと思います。
ここで言う「何者かになる」とは、「自分という存在や、その個性・独自性が、自分以外の誰かに識別されている状態」のこと。
企業であれば、「自社や自社の商品・サービスの存在や独自性が、ステークホルダーに識別されている状態」を指しています。
八方美人でも何者にもなれない。
私は以前、カフェの経営に携わっていたことがあります。
その時に強く意識していたのが、「幕の内弁当ではなく、唐揚げ弁当を作るようなイメージ」でお店の基盤をつくることでした。
「なんでもあって、まぁ便利!」なお店ではなく、強く満足してくださる方がいる一方で、「ちょっと違うかも」と感じる方もいる。
そんな、ある意味で“振り切った”店づくりを目指していたんです。
あらゆるニーズに応えようとすると、どうしても資源は分散しますし、大手企業が提供する利便性や価格には太刀打ちできません。
さらに、お客様の声にすべて応えようとして、あれもこれも取り入れてしまえば、「便利なお店」としては機能するかもしれませんが、「記憶に残る店」にはならない。そう思ったんです。
だからこそ、まず、「一人の心を圧倒的に満たす」というスタンスで、サービスを磨いていきました。
そしてその一人のために、商品やサービスの改良を重ねるうちに、結果として売上も大きく伸びました。
ここで伝えたいのは、「人の目を気にすることは大事ではあるが、あらゆる人の目を気にしてすべてのニーズに応えようとするのはあまり良いことではない」ということ。
強い感動や満足は、“ピンポイントな共鳴”からしか生まれません。
だからこそ、「人の目を気にする」ことには意味があっても、「すべての目を気にする」ことには大きな落とし穴があるんです。
対立構造で捉えず、コミュニケーションを整える
「人の目を気にすること」と「自分の軸を持つこと」って、対立するように思われがちです。
でも、実はそこに対立構造はありません。
繰り返しになりますが、本当に問題なのは、「誰の目を気にするのか」を選ばず、ただ“みんな”に嫌われたくない、と思ってしまうこと。
この“みんな”というふんわりとした対象を意識しはじめると、どんな表現も角が取れて、まるく、まるくなっていきます。
結果、「誰にも嫌われない」かもしれないけれど、「誰の心にも残らない」ものができあがってしまう。
私たちがブランディングで扱っている「誰にどう思われたいか」という問いは、むやみに人の目を気にするという話ではありません。
「このニーズを持っている人たちには、こう見られた方が良い。けれど、それ以外の人には、別に興味を持たれなくてもいい」
そんなふうに、意図して“共感を選び”、コミュニケーションを整えていくという行為なんです。
まとめ
「人の目を気にする」と聞くと、どうしてもネガティブな印象があります。
でもそれは、「不特定多数の人から嫌われたくない=人の目を気にする」と誤解されがちだから。
けれど、ターゲットとなる人との関係性を育むために、あるいは、独自性を認知してもらうために、「誰の目(欲求や感情)に気を配るのか」と捉え直すと、それは全然ポジティブなこと。
そして、これは「自分の価値観を貫くこと」と案外同義だと思っています。
むしろそれこそが、コミュニケーションの原点なのではないかと思います。
結論、「自分軸を貫くこと」と「人の目を気にすること」は、まったく対立するものではないので注意しよう、という話でした。
そもそも自分軸(会社ならば会社の価値観やスタンス)の先にも、必ず人がいるものなので。
だからこそ、ブランディングは自己表現ではなく、「他者との関係性の設計」です。
P.S.
個人的な意見ですが、「自分は自分」と自分を絶対視するよりも、譲れない部分をきちんと持ちながら、相手の感じ方や文脈に合わせて柔軟にスタイルや伝え方を変えていける人の方が、ずっと魅力的だと思っています。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級