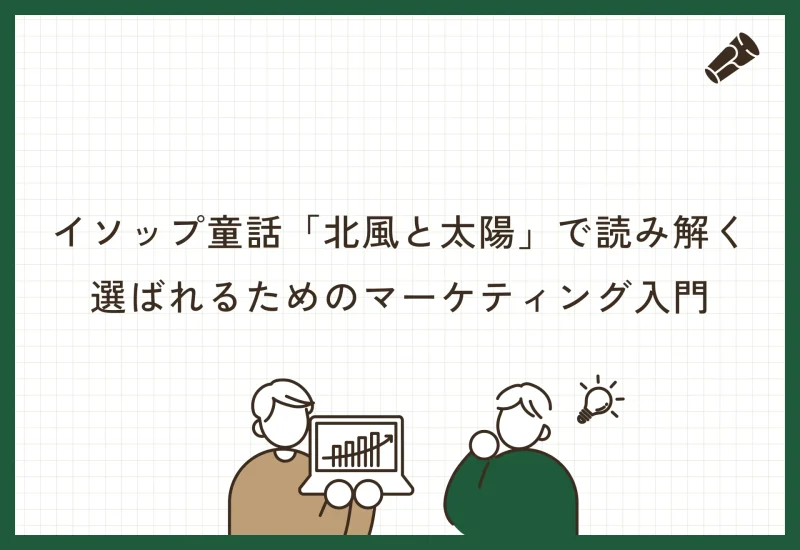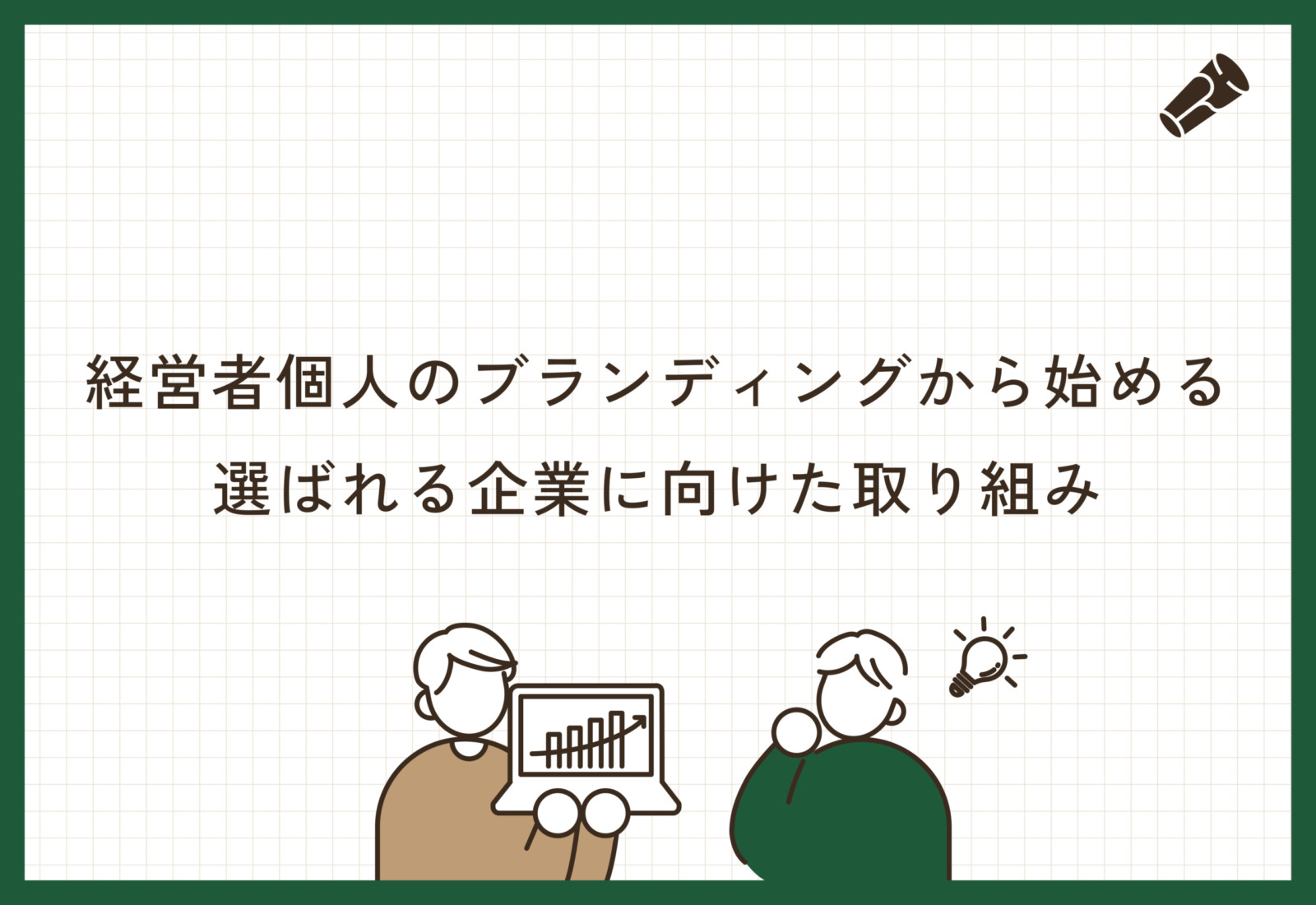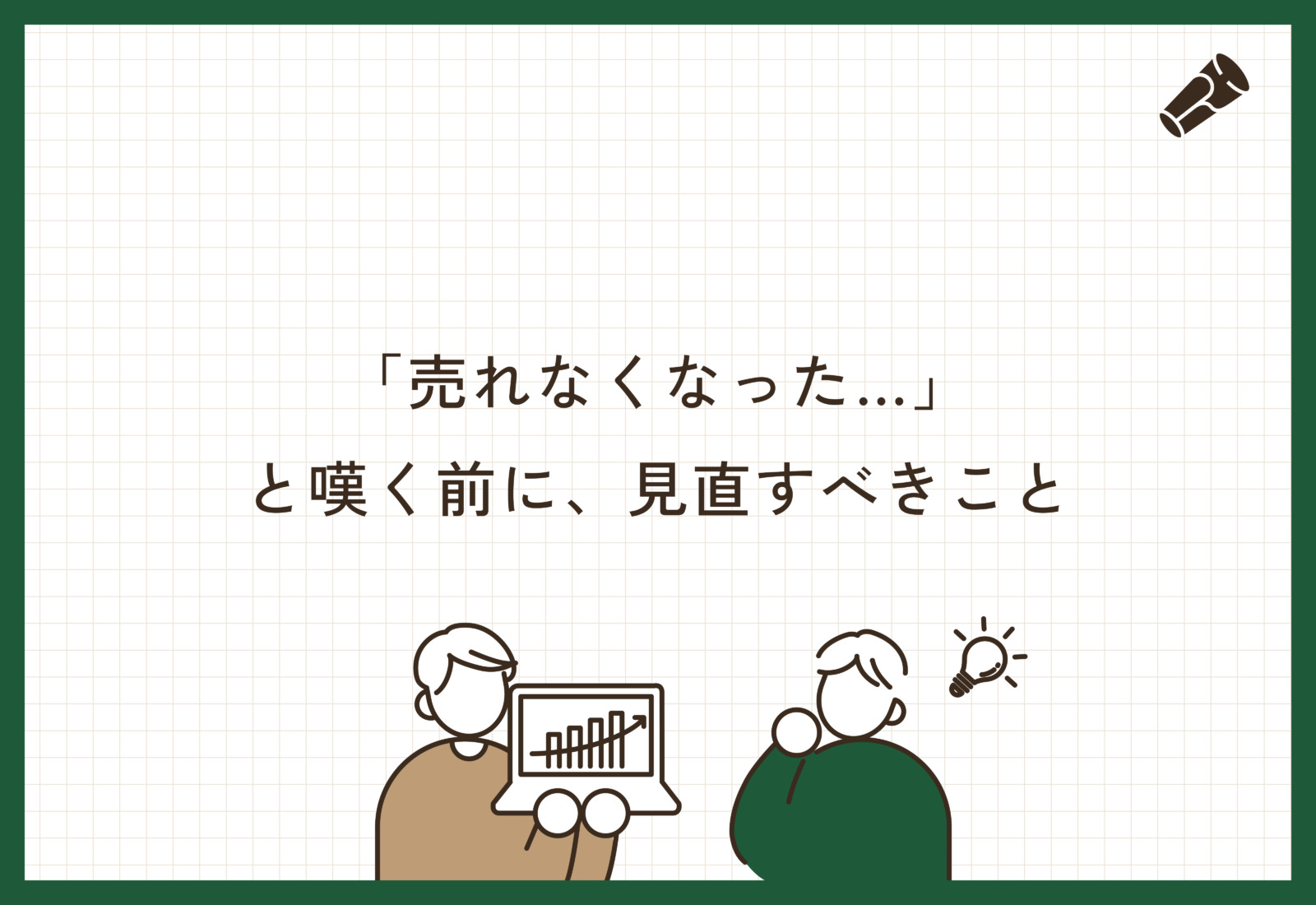Index
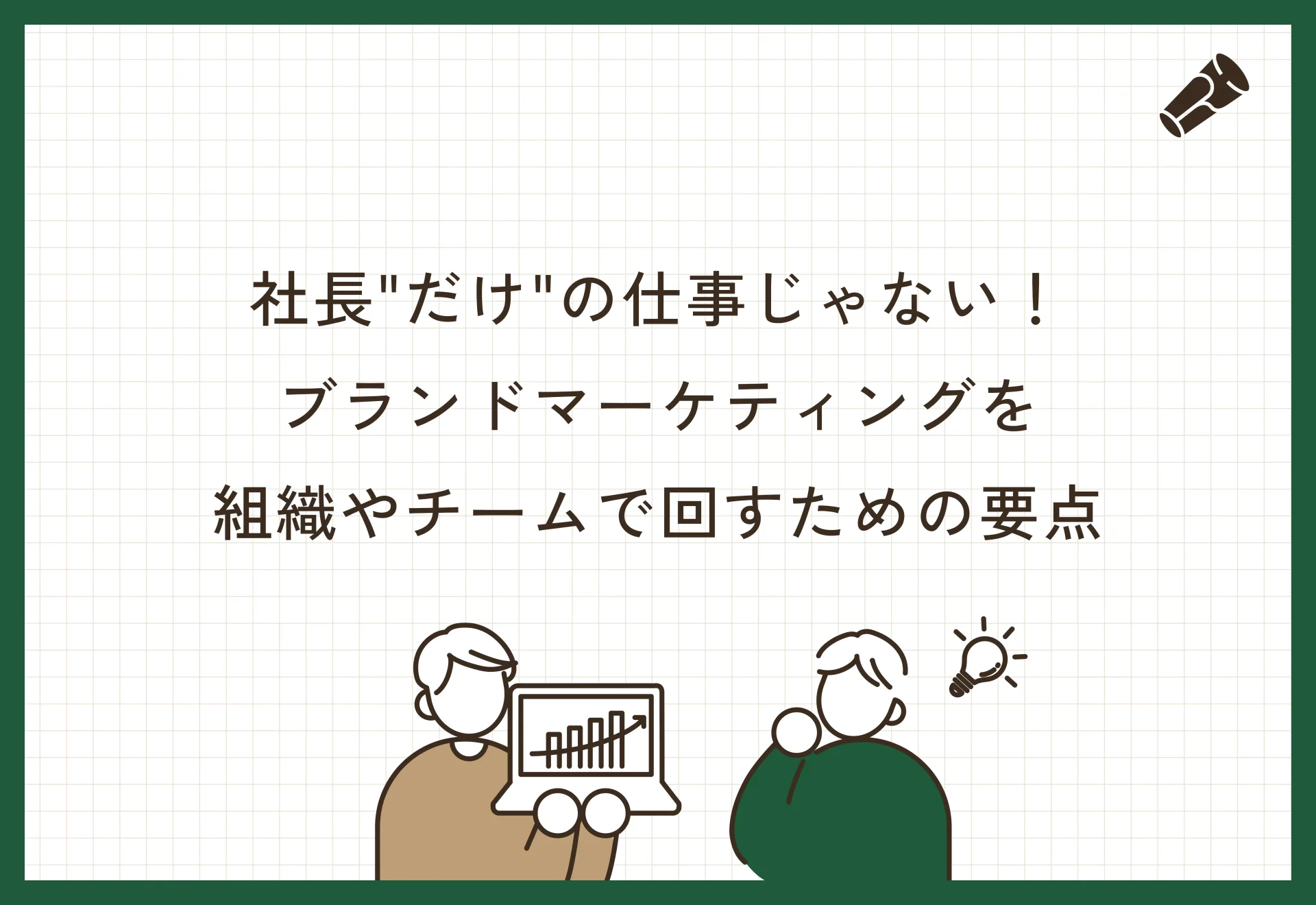
「マーケティングは社長がやるものでしょ?」
「ブランディングはデザイナーの領域。」
「マーケチームだけでやっておいてよ。」
こうした“思い込み”が組織に蔓延していたら、要注意です。
放っておくと、確実に競争力が落ちていきます。
大前提、私たちは「餅は餅屋」の考えを大切にしています。
強みは人それぞれ違う。
だからこそ、弱みにばかり目を向けるのではなく、強みを土台に役割を明確にする。
その上で、弱みはチームで補い合えばいい。それが組織であることの意味だと思っています。
じゃあなぜ、全員がマーケティングやブランディングに関わる必要があるのか?
それは、価値の起点が“顧客”にあるからです。
職種が違えば、アウトプットの形も違って当然。
でも、「誰に、何を、なぜ届けるのか?」という共通認識がなければ、ブランドはブレます。
お客様にとっての“意味ある価値”は、一貫性のあるチームからしか生まれません。
強いブランドには、強い“全体感”があります。
それは、全員が自分ごととして顧客視点を持ち、価値創出の担い手であろうとするからこそ成り立つのです。
【失敗談】やっているつもりが一番危険
以前、私は機械メーカーで営業マネージャー兼、新規事業の責任者をしていました。
その中で一番の壁は、設計部との連携でした。
顧客が本当に求めていることと、設計の技術力の接点を見つけるのが難しい。
さらに厄介だったのは、設計と営業の方向性が噛み合わず、ベクトルが揃わなかったことです。
当時の私はまだ未熟で、「お客様はきっとこういうものを求めている」という感覚をうまく言語化できず、設計部長からは「言ってることがよくわからない」「うちがやるべきことなのか?」と疑問を投げかけられる日々。
ただ私は、現場で感じるニーズと製品づくりの方向に、明確なズレを感じていました。
何度も話し合いを重ねた末、設計部から返ってきたのはこんな言葉でした。
「営業部の言いたいことは、なんとなくわかっている。こっちも、それをくみ取ってモノづくりと向き合っている“つもり”なんです。それだけは信じてほしい。」
私はこの一言に、強く反省させられました。
営業側は「伝えたつもり」。設計側は「応えたつもり」。
でも、実際にはお互いがズレたまま進んでいた。
どちらも“真面目にやっている”んです。でも、だからこそ怖い。
「つもり」は、組織の中でじわじわとズレを拡大させます。
“誤解の連鎖”が起きていることに気づかず、成果が出ない理由を外に求め始める。
ここで必要なのは、「顧客は誰で、どんな価値を届けるのか」という認識を全体で揃えること。
現場感覚と技術、そして戦略がつながらない限り、どんなに頑張ってもズレは解消されない。
「やってるつもり」の怖さに気づけたこの経験は、今の根本的なブランドマーケティング支援の原動力になっています。
チームの中にズレがあるとき、それは誰かの能力不足ではなく、意思統一の不足です。
だから、私たちは現場にも戦略にも入り込むんです。
組織単位でマーケティングを実践するための鍵は腹落ち感
私がこの失敗から得た最も大きな学びのひとつは、「理解していること」と「実際にできること」の間には、大きな溝があるということ。
そして、その溝を埋める鍵は、「自分たちが提供する価値に対して、腹落ちしているかどうか」にあります。
言葉にするとシンプルですが、組織の全員がこの腹落ち感を持つためには、それ相応の時間と工夫が必要です。
しかし裏を返せば、ここが腹落ちしているメンバーが増えれば増えるほど、組織のアウトプットには力強さが生まれます。
経営者の方なら余計に、この“腹落ちの威力”を実感されたことがあるかもしれません。
もちろん、全員が複雑な戦略や事業構造まで理解し、納得しきるのは現実的に難しい。
ですが、最低限、「この仕事は誰のどんな困りごとを解決するためにあるのか?」「自分は今、そのために何をするべきなのか?」
この問いに対して明確に答えられる状態をつくることは、やろうと思えばできます。
実際に、私のクライアントでもこの「腹落ちの設計」ができている会社さんほど、戦略と現場の行動がしっかりと接続し、成果を出しています。
個人が腹落ちして動くと、組織は想像以上の推進力を持ちます。
マーケティングを“機能”で終わらせず、“組織の力”として使うために、この感覚は欠かせません。
腹落ち感に欠かせない「センスメイキング理論」
組織全体で「腹落ち感」を共有し、個人の行動を組織の目的に接続させるためには、単なる根性論では足りません。
そこで鍵になるのが、「センスメイキング理論(Sensemaking Theory)」の理解と実践です。
この理論は、組織論の大家カール・ワイク(Karl E. Weick)が提唱したもので、組織や個人が不確実で曖昧な状況に置かれたとき、意味づけを通じて行動の方向性を見出していくプロセスを示したものです。
簡単に言えば、「人は意味づけをして初めて、動くことができる」という、極めて実践的な人間理解に基づいた理論です。
センスメイキングは、おおよそ以下の3つのステップから成り立っています:
1. 環境の感知(Enactment)
外部環境や顧客ニーズ、社内の空気感といった“変化の兆し”を感知し、現場から情報を拾い上げる段階。
2. 解釈・意味づけ(Selection)
感知した情報を自分たちの文脈で咀嚼し、「この変化は自分たちにとってどういう意味を持つのか」を判断するフェーズ。
3. 行動・実践(Retention)
意味づけをもとに具体的な行動を起こし、その結果を記憶として残す。これが次の判断に影響し、プロセスは循環していきます。
重要なのは、このプロセスが「一回きり」ではなく、変化し続ける環境の中で“何度も繰り返される”という点です。
つまり、腹落ちとは一度与えられるものではなく、日々の観察・対話・実践を通じて、徐々に深まっていくものなのです。
マーケティングやブランディングのように、「未来の可能性」を形にしていく仕事においては、このセンスメイキングが極めて重要になります。
「なぜこの方向なのか?」「なぜこの顧客に届けるべきなのか?」という問いに対する納得感が組織に浸透していれば、戦略の実行力が格段に上がります。
逆に、この納得感がなければ、どんなに優れた戦略も現場で空回りしてしまう。
センスメイキングは、腹落ちを構造的につくり出すための武器です。
マーケティングを“知ってるだけの活動”に終わらせず、“組織の血肉”にしていくためには、欠かせない視点だと私は考えています。

腹落ちを“文化”に変えるために必要な3つの取り組み
組織全体に腹落ち感を持ってもらうにあたっておすすめの3つの取り組みを紹介します。
他にも方法はいくつもありますが、この記事ではよくご相談いただく3つの絞って解説します。
1. 日常業務と接続されたMVVの設計
ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を掲げてはいるが、現場では誰も言えない。
そんな状態では、腹落ちしようがありません。
重要なのは、メンバー一人ひとりが「これは自分の仕事とどうつながっているのか?」とイメージできるようにすること。
抽象的な言葉を並べるのではなく、実務と接続できる具体性を持たせる。
「これはこの判断の拠り所になる」と思えるレベルまで落とし込まれたMVVこそが、組織の重心になります。
(この取り組みは意味合いはインナーブランディングと近しいです。)
これまでの経験的には、MVVは多くの意見の最大公約数的な内容にすべきではないと考えています。
そのため、ここはリーダーや主要メンバーのみでじっくり深掘りしながら再構築していくことをおすすめします。
ただ、そのMVVに込められた想いは何なのか? どう日々に落とし込むべきなのか?
それらについて考えるワークショップは、スタッフ全員とまでは言わないまでも、より多くのメンバーを巻き込んでディスカッションする場を設ける必要があります。
また、企業全体としてMVVを体現する様子を事細かく可視化するという取り組みも欠かせません。
たとえば、MVVに基づいた誰かの何気ない行動の様子を広報・PR担当にコンテンツにしてもらうことや、一つの大きな決断の意図を経営者自らが発信する場を(オンライン上でも構わないので)設けることなど。
こうした一つひとつの取り組みが、腹落ち感を育てていくことにつながっていきます。
▼ビジョンやミッションについては、以下の記事でより詳しくご紹介しています。
ぜひあわせてお読みください。
MVV策定の意味とは?MVVはなぜ、中小企業のブランディングにも必要なのか
2. 主要メンバーを巻き込んだ、新たな取り組みをつくるワークショップ
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を上から現場に「落とし込む」だけでは、組織に定着させるには不十分です。
むしろ重要なのは、主要メンバー自身がその思考プロセスに参加し、自らの言葉で語れるようになること。
「なぜ、今この方向に進もうとしているのか?」
「なぜ、この市場に挑むのか?」
その問いに対して腹落ちするには、頭で理解するだけではなく、自分の言葉で話し、仲間と議論しながら納得していくプロセスが必要です。
そうした意味でも、「企業として新しい取り組みをつくるためのワークショップ」は非常に有効です。
そこでは、戦略や方針の理解を深めるだけでなく、現場で機能する共通言語や価値観を形にしていくことができます。
つまり、単なるアイデア出しの場ではなく、「戦略を自分たちのものにしていく」ための内製化の第一歩として、非常に意味のある場になるのです。
ちなみに、これまでの現場では、ある企業さんにおいて、この取り組みを通じてスタッフ主導で以下のような新たな施策が始まった事例があります。
- 自社のカルチャーを広く伝えるための広報・PR部署が新設された
- 自社商品と顧客の接点を増やすためのオウンドメディアが立ち上がった
- 固定客(リピーター)向けの新サービスが開発された
など…。
この取り組みは現在も継続されており、徐々にその成果が「売上」や「企業への応募者数の増加」といった形で表れ始めています。
3. 客観性のあるフィードバックと “軌道修正文化” の醸成
どんなに精緻な戦略や方針であっても、現場での実行フェーズでは必ず“想定外”が起こります。
だからこそ、一度決めた方針を盲目的に遂行するのではなく、現場の肌感や変化を適切に汲み取り、柔軟に軌道修正していく仕組みが不可欠です。
そのためには、定期的なフィードバックの場を持つこと。
そして、組織として「改善を前向きに受け止める文化」を育てていくことが重要です。
たとえば、週1回のミーティングで「この施策、どこまで本来の価値提供につながっているか?」を確認する。
あるいは、プロジェクトの終わりに戦略との接続度を振り返るレビューをチームで実施する。
そうした機会を仕組みとして組み込むことで、軌道修正が当たり前の行動になります。
大事なのは、フィードバックを個人への批判と捉えず、「仮説と現実の差分を見極める営み」として定着させること。
評価ではなく、観察と問い直し。
誰かを責めるのではなく、組織全体で学びを蓄積していくための習慣にしていく。
この“軌道修正文化”が根づくと、メンバー一人ひとりの判断力や行動の解像度が格段に上がり、結果的に「なぜこれをやっているのか?」という腹落ち感も自然と深まっていきます。

マーケティングは本来、組織で実践するもの
冒頭でも触れた通り、企業には、それぞれ異なる強みがあります。
その強みを活かさずに事業を回すなんて、宝の持ち腐れ以外の何物でもない。
ただし、問題は「向いている方向がバラバラだと、せっかくの強みも相殺されてしまう」ということです。
強みは、足し算ではなく掛け算で捉えるべきなんです。
一人ひとりの力をただ寄せ集めるのではなく、顧客にとって“意味のある価値”として束ねることができれば、ブランドは驚くほどの推進力を手に入れます。
これは、単なる理想論ではありません。
組織の方向性がひとつにまとまれば、現場にムダな負担がかかることも減り、スタッフが「ちゃんと価値を届けられている」という手応えを持ちながら動けるようになります。
その実感が、さらに行動のエンジンになる。ポジティブな循環が生まれ始めるんです。
だからこそ、リコルクが大切にしているのは、売り上げの一発花火ではなく、「売れ続ける」「選ばれ続ける」「愛され続ける」ブランドをつくる現場に、共に立ち続けること。
ブランディングも、マーケティングも、どこか“専門家が外側から語るもの”のように扱われがちですが、それではうまくいきません。
私たちは、理論を語って終わりにせず、企業と一緒に実践の地面を踏みしめながら、ブランドの軸を組織に落とし込んでいきたい。
それが、コンサルとも制作会社とも違う、リコルクの立ち位置です。
今まさに、複数のクライアントさんと一緒に、この取り組みを進めている最中です。
それが、ブランドマーケティングの実践者としての私たちの使命だと思っています。
最後に
はっきり言います。
社長一人が腹落ちしていても、ブランドは強くなりません!
はたまた、社長自身もまだ納得できていない状態なら、そのブランドは持続的に価値を発揮できるはずがないんです。
組織やチームが“納得して動ける状態”をどうつくるか。
そこに真剣に向き合うことが、これからのマーケティングには欠かせないんです!
私たちはこれからも、企業と共に「耐久性のある強いブランド」づくりに、本気で伴走していきます。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級