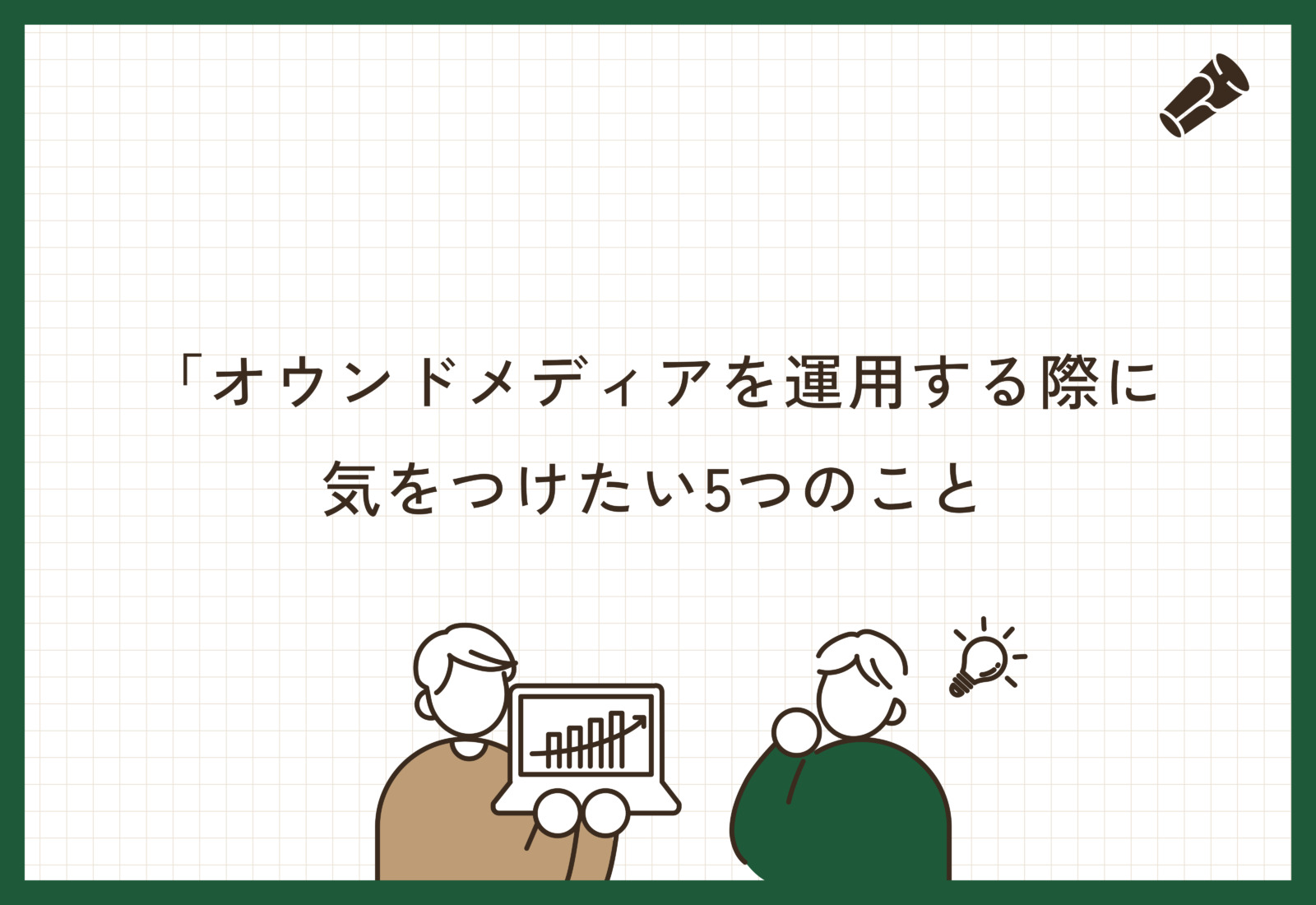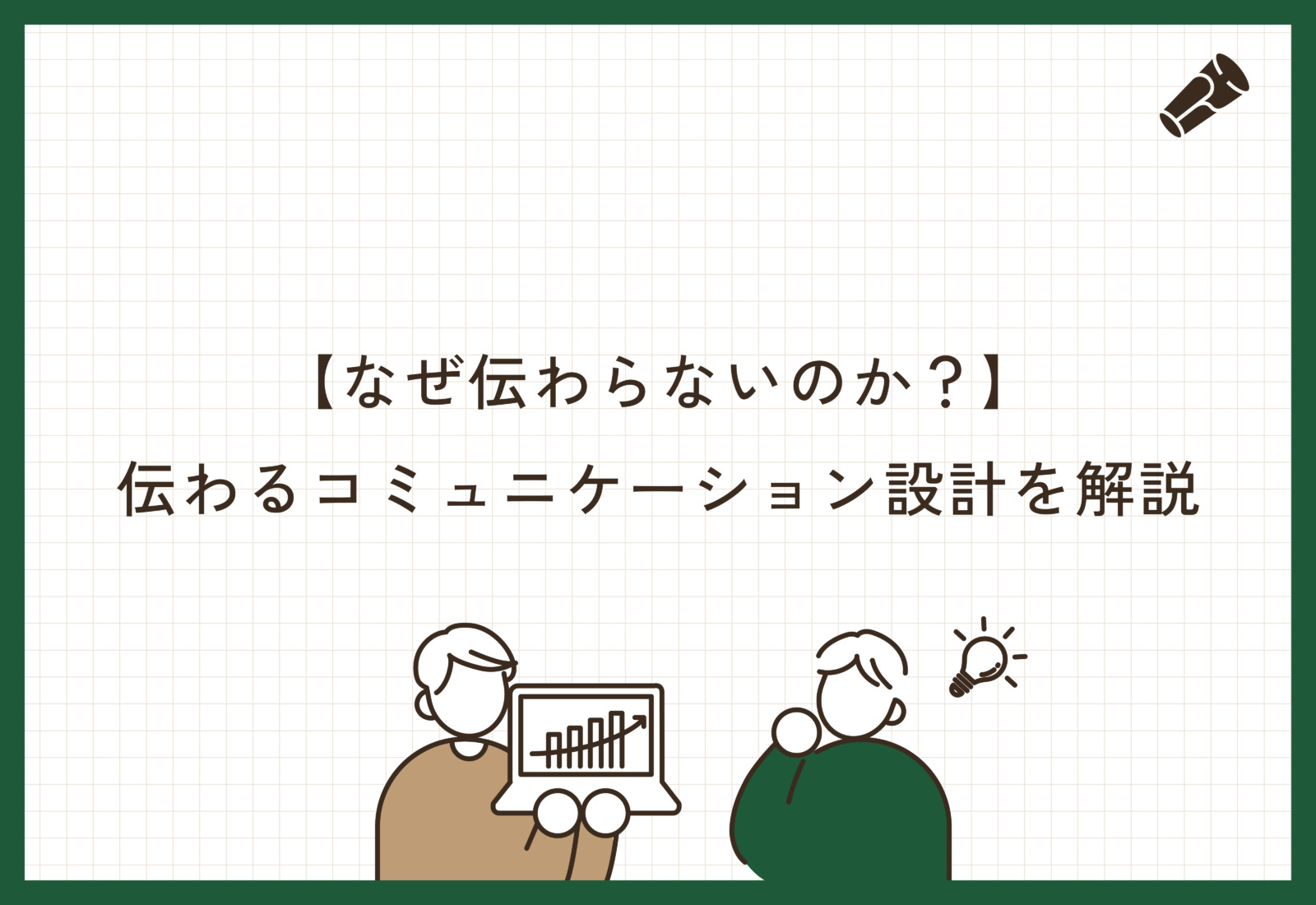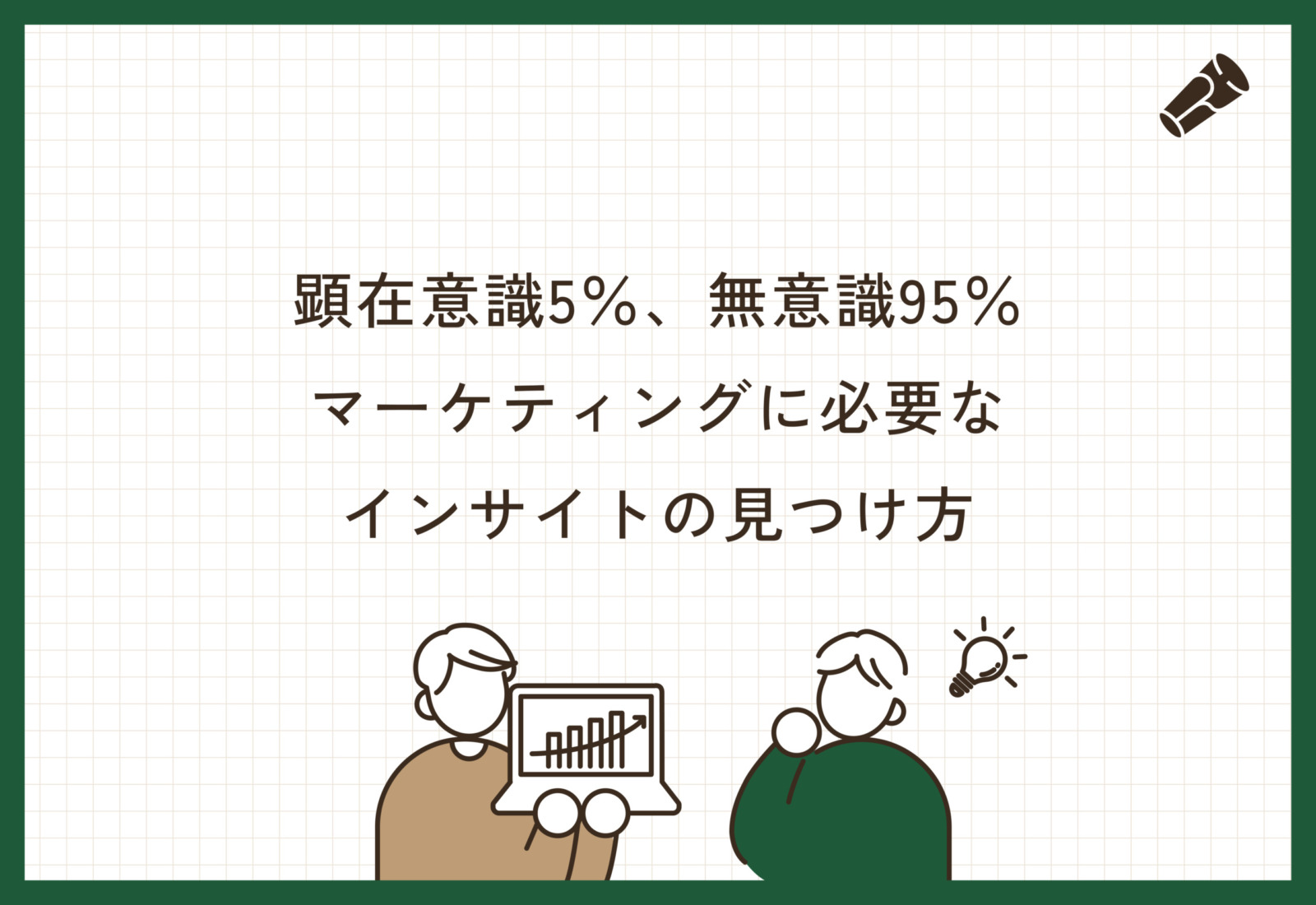Index

生成AIの登場以降、情報発信やコンテンツ制作は格段に容易になりました。
メールの作成、企画書の作成、こうした記事の執筆なども、生成AIが登場する以前と比べると、制作スピードは大きく向上しています。
それと同時に、言わずもがな、世の中に発信されるコンテンツの量も圧倒的に増えています。
総務省が発表したデータによると、「2002年のインターネット全体の情報量を10とした場合、2020年にはその6000倍にあたる6万」になっているそうです。
こうした時代において、情報発信はどのような視点で行っていくべきなのでしょうか?
- 自分よりも生成AIをうまく活用して情報発信をしている人なんて5万といる。
- これだけ情報が溢れているんだから、実はもう、情報発信って必要ないんじゃないの?
- 他社と違うことを発信したいが、顧客の疑問に応えようとすると結局似たようなコンテンツになる。
そう思い情報発信にいまいち前向きになれない方もいるんじゃないかと思います。
今回の記事は、そのような課題をどう突破するべきなのかを解説した記事になります。
読み手の「時間」に配慮する
良質なコンテンツが溢れる今の時代。
読み手は書き手の「60点の努力」にはほとんど興味を示しません!
「情報発信は量が大事」とよく言われますが、実際にはユーザーの可処分時間をあらゆる企業が取り合っている状況。
そんななか、“とりあえず出す”という温度感のコンテンツは、むしろ相手の時間を奪ってしまうものになります。
私は仕事柄、日々さまざまな記事や資料に目を通しますが、「今日はこのくらいで」「あとで誰かが直すかも」といった“妥協の匂い”がするものには、読む気さえ起きません。
おそらく読み手も同じで、ものの10秒でその温度感を察知し、そっと離れていくのではないでしょうか。
だからこそ大切なのは、「コンテンツを作ること」そのものを目的化しないこと。
届ける相手の気持ちを想像し、「この人の時間を預かるに値するか?」を常に自問自答しながら、目的に応じて丁寧に詰めることが求められています。
とはいえ、「じゃあ全部を長く丁寧にすればいいのか?」というと、それもまた違います。
情報量を増やせば良いのではなく、“最短距離で伝えるための丁寧さ”が必要なのです。
目的に応じて、構成も表現もシンプルなかたちへと突き詰める。
その上での「情報密度」「深度」が、相手の時間に対する本当の配慮になります。
ちなみに補足ですが、企画によっては、あえて60%の完成度を意識することもあります。
それは、「情報を置く場所」や「ユーザーの期待値」的に、60%の仕上がりの方が理にかなっているというケース。
なので、ここでお伝えしたいのは、「意図せずして“妥協臭”がするコンテンツは発信してはならない」ということ。
その根底には、まずユーザーの時間への配慮という姿勢が必要だと考えています。

AIだけに頼らず、「ならでは」も大切に
生成AIがあれば、ある程度の文章は誰でも書ける時代です。
便利な反面、その出力には、“どこかで見たような内容”という印象がつきまとうことも増えました。
AIが生成したと感じる文章には、いくら役に立つ内容が書かれていても、「誰が、どんな想いで書いたのか」が見えないため、感情的な接続が生まれません。
情報としては消費されても、ブランドとして記憶には残りにくい。
- 感情の揺れ動きが見える言い回し。
- 自分独自の言葉で語る経験談。
- ふとした気づきをダイレクトに届けるような共有。
- 現場で見つけた意外性のあるファクト。
など、「あらゆる独自性を感じさせる要素」が今あらためて求められていると感じます。
ちなみにこれは、私が個人的にやっていることでもあるのですが、コンテンツの企画を考える際に必ず行っていることの一つが、「世の中の通説の真逆から考える」というアプローチです。
例えば、この記事においても、「これだけテクノロジーが発達して役に立つ情報があふれているんだから、そもそも情報発信なんて必要ないんじゃないの?」というところから発想しています。
集客力やブランド価値を高めるためには、情報発信は必要不可欠!
そんな常識に対して、「ちょっと待った!実はもう、情報発信って必要ないんじゃないの?」という問いから始めたイメージです。
私は、“ならではの読まれるコンテンツ”には、「明確な意図」と「一つの深い洞察・視点」が欠かせないと考えています。
もちろん最終的には、意図が見えすぎないようにチューニングしたり、第三者の客観的視点も盛り込む必要がありますが、「明確な意図」と「一つの深い洞察・視点」が存在しないコンテンツは、深く刺さらないということが、これまでの経験上明らかなんです。
・・・
AIを活用すること自体は、まったく悪いことではありません。
むしろ、時短や構成の補助、それにコンテンツを一から生み出す際には非常に有効です。
ただ、「仕上げ」はあくまで人間の仕事。
現時点では、そう捉えています。
日記のようなコンテンツはある程度ブランド化した後で。
読み手の興味や関心を引く前に、いきなり日記のような“内向きの発信”をしてしまうと、多くの場合はスルーされてしまいます。
これは発信者の認知度がまだ高くない場合によくある失敗です。
そもそも、情報発信における日記的な内容は、「誰が書いたか」が前提になるコンテンツ。
つまり、書き手にある程度のブランドや信頼があるからこそ、“その人の考え”や“日常”が価値になるのです。
逆に言えば、まだブランドとしての立ち位置が定まっていない段階では、読み手にとっては「知らない誰かの一日」でしかなく、そこに意味を見出すのは難しいのが現実。
一見、先ほどの章とは真逆のことを言っているように見えますが、「独自の視点から生まれた価値ある情報」と、「誰のためのコンテンツなのかが全くわからない自己満足なコンテンツ」は全く別物です。
日記的なコンテンツを活かすには、「ある程度ブランドが築かれてから」あるいは「その文脈が読み手に伝わる状態」が必要です。
それまでは、読み手の課題や関心にフォーカスした外向きの発信が優先されるべき。
つまり、「読まれる準備が整ってから、読まれる内容を発信する」。
順番を間違えると、せっかくの発信も空回りしてしまいます。
書きたいことではなく、読みたいコンテンツを
一つ前の章の続きのような内容になりますが、つい、自社の思いやメッセージを中心に企画を考えてしまいがちですが、まず見るべきは、そもそも自分自身が「読みたい」と心から思えるコンテンツかどうか。
“読みたいコンテンツ”とは、まだ見たことない情報であり、まだうまく言葉にできていない違和感を解消してくれる情報のこと。
これを生み出すためには、まず、自社の発信カテゴリーを整理し、競合がどのような発信をしているかを徹底的に把握することが第一歩。
そのうえで、やるべきことは、インサイトの言語化。
インサイトとは何かを一言で表すなら、「その人自身もまだ気づいていない欲望」 のことです。
▼「インサイト」については以下の記事で詳しく解説していますのでぜひ併せてご覧ください。
【顕在意識5%、無意識95%】マーケティングに必要なインサイトの見つけ方
つまり、自分の中にあるインサイト言語化し、そのインサイトを自分で満たすために、あらゆる情報を探し回りそこで得た気づきをコンテンツにするイメージです。
インサイトは、検索キーワードだけでは見えてきませんし、読まれるコンテンツは、偶然できるものではありません。
まずは自分自身が、今どんな情報に飢えているかを見極めた上で設計する必要があります。

「そのコンテンツにたどり着く前」を設計する
インサイトをベースにした独自性の高い発信は、その本質が伝わるまでに一定の「読み進める動機」が必要です。
だからこそ、いきなり本編を読んでもらおうとするのではなく、「興味を惹きつけるきっかけ」や「入口の設計」が欠かせない。
SNSでの導線づくり、メルマガやLINEでの通知、パートナーとの協業による外部チャネルの活用など、コンテンツにたどり着くまでのルートを複数設計しておくことが、今の時代には求められています。
つまり、例えばブログ記事の場合は、1本の記事をアップしただけで「発信したつもり」になってはいけないということ。
まずは注意を惹く「入口となるコンテンツ」で興味を喚起し、そこから本質に触れる「詳細記事」へと自然に遷移させていく。
この段階設計によって、“意味を感じる度合い”は格段に変わります。
今の情報発信に必要なのは、「どんな人に、どんな経路で、どんな順序で伝えるか」という視点のシフト。文脈の設計です。
言い換えれば、届けたい相手の行動や関心の流れを、あらかじめ設計しておくことが、コンテンツの価値を最大限に活かす鍵になります。
最後に
冒頭でも触れたように、今は誰もが簡単に情報を発信できる時代。
生成AIの普及で、コンテンツの量は爆発的に増えました。
だからこそ「役に立つ情報」を出せばいい時代はもうすでに終わっています。
これから必要なのは、読み手の時間に配慮した「意味のある情報」。
そして、読み手に届く設計と、自分の言葉で語る手間です。
私自身、机の上で頭をひねるよりも、現場に足を運んで出会った“違和感”や“リアルな声”から生まれたコンテンツの方が、何倍も反響がありました。
情報発信の質を高めるには、効率や流行だけでなく、「誰のために」「なぜ今伝えるのか」を立ち止まって考えることが欠かせません!
その積み重ねが、「意味のある発信」をつくっていくのだと思います。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級