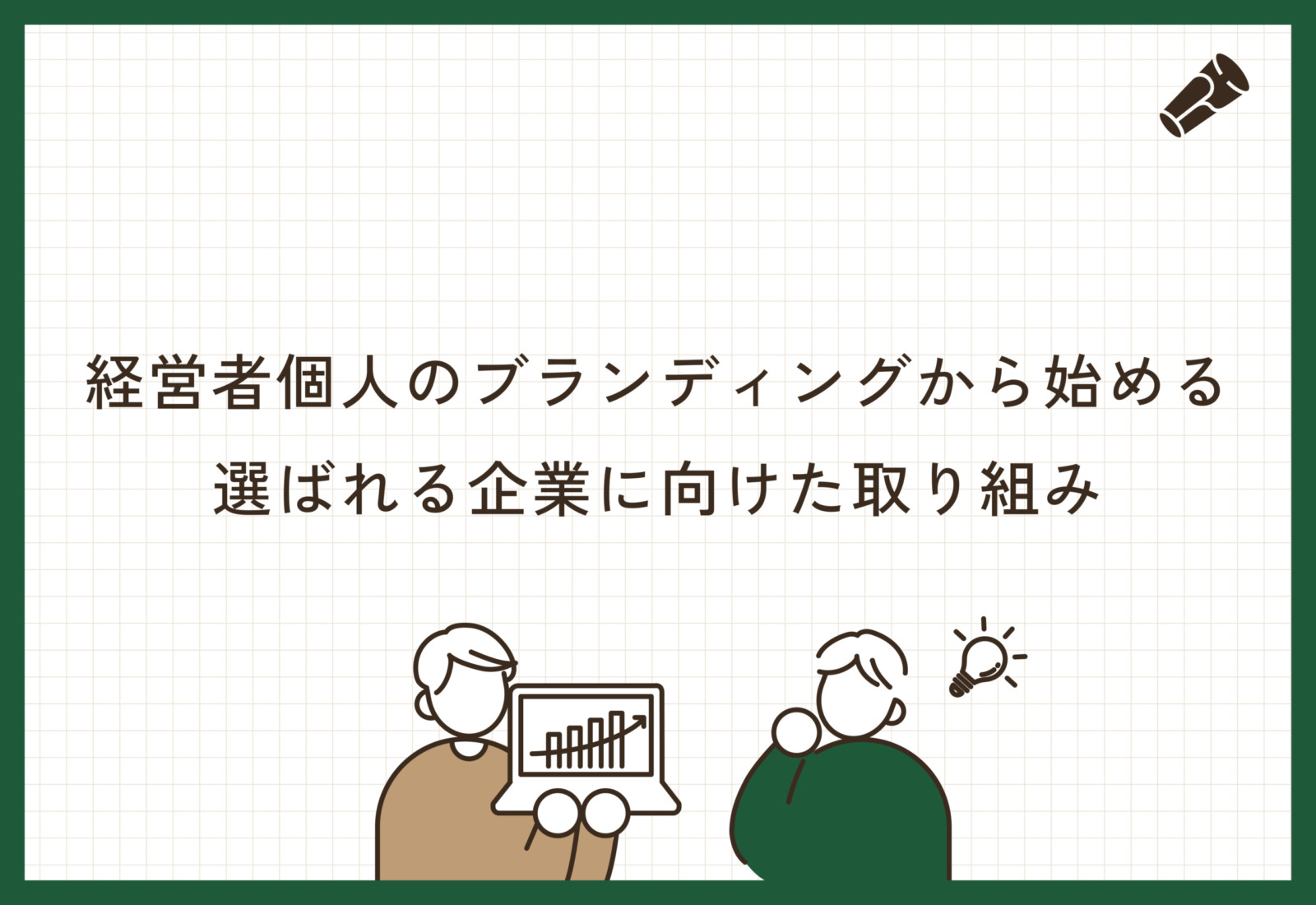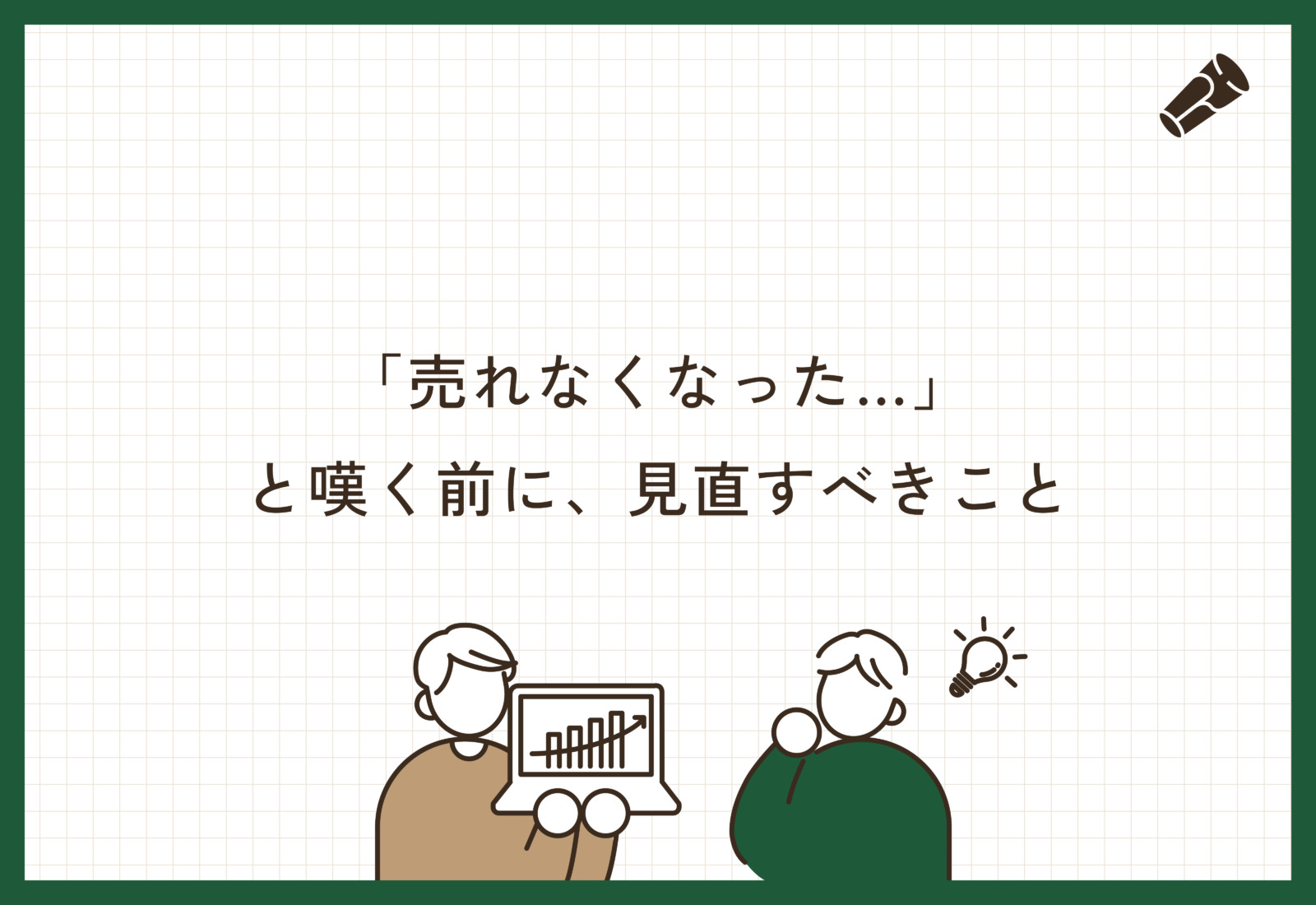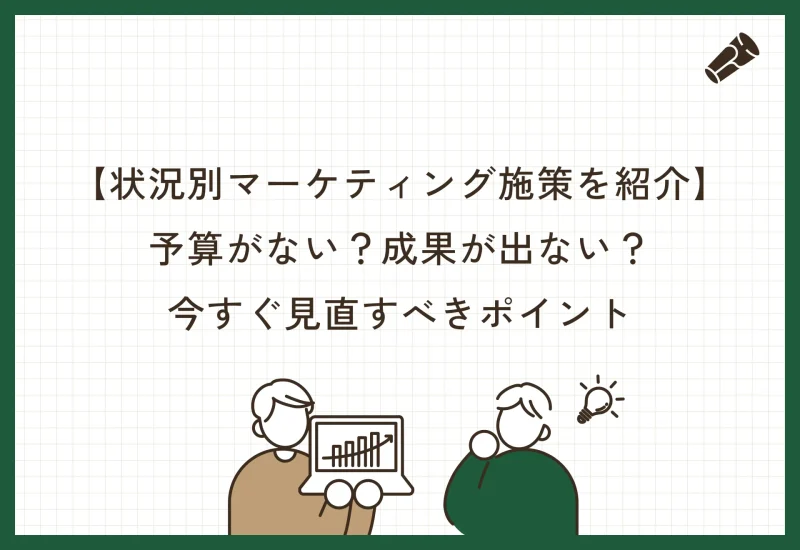Index
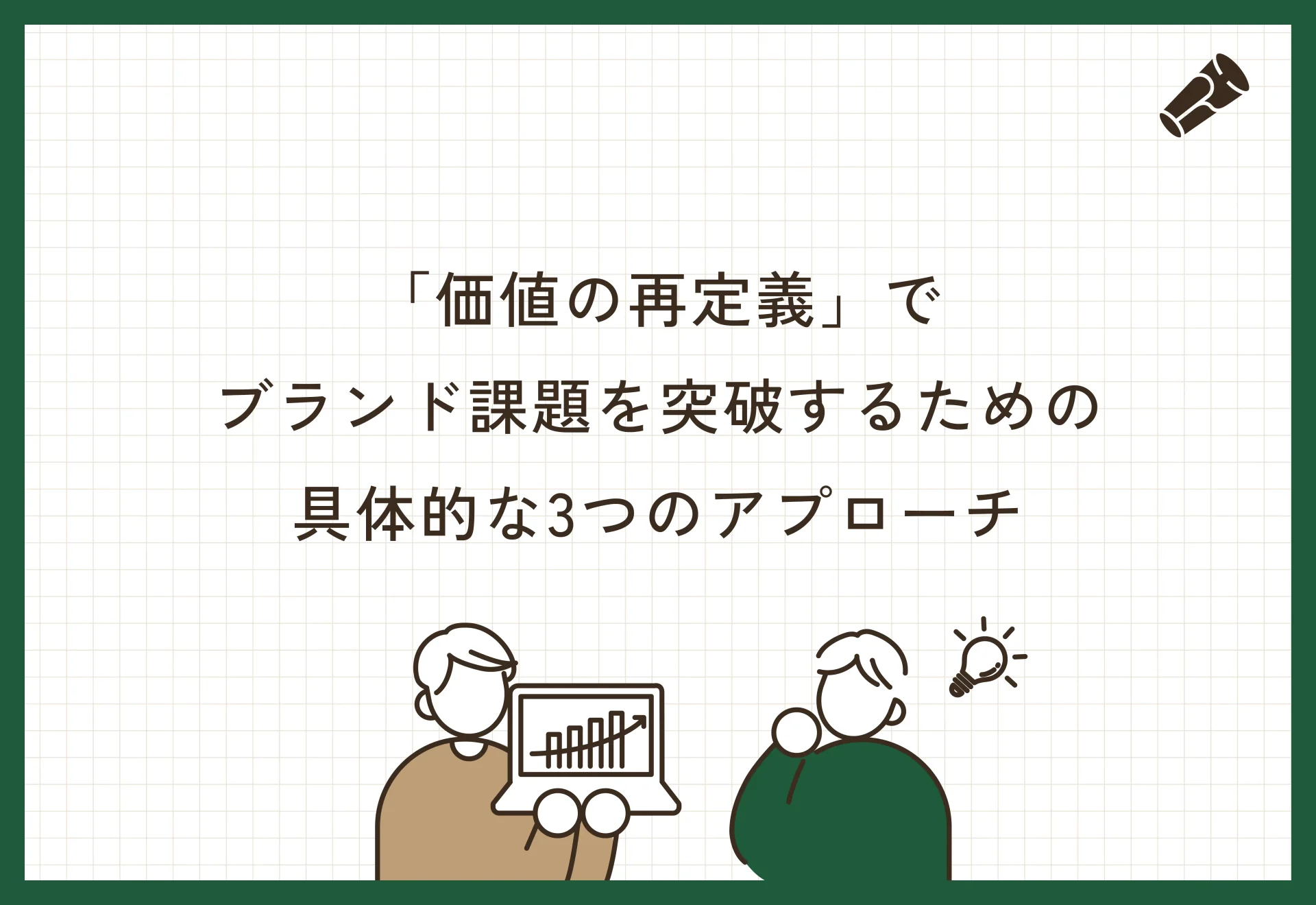
「昔からあるこの商品、良いものなんだけど、どうも魅力が伝わらない」
「持っているスキルや技術は競合にも負けないはずだが、どうもうまく伝えられない」
そんな悩みを抱えている企業は少なくありません。
実際、長く使われてきたロゴや、昔からある商品、独自の製造工程、ブランドの歴史などは、それ自体に価値があるはずなのに、「何だか古くさく見える」「今の世代には刺さらない」と扱いが難しくなっているケースもあります。
しかし、それは“資産の価値がなくなった”わけではなく、“使い方や伝え方が今の感覚に合っていない”だけのことが多いです。
つまり、「モノ」自体ではなく、「見方や捉え方」が時代に取り残されているんです。
たとえば、Tシャツにロゴを入れただけの「Supreme」は、音楽やアートなどストリートカルチャーと結びつけて価値を再定義したことで、若者の支持を集めました。
ブランドの本質を見極めた上で、新しいアイデアとアクション(他ブランドとのコラボなど)で「捉えられ方」を変えたことで、「ただのロゴT」が「自分の価値観を表現するツール」に変わったのです。
価値の再定義とは?〜打ち出し方は、「捉え方」で決まる〜
ブランドが持つ“資産”は、それ単体では機能しません。
重要なのは、それを今の文脈でどう読み替えるかです。
たとえば、昔ながらの旅館。
客室にテレビがなかったり、鍵がアナログ式だったりすると、「不便だ」と思われがちです。
でもそれを、
「デジタルから少し距離を置いて、人と人がちゃんと向き合える」
「アナログだからこその安心感」
と打ち出せば、“温かみのある体験”として受け止められる可能性があります。
つまり、“不便さ”を“人間らしさ”として価値に変換できるかどうかがカギになります。
米国の広告代理店Wieden+Kennedyのクリエイティブ責任者だったスーザン・ホフマンの言葉にヒントがあります。
“Sometimes you just need to look at something upside down to see its real value.”
「ときには、逆さまに見てみると、本当の価値が見えてくることがある」
変えるべきは資産そのものではなく、資産の“捉え方”なのです。
つまり、価値の再定義とは、単に「持っている資産(技術・商品・歴史)」の形や機能を変えることではなく、それらが持つ「意味」や「捉えられ方」を、今の時代や顧客の感覚に合わせて読み替え直すことです。
意味をアップデートしてうまくいっている事例
資産を再活用するには、「形を変える」のではなく、「意味を変える」ことが必要です。
たとえばプロ野球球団・横浜DeNAベイスターズは、球場を「ただ野球を観戦する場所」としてではなく、「野球を観ながらお酒や食事を楽しめる“居酒屋”」と捉え直しました。
実際にスタジアムでは、グループ観戦席やBBQエリア、地元グルメを取り入れた飲食体験など、従来の“球場”の枠を超えた場づくりを展開。
「勝敗だけでなく、その場にいること自体が楽しい」と感じるファンを増やし、2024年には観客動員数が過去最高を記録するまでに至っています。
ブランドがすでに持っている“資産”に新しい意味を与えることで、その見え方や価値が根本から変わる好例だと言えます。

価値を再定義するために、すぐできる3つの実践アプローチ
では、どうすれば「今あるもの」の価値を見直すことができるのでしょうか?
実際にプロジェクトで使われている3つの方法をご紹介します。
1.ブランドを構成する要素を、細かく分解してみる
「ブランド資産を見直す」と言うと、つい過去の広告コピーや営業資料を見返したり、コンセプトの言い回しを磨こうとしがちです。
けれど、それだけでは本質にたどり着けないこともあります。
そこでおすすめしたいのが、「自分たちのブランドを構成している要素を、とにかく細かく分解してみる」というアプローチです。
たとえば、あるカフェがあるとします。
自分たちは「豆の質」や「焙煎技術の高さ」を強みだと考えていたとしても、実は常連のお客さんにとっての価値は別のところにあるかもしれません。
たとえば、「ついついくつろいでしまうほど座り心地のよいソファ」や、「自然光がきれいに差し込む午後の窓辺の席」といった空間的な特徴。
あるいは、「BGMの音量がちょうどよくて集中できる」や、「混んでいない時間帯を見計らえば、2時間いても嫌な顔をされない」などの運営スタイルに価値を感じていることもあるでしょう。
このように、空間・接客・運営スタイル・時間の使われ方など、ブランドは無数のアセットの集合体として成り立っています。
それぞれを棚卸しし、細かく分解することで、「自分たちが価値だと思っていたもの」と「生活者が感じている価値」のズレが浮かび上がってくる。
そのズレこそが、ブランドの意味を更新するヒントになります。
2. 自社ブランドを“異業種”に置き換えてみる
次に、自分たちの事業をまったく別の業種に置き換えてみるという方法です。
たとえば、あなたの会社が住宅会社だとします。
「設計力」を強みと考えていたとして、それをホームページ制作会社に置き換えてみるとどうでしょう。
ホームページ制作の現場では、ただ「見た目がきれいなサイト」をつくるのではなく、クライアントの事業戦略を把握した上で、ビジネス目標に沿ったサイト設計を行うことが求められます。
この視点に置き換えると、住宅の設計もまた「家族の人生戦略に寄り添い、その暮らしに最適な導線や空間構成をデザインする」という意味で、戦略的な“設計力”として再定義できるかもしれません。
(需要があるかはさておき)
このように異業種に置き換えてみることで、自分たちが当たり前に語っていた「強み」や「資産」が、実はもっと深いところで“どんな体験を支えていたのか”が見えてくる。
つまり、“業種の常識”というフィルターを外すことで、新しいブランドの意味が解像度高く浮かび上がってくるのです。
3. “使われているシーン”における異常値から、価値を逆算する
資産の定義を、持っている「モノ」ではなく、実際に使われている「場面」から考える方法です。
何気ないレビューやアンケートの回答の中に、「朝の忙しい時間にすごく助かってます」「子どもが自分からこれを選ぶんです」といった生活に根ざした表現が見つかることがあります。
こうしたリアルな言葉には、ブランドが意図していなかったけれど、生活者にとっては“意味ある価値”が表れていることも多いのです。
たとえば、「吸引力の強い掃除機」というのは、単なるスペックの説明です。
しかし、「朝の10分をつくる掃除機」と表現すれば、忙しい家庭にとって具体的な価値が伝わります。
このように、商品の性能そのものではなく、利用者の時間や感情、日々の行動にどのような影響を与えるかを軸に価値を考え直す手法があります。
実際、多くの大手メーカーでは、単なるスペックの訴求から生活者のくらしやニーズに寄り添った提案型のマーケティングへ転換が進んでいます。
パナソニックもその代表例で、商品の技術力や性能を前面に出すだけでなく、「くらしの課題解決」や「時間のゆとり」など、生活者が実感しやすい価値を重視する戦略を採っています。

大きく作り変えなくても、ブランドは変われる。
「新しい商品をつくらないと、ブランドは変われない」。
そんなふうに思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。
もちろん、新商品や新サービスがブランドに大きな変化をもたらすこともあります。
また新商品が生まれることでブランドの意味がより強くなることもある。
ただし、現時点で優れた技術や良質な商品・サービスを持っているにもかかわらず、期待した成果が出ていないというケースも少なくありません。
そういった場合には、「新しいものをつくる」ことよりも、今あるものをどう捉え直し、どう伝えるかが重要になってきます。
ここで大切なのは、ただ見た目を変えれば良いという話ではないということ。
まず取り組むべきは、自社のブランドがどういう意味で捉えられているのか、そしてそれが自分たちの意図とズレていないかを見直すことです。
そのうえで、「見た目」=ビジュアル表現も、必要に応じて変える。
必要があれば、商品やサービス自体の改良にも踏み込む。
意味が変わっていないのに、ビジュアルだけを一新したり、なんとなく新商品を投入しても、一時的な反応は得られるかもしれませんが、それは長く続きません。
(ビジュアル制作や商品開発が、目的化してしまっては本末転倒です)
意味の再定義と、その伝え方の工夫。
この積み重ねこそが、ブランドの成長につながっていきます。
まとめ
「古くなったから変える」のではなく、既存の資産の本質に立ち返り、その意味を捉え直す。
それだけで、これまで届かなかった相手に届いたり、止まっていた成果が再び動き出します。
だから大切なのは、無理に刷新することではなく、今あるものの価値を見直し、未来にどう活かすか。
少し視点を変えるだけで、眠っていた強みが“これからの武器”になる。
ちなみに本記事は、「リブランディング」や「クリエイティブディレクション」に関する内容でした。なので興味があれば、以下の記事もあわせてご覧ください。
▼クリエイティブディレクションについて
クリエイティブディレクターとは?今多くの中小企業でCDの参画が進む理由
▼リブランディングの本質について
価格を値切ってくる方と仕事をしないためにやるべきこと。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級