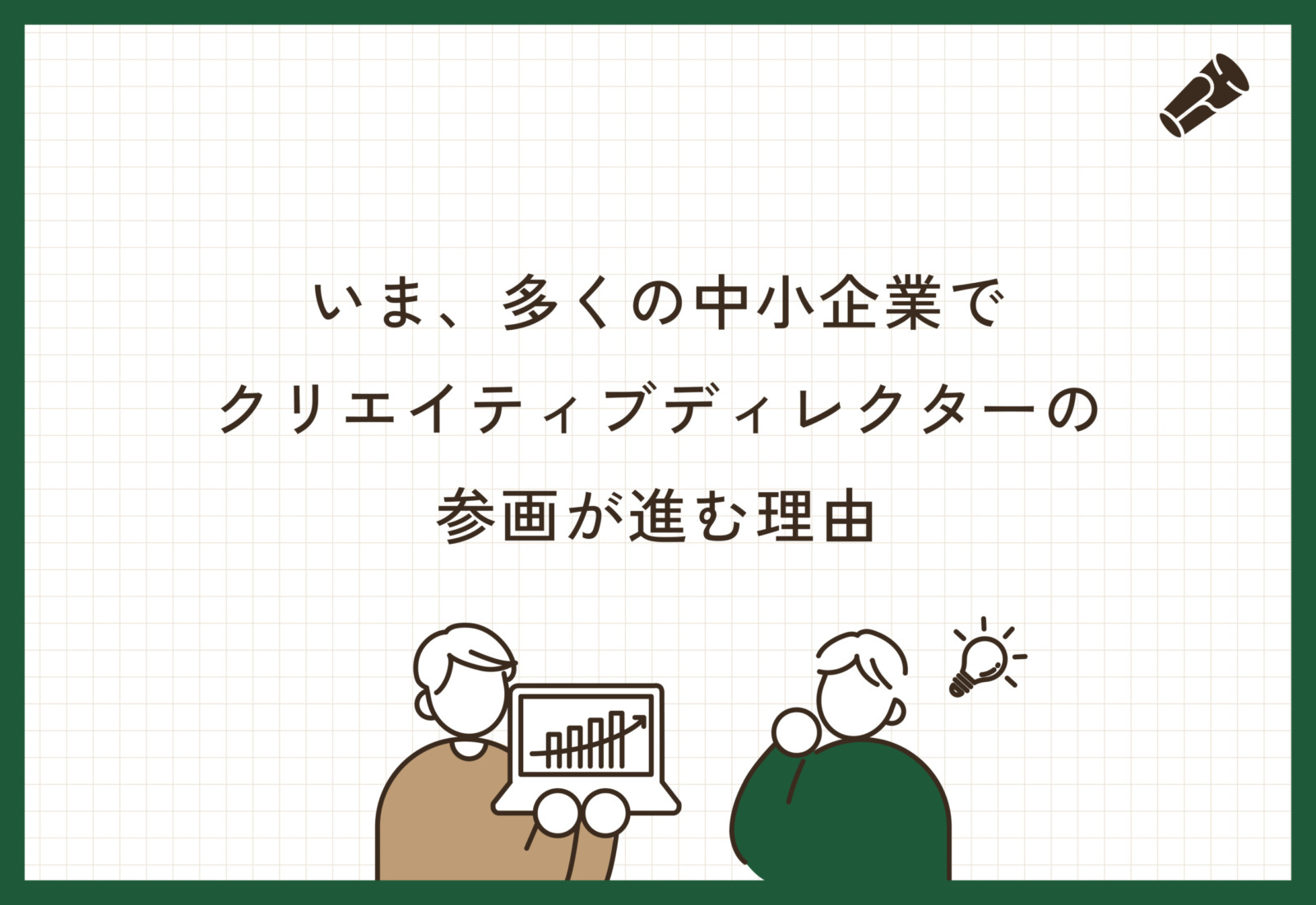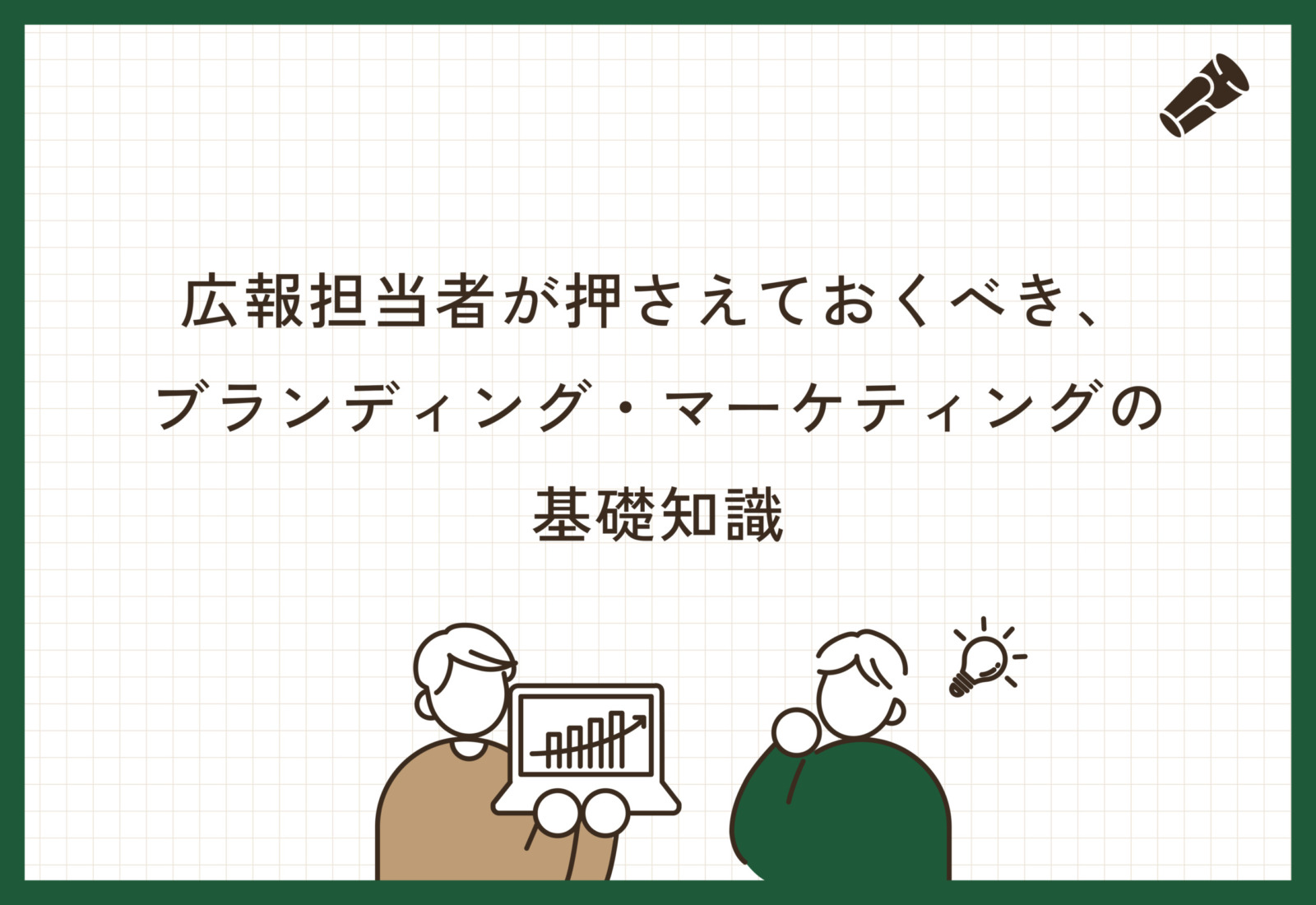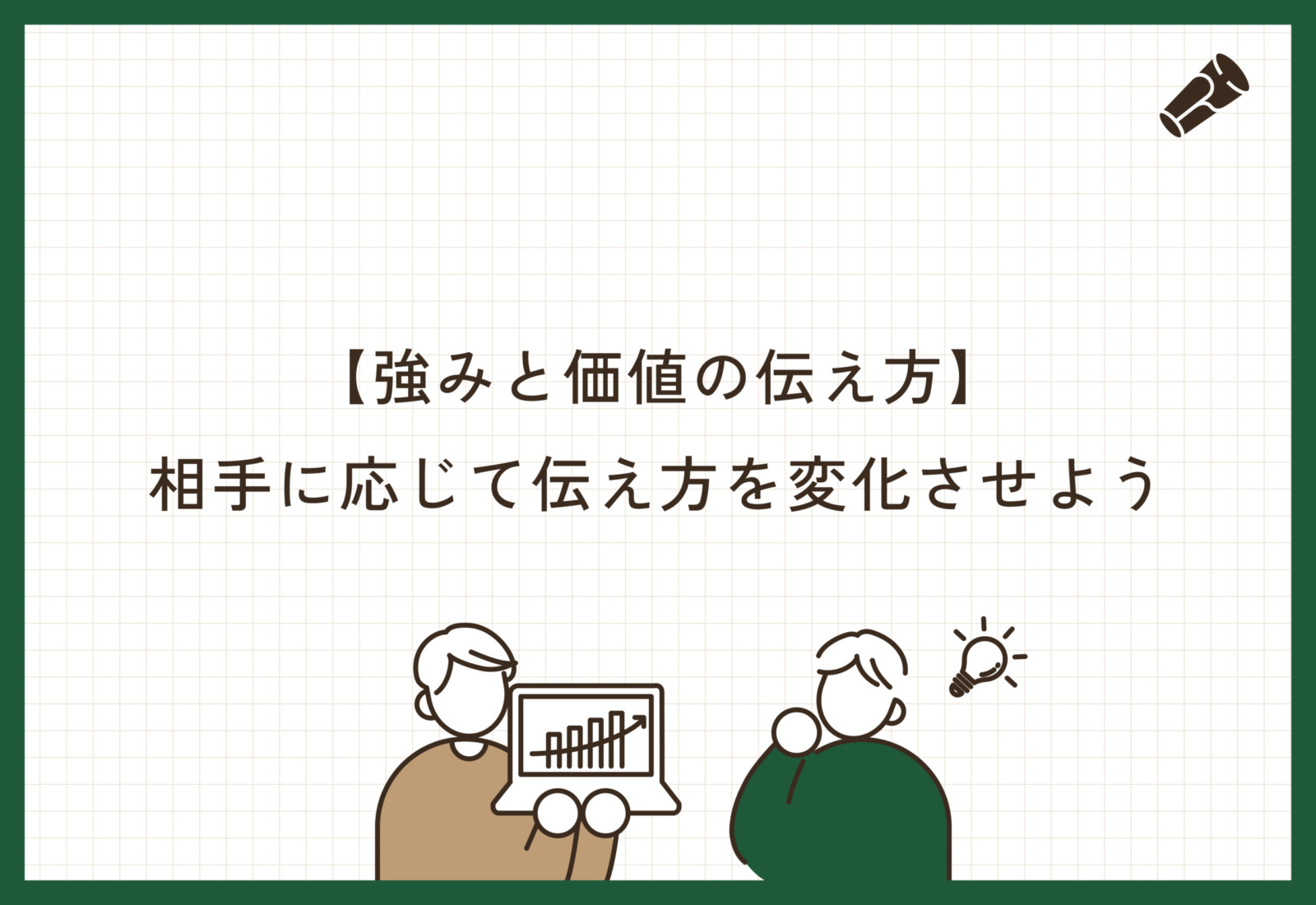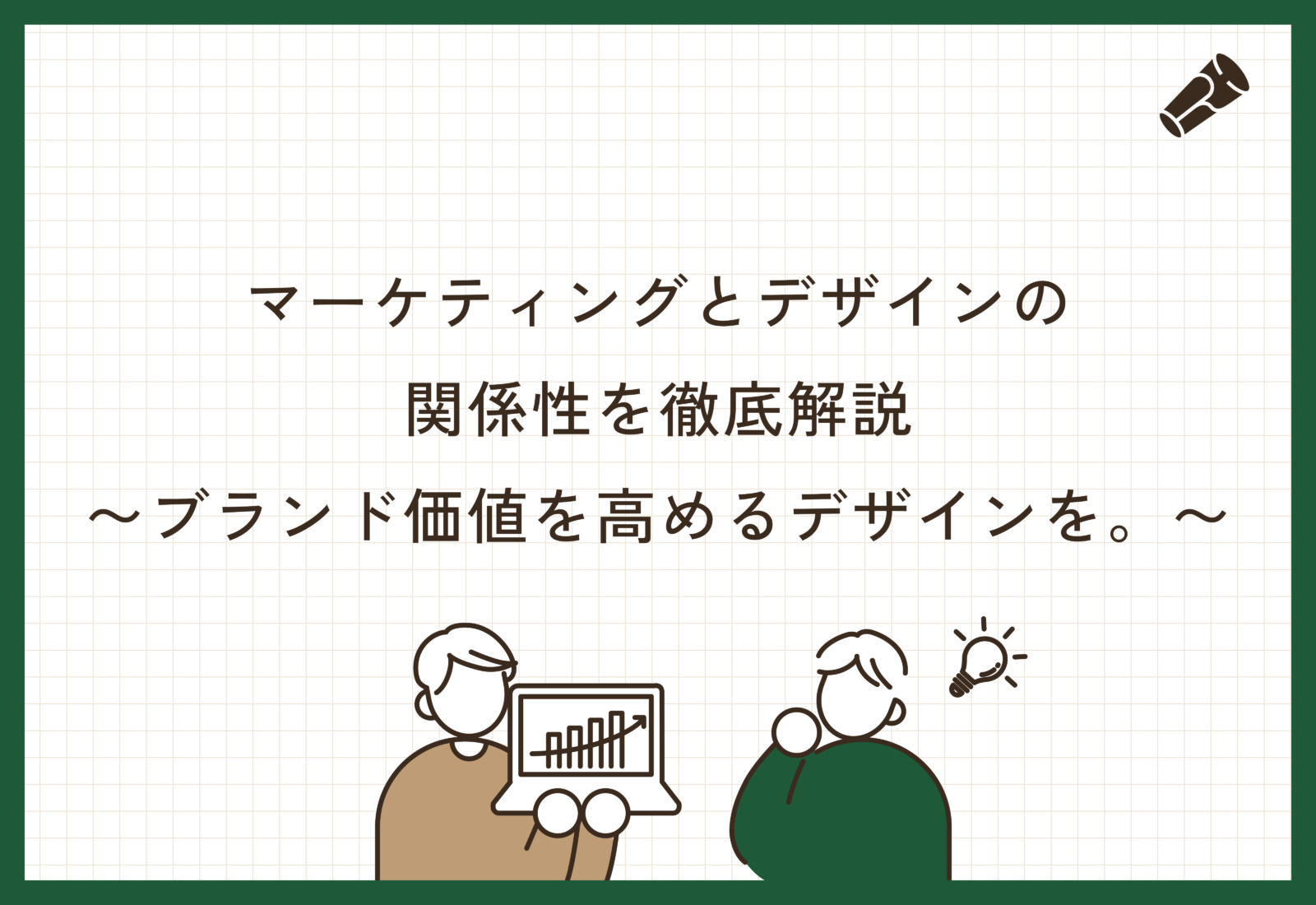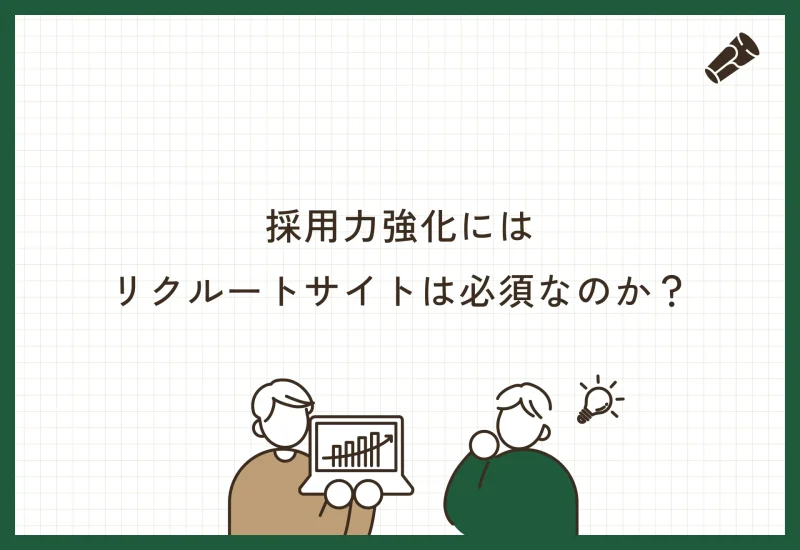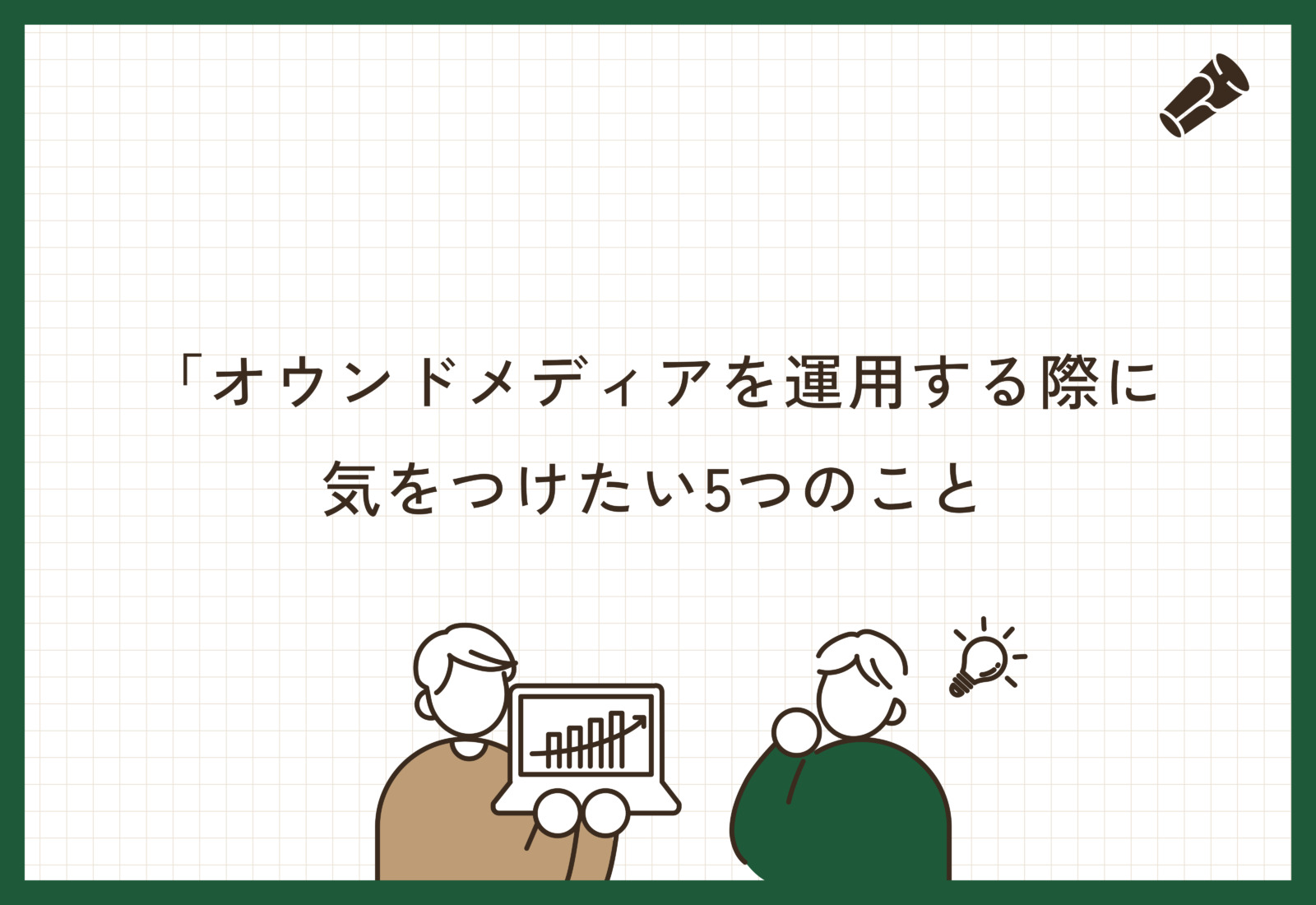Index
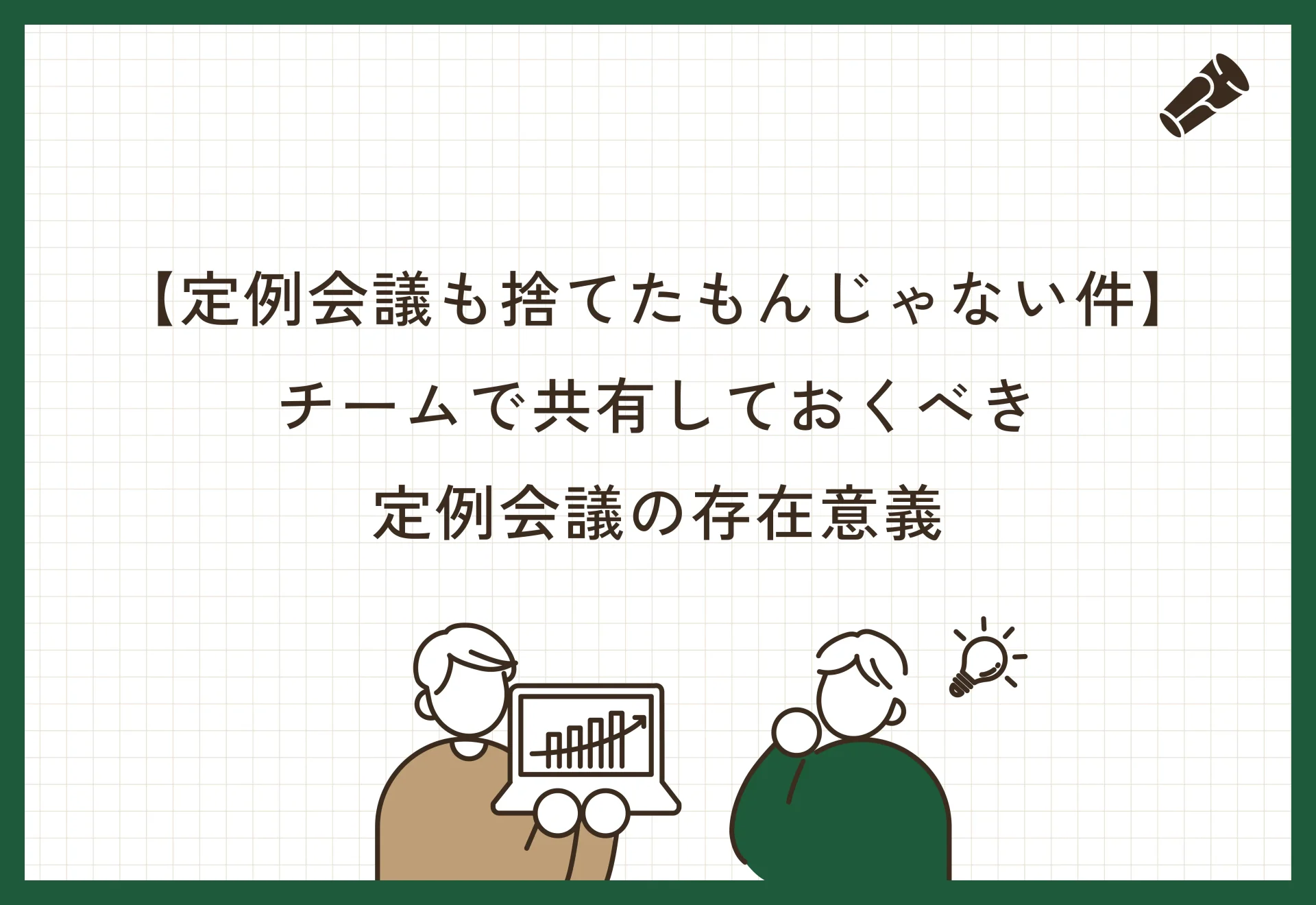
「毎週の定例会議なんて、要らなくないですか?」
私がまだ20代の頃、当時の上司に「定例会議は無意味だ!」とよく噛みついていました。
当時の定例会議の内容は、開始前にちょっとばかり雑談して、ぬるりと会議が始まり、それぞれ曖昧な活動報告を済ませ、相談事項があればそれについて議論し、最後に「今週も頑張ろう!おー!」というものでした。
「この時間があったらクライアントにメールを返したり、現場に足を運んでいろいろ調査した方がよっぽど生産的だ」。そう思っていました。
もちろん、会議の内容に問題があっただけの話なんですが、そんな経験をしたからか、当時は定例会議という存在そのものにも懐疑的でした。
「必要な時だけやればいいじゃないの?」と。
けれども今では、「定例会議があったから救われた」「定例会議って本当に大事」と思っています。
(もちろんすべてのシーンに当てはまるわけではありませんが、ブランドマーケティングの現場においては必要なケースがほとんど)
なので今回の記事では、定例会議が必要なシーンや定例会議自体の存在意義について書いていきたいと思います。
無駄な会議はリスクでしかない
会議にどれだけの時間を使っているか、意識したことはありますか?
私は数年前の年末に、ふと思い立って今年の会議総時間をざっくり計算してみたことがあります。
すると、まさかの数字が出てきて、年越しそばが喉を通らなくなりました。
パーソル総合研究所によると、「ムダな会議」によって企業が被る年間損失はなんと15億円にものぼるといいます。
(※パーソル総合研究所『「ムダな会議」による企業の損失は年間15億円』より引用
我々の調査結果から、役職別の年間の社内会議・打ち合わせの時間を推計しました。メンバー層で週に3時間を超え、係長級で6時間、部長級になると8.6時間になりました。これを年間の時間に拡大推計すると、メンバー層で154時間、部長級では434時間を超えます。そして、従業員規模が多いほど、上司層の会議時間は飛躍的に伸び、1万人を超える大企業になると、630時間にも及びます。注意してほしいのは、この時間に、顧客・クライアントなどの社外関係者との打ち合わせは入っていないということです。
お金は取り戻せても、時間は取り戻せません。
だからこそ、私たちは「この会議は本当に必要か?」「この時間をもっと有効に使えないか?」という視点を持っておくべきだと思うんです。
会議のあり方を見直すことは、働き方全体の効率化にもつながっていきます。
それでも定例会議が必要なのは、どんな時?
これまで多くのブランディング案件に関わってきました。
採用ブランディングで自己応募を増やす仕組みを設計したり、リブランディングでブランドコンセプトの再構築やWEBサイトの刷新を進めたり。
プロジェクトの形や規模はさまざまですが、それぞれのプロジェクトにおいて、定例会議が組まれているケースと、そうでないケースがありました。
どちらが成果に直結していたか。
その違いが気になって、過去に関わった複数のプロジェクトを振り返り、定例会議の有無と生産性の関係をざっくりですが比較してみたんです。
かかった工数や進行のスムーズさ、仕上がりの質やクライアント満足度など、いくつかの観点で整理してみると、定例会議がある方が全体として生産性が高い傾向がありました。
理由はいくつかありますが、なにより大きいのは「共通認識を持てること」。
細かな進捗報告やタスク、目標の確認だけでなく、目指す方向性のズレを早期に察知できたり、「あ、そこ気づいてなかった」という盲点を拾えたり。
定例的な対話の場があることで、プロジェクトが立ち止まることなくスムーズに進み、チームが強くなっていく感覚を持ちながら取り組むことができました。
では、どんなときに定例会議が必要になるのか?
個人的には、以下のようなケースが当てはまると感じています。
- 課題やゴールが明確で、プロジェクトとして設計されている仕事
- 複数人のチームで連携しながら進める仕事
- 現状維持ではなく、新たな価値創出や成長を求める仕事
こうしたケースでは、「必要なときだけ話す」スタイルだと、情報の行き違いや判断の遅れが起きやすくなる。
逆に、定例会議があることで小さな齟齬も早めに拾え、結果的にスムーズに進めやすくなる。
つまり、定例会議は“何かを一気に進めるため”というより、“立ち止まらずに前に進み続けるため”の仕組みとして機能するのだと思います。
定例会議の役割を再定義してみる
私自身が考える定例会議の役割は、大きく3つあります。
1.プロジェクトの現在地について理解を深める
メンバー全員がそれぞれ別の業務を持っている中で、「いま、どこまで進んでいて、どこに課題があるのか」を共有する時間は、やはり必要です。
進捗が止まりそうな箇所を早めに見つけるだけでも、大きな価値があります。
2.チームとしてのベクトル、温度感を揃える
仕事をしていると、忙しさや立場の違いから、知らないうちに温度差が出てきます。
定例会議の場で、直接話すことや表情を見ることで、「今このプロジェクトにどれくらい集中しているか」が伝わる。
それだけで、自然と意思疎通のズレが減っていきます。
3.安心感や細かな合意形成をつくる
意外と見過ごされがちですが、「定期的に確認し合える」ということ自体が、チームにとっての心理的安全性につながります。
大きな方向転換や重要な判断が必要な場面だけでなく、ちょっとした認識のズレをなくしたい場面でも、定例会議であらかじめ共通認識を持っておけると、その後の意思決定がスムーズになります。
・・・
こうして見ると、定例会議は単なる作業の場ではなく、“最低限の成果を出すための防護壁”のような存在なんだと思います。
いわば、チームやプロジェクトを脱線させないためのガードレールのようなもの。
定例会議の良し悪しは、間違いなく「やり方」で決まります。
ただ予定通りに開くだけでは意味がないし、なんとなくの雑談で終わってしまえば、メンバーの時間を奪うだけになってしまいます。
ブランドやチームを強くする会議の作り方
では、どのようにすれば生産性の高い会議を作れるのでしょうか。
個人的には以下の内容は毎回意識しています。
1.目的やアジェンダを事前に共有しておく
会議を「なんとなく始めて、なんとなく終わる」時間にしないためには、事前の目的とアジェンダ共有が欠かせません。
特に定例会議のようなリズムで開催される場では、「何のための会か」があいまいだと、習慣が形骸化していきます。
共有のタイミングは前日までが理想。
参加者が心の準備を整えられる状態をつくることが、内容の濃さにつながります。
2.ファシリテーターをつける
ファシリテーターとは、参加者が意見を出しやすい場をつくり、会議を目的に沿って円滑に進行させる役割を担う人のこと。
発言が一部の人に偏ってしまったり、議論が迷子になったときに舵を取る存在がいるかいないかで、会議の質は大きく変わります。
定例会議では、担当を固定せず持ち回りにしてみるのも、主体性を育てるひとつの方法です。
(※ちなみに、今あげている6つの中でこれが一番大事だと思っています)
3.疑問点やわからないことはこの場で解消する
会議が終わった後に、「結局あれってどういう意味だったんだっけ?」というモヤモヤが残ると、チーム全体の足並みがずれていきます。
定例会議の場では、わからないことを持ち帰らない勇気も大事なんです。
小さな違和感を見て見ぬふりしないこと。
そのひとつひとつを、その場で、ちゃんと解消しておくこと。
そういう丁寧さが、あとからじわじわと効いてきて、チームにとっての推進力になっていきます。
4.プロジェクト全体の目的や目標、指針も絶えず共有する
定例会議は、進捗確認や課題整理の場になりがちですが、「なぜこのプロジェクトをやっているのか」に立ち戻る時間でもあります。
目的を繰り返し共有することで、判断に迷ったときの基準が生まれ、各自の動きに芯が通ります。
忙しい時ほど、この“立ち返る視点”をおざなりにしないことが大切です。
5.次回のMTGまでのアクションや次回の議題も整理しておく
会議の終わりこそ、次に向けた準備の始まりです。
「じゃあ、また来週」で解散してしまうと、次回のMTGがゼロベースで始まりがちです。
だからこそ、その場で次回までのアクションと、次回取り上げるべき議題を整理しておくことが重要です。
「誰が、何を、いつまでに?」を明確にし、「次回はこの話をしようね」と方向性を持たせておくことが肝心です。
また、この点のすり合わせを入念に行なっておくことで、「次回のMTGまでの時間」がより意味のあるものになります。
「次回までに〇〇をやっておく必要がある」という認識をこの時点で共有することで、行動目標が必然的に立ち上がるからです。
その明確さが各々の業務の精度を高め、結果としてプロジェクト全体の価値も向上する。
定例会議は、ただの報告や相談の場ではなく、次に進むための推進力を生む時間でもあるのです。
6.意見を真っ向から否定しない。全員で第3案を考える
誰かの意見に対してすぐ「それは違う」と返すのは簡単です。
ただ、それをやると、会議は“ただの報告会”や“批評会”に堕ちてしまう。
定例会議の意義は、視点の違いを持ち寄りながら、ひとつのゴールに向かって共に考えることにあると思っています。
A案とB案のどちらかではなく、みんなで「じゃあC案ってありえる?」と、第3案を探す。
そんなふうにして、会議は価値ある時間に変わっていきます。
(どうしても長くなりそうな場合は、定例会議とは別の時間を取ることも大切)
ちなみに、個人的に思うのは、こうした場で一切意見を発しないか、もしくは、斜に構えて粗探しだけをしている人がいるなら、その人にはその会議から退いてもらった方が良いです。
間違いなく、その場の生産性が落ちるので。
良い会議は参加者全員でつくるもの(まとめ)
定例会議を「意味のある時間」にするか「時間の消費」にするかは、進行役や一部の人だけの努力では成り立たないんです。
むしろ、その場にいる全員が「どうすれば前に進む話し合いになるか」を意識することが、何より大事だと思います。
- 共有すべきことは何か。
- 今の議論は本質に迫れているか。
- 誰かの意見や発言に対してリアクションをとっているか。
- 疑問な点や違和感を感じていることを後回しにしていないか。
- もっと問いやアイディアはないか。
そんなふうに、それぞれが主体的に関わることで、場の温度も、話の深さも変わってきます。
会議の空気はチームそのものを映すようなもの。
いいチームには、いい会議がある。
「意味のある会議だった」と思える場を、全員でつくっていく。
その意識を持つだけでも、会議の価値はずっと変わってくるはずです。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級