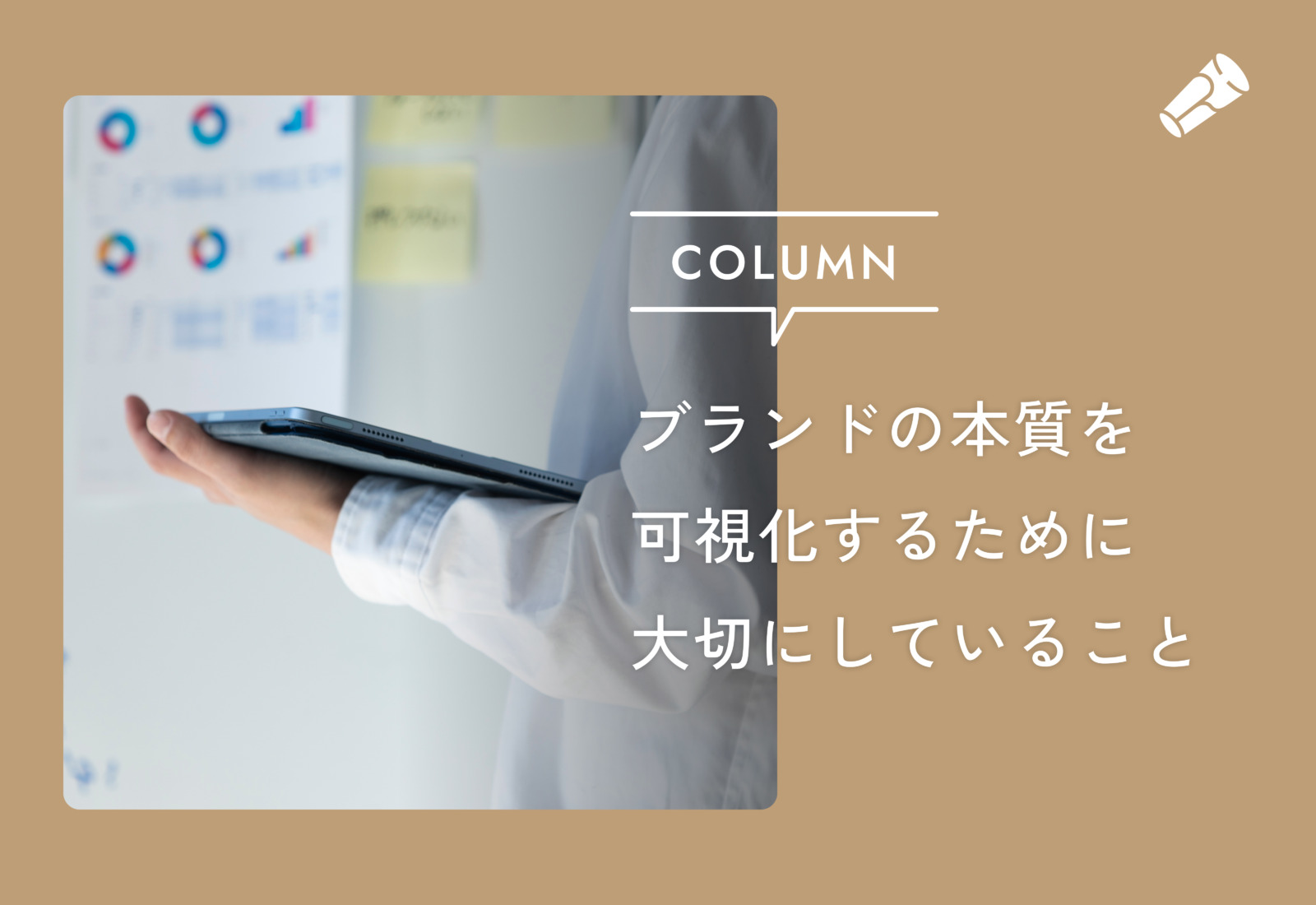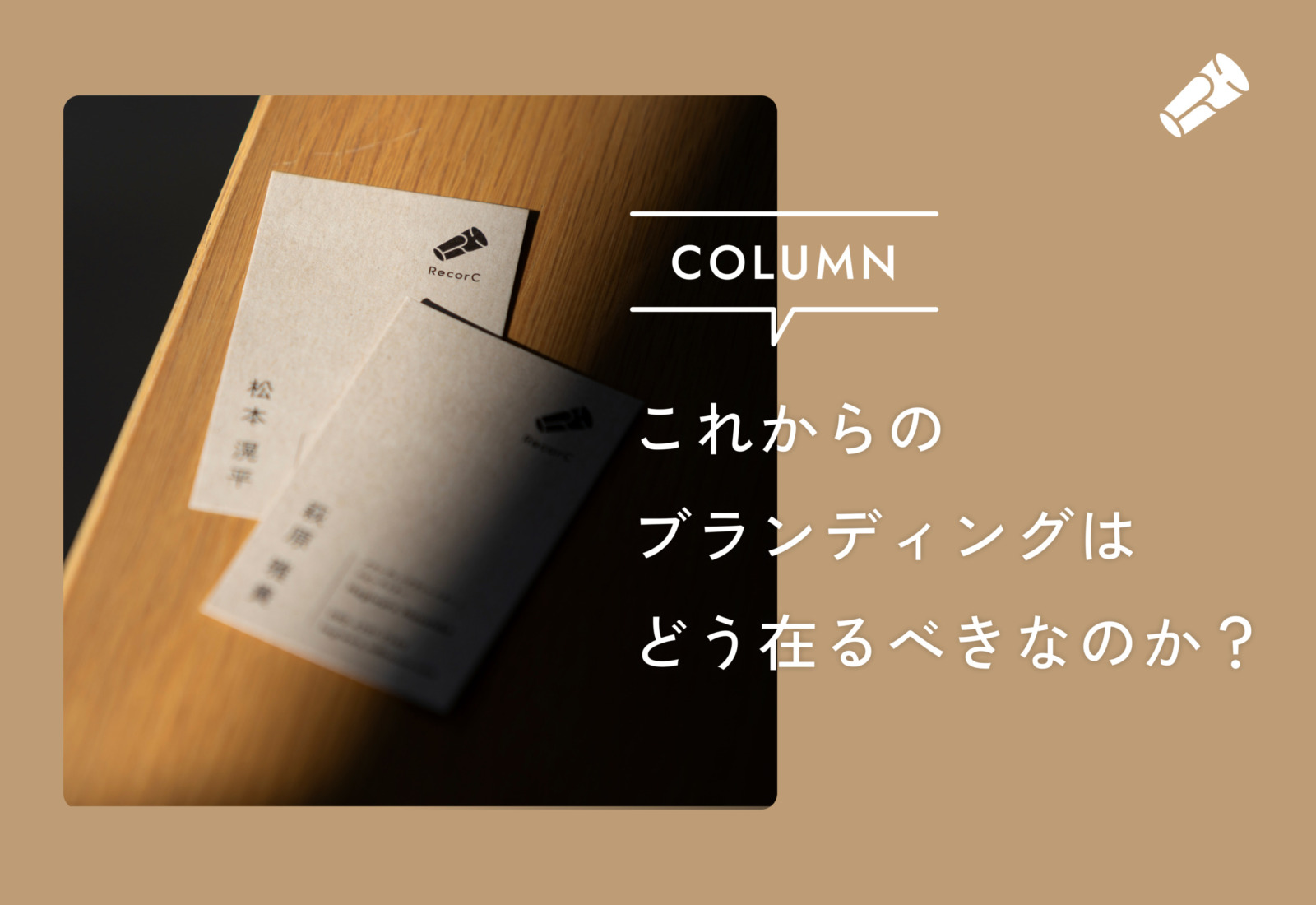Index
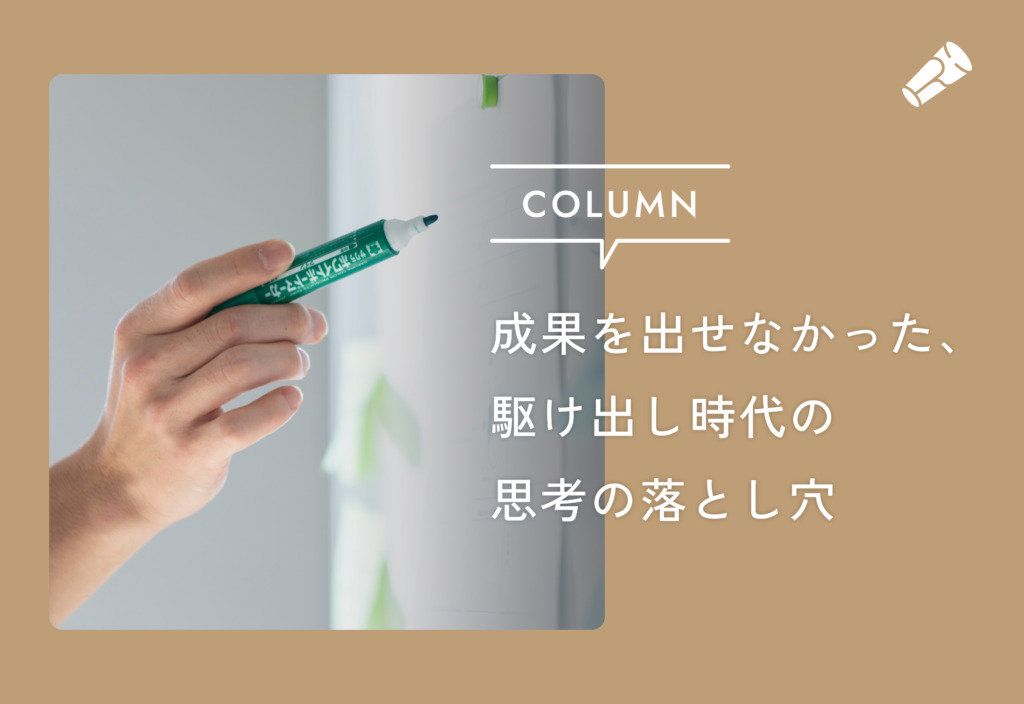
駆け出しの頃は失敗の連続で、「この仕事(ブランディング、マーケティング支援)向いてないかも」と何度も思いました。
ただ、いくつかの成功体験をきっかけに、「クライアントと共に成果を追求する仕事」に対する考え方や行動が180度変わりました。
この記事では、この変化について深掘りしたり、クライアントと成果を出すために大事にしていることについて書いていきたいと思います。
あくまでも私個人の体験をベースにした話であり、持論なので当てはまらない方もいるかもしれませんがその点はご容赦ください。
アウトプットの責任者としての自覚
「いつまで、そんなにかしこまっているの?」この言葉は、かつてクライアントから言われた一言です。この言葉の真意はおそらく「いつまでそんなに他人事なの?」だと思いますが、とても優しいクライアントだったのでそこまでズバッと言われませんでしたが、少なくとも私にはそう聞こえました。
「他人事」。
これはクライアントワークを自分自身でつまらない仕事にしている最も大きな原因と言っても過言ではないと思います。つまらないどころか成果ももちろんついてきません。
ちなみに私は当時、何か大きなトラブルを起こしてこれを言われたわけではありません。些細な会話の中でそうした言葉を発していたのだと思います。
「ここは好みじゃないですかね?」
「どちらでも良いと思いますよ」
「それで良いんじゃないですかね。」
「後は御社で〇〇していただければと思います」
など、一見するとそこまで違和感を感じない言葉たちですが、ブランディングディレクターもしくはクリエイティブディレクターは、大前提としてコンサルタントではないので、最後までアウトプットに対する責任を持つべきです。
それに、真のパートナーシップを求めるクライアントからしてみれば、「なんか他人事だな..」「最後の最後で詰め甘くない?」と思うはずです。
こうした些細なことの積み重ねによって信頼関係が失われていき、話が噛み合わなくなり、さらには責任の範囲も狭くなってしまう。
つまり自ら「”生み出す人”ではなく、”作業する人”」になりにいっていたのです。
そんな状態になってしまえば、そのプロジェクトから想像以上の成果が生まれることは、ほぼありません。
そして私はこれ以降、自身の姿勢の甘さ、詰めの甘さに対して猛反省し、改めて、今なぜこの仕事をしているのか?誰のためにやっているのか?頑張った先に何を得たいのか?など一つひとつ自分なりに言語化していきました。
この言語化の過程では多くの気づきがあり、諸々整理した上で、いまは「未来に向けた挑戦を支える、圧倒的な応援者」を指針に活動を続けています。
もちろん簡単な話ではありません。自分の中で「圧倒的な応援者像(もしくは1番のファン)」をイメージし、仕組み化し、そのための行動を常にとっています。ただ、この姿勢を貫くようにしてから、課題が突破されるような成果を出すことができ、クライアントとの信頼関係も徐々に育まれるようになりました。
確かに形式的にはクライアントはお客様で、自分は社外の人間かもしれません。ですがこの垣根を自らの行動で無くそうとしなければ、本当の意味で支援なんてできません。なので今はとにかくあらゆる場面で「自分ゴトを増やすこと。」を大切にしています。
コミュニケーションは常に対等である
私はこれまで「もっと察することができるように」という意識でいつもクライアントワークに取り組んでいました。ただこれは、行き過ぎると良くないなと思うようになりました。
誤解がないように念の為お伝えしておくと、察しようとすること自体は全く悪いことではありません。むしろ察する能力はどんな仕事においても必要です。
私がここで言いたいことは、過度に察しようとして、積極的に「問いかけること」「確認すること」を怠ってはならない。ということです。
少し余談になりますが、日本人は「ハイコンテクスト文化」と呼ばれる文化が根付いているそうです。(世界で一番「ハイコンテクスト」な国)
かなり噛み砕くと「言葉がなくても雰囲気で察して!」という文化です。
注意したいのが、ハイコンテクスト文化は聞き手(受け取り手)に委ねられる部分が大きいという事。一方で、ローコンテクスト文化もあります。
これはハイコンテクスト文化の逆で「しっかり言語化して相手に伝えよう」という文化です。つまり、ローコンテクスト文化では、伝わるか伝わらないかは、話し手に委ねられる部分も大きい。
なぜこんな話をしたのかというと、どちらの文化が良いかという議論ではなくて、コミュニケーションは対等であり、もちろんそれはクライアントとの仕事においても同様だと思うからです。
聞き手は相手の心の中を察するよう努めないといけないし、話し手は聞き手の状況を観察して言葉を探さないといけない。そして聞き手は、話し手でもある。(表裏一体)
なので、思っていることや問いたいことを余す事なく言語化し、ハッキリと伝えるというのが、成果に繋げるためにかなり重要な姿勢だと思っています。
気が合うではなく、ベクトルを合わせる
価値観が合う人との仕事は、事がスムーズに進むと思います。誰もが誰かの意見を疑うこともなく、意見が割れることも少ない。だから提案も通りやすい。
これに関しても一見良さそうに見えますし、私もそんな仕事を理想としていました。ただ、実はそれだけでは足りないのと、案外それは幻想だということに気がつきました。
似た価値観の人ばかりが集まると、逆に新しい発想が生まれないんですよね。だから大事なのは「価値観」よりも「ベクトル」があっているか。だと思うようになりました。
価値観を強引に押し付けるのではなく、それぞれが持つ違いを受け入れ、価値観もすり合わせながら、共通の目的をつくり、同じ方向を目指して進む。意見を交わす。
そんなチームの方がきっと面白いものを生み出せる。これだけ情報やモノが溢れる今の時代においても、新しいモノづくり、新しいコンテンツづくり、新しい価値がつくれるようになる。
また、本当の伴走は、価値観の違いを受け入れたその先にあるものだと、多くのプロジェクトを通じて実感してきました。価値観を理解し合うことで初めて「本当に良い提案」と「押し付けがましい提案」の違いに気づけるようになります。
だから大事なのは「ベクトル」。価値観は違って当たり前。違った上でどうするか?です。
互いにイメージでき、成し遂げたいと思えるような目的や目標がなければつくる(明文化する、定義する、接点を見つける)必要があるし、もう既にあるのであればもっとそれに沿った戦略や計画を絶えず共有し続ける必要があります。
ベクトルが合うことによって、意見が割れても、敵対はせず、同じ方向を向きながらそれぞれが納得する第三案が生まれるようになると思っています。
人間関係が良いから仕事がうまくいくのではない。
一つ前の話と少し重複するところもあると思いますが、「人間関係が良いから仕事がうまくいく」という順序で考えていると、全くと言っていいほど良い仕事ができなくなります。
かつて私も「まずは人間関係が大事。だからクライアントと仲良くなろう。そうすれば成果が出る」と思っていました。
ただ振り返ってみると、本当に人間関係がよくなる瞬間というのは、「チームで結果を出せた時」だったのです。
つまり、良好な人間関係は成果が伴ってこそ成り立つんです。
「人間関係が良いから仕事がうまくいく」だと、今は良くても、後々成果への意識が薄くなり(本来の目的を見失い)、相手のご機嫌をうかがいながら仕事を進めるようになります。
一方で「仕事がうまくいっているから人間関係が良くなる」という発想は、目的意識や未来志向を持ったチームづくりにつながり、成果もついてきやすくなる。
そして結果的にメンバーそれぞれに自信がつき、互いを共通の志を持った仲間として認め、尊重し合う関係性が生まれる。
なので、目的を明確にすること、目標を細かく設定すること、それに沿ったそのプロジェクトにおけるルールを設定することは個人的にも会社としてもかなり大事にしているポイントです。
ルールは堅苦しいものではなく、発想を尖らせるもの
「ルールなんて必要ない。ルールが多いチームからは柔軟な発想が生まれないんだ。」
これも通用しない考え方でした。クライアントとチームを組んで目標達成を目指すならばルールは必ず必要なんです。
あくまでシーンや作られるルールの内容によってどれほど機能するかはさまざまですが、個人的にはルールがあるからこそ面白いアイディアが生まれたり、生産性が向上したりすると思っています。ルールはガードレールのようなものなんです。
ルールが明確だから、
- 言った、言ってないのトラブルが防げる。
- やるべきことと、やってはいけないことが分かる。
- 思考の範囲が良い意味で限定的になり、尖ったアイディアを生み出せる。
- 余計な確認が少なくなる。
- 目的としっかり向き合える。
ある意味、一つのゲームのルールをしっかり作りこむイメージです。
なので真っ先にルールを破る人がいた場合、すぐに注意するか、注意しても改善されない場合はすぐに退場させた方が良いです。サッカーの試合で、手を使い始めたり、相手選手をめがけて思い切りタックルできてしまったらもうゲームは成立しないですもんね。
理由なき値引きは成果から逃げる行為
特に理由なく「値引き(安売り)」するのは、いつしか大きな溝を生むことがあります。 それは、十分な価値を届ける機会を自ら奪ってしまう行為だからです。
さらに、値引きは麻薬のようなもので、一度手を出すと、「プロジェクトの成功」ではなく「案件の獲得」に目がくらみ、今後も何度も繰り返してしまいます。
その結果、自社や自分のブランド価値が下がり、新たな依頼も、結局見合った低単価のものばかりになりがちです。するとどうなるか…?どの案件も低単価になると、一つのブランドに時間も情熱を注ぐことができず、すべて片手間な対応になってしまうのです。
また、ちょっと内面的な話ですが、値下げすると無意識のうちに自分自身にブレーキをかけてしまうことも少なくないと思います。「値引きもしているし、これくらいだろう」って。
つまり、値引きは、成果を出すということから自分を遠ざけてしまう行為です。
クライアント企業で働くスタッフさんが一生懸命に稼いだ利益が「投資のため」ではなく「消費」にならないためにも、今後さらなる価値を提供するためにも、値付けや予算管理は慎重に行うことを大切にしています。
最後に
私たちの仕事はどこまでいこうと「支援・応援」です。ただ、そもそも支援ってかなり究極のスキルだと思っています。
なぜなら、自分が他人の目を気にしてばかりで満たされていなければ、本来支援なんてできっこないんです。(矛先が目の前にいる相手や目的ではなく、自分を守ることになってしまう。)
なので、他人の評価を気にしすぎて、他人の人生を生きてしまうのではなく、まずはちゃんと自分の人生を生きることを大事にしています。
100%は難しかったとしても本当の意味で支援ができるようになるのはある程度その状態を作れてからなのかなと。
「だからまずは自分が自分に嘘をつかないこと。」を自分との約束として、日々の課題や誰からのコミュニケーションと向き合っています。