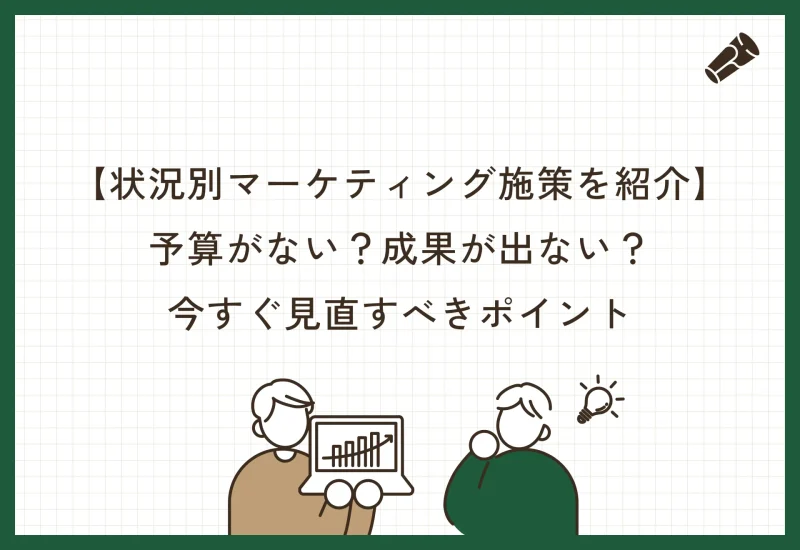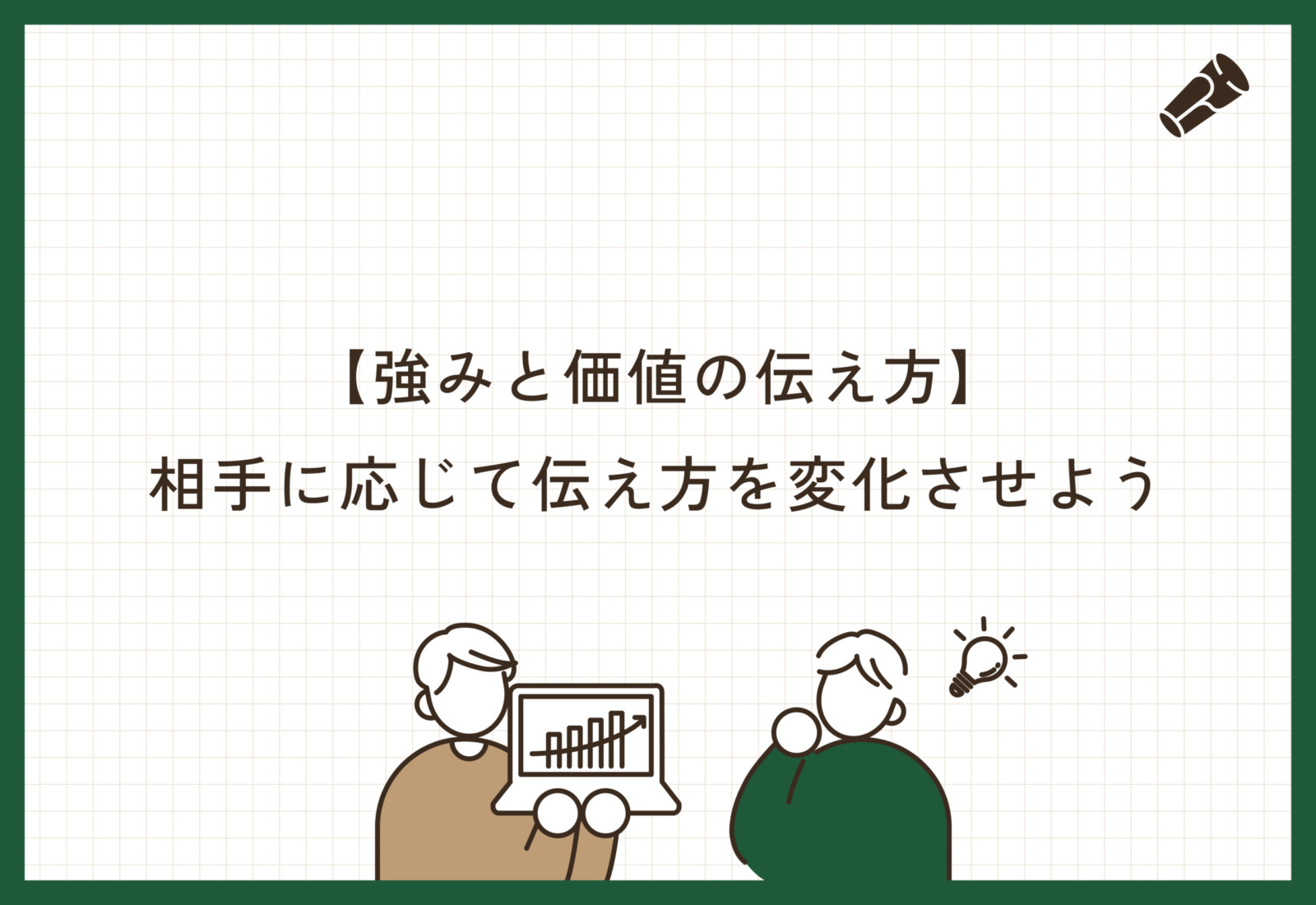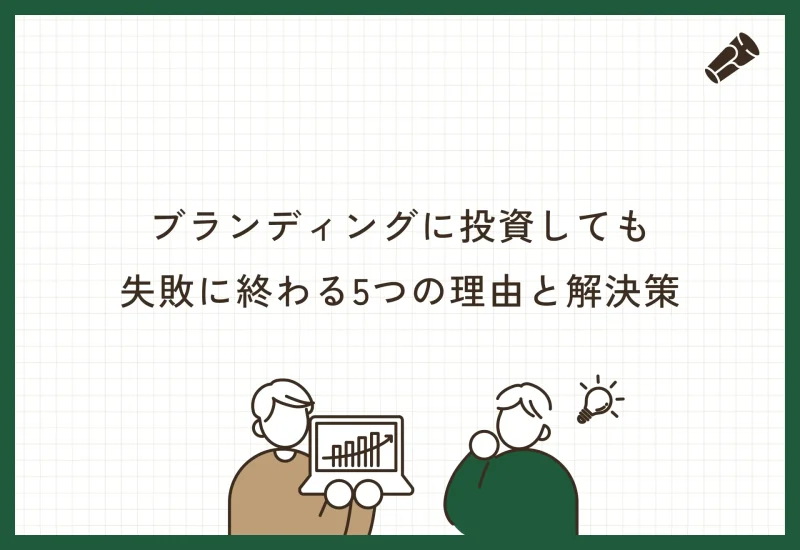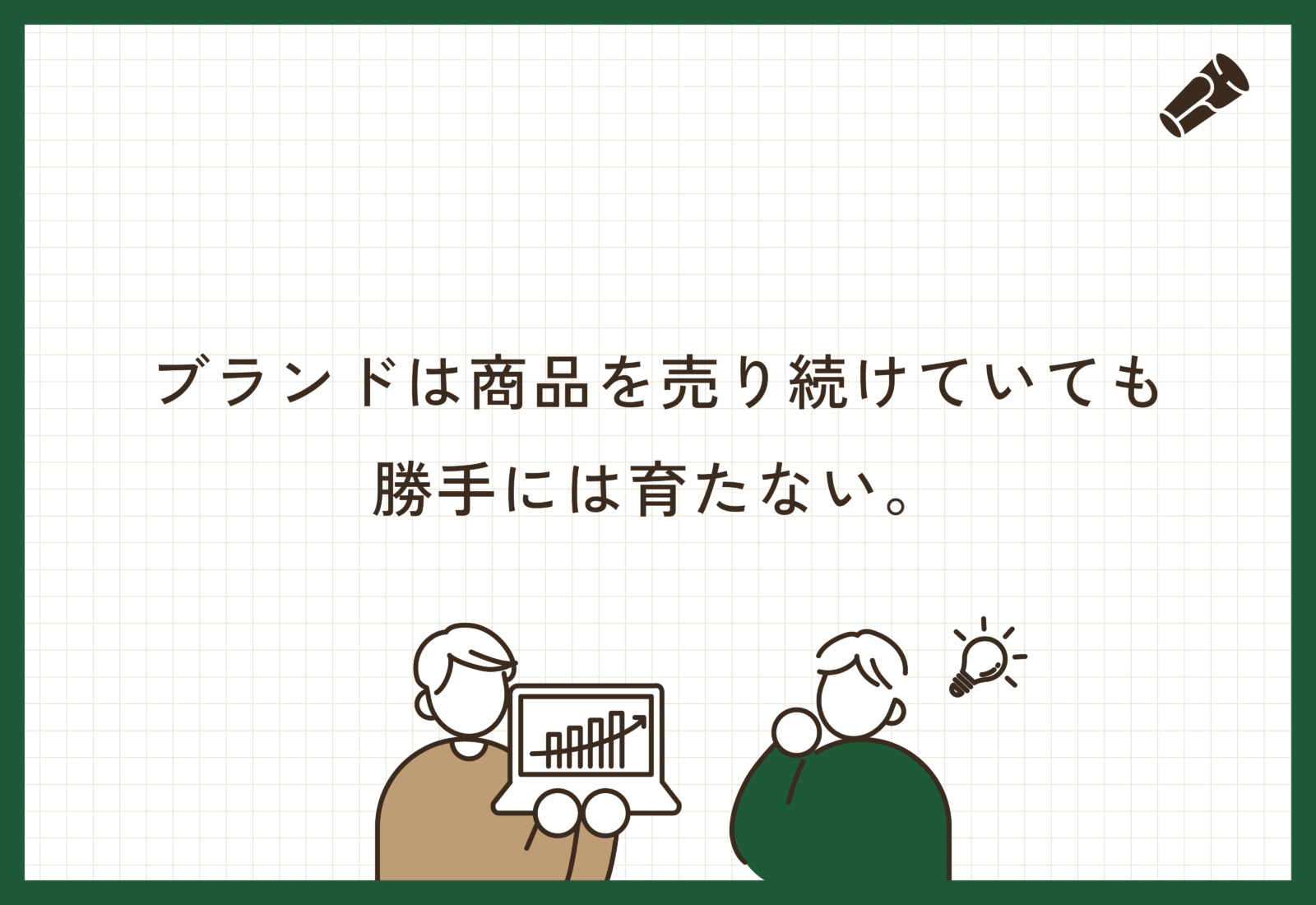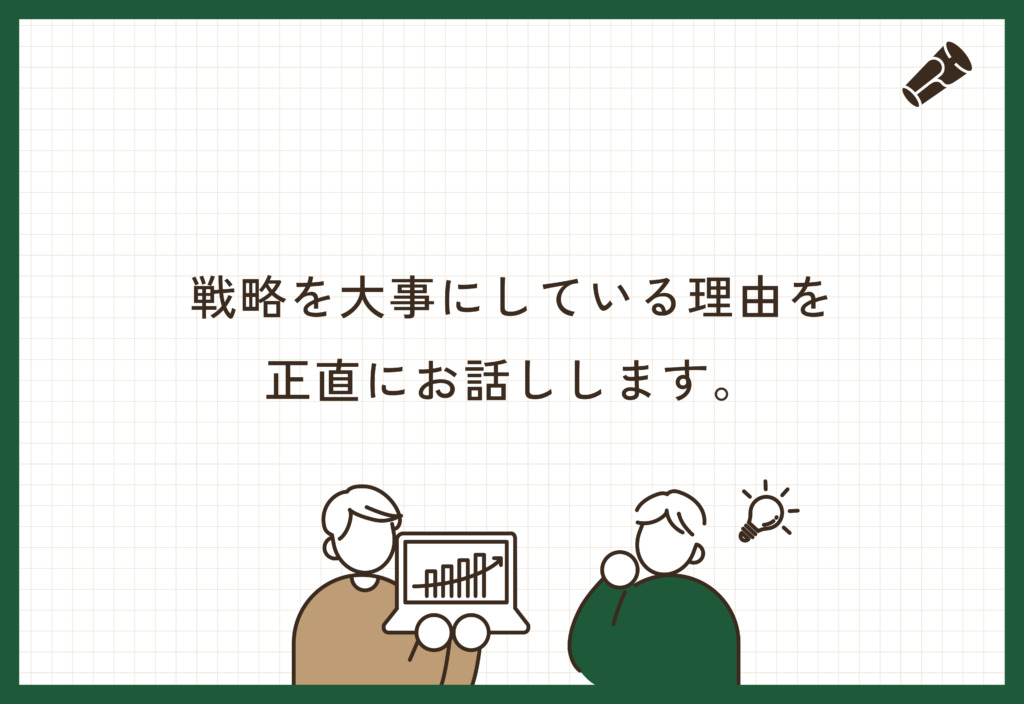
「この取り組みって何に繋がっているんだっけ?」
「やってもやっても成果が全く出ない。いや、そもそも成果定義が曖昧」
「あらゆる手段を使って色々やってみたが、全て中途半端に終わってしまった」
こうした経験はありませんか?
私はこれまでの経験の中こういった場面に何度も遭遇しました。結果的にスタッフのモチベーションが著しく低下してしまったり、大事な場面で必要な資源が不足していたり、得られたデータやナレッジが少なかったり。一体あの時間と労力とお金はどこへ消えてしまったのだろう。きっと誰にでもある経験ではないかと思います。
こうした状況にならないために戦略がある。私がこの事実に気づいたのは20代の頃ですが、正直もっと前から知っておきたかったなというのが本音です。(自分の息子には小学生の頃から教えていきたいと思っている。#親のエゴ)
よくお問い合わせいただいた方から、
「今回の取り組みにおいては戦略はいらない。」
「戦略が必要なほど大きな取り組みではない。」
「なんか難しそうだから今回はとりあえずホームページの改修だけに留めておこうと思う」
「とりあえず行動!」
などのお話をいただくことがあります。
そう思われるのも無理はないと思いますし、実際に過去の私もそう思っていたので全く否定はしません。ただ、その上でこれだけは言わせてください。「企業活動において戦略が必要のない場面はほぼない」と。
そのことをお伝えしたく本記事を書こうと思いました。
そもそも戦略とは??
戦略と聞くと少々堅苦しく難しい印象を受ける方もいるかと思いますが、意外と身近な存在です。
例えば旅行にいこうと思った時、まず何をしますか?
- いきたい地域を決める(目的地を決める)
- その地域の周辺でいきたいスポットを決める
- 宿泊の場所を決める
- 行き方を決める
- 最もロスが少ない観光ルートを決める。
- 何を持っていくかを決める…
かなりざっくりですがこのようなことを行うと思います。
個人的な話ですが、私は大の旅行好きなので、観光する場所の歴史や良い写真スポットなんかも調べてしまいます。
そんな話はさておき、実は何気なくやっているこの行為こそ戦略です。
戦略の定義はそれぞれですが、RecorCでは以下のように定義しています。
戦略とは「選ぶこと(選択する)」。
企業活動において考えると、「どの市場で戦うのかを選択する」「誰に向けて事業や商品をつくるのかを選択する。」「誰にどんな行動変化を起こしたいのかを選択する」ということです。
戦を略すと書くように、無駄な戦いを避け、資源に余裕を持ったまま最短ルートで目的地に向かう。そのため、目的地も定かではなく、選択もせずにあらゆることに手を出している状態は、戦略がないのと同じです。
そして、私たちがブランドマーケティングを行う上で最も大事にしている「コアコンセプト」は、まさに戦略そのものを表していて、「目的に応じてリソースをどう配分するか、どう使うかを選択する指針」になります。(コアコンセプト=戦略を言語化、メッセージ化したもの)
ちなみに「ブランディングやマーケティングにおけるコンセプトの重要性」については以下の記事で詳しく紹介していますので、興味があればこちらの記事もご覧ください。
▼【コンセプトの価値とは何か】一貫性も、共感も、選ばれる理由も、すべてはコンセプトから始まる。
https://recorc.com/media/brand-marketing-concept/
戦略が必要のない場面はあるの?
戦略の重要性ばかりをお話ししてしまうと、腹落ちしない点も出てくると思いますので、逆に戦略が必要のない場面があるのか?についても書いていきたいと思います。
先ほどの「戦略とは選択すること」の定義に沿って話を進めるならば、そもそも選択とは何なのかを紐解く必要があると思います。
みなさんは何かを選択する際、どのようなことを考えますか?
例えば先ほどの旅行を例にして考えてみた場合、東京在住で、「できるだけ長い時間、北海道を満喫し、日々の疲れを癒そう」という目的が仮にあった場合、飛行機で現地に向かうという選択をすると思います。そして車や電車という選択肢は捨てることになります。
つまり選択とは「目的に沿って、何かを捨てること」と定義することができます。
先ほど紹介したコアコンセプトの定義においても「目的に応じてリソースをどう配分するか、どう使うかを選択する指針」です。
もうお分かりかと思いますが、戦略が必要のない場面というのは「目的」や「目標」がない場面(活動、取り組み)です。なので、「この商品の、この価値を、こういった顧客に届けたい」という場合は必ず戦略が必要になります。
社会、顧客に対して何らかの価値を提供し利益を上げ、さらなる価値を提供するために投資を行う。
これが企業という存在だとするならば、「戦略がない場面はほぼない」と思っています。
私たちは石油王ではないから資源に限りがある。
また、もう一つ戦略が必要ない場面を挙げるならば、資源が無限にあるという場合です。資源が有り余るほどあるのであれば、わざわざ選択せずとも、全ての選択肢に対して資源を投下してしまえば良いはずです。ただ、石油王でもない限り資金的な制約は必ずあると思います。そして、たとえ石油王だったとしても”時間”においては有限です。
私たちもそうですが、特に中小企業は大企業に比べて、資源に限りがあります。RecorCは主に中小企業の経営者の方とお仕事をさせていただく機会が多いです。何度も、クリエイティブの話やマーケティングアクションについて議論になりますが、どんなテーマにおいてもやはりメインの議題は戦略に関してです。資源が限られている中小企業にこそ戦略が必要だということを現場での経験から何度も感じてきました。スタッフの方々が一生懸命稼いだ資源を無駄にしないためにも私たちは戦略を大事にしたい。
戦略をつくる上で最も大切にしていること
「彼を知り、己を知れば、百戦して殆(あや)うからず」
これは名だたる戦略家が必ずと言っていいほど知っている孫氏が残した言葉です。
ここで書かれている「彼」というのは、同じ業界の企業のことと受け取ることもできますが、個人的にはそれだけでなく、市場や社会環境なども含まれていると思っています。そして己というのは、自分たちの今ある資源、強みや弱みを指している。もちろんそれらに加えて、企業や事業の「目的や目標」も含まれます。
先ほど書いた孫氏の言葉は、戦略を実際に言語化したり、または実際にアクションを起こすこと以前に、「知ること」がどれだけ大きな意味を持つかを表しています。なので私たちもクライアントさんと一緒に戦略を構築する際は、まずは知ること、理解することを徹底しています。
記事の前半にも書きましたが、戦略やコンセプトは、「目的に応じてリソースをどう配分するか、どう使うかを選択するための指針」です。つまり目的が変われば戦略も変えなければならないということです。
極端な例えになりますが、
「自分が生まれ育った地域をもっと元気にしたい」という目的を抱えてる方と、「世界中の人に選択肢や可能性を届けたい」という目的を抱えている方とでは、取るべき戦略や戦術の”優先順位”が変わってきます。
定量的な面においても、「客単価を昨対50%増にする目標設定」と「新規のお問い合わせを昨対50%増にする」という目標設定ではKPIも変わってきますし、もちろん取るべき戦略や戦術の”優先順位”も変わってきます。つまり目的や目標、目指すビジネスの規模などに応じて、”いま”何を選択すべきか変わります。
プロジェクトによっては、目的や目標を明確にすることに最も時間をかけるケースもあります。それが一番の最短ルートであり、戦略がハマる必須条件だからです。デザインや広告などの力を十分に発揮させるにも、ここの前提(企業や事業にまつわるあらゆるものの理解)があってこそなんです。
常に問い続ける戦略の質
私自身、今こうして起業し、ブランディングディレクターとして活動するまでに、リーダーという立場でありながら戦略を度外視し、何度も痛い目に遭ってきました。どれだけやってもうまくいかず、目に見えないプレッシャーは増していくばかり。そこから何か得られたか?と問われると特にない。(戦略の重要性には気づけたが)
いや、痛い目に遭っていたのは私だけではありません。周囲の方々に無茶させてしまい、もしかしたら一緒に仕事をする仲間の方がしんどかったかもしれません。
頑張ること、苦労すること、努力することはもちろん大事なこと。実際私自身もこれまで何かしらの成果が得られた時は、これらがセットでつきまとっていました。
ただ、”考えることを怠り”体力勝負で動き続け、いつも頑張っている状態というのもなかなかしんどく確実に長続きしません。
企業活動においても、分析・戦略・戦術の構築やブラッシュアップが全くなく、ナレッジが蓄積されない状態で「とにかく行動」「質より量、量、量!」「一生懸命やっていればいつか報われる」という大義名分の下、動き続けてしまっていれば、いざ壁にぶち当たった時に一気に停滞することになります。
なぜなら、今はうまくいっていたとしても、取り巻く環境の変化によって突然状況が悪化した際に、何をどう改善すれば全くわからない状態に陥るからです。そして、うまくいかないときに余計にスタッフに行動力でカバーするよう促してしまうと、人が少しずつ離れていってしまいます。
バケツの底に大きな穴が空いているようなイメージで、小さな成果が出ている割に出ていくものの方が大きく、リカバリーも効かなくなってしまうんですね。
米国MITスローン経営大学院のピーター・M・センゲの著作「学習する組織――システム思考で未来を創造する」では上記に書いた状態のことを相殺フィードバックという言葉で表現しています。
多くの企業が、自社製品が突然に市場での魅力を失い始めるとき、相殺フィードバックを経験する。
企業はより積極的な売り込みを推し進める──
それが今までいつもうまくいっていたやり方だ。 宣伝費を増やし、価格を下げるのである。
こういった方法によって、一時的には顧客が戻ってくるかもしれないが、同時に会社からお金が流れ出ていくので、会社はそれを補うために経費を切り詰め、サービスの質(たとえば、納期の早さや検査の丁寧さ)が低下し始める。長期的には、会社が熱心に売り込めば売り込むほど、 より多くの顧客を失うことになるのだ。
ざっくり言ってしまえば、「今の環境、やり方のままで、頑張れば頑張るほど状況が悪くなり、選ばれなくなる」ということだと思います。そもそも何事もがむしゃらに頑張ることでなんとかなっていれば、事業活動の中にマーケティングやブランディングなどの「〇〇戦略」という言葉自体生まれていなかったと思います。
本来は頑張り始める前から常に見直ししていくものなのだと思いますが、もし今頑張っている状況であれば、戦略の見直しやリソース配分の見直しを行う時期だと思います。
最後に
今回の記事でお伝えしたいのは、「戦略の定義とその重要性」、そして「行き詰まりを感じている場合は、努力の方向を見直してみませんか?」ということです。
環境の変化や逆風に果敢に立ち向かうのではなく、それらをむしろ味方につけ、努力すべきポイントを見極める。最小の労力で活動を続けながら、社会や人に価値を提供する。
理想論に聞こえるかもしれませんが、実際にこれを体現されている方がいるのも事実です。
ちょうど先日、この記事を書き始める前に、尊敬する経営者の方とお話する機会がありました。その中で、「無理して頑張らず、最大の成果が出せる場所を常に探している」と語られていたのが印象的でした。数えきれない挑戦を続けているにもかかわらず、良い意味で余裕を感じさせる姿に、「まさに戦略の意義はこのことだな」と思いました。
この話は企業活動だけでなく個人のキャリアにおいても同じことが言えると思います。苦労や努力、頑張ることは一見美しいこととされていますが、それだけがひとり歩きしてしまうと好きな仕事も好きでなくなってしまいます。
決して「のらりくらりやっていこうよ」と言いたいわけでなく、常に学習しながら効率的に成果を最大化していくことで、それ自体が大きな他者貢献に繋がり、顧客も自分たちも満たされていきます。
時間や体力は有限ですし、過酷な労働を誰かに強要したい人なんていないと思っています。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級