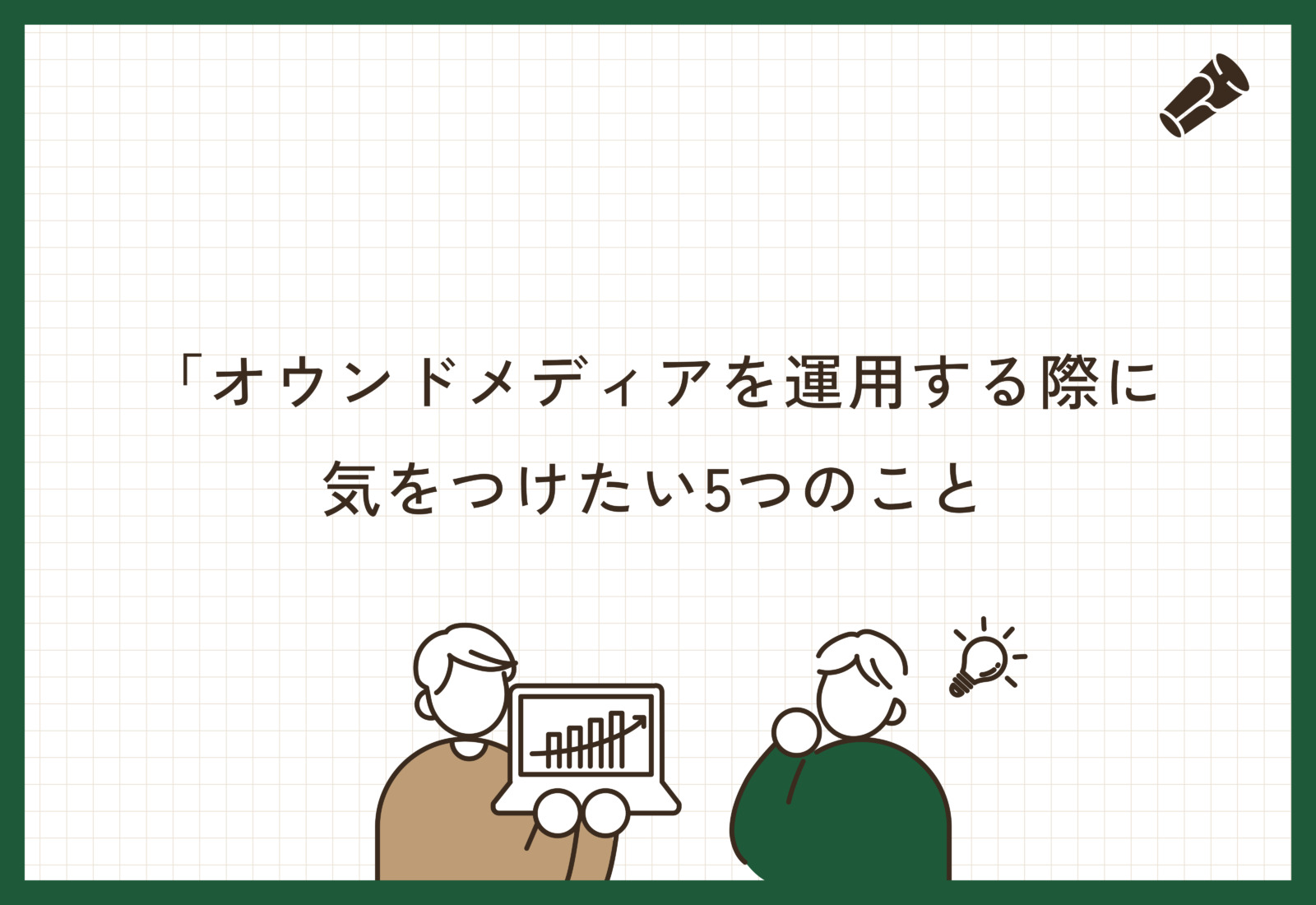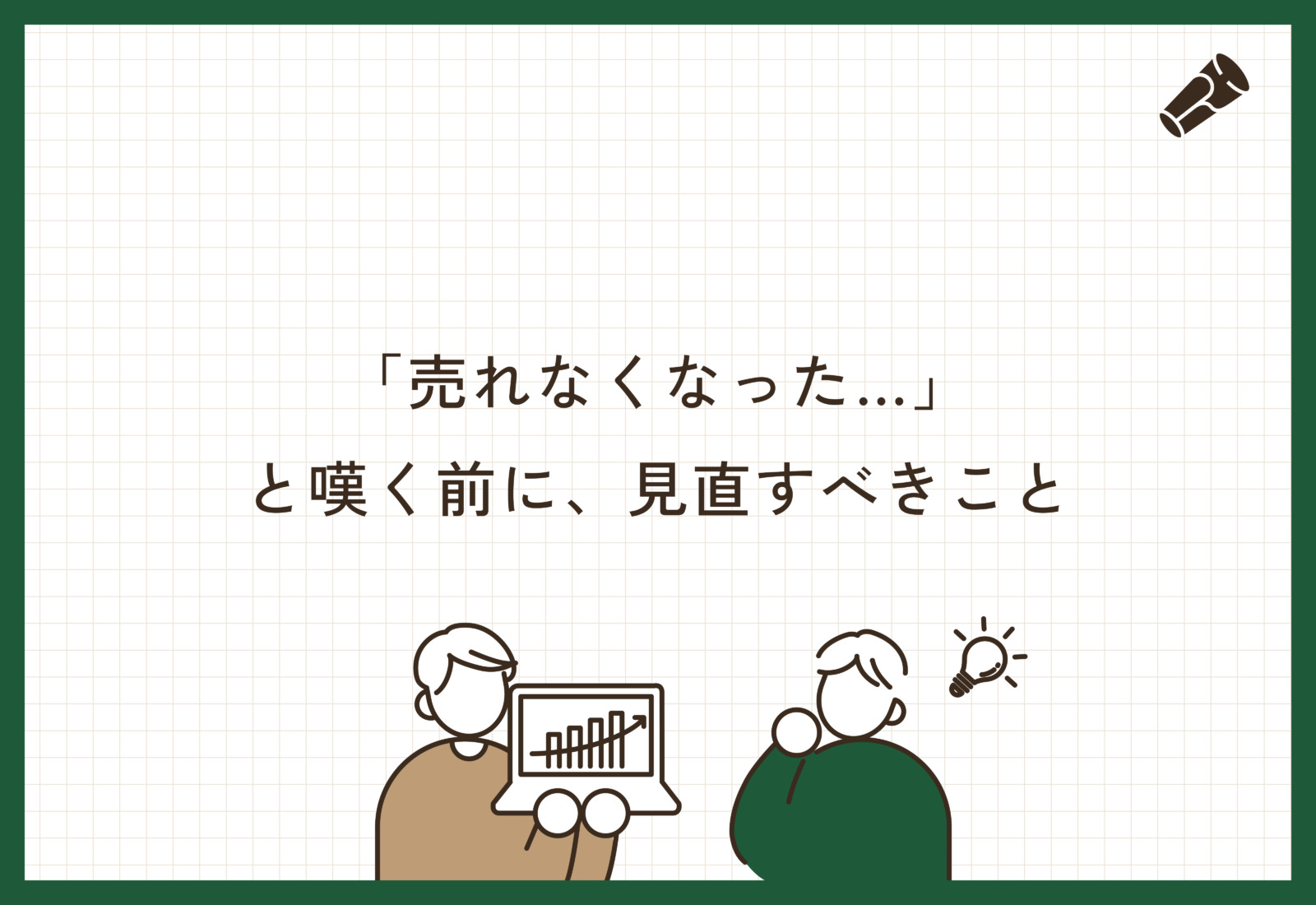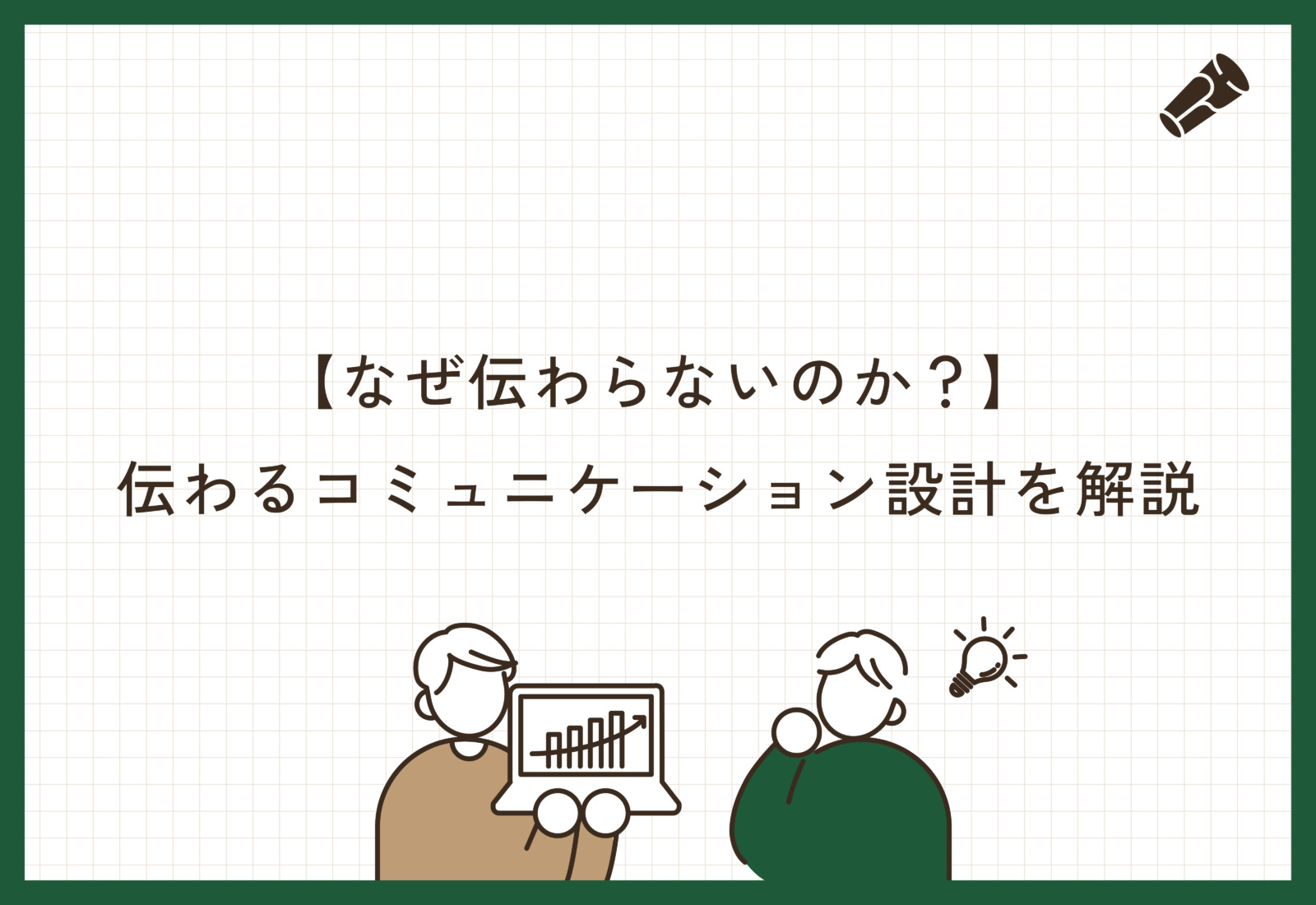Index
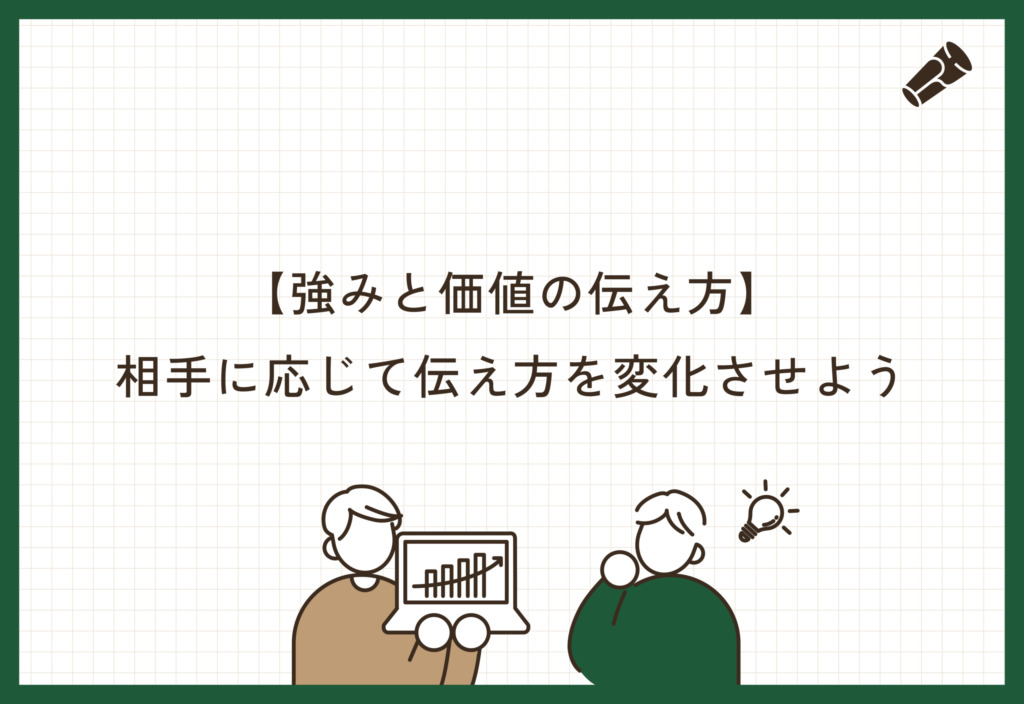
「強み」や「価値」という言葉、簡単に使われがちですが、実際にはこの2つをどうやって相手に響かせるか、それが最も難しく、また最も重要な部分です。
どんなに素晴らしい商品やサービスがあっても、その強みを適切に伝えなければ、誰にも届きません。時に、ほんの少しの伝え方を変えるだけで、反応は劇的に変わることもあります。
この記事では、どんな伝え方が最も効果的なのか、その答えを見つけるためのヒントを探しながら、相手にどう伝えればその強みが最大限に響くのか、具体的な方法を掘り下げていきます。
強みを伝えるための基本的なフレームワーク
商品の強みを効果的に伝えるためには、その本質を明確に把握した上で、どう伝えるかを計画的に整理することが求められます。
まず重要なのは、その強みをしっかりと理解し、伝えるべき内容を整理すること。
そこで、以下の3つの視点で要素を分解し、伝え方を考えることがカギになります。
1. ファクト(事実)
商品がどのような特徴を持っているのか、具体的な事実に基づいた部分。
2. メリット(利点)
事実から生まれる「利点」。商品の特徴がどのように顧客にとって役立つのか、どんな利益をもたらすのか。
3. ベネフィット(便益)
その利点が顧客にどのような感情的・実質的な価値を提供するのか。
例えば、架空の商品の例として「乳酸菌シロタ株を2,000億個含む飲料(以下A商品)」があるとします。その場合以下のように整理できます。
- ファクト:乳酸菌シロタ株を2,000億個含む飲料である。
- メリット:睡眠の質が向上し、熟眠時間が増加するという報告がある。
- ベネフィット:毎日、仕事に対して前向きな気持ちを持ち、パフォーマンスが向上する。
このように、強みを伝えるための要素を整理することで、伝えるべき内容が自然に明確になります。
相手の立場を考えて、伝え方を変える
次に大切なのは、伝え方を相手のニーズに合わせて変えることです。
何を伝えたいかが決まったら、次は、ファクト・メリット・ベネフィットを「誰に」「どの順番で」伝えるかを考える必要があります。
相手が何を求めているのか、どんな情報を最初に知りたいと思っているのかを見極め、伝える順番を変えるイメージです。
具体的な例としては以下のようになります。
ケース1:すでに睡眠の質に問題を抱えている人で、商品に関心がある人
こうした人に対しては、「乳酸菌シロタ株を2,000億個含む飲料(ファクト)」という情報から入り、その後に「これにより睡眠の質が向上し、熟眠を得られる(メリット)」。
そして最終的に「これによって毎朝、ポジティブな気持ちで一日を始められる(ベネフィット)」という順番で伝えると効果的です。
ケース2:疲れが取れず、健康的なエナジードリンクを探している人
この人には、最初に「ベネフィット」から入るのが理にかなっています。
例えば、「毎日疲れを感じることなく、仕事も家事も全力でこなせるようになる」というメッセージで興味を引き、その後で「これがどのように実現できるか(メリット)」を伝え、「乳酸菌シロタ株2,000億個(ファクト)」でその”根拠”を説明します。
これらの違いをしっかりと理解して、相手の立場に立った伝え方を選ぶことが大切なんです。
ベネフィット自体もターゲットに応じて変化させる
さらに、ベネフィットも、ターゲットに合わせて変化させるべきです。
例えば、「睡眠の質を向上させる(メリット)」という効能ひとつとっても、それを求める理由は人それぞれ異なります。
ある人は「仕事のパフォーマンス向上」を目指しているかもしれませんし、また別の人は「休日に家族との時間をもっと充実させるため」に改善を望んでいる場合もあります。
だからこそ、ターゲットの動機に合わせてベネフィットを調整し、その人にとって最も響くメッセージを届けることが不可欠。
ターゲットが本当に求めていること、彼らが置かれている状況をしっかりと理解し、その人にとっての「意味」を伝えることで、より深く共感を得ることができるんです。
鍵は、ストーリーを活用した情緒的価値の伝達
価値は大きく分けて「機能的価値」と「情緒的価値」に分けられます。
- 機能的価値:性能やスペックに基づく価値
- 情緒的価値:感覚的・精神的な価値
ベネフィットはこの情緒的価値に近いものですが、そのままストレートに伝えようとしても、どこか響かないことが多い。
むしろ、それがあまりにも露骨だと、逆に胡散臭く聞こえてしまいます。結果、顧客が離れていくなんてことも。だからこそ、「ストーリー」が必要になるんです。
ストーリーには、直感的に理解されやすい力があります。そして記憶にも残りやすい。
わかりやすい物語を語り、テキストとビジュアルをうまく組み合わせてデザインをすることで、情景が自然と想起され、感情移入を引き出すことができます。
だから、強みや特徴を伝えたいときには、単に「気分が晴れやかになり、日々幸福感を実感できますよ」といった情緒的価値をそのまま言葉にするのではなく、ストーリーやデザインを通じて、“価値を感じさせる工夫”が欠かせません。
ただ、ストーリーを組み立てるのはなかなか難しいもの。少しでも誤ると、こそばゆいポエムのようになってしまうリスクもあるので、注意が必要です。
まとめ
この記事で紹介した内容は、あくまで一つのアプローチに過ぎません。他にも商品の特徴や強みを伝える方法は無限にあります。
しかし、ひとつ確かなことは、顧客が物理的な商品そのものに対してお金を払っているわけではないという点です。
顧客が支払っているのは、その商品がもたらす「役割」や「意味」、つまりその商品が生活や心情に与える影響に対してです。
そのため、単にスペックや特徴を並べるだけではもちろん足りません。
だからこそ、ストーリーやデザインを駆使して、その商品が顧客にもたらす価値を深く、感覚的に伝える必要があるんです。
価値を伝える方法を巧みに活かす企業こそが、競争を抜け出し、選ばれる存在となる。
物やサービスが溢れる今、このアプローチはますます加速し、顧客の心をつかむための強力な武器となるに違いありません。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級