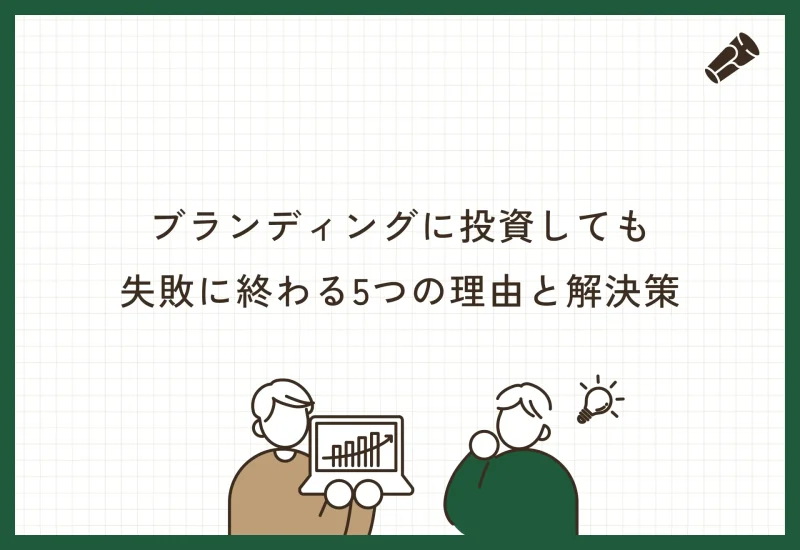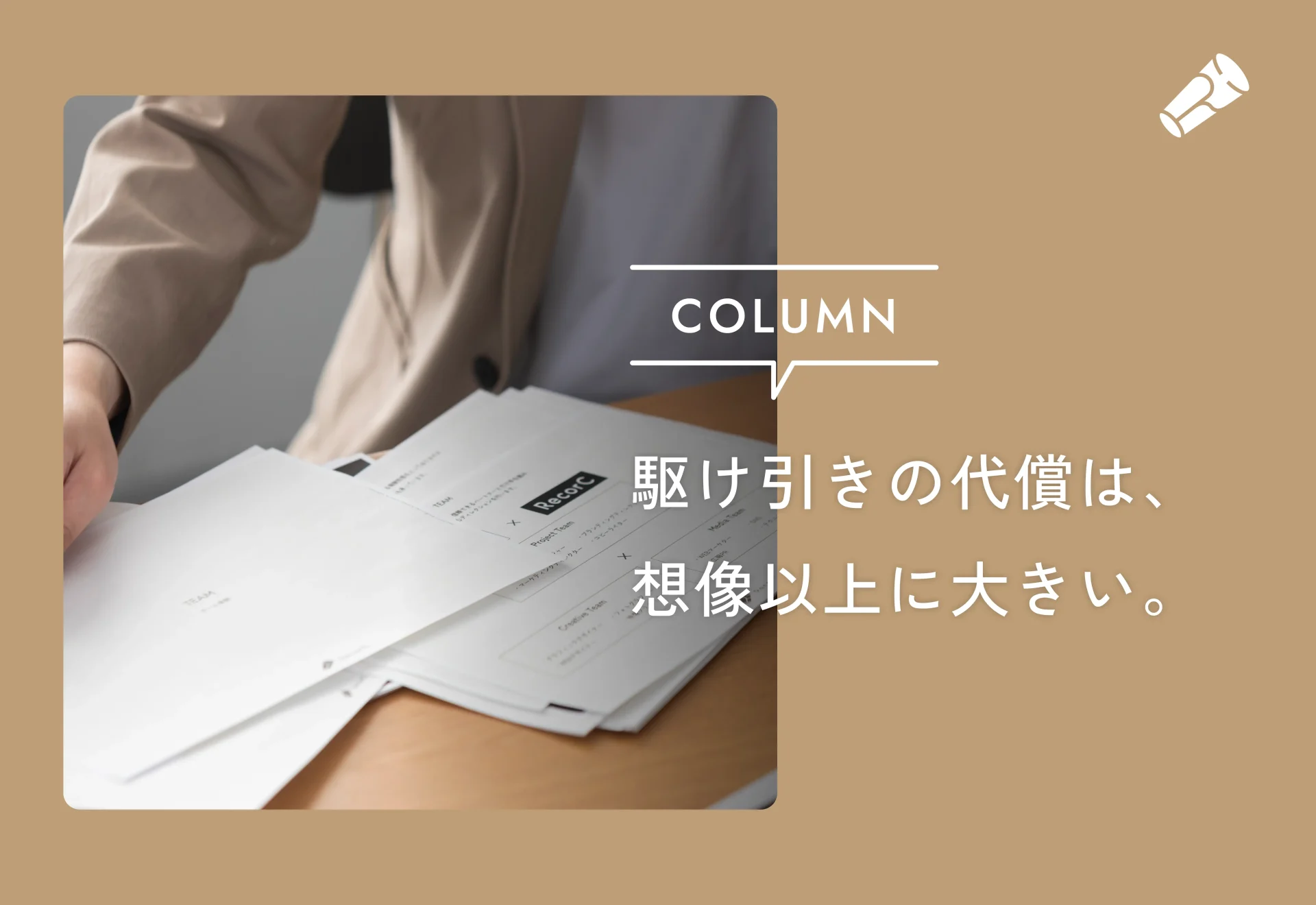
ビジネスをする上で当たり前のように存在している「駆け引き」。
大前提として、必要な場面とそうでない場面があるのは重々承知しています。
ただ、ブランディングやマーケティングを通じた事業伴走においては、本当にいらないものだなと常々感じています。
ちなみにここで言う駆け引きとは、自分にとって有利な条件や展開を引き出すために、情報や態度を意図的に操作することを指しています。
今回の記事は、特にノウハウ的に役立つものではありません。
ですが、こうしたコミュニケーションに関する考え方を正直に綴ることで、少しでも私たちがどんなスタンスでプロジェクトに向き合っているかを伝えられたらと思っています。
プロジェクト内で駆け引きが散漫するとどうなるか?
駆け引きがプロジェクトに入り込むと、チームの中に無用な警戒心や誤解が生まれます。
それが進行のスピードや意思決定の質にまで影響するのです。
たとえば、実際の商談の場面での話。
初回の打ち合わせで「100万円でお受けできます」とお伝えしたとします。
するとお客様から「他社さんは80万円と言ってくれましたよ」と返された場合、もしこちらが「じゃあ、うちも80万円で大丈夫です」と即座に値下げに応じたとしたら、どうなるでしょうか?
お客様側としては「安くなってラッキー」と思うかもしれません。
私自身がその立場でも、きっとそう感じると思います。
ただそれと同時に、「それができるなら最初から言ってよ」と、少しだけ不信感が芽生えるのではないでしょうか。
そしてこの小さな違和感は、のちのちプロジェクトに影響を及ぼします。
たとえば、別の施策が発生し、どうしても追加の費用が必要になる場面があったとします。
「また高めに伝えているんじゃないか?」「本当はもっと下げられるのでは?」という疑念が生まれる。
すると視点は相手に向いてしまい、本来注力すべき課題や目標から意識がそれてしまうのです。
駆け引きなんてやっている暇があったら、その時間で一緒に課題突破のためのアイディアを振り絞る議論した方がいい。
もしくは目の前のタスクを建設的にこなす方が、何倍も未来に効いてきます。
仕組みで解決するしかない
駆け引きが起きるのは性格の問題ではありません。
むしろ人間の自然な防衛反応。
だから、「信じてくれ」や「空気を読んでほしい」といった精神論に頼っても無意味です。
重要なのは、駆け引きが入り込めない仕組みを作ること。
たとえば、プロジェクトの初期段階で期待値や前提条件を丁寧にすり合わせ、情報を可能な限りオープンにする。
こうした基本的なルールを徹底することで、隠したり探ったりする必要をそもそもなくしてしまうのです。
冒頭で触れたような値引きの駆け引きも会社単位でなくす。
私たちの場合においても、他社が80万円で弊社が100万円の場合、差額の20万円で、目標や目的に対して何ができるのか、どんな価値があるのかを明確に説明します。
予算の上限が80万円だったなら、80万円で何が可能かを整理し直し、課題を再定義する。
信頼は感情論ではなく、仕組みと設計で作り上げるもの。
これを理解して行動すれば、チームの空気も成果も変わります。
メンバー全員が向き合うべきは課題や目標
駆け引きが生まれる背景には、「相手がどう出るか」という“人”への意識が強くなりすぎていることがあります。
でも、本来注目すべきは“相手の出方”ではなく、“課題”や“目標”であるはず。
私たちのプロジェクトでは、常に「今、向き合うべきテーマは何か?」「それに対して最善を尽くすにはどうすればいいか?」を対話の軸にしています。
そうすることで、個人の思惑ではなく、目的に対する純粋な提案や議論が生まれやすくなります。
もちろん、相手の感情や状況を慮ることも大切です。
ただ、それが主軸になると判断が鈍ったり、遠回りになってしまう。
だからこそ、立場や意見の違いがあっても、同じ方向を見ながら議論できる“軸”を整えておくことが重要なんです。
向き合うべきは、メンバー同士の探り合いや人間関係ではなく、プロジェクトの目的そのもの。
それが、駆け引きのいらない健全なプロジェクトの土台になります。
目標の先に、さらなる挑戦と成長を
私たちは、プロジェクトの目標を「ゴール」だとは考えていません。
それはあくまでも通過点で、本当の価値は、その先にある“次の挑戦”にあります。
たとえば「採用数を増やす」「ブランド認知を高める」といった成果は重要です。
しかし、それ自体が最終目的ではなく、次のステージへ進むための“土台”に過ぎません。
重要なのは、プロジェクトが一区切りついたときに、自然と次の問いが生まれる状態をつくること。
「この経験をどう活かすか?」「次に何を仕掛けるか?」そうした問いが出てくるチームこそ、ブランドを着々と成長させていくことができます。
そして、私たちはそうした新しい動きの起点に立ち会える瞬間に、いちばんやりがいを感じます。
だからこそ、私たちが設計すべきなのは、関係者全員が目的に向けて真っすぐ進める構造。
そこには探り合いや駆け引きの余地はありません。
信頼と対話。これが関係性のベースにあれば、プロジェクトのプロセスそのものが前向きな体験に変わります。
その“前向きさ”が、当事者のモチベーションを高め、結果的に事業全体の成果にも直結していくのです。
成果を出すことと、プロセスを楽しむこと。その両立を仕組みとして実現する。
それが、私たちが本気で向き合っている「プロジェクトの在り方」です。
最後に
この記事に書いたことは、私たちの“こだわり”であり、“当たり前”でもあります。
すべての現場で通用するとは思っていませんが、少なくとも私たちはこのスタンスで仕事をしています。
もし、「うちもそうだよ」「そのやり方でやってみたい」と思ってくださった方がいれば、ぜひご一緒したいです。
考え方が近い者同士が組めば、無駄な心配をせずに、より本質的なところに集中できます。
そしてその先に、さらに面白いことが待っていたら、最高ですよね。
これからも、駆け引きのいらないプロジェクトを、一つひとつ丁寧に積み重ねていきます。