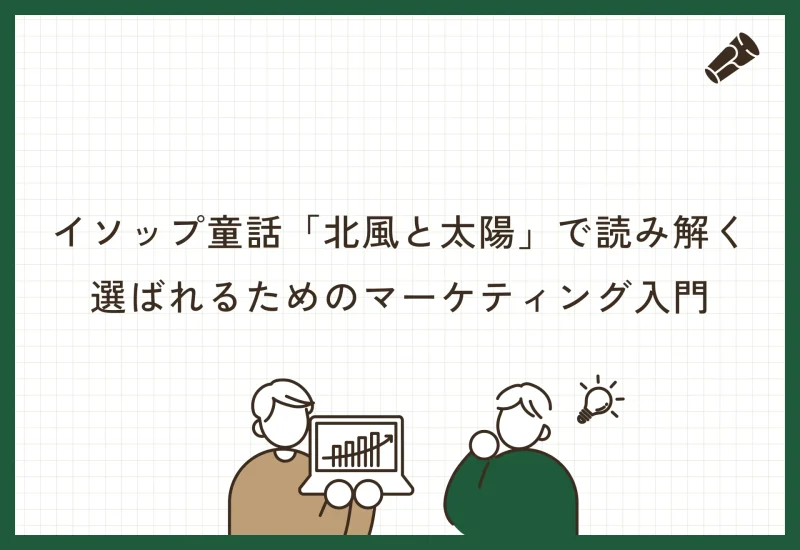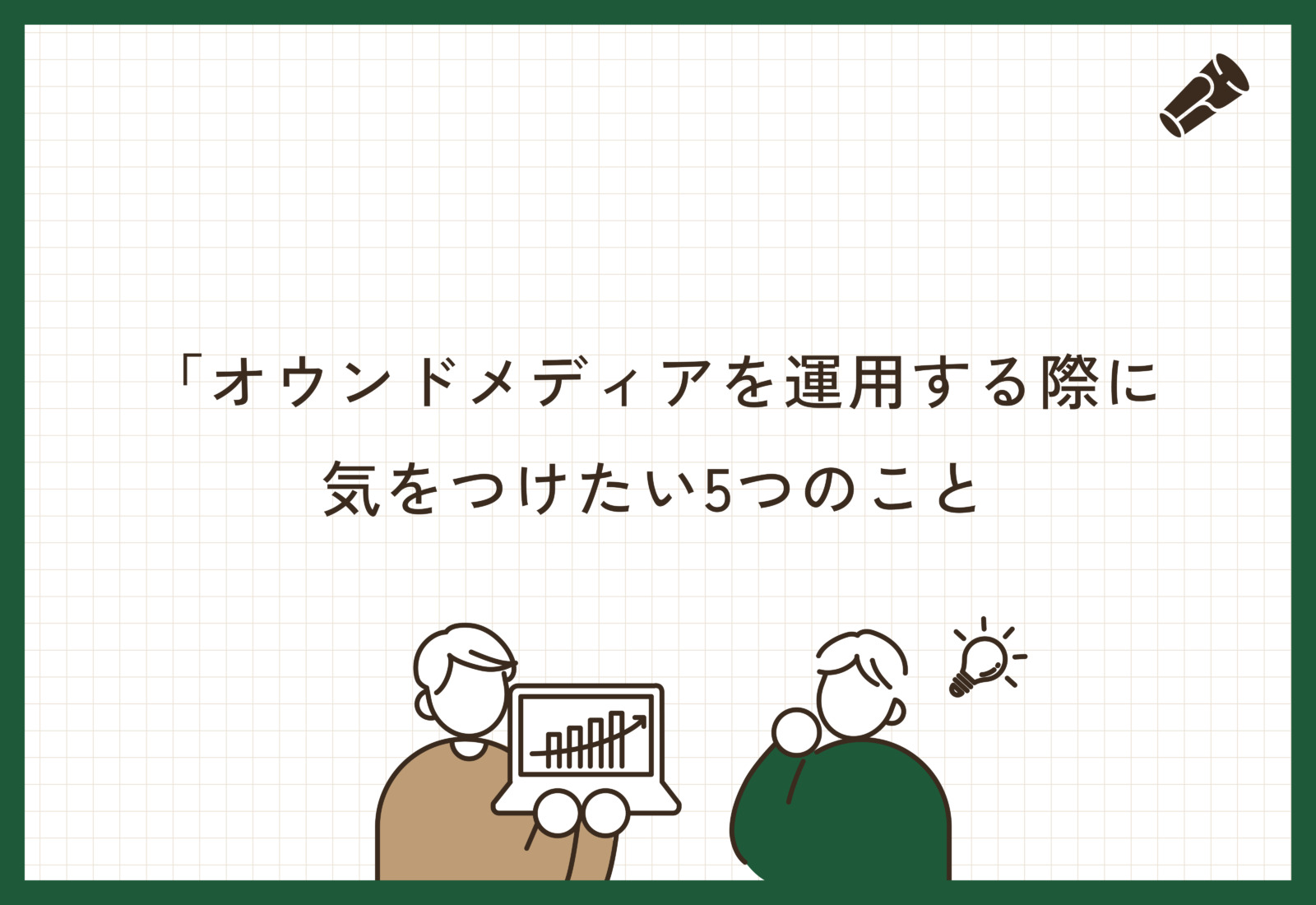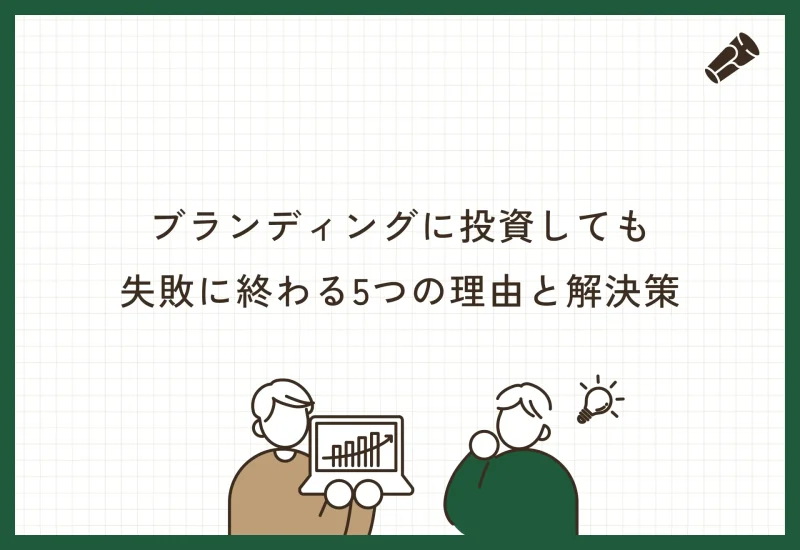Index
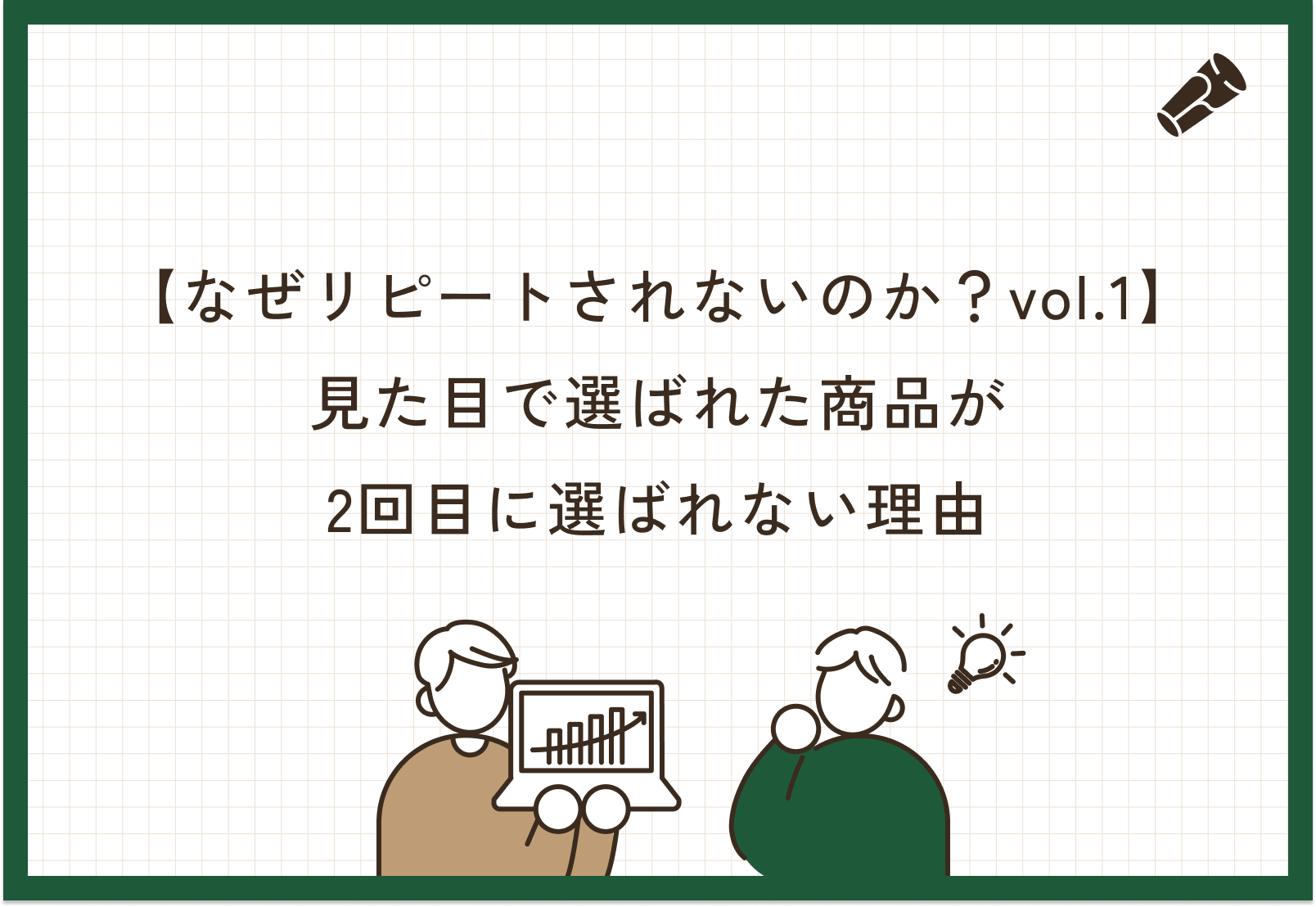
商品やサービスを開発するうえで、ニーズ分析とターゲティングは必須の工程です。この工程を甘く見ると、どれだけ注目された商品であっても、継続的に売れることはありません。
マーケティングにおける目的は、「一度買って終わり」ではなく「何度も買ってもらうこと」です。
にもかかわらず、現場では“映える商品”や“話題になりそうな企画”に重きを置いて設計が進められるケースが少なくありません。
リピーターを増やすほうが、コスト効率は5倍良い
本題に入る前に、前置きにはなりますが、マーケティングの世界では、「新規顧客の獲得には、リピーターを維持するコストの5倍かかる」とよく言われます。
これは実務の現場でも体感できる、非常に現実的な法則です。
広告費をかけ、SNSでバズらせ、キャンペーンを打つ。こうした新規獲得施策はすべてコストが高くつきます。しかも、その効果は一時的なことが多く、長期的な利益にはつながりにくい。
一方、すでに自社の商品やサービスを購入し、体験してくれた顧客は、リピートに対する心理的ハードルが低い。
ブランドに対して信頼を持っていれば、再購入の動機付けは小さなきっかけで済みます。
つまり、同じコストをかけるなら、新規よりも既存顧客の継続に投資した方が、遥かに費用対効果が高いのです。
現代の日本は人口が減少し、今後市場そのものが縮小していくのは明らかです。
その中で、常に新規を取り続けるモデルでは、やがて限界が来ます。
だからこそ、いま注力すべきは「顧客との関係性を育てる」こと。商品設計の段階から、どうすれば“繰り返し買いたくなるか”を考えておくことが重要です。
商品が売れるのは、単に話題になったからではありません。
「もう一度買いたい」と思わせられるかどうか。
そのためには、見た目や話題性の前に、まず機能的価値、本質的価値(後ほど詳しく解説します)が問われます。
企業としての利益構造を健全に保ち、持続的に成長していくためには、リピーターにこそ軸を置く必要があります。
価値の中心を「映え」にするとリピート機会は減る
ここから本題に入っていきます。
例えば、インスタ映えするような可愛らしいデザインのお団子。
他社との差別化のために、味や食感はさておき、見た目だけにこだわり抜いたお団子だったとします。
華やかで注目されやすく、SNS上では一時的にバズるかもしれません。
初速は確かに出る。
しかしその商品は、和菓子が好きな層をターゲットにしているわけではなく、写真を撮ることに価値を感じる層だけを呼び寄せてしまう確率が高くなります。
結果として、話題にはなるが、味や品質には期待していない顧客が中心となり、リピートにつながらない。
ここでの失敗は、「話題になりそうな見た目」でニーズを捉えたつもりになっていること。
本来であれば、大前提として「和菓子を楽しむ層」にニーズがあるかどうかを見極め、そのニーズを満たす設計にするべきです。
ターゲットの解像度が低いと、初速のブームだけで終わってしまうのです。
まず“本質的なニーズ”を捉えること
リピートされる商品には、共通した一つの構造があります。
それは、「その商品カテゴリーを本質的に好んでいる人」のニーズを的確に捉えているということです。
ここを押さえていない商品は、どれだけ話題になっても継続的には売れません。
つまり、見た目やトレンドではなく、カテゴリそのものに対する愛着や習慣を持つ顧客層に対して価値を届けられているかどうかが、継続的な売上を左右します。
先ほどのお団子の例で言えば、和菓子が日常的に好きな人、定期的に買って楽しんでいる人たちが求めるものは何か。
それは、素材の風味や食感、この場所でこのお団子を味わうという“背景”まで含めた、見た目も一部として組み込まれた「食体験そのものの満足」です。
そうした顧客のニーズを満たす工夫がなければ、表層的なデザインだけで買われる商品になってしまい、1回の購入で終わってしまう。
この話を簡単にまとめると以下のようなイメージです。
■リピートされにくいケース(映え重視)
- 商品開発側が「SNSで注目されること」を狙って企画
- 「お団子そのもの」よりも、見た目の可愛さ・華やかさを重視
- 想定したターゲットは、「写真を撮って投稿したい層」
- 顧客の主な動機は、注目されたい・褒められたいという承認欲求
- 投稿して目的を達成したら、満足して離脱
- 味や品質には期待していないため、再購入されない
- 結果、SNSでは話題になっても、継続的な売上につながらない
■リピートされるケース(本質的価値重視)
- 商品開発側が「お団子を食べたい人」の実需を起点に設計
- ターゲットは、和菓子を日常的に楽しんでいる層
- 顧客が求める「食体験」全体を重視(風味・食感・量・満足感)
- たとえば「他よりももっちり」「ボリューム満天で幸福感を感じる」など、日常的な満足を提供
- 結果として、「また食べたい」という感情が自然に湧く
- “付加価値として”見た目も好印象だから、手土産やギフトにも選ばれやすい
- 「誰かにすすめたい」「喜ばせたい」という気持ちが広がる
- こうして再購入や紹介が生まれ、自然とリピートされていく
これ、そもそも同じお団子でも提供している価値全く違いますよね?
狙うニーズが違えば提供する価値ももちろん変わります。
本質的なニーズを無視してターゲティングした商品は、いわば“自転車のペダルを空回し”している状態。前には進んでいるように見えても、すぐに立ち止まります。
一方で、ニーズの中核を捉えた商品は、広告を打たずともじわじわと支持を広げ、やがてはブランドのファンを育てていきます。
だからこそ、商品設計の初期段階で「どのニーズに応えるのか?」を明確にしておくこと。
これは、目の前のトレンドに乗るより、よほど強い成長エンジンになるんです。
「尖った商品設計」は順番を間違えると逆効果になる
独自性を出そうとするあまり、本質的なニーズや主要ターゲットから外れた商品設計をしてしまうケースは、意外に多く存在します。
もちろん、尖った商品設計はマーケティングにおいて重要な武器です。
しかし、それを“最初にやるべきこと”と勘違いしてしまうと、かえってリスクが大きくなります。
繰り返しになりますが、商品開発で最優先すべきは「誰のどんな課題を解決するか」です。
顧客の生活の中にある“確かなニーズ”を掘り起こし、そこに対して商品を設計する。
この順番を飛ばして、いきなり独自性や話題性を狙ってしまうと、「ウケ狙いの商品」で終わる危険性が高くなります。
「他と違うから売れる」というのは一見正しいようで、実は極めて条件付きの話です。
まず土台として、カテゴリー全体に存在する共通の価値をしっかりと押さえていること。
そのうえで、他社と差別化するための“ズラし”を加える。
この順番でなければ、顧客の心には響きません。
たとえば、和菓子好きが定期的に通う老舗に、「超奇抜な変わり種団子」がメインで置かれていたら、どう思うでしょうか。
興味本位で買ってみる人はいても、通い続ける理由にはなりません。
リピーターとは、「安心して期待できる定番」を求めている人たちです。
定番を作り、そこに変化球を加える。
この順番こそが、ブランドの継続的な成長に必要な思考です。
もちろん見た目も大事
誤解がないように念の為お伝えしておくと、たしかに、バズ狙いや一過性の施策ばかりに頼るのは、ブランドを短命にしてしまうリスクがあります。
けれど、それは「バズ型商品や新規施策が全部ダメ」という話ではありません。
むしろ、今の時代、話題性や新規性がないと、どんなに良い商品でも見向きもされないケースは少なくありません。
大切なのは、「映え」と「本質価値」、「新規性」と「継続性」を対立構造で捉えず、戦略的に掛け合わせること。
たとえば、ブランドの根幹をなす価値をしっかり育てながら、それを鮮やかに伝える“仕掛け”としてバズ型のクリエイティブを取り入れる。
あるいは、長年積み上げてきた顧客体験の信頼感に、新規チャネルやプロダクト開発で新しい驚きを添える。
表層のインパクトと、内側にある価値。
どちらか片方ではなく、両方をどう活かすか。
ブランドを持続的に育てていくには、そうした“掛け算の思考”が欠かせません。
まとめ
商品やサービスを設計する際にもっとも重要なのは、「選ばれ続ける状態」をどう作るかという視点です。
一度の購入や利用ではなく、生活や習慣の一部として自然に選ばれ続ける。
その状態を設計段階から意図することで、ブランドや事業は安定して成長していきます。
短期的な話題性やバズを狙う設計は、一時的な集客には効果的ですが、長期的なブランド構築には不向きです。
なぜなら、その手法では“次の話題”を常に提供し続けなければならず、時間もお金も消耗していくからです。
安定した成長とは、常連が自然に増えていく構造をつくること。
つまり、再現性がある状態を仕組みに落とし込むことです。
そのために必要なのが、“芯”のニーズを捉えた商品設計。
- 顧客が本当に求めている価値とは何か?
- 日常の中でどう使われ、どんな文脈で選ばれるのか?
- そもそも顧客は誰なのか?
この問いを深く掘り下げ、そこに真っ直ぐ応えること。
ここを外さずに設計すれば、ターゲットは商品と自然に関係性を築いていきます。
ビジネスの不確実性が増す現代においてこそ、再現性のある設計が価値を持ちます。
表層的なブームに翻弄されず、軸を持って商品やブランドを磨き上げていく。
その積み重ねこそが、安定した事業基盤をつくる最短ルートです。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級