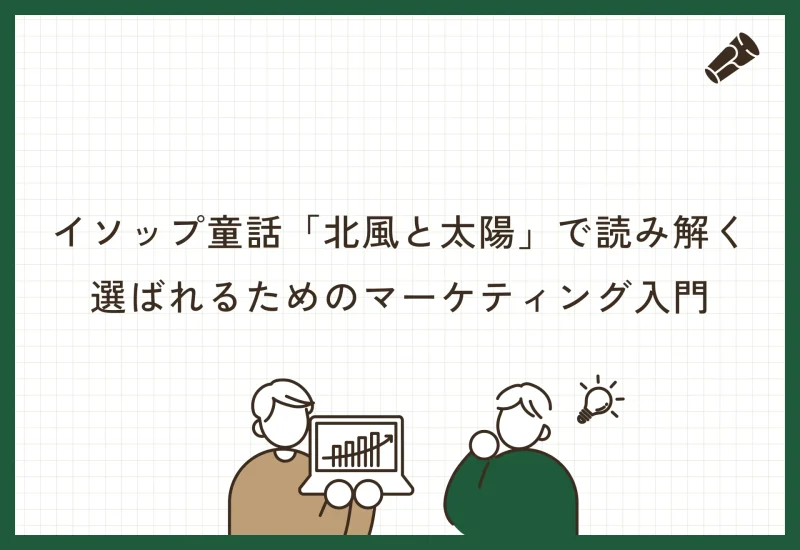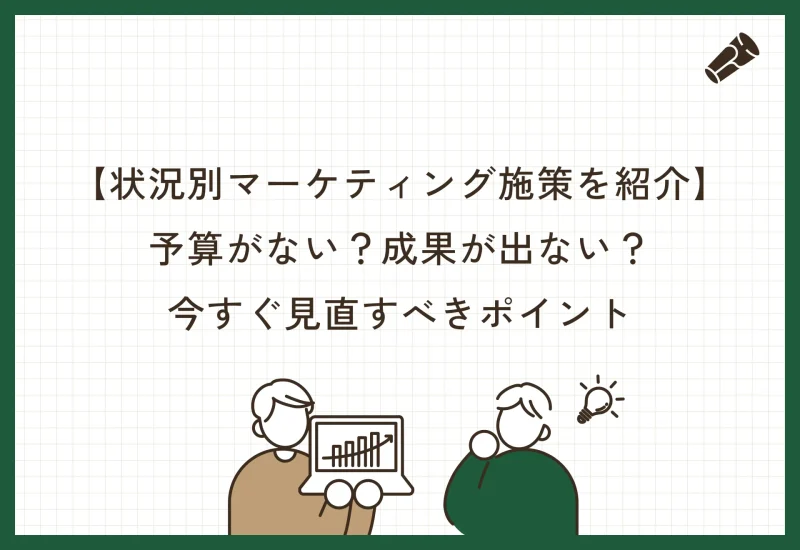Index
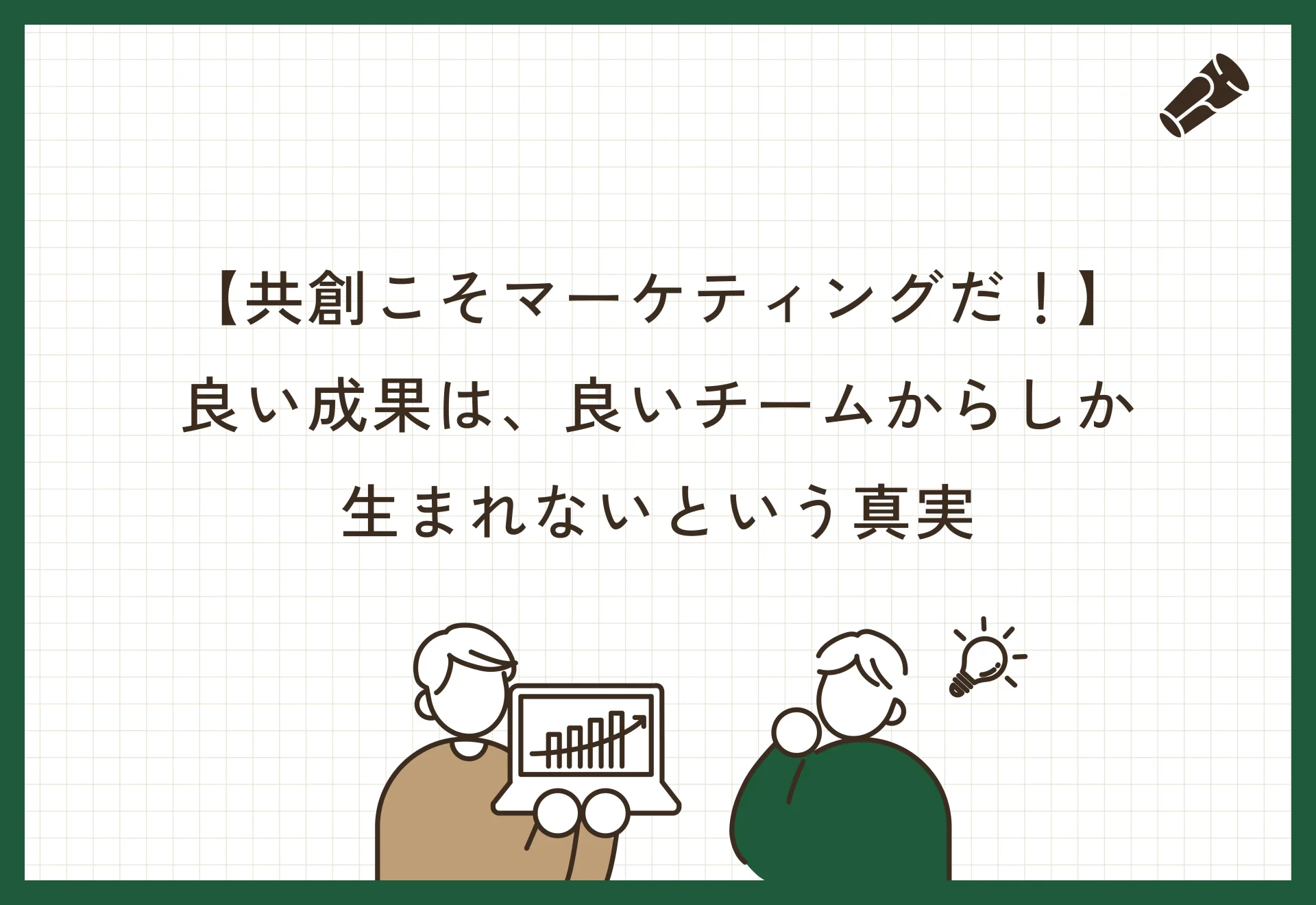
結果を出し続けるチームには、決まって一つの共通項があります。
それは、「異なる強みを持つメンバーが、明確な目的と、信頼を共有している」こと。
逆に言えば、どれだけ優秀なプレイヤーを集めても、その前提がなければ、チームは空中分解する。
そして、成果は出ない。
これは数多くの現場を見てきた中で、断言できる事実です。
マーケティングや事業開発における成果が出ない最大の理由。
それは、戦略ミスではない。資源不足でもない。
「組織力がない」。それが本質的な原因なんです。
実際、成果が止まる現場には、ある“お決まりの症状”が現れています。
- 本音を言い合えず、チーム内に緊張感だけが漂っている
- 「自分でやった方が早い」という考えが蔓延し、知が分断されている
- 専門性の欠如を埋めないまま、トレンドや目先の手段に飛びついている
- 分析も振り返りもせず、各自が勝手に動いている
このような状態では、いくら頑張っても「点」で終わってしまうんです!
線にならない、面にならない!
結果、スケールせず、再現性もない。事業は伸びない。
そんな状況に陥ります。
なぜ個では勝てないのか?チームとは、そもそも何のために存在するのか?
そして、「成果を出すチーム運営」とは、何をどう設計すべきなのか?
この記事では、そうした根本の問いからスタートし、実践に落とし込むための原則までを書いていきたいと思います。
“個の限界”を知り、“チームの本質”に迫る。それが、勝ち続けるための第一歩です!
なぜ個では勝てないのか?
マーケティングの現場で本当に結果を出そうとするなら、「ひとりで何とかしよう」という発想自体が危険です。
なぜなら、マーケティングやクリエイティブの仕事は、複数の視点と技術領域が交差する構造になっているからです。
たとえば、
- 外的環境や市場の特性を分析する力。
- 消費者インサイトを鋭く掘り起こす力。
- 数値からユーザーの行動原理を読み解く力。
- 商品やサービスの価値を言語で精緻に定義する力。
- クリエイティブジャンプを起こす力。
- それを視覚・映像表現として社会に伝える力。
- 戦略に沿ったアクションを仕組み化する力
- デジタルを駆使して、生産性を上げる力
- 優先順位や目標数値を明確にし集客コストを最適化する力。
これらすべてを、たったひとりの人間が高精度で担うのは、ほぼ不可能だと思いませんか?
「異なる脳が交わる」ことで、成果は飛躍する
スタンフォード大学での創造性に関する実験で、多様な専門性を持つ3人組のチームが、同じスキルを持つ3人組や個人よりも、質の高いアウトプットを安定して生み出したという結果が出ているそうです。
要因は明確。
「異なる脳が交わる」ことで、固定観念が壊れ、より大胆で深い発想が生まれるから。
これは脳科学の分野でも裏付けられていて、他者の視点を取り入れるとき、脳内のデフォルトモードネットワーク(内省や発想時に活性化する脳のネットワーク)が活性化し、思考の柔軟性が高まることがわかっています。
つまり、良いチームにおいては、チームの人数は単なる足し算ではなく、“掛け算”であるということ。
まず認識すべきは「個人の限界」。
優れたチームは、異なる専門性をもつメンバー同士が互いの視点を補い、技術を補強し合う関係性を築いています。
一人では平面的にしか見えなかった課題やアイデアも、チームという“レンズ”を通すことで、立体的に捉えられるようになる。
自分の弱みを、誰かの強みで補ってもらえる。
その結果として弱点は消え、強みはさらに引き上げられていく。
結果、アウトプットには「深さ」と「広がり」が加わり、生産性も飛躍的に上がる。
現実として、どんなに優れた個人でも、専門外の領域では必ず「ズレ」が生じます。
そして、そのズレが成果を出す確率とインパクトすらも削ってしまう。
先ほども書きましたが、だからこそ、まず認識すべきは「個人の限界」。
その限界を正確に理解している人だけが、本当の意味で「チームで戦う価値」を知るのだと思います。
個の限界に執着するより、信頼できる仲間とともに前へ進む方が、圧倒的に強い成果を、より再現性高く手に入れられるんです!
チームに最もいらないものは遠慮
とはいえ、肩書きや組織図で構成された「チーム」は、あくまで枠組みにすぎません。
そこに信頼関係がなく、率直な対話ができなければ、ただの寄せ集めです。
遠慮がはびこると、本質的な指摘が出なくなり、改善のチャンスも失われていきます。
たとえば、デザイナーがクライアントのアイディアに対して「これはずれている」と思っても、相手への気遣いから黙ってしまう。
トレンドに敏感な若手が意見を飲み込み、結果として平凡なアイデアに落ち着く。
そんなチームは、もはや集まらない方がマシです。
本当に機能するチームとは、立場や年次を越えて率直に意見を交わせる関係性の中にあります。
チームを名乗るなら、まず“遠慮”を手放せる空気と、それを支える「心理的安全性」のある仕組みづくりから始めるべきです。
「共に創る価値」は、世界中のリーダーが重視している
ここで少しばかり誰もが知っているリーダーの名言をご紹介したいと思います。
■ スティーブ・ジョブズ
「ビジネスで偉大なことを成し遂げるのは、常にチームであって、一人ではない」
Appleの革新は、ジョブズ一人の発想では生まれませんでした。多様なプロフェッショナルたちが、それぞれの力を持ち寄ったからこそ実現したものです。
■ マイケル・ジョーダン
「才能があれば試合には勝てる。でも、チームワークと知恵がなければ、優勝はできない」
短期的な成果は個の力で得られることもありますが、真の成功=チャンピオンを目指すなら、仲間との連携が不可欠です。
■ 松下幸之助
「自分の仕事は、人の助けなくして、一日も進み得ないのである。」
松下氏は、「衆知を集める経営」を重んじ、現場の知恵や声を何よりも尊重しました。トップの独断ではなく、みんなで考え抜くこと。その積み重ねが、一人ひとりの力を引き出し、企業の大きな成長へとつながったのです。
・・・
これらの言葉は、日々の活動や、今のチームの在り方を改めて考えさせられます。
数字を追うことももちろん大切ですが、その前に、まずは身近な仲間に目を向け、互いの個性を活かす視点で活動していきたいですね。
現場で実践すべき5原則
理想論ではなく、現場で機能するチームづくりには具体的な仕組みが必要です。
以下の5原則は、多くの実績に裏打ちされた実践知です。
共通目的の明文化
チームが迷わず進むためには、何のために集まっているのかを明確に共有することが大切です。目的が曖昧だと、行動や意識がバラバラになりやすくなります。
以下、日々意識しておきたいポイント
- 目的を言語化する。(意志があり、他者が共感でき、一人では達成できない目的を。)
- 全員が目的を理解・納得ための機会を定期的につくる。(ワークショップを開催するなど。)
- 目に見える場所に掲示し、常に意識できるようにする。
多様性の受容と尊重
異なる視点やスキルがあることでチームは強くなりますが、そのぶつかり合いを恐れず、建設的に活かす文化をつくることが不可欠です。
以下、日々意識しておきたいポイント
- 意図的に多様なメンバーをチームに迎える。
- 意見に「否定ではなく質問」で返す習慣をつくる。
- 異なる意見もまずは受け止める姿勢を全員が持つ。
心理的安全性の醸成
意見を言っても否定されず、失敗しても責められない環境が挑戦を生みます。リーダーから率先して弱みを見せることも効果的です。
以下、日々意識しておきたいポイント
- リーダーが自分の迷いや失敗をオープンにする。
- 発言には共感や理解を示す言葉を添える。
- ミスを責めず、改善の機会と捉える文化をつくる。
定期的な振り返りと学習
振り返りを怠らず、成功と失敗から学びを引き出し、次の行動に活かすことが成長の鍵です。
以下、日々意識しておきたいポイント
- 定期的に振り返りの時間を設ける。
- 成功要因と改善点をチームで共有、小さな成果でもその達成感を分かち合う。
- 学びを次のプロジェクトや活動に具体的に落とし込む。
リーダーシップの開放
リーダーは大枠の方向性を示しつつ、細かい判断や実行はメンバーに任せることで、主体的な動きを促します。
以下、日々意識しておきたいポイント
- 権限委譲の範囲と基準を明確にする。
- メンバーの意見を尊重し、裁量を与える。
- 「褒める」よりも「認める」をベースにしたコミュニケーションを心がける。
【まとめ】共創こそマーケティングの本質
マーケティングやクリエイティブは、「正解のない問い」に挑み続ける仕事です。
そこでは、複数の視点や専門性、そして相互の信頼が不可欠。
一人の力では届かない領域に踏み込むためには、良いチームが必要。
だから共通目的を明文化し、心理的安全性のある環境を徹底して整える。
そして、多様性を受け入れながら振り返りと学習を重ね、集団知にする。
誤解を避けるためにお伝えすると、共創の基盤として最も大切なのは、個々が自分の強みを徹底的に磨き、自立し、主体的に動くことです。
個が自立していなければ、チームの力は十分に発揮されず、単なる馴れ合いに陥ってしまいます。
なのであくまでも個を無視するわけではありません。むしろ個をより活かすためのチーム。
成果を出している組織は、偶然ではなく、こうした「共創の土台」を意図的に設計しています。
あなたの現場でも、今あるチームの状態を見直すことから始めてみてください。
▼以下の記事は本記事と深く関係する記事になりますので、ぜひ併せてご覧いただきたいです。
- 「社長”だけ”の仕事」じゃない!ブランドマーケティングを組織で回すための要点。
- ブランドマネジメントとは?経営戦略と外部コミュニケーションの一貫性を強化するには?
- ブランドコンセプトの価値とは?一貫性も、選ばれる理由も、すべてコンセプトから始まる。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級