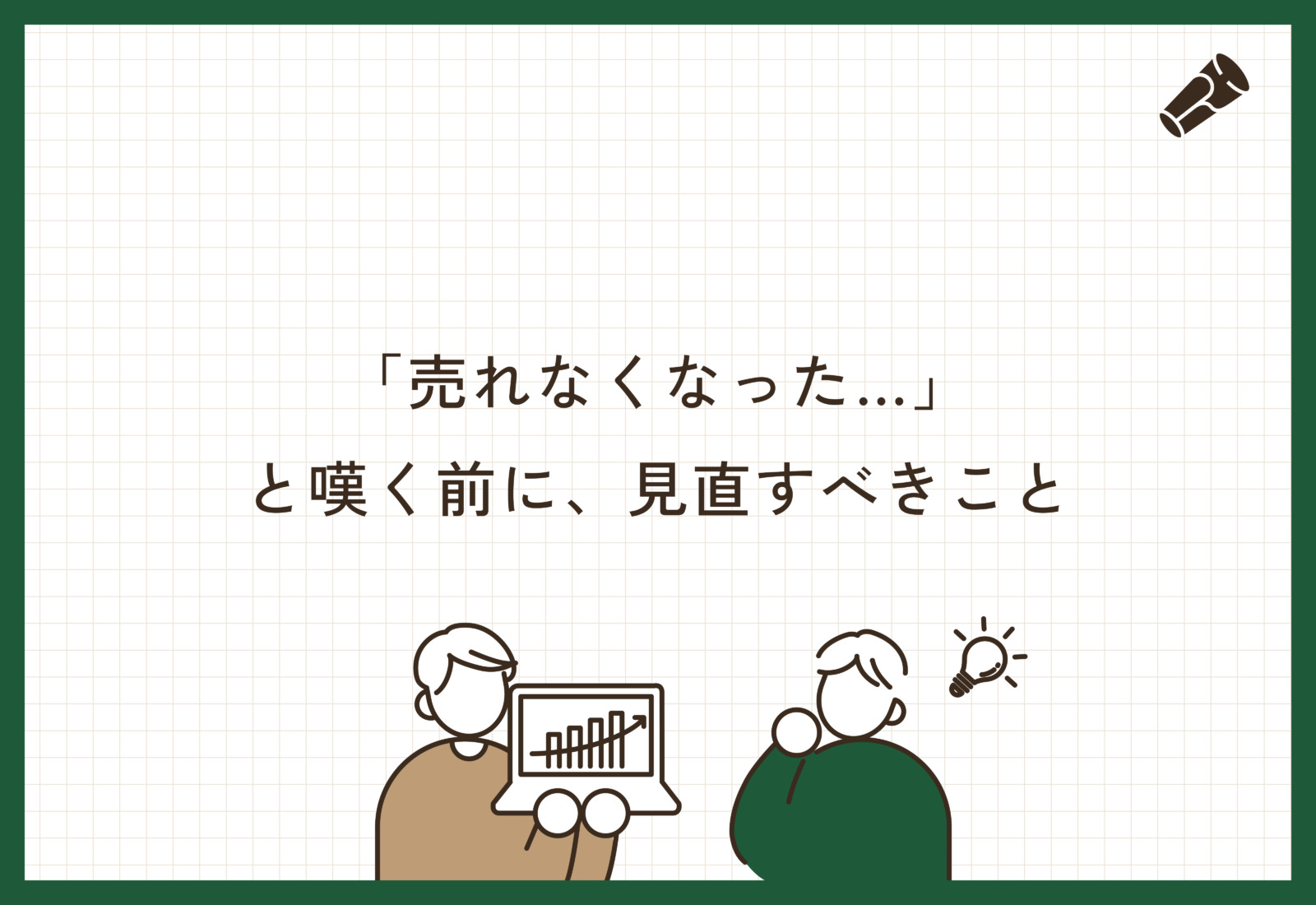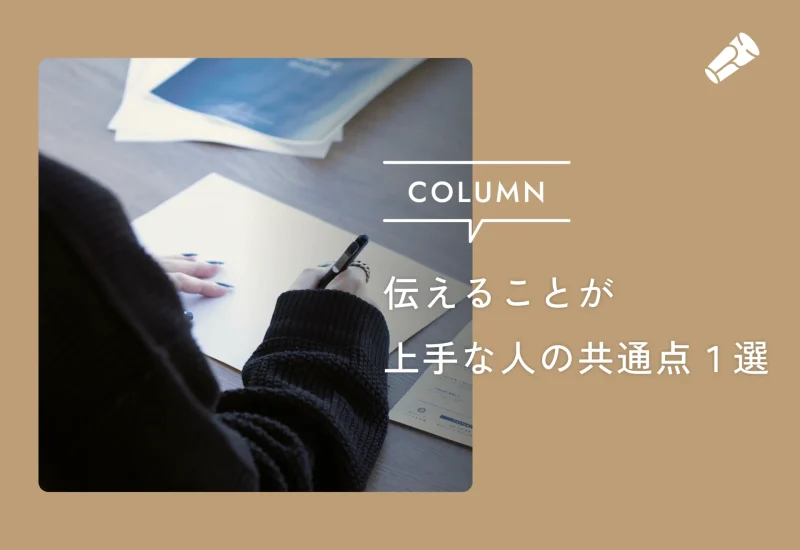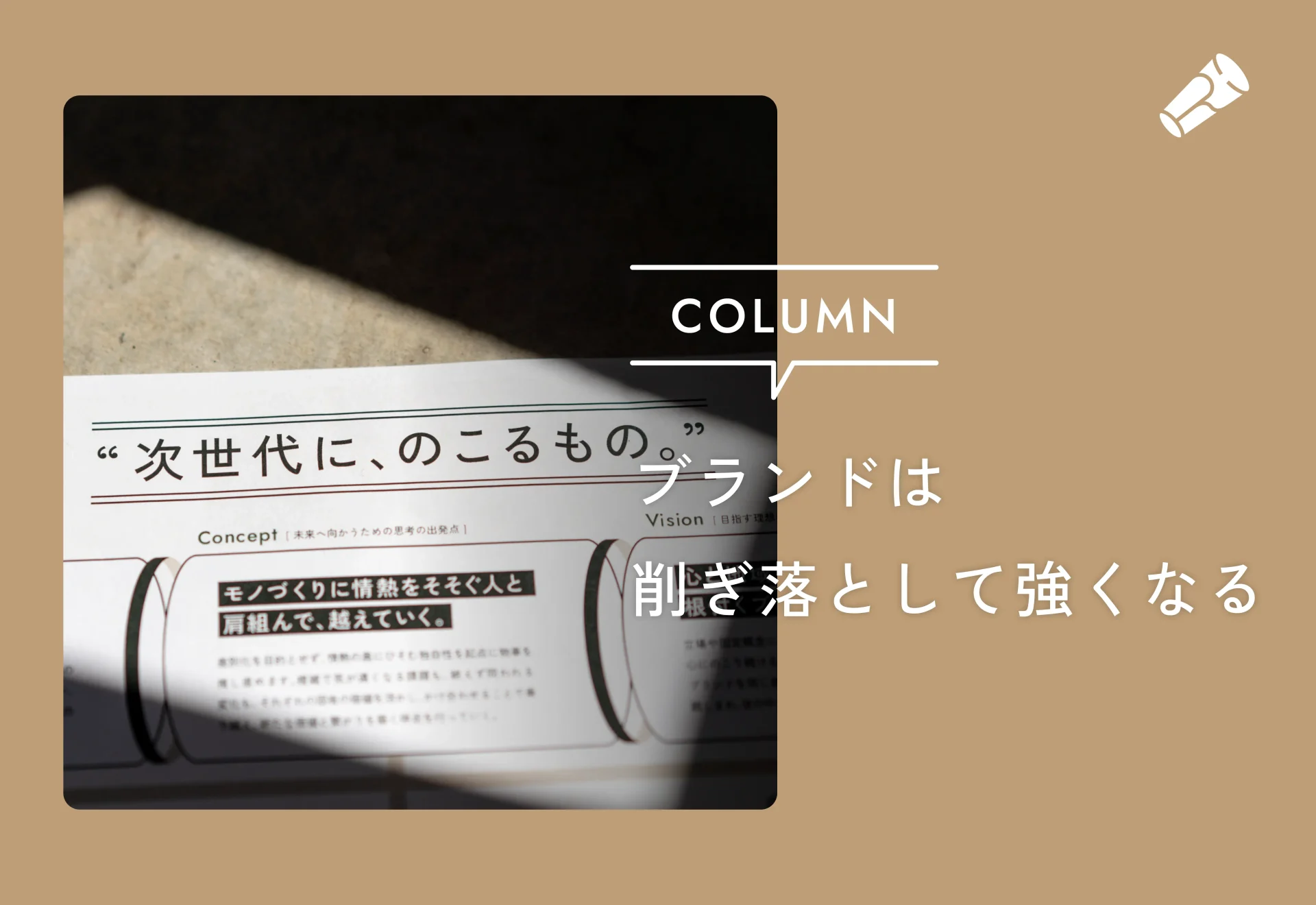
ここ最近、つくづく「捨てること、手放すこと」の大切さに改めて気づかされています。
ブランディングやマーケティングの仕事をしていると、毎日決断の連続で、何かを選んでは何かを捨てる。その繰り返しです。
個人的にも、この1、2年はこれまでの人生で最も断捨離をした時期だったと思います。
がむしゃらに続けてきた業務、当たり前になっていた習慣、居心地の良かった立場。
それらを一切捨て去り、冷や汗をかくくらいに空っぽにしてみたのがこの1、2年の個人的な取り組みです。
ただ、不思議なことに、空いたその余白には、新しい何かが自然と入ってくるものです。
これまでにはなかった新しい出会いや仕事が、生まれ始めています。
なので、改めて「捨てることの価値」について記事にしてみようと思いました。
企業活動においても役立つ話にしたいので、ブランディング戦略の観点から、これから少し掘り下げてみます。
リブランディング=見た目を変えるではない
最近は「ゼロからブランドを立ち上げたい」というより、「今あるブランドを見直したい」という相談が増えています。
いわゆるリブランディングです。
ロゴやスローガンを変えるだけの話ではありません。
リブランディングとは、「自分たちは、何を大切にして、誰にどう役立ちたいのか」をあらためて言語化し直し、それに合わせて伝え方を調整していく取り組みです。
デザインも、打ち出す内容も、営業の仕方すらも見直す。
いわば、足元を固め直す作業です。
実際、相談に来られる方の多くは「このままじゃ、じわじわ伸び悩む」と感覚的に気づいています。
社員が増えて、意思決定の軸がブレはじめているとか。
つくっているものには自信があるけれど、どう伝えていいかがわからないとか。
たとえば、
「創業から10年。これまでがむしゃらに走ってきたけど、そろそろ“らしさ”をはっきりさせたい」
「言ってることが部署ごとにバラバラで、結局何屋かわからなくなってる」
「営業をがんばっても、お客さんの印象に残ってない気がする」
そんなも声をよく聞きます。
「リブランディングしたい」の裏側にある欲求と本来の目的
リブランディングを相談される経営者の方の話をよくよく聞いていくと、「今あるものを整理したい」「このごちゃごちゃをどうにかしたい」というニュアンスが強いんです。
つまり、新しいチャレンジや次のステージに進む前に、今当たり前になってしまっている、不要で重たいものを「捨てたい」のだと思います。
これまで積み上げてきた実績や、まわりに合わせてなんとなくやってきたこと。
その中に、今となっては本当はやりたくないこと、なんとなく惰性で続けているものがある。
そこに気づき始めているからこそ、リブランディングが必要になってくるんですよね。
本質的なリブランディングとは、「足す」ことではなく「絞る」こと。
あれもこれもやらない。代わりに、本当にやるべきことだけに集中する。
そのために、一度ぜんぶ棚卸して、余分なものを捨てていく。
そうしないと、何をどう見せても、伝わるものが薄くなってしまう。
だから私は最近、リブランディングのことを「破壊と創造の取り組み」と説明しています。
少し極端な表現ではあるのですが、ただの“見せ方の変更”ではなく、“これからの戦い方を再設計するクリエイティブな作業”なので、リブランディングの目的とも合致していると思っています。
「とりあえずロゴ新しくします?」で済む話ではありません。
もっと根っこの話。
だからこそ、時間もかかるし、決断が必要だし、でもやりがいもある。
選ばれたいなら、まず選ぶこと
ここまで「新しい何かを生み出すためには、まず捨てることから始める」という話をしてきました。
しかし、実は、戦略そのものにおいても「捨てること」が大切です。
私たちはよく、「まだ弱い立場だからこそ、なんでもやるべきだ」と言われがちです。
とくに中小企業においては、“全部やる”ということが正義のように語られることもある。
けれど本当にそうでしょうか。
戦略とは、あれもこれもやることではありません。むしろ、何をやらないかを決めることです。
そして何をやらないかを決めるためには現状の課題や目的・目標についてを正しく把握する必要があります。
この考え方は、古代中国の軍事戦略家・孫子の名言孫子の「彼を知り、己を知れば、百戦して殆(あや)うからず」という名言に通じます。
ここで言う「彼」とは、競合や顧客ニーズ、社会環境のこと。
そして「己」とは、私たちの資源、強みや弱み、そして目指すべき目的や目標です。
この言葉の本質は、実際に施策を実行する前に「知ること」の重要さを強調しています。
知ること。つまり、いまの自分たちのリソースやポジショニングを正確に理解し、それをどう活かすかを見極めることが、戦いを有利に進めるための鍵となります。
中小企業やスモールブランドが勝負するためには、どれだけ自分たちの強みを活かすかが肝心。
大企業のように大量の資本や広告費をかけることはできません。
だからこそ、限られた資源の中で“何をやらないか”を選ぶことが、他との差別化に繋がります。
選ばれたいなら、まず選択すること。
なので、中小企業の戦い方、戦略という面においても「捨てること」が一番のポイントになると思っています。
最小限の力で、最大限の成果を出すための設計を
リコルクではよく「最小限の力で、最大限の成果を出すための設計をしよう」と言います。
でもそれは、効率主義とは少し違っていて。
短期的に見れば不合理だけど、長期的に見れば合理的。
何も知らない人たちから見れば不合理だけど、ブランドの独自性を知る人から見れば合理的。
要素を詰め込むより、空間を作る。
情報を足すより、削って腹八分目に。
誰かの期待に応えようとするより、自分たちの尖ったスタンスに従う。
「最小限の力で、最大限の成果を出すための設計をしよう」とは、そんな、ちょっと覚悟のいる選択です。
けれども、そうした最大限を探るための引き算こそが、“掛け算する価値”になると思っています。
伝えても伝えても届かない取り組みにこのままリソースを割き続けたいですか?
価格を値切ってくる方と仕事がしたいですか?
価値を正当に評価しようとしない方と仕事がしたいですか?
そこから脱するために、最初にやるべきは“捨てること”なんです。
潔く手放す。その上で、何を大切に育てていくのかを選び直す。
そこからしか、価値の最大化や、本当に面白いことは始まらないと思っています。
つまり、捨てることの価値とは、何かが大きく動き始める“きっかけ”になることです。
ちなみに、「捨てられないこと」は、ブランディングにおけるよくある失敗要因のひとつでもあります。ほかにも、よくある失敗要因はいくつかあり、以前まとめた記事がありますので、ご興味があれば以下もご覧いただければと思います。
この記事を書いた人

クリエイティブディレクター
萩原 雅貴
これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級